
- 運営しているクリエイター
#自説
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] 5月22日-1965年 [昭和40年] 5月3日) 小説家・詩人・随筆家。
🔍 青空文庫 中勘助の作品
🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」(1946年改訂版 [初版は1919年])
七章、二十一章に出てくる、奈良帝室博物館 (現・奈良国立博物館) にほぼ毎朝行き、東大寺に宿泊し、當麻寺の塔の風鐸をどう思います、と聞くN君が
奈良の『破石(わりいし)』 関連記事 /2014年記事のバックアップ (第2次)
⚜
🔶『破石』で誰かが得する? - 2014/10/21(火) 午前 2:55
奈良の『破石(わりいし)』、もっともパワフルな塚と言われる『吉備塚』
このブログが今の状況をよく伝えておられます。
= http://www5.kcn.ne.jp/~book-h/mm057.html /
以下、私の見解であります。
(吉備塚の北に『晴明塚』もあると聞きますが、)これらの吉備塚をメインと
醍醐寺薬師三尊, 法隆寺地蔵, 興福寺東金堂十二神将立像 国宝指定日 (1953年2月14日)
🍁 醍醐寺薬師三尊像 平安前期(醍醐寺開創 [874年] の理源大師聖宝 [しょうぼう 832-909] が醍醐天皇 [885-930] の発願により907年 [延喜7年] から造営、913年 [延喜13年] 完成) 木造漆箔 像高176.5cm (中尊薬師如来). 120cm (日光菩薩). 121cm (月光菩薩). 2000年に上醍醐薬師堂 (国宝) から霊宝館へ移される。
🐥
「長屋王の変」 729年3月16日 (神亀6年2月12日) ・ 関連記事 (虚言が圧倒的多数となるネット等の論評の奇妙さ、など)
「長屋王の変」 と 「お水取り」東大寺修二会 (通称 お水取り) の時期が
旧暦では2月1日からだったそうなので (修二会が15日間ならば、)
続日本紀に旧暦2月10日から12日とある
「長屋王の変」の時期と日時的に重なっていたことになりますね。
🔍参考 東大寺公式ページ
「長屋王の変」に関して、 虚言が圧倒的多数となるネット等の論評の奇妙さ🍁
政務に当たる太政官の最高位の左大臣とし
「お水取り」で「青衣の女人」はやはり大きい存在だった (リライト増補版)
東大寺二月堂で3月1日から毎年行われる「修二会」( しゅにえ。通称「お水取り」)。
5日と12日 (※1) に東大寺に縁のある人々の名を記した「過去帳」を読み上げ、その中の「青衣の女人」( しょうえのにょにん ) が謎の存在として、マスコミやネットなどでよく話題になります。
「神名帳」の読み上げの後、数分ほど間を置いて午後10時頃から「過去帳」の読み上げが始まりました。
と言っても、「これか
玄昉僧正の肘塚伝承地発見か
村井古道「奈良坊目拙解」(江戸時代中期 1735年 ※1) にある玄昉僧正の「肘塚」(かいなづか) 伝承地は、この位置だと思います。
詳しくはこちらに写真とご説明があります。
🔶
※1.
🔍奈良県立図書情報館公式ページ「奈良坊目拙解 第二巻」 (原文)
📝 「今當社並肘塚旧跡搆塀於大道傍穿圓形窓使行人拝其所在焉」は
「今当社 (春日神社) 並びに肘塚旧跡は塀を大道の傍に構え、円
岡寺 奥の院石窟 (太陽神と鎮魂)
📷 岡寺 (おかでら / 創建時の正式名 龍蓋寺 りゅうがいじ) 本堂
画像右 (石の囲い) が龍を封じたという龍蓋石のある池 (本ブログ 龍蓋写真等の記事 https://note.com/artandmovie/n/ncf1967ed43e4 )
📷 岡寺奥の院の石窟 本堂前から東へ山道を登った所にある西向きの石室。弥勒菩薩と書いてますね。
学芸員資格を取得 (同志社大学博物
1月9日 大友皇子が天皇に即位(弘文天皇。 大友皇子即位説より) 672年(天智天皇10年12月5日)・ 「天智天皇暗殺説」への疑問点
1月9日 大友皇子が天皇に即位(弘文天皇。 大友皇子即位説より) 672年(天智天皇10年12月5日)。
以前、弘文天皇陵と三井寺新羅善神堂について書きましたが
( https://note.com/artandmovie/n/nba48babd85ab?creator_urlname=chiichan )
近辺の、大友皇子 (弘文天皇) と父親の天智天皇に関連する史跡を
この数年幾つか巡
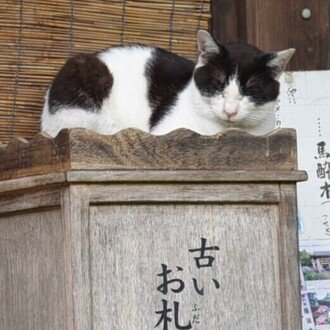

![中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41799545/rectangle_large_type_2_4556d0cef7fff55eaf8a225b9e86f7e4.jpg?width=800)







![玄昉 (げんぼう) 僧正が藤原広嗣の霊に掴み上げられ、空から降ってきた腕の塚との伝説がある肘塚 (かいなづか) 伝承地 (の一つ) の南面。四つ辻の南東にあります。町名 (肘塚 [かいのつか] 町) の由来になっていますが、この地点は「椚神社」(くぬぎじんじゃ) の表示のみとなっていて、ウィキペディアにも「椚神社」の記事は有りますが [🔍 https://ja.wikipedia.org/wiki/椚神社 ]、弘法大師が立てた杖が椚の木となった等の記述で、玄昉僧正のことは書かれていません。 玄昉 (げんぼう) 僧正が藤原広嗣の霊に掴み上げられ、空から降ってきた腕の塚との伝説がある肘塚 (かいなづか) 伝承地 (の一つ) の南面。四つ辻の南東にあります。町名 (肘塚 [かいのつか] 町) の由来になっていますが、この地点は「椚神社」(くぬぎじんじゃ) の表示のみとなっていて、ウィキペディアにも「椚神社」の記事は有りますが [🔍 https://ja.wikipedia.org/wiki/椚神社 ]、弘法大師が立てた杖が椚の木となった等の記述で、玄昉僧正のことは書かれていません。](https://assets.st-note.com/img/1614797121425-clcNbuogMD.jpg?width=800)



