
読みやすく、わかりやすい文章の書き方(面白いかはさておいて)
noteを書きはじめてしばらく経ちますが、しばしば「読みやすい」「わかりやすい」と言ってもらえることがあります。
実際、私自身は書く時に気をつけて書いているつもりなので、お世辞だとしても結構嬉しく思っています。
さて、今日は私が書く時に気をつけていること、
そしてそもそも論述することについて。
日本の教育ってほんと文章の書き方教えないよね。
-- !Caution!--
本日は文章を書くことについてであって、文書きについてではありません。
そのため、綺麗な文の作り方、丁寧な言葉遣いなどについてではなく、
文章の構成などについての話になります。
忙しい人のための文章講座
本日は、「文章とはなにか」から掘り下げるので、「実際書くときに注意してること」についてはだいぶ後半になってしまいます。
なので、忙しい人のために文章講座だけ書いておきます。
(それだけ読みたい人がいるかもしれない)
主に私が注意しているのはこの4つです。

特に1番を大切にしています。
また、私自身はキャッチーなテーマが好きということも、読みやすさの一助になっていると考えています。
専門性の高い話はそれだけで読む人が少なくなってしまい、同じ分野の中でもカジュアルでとっつきやすい話を書く方が読まれると思います。
つまりは需要の観点です。

忙しい人のための文章講座は以上です。
本日のお品書き
本日は三部構成です。
1.文章について
2.論について
3.文章を書くことについて
文章について

私はなぜ文章を書くか
私は文章を書くのが好きです。
読むことも好きですし、読んでもらうことも好きです。
私自身が文章を書くモチベーションは大きく3つあります。
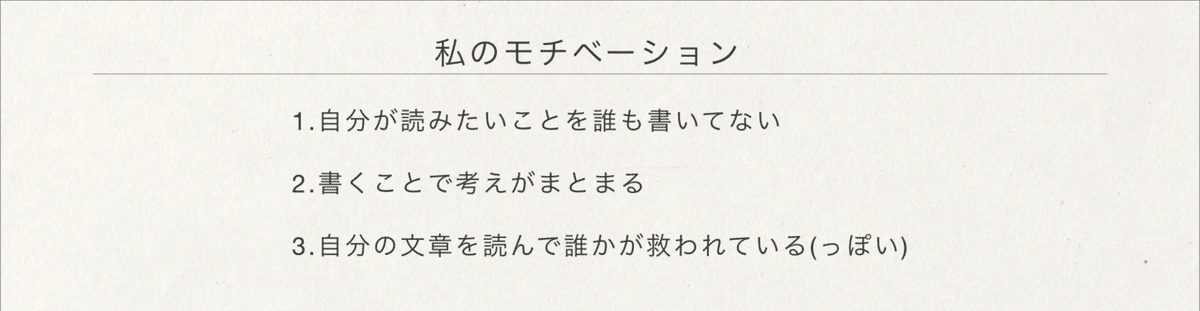
1.自分が読みたいことを誰も書いてない
私はみんなと意見が食い違う瞬間が少なからずあります。
一般的に言われていることと自分の考えが一致しないことも少なくなく、自分の考えを補強するため、しばしば自分の考えに似た文章を探すことがあります。
でもなかなか見つかりません。
ですので、こういう主張が世にあるということを、私が知らしめるぞ、と思って書いています。
また、読みたいことを書けばいいと誰かが言っていたので、基本的にはそれに従って書いています。
2.書くことで考えがまとまる
話すと考えがまとまる……というのは比較的よく言われることですが、書くことによっても考えがまとまると感じています。
書く作業はわりと奔放で、手書きならいざ知らずデジタルツールを使う我々は、とにかく文章の修正と推敲、再編集が簡単にできます。
私自身はとりあえず色んな要素を書いて見返し、文章を組み直したり、要素を足したり消してひとつの文章にします。
その過程で、理解が深まり、言語化に成功し、意見が変遷します。
noteの書き始めと書き終わりで主張が変化することも少なからずあり、書くことで考えがまとまることが楽しいのです。
3.自分の文章を読んで誰かが救われている(っぽい)
これは微妙に眉唾なのですが、自分の文章に対して「すっきりした」「もやもやしたものが解消された」という意見をいただくことがあり、それをとても嬉しく思います。
私は自分の考えを言語化するのが得意なのだと思います。
だから、自分が考えを言語化することで、誰かがそれを読み、彼らの理解や解釈を深めたり、同じ意見の人がいると知ることが出来るのです。
自分が文章を書くことで誰かが救われる。
それって、書き手冥利に尽きると思いませんか?
私はこういうことが楽しくて文章を書いています。
みなさんはなぜ、文章を書きたいと思っていますか?
(多くの人は主張すること、それに対しての反応があることをモチベーションにしてるのかな?という気がします)
なぜ文章を書きたいかのモチベーションは人それぞれです。
なぜあなたは文章が書けないか
しばしば「文章が書けない」という人がいますが、多くの場合は文章が書けないのではありません。
そもそも文章を書くことが、文を作ることを意味するのであれば、日本語ネイティブであれば日本語での作文技術にはさほど困らないでしょう。
とすれば、なぜあなたは文章が書けないのでしょうか。
それは、あなたが何を文章で書きたいかがまとまっていない。
文章が書けないのではなく、文章を構成する要素自体が不明瞭なのです。
文章の種類
文章の書き方を理解する前に、文章とは何かについて考えを深めましょう。
文章の種類はさほど多様ではありません。
私自身は大きく4タイプに分けています。
・お気持ち
・説明
・論述
・記録
お気持ち
何かしらの感想を表現する。
あれが好き、あれが嫌い。良い悪い。
共感できる文章であることが問われる。
キャッチーさなど。論理的で一貫性があることより、情念の強さが大切だと考えている。
説明
何かしらの説明をする。
道具の使い方、概念、知識。
ジャンルはさまざま。
説明力が問われます。
相手が何を理解できないか察する力など。
あるいは比喩や図示などの説明手段。
論述
何かしらの論をもちいて主張する。
お気持ちとの違いは、論理的に展開する所。
説明との違いは、事象の説明を超えて個人の解釈が入っていること。
必然的に論理的であることが要求される。
切り口の切れ味の良さや、論理としての構成力が問われる。
記録
何があったかを記録・記載する。
正確な記載や時系列の整理力が問われる。
どれもnoteで多く見られる形態かと思います。
また、単体で成立していることもあれば、複数の要素を兼ね揃えているものもあります。
改めて、自分は何を書きたい人なのか振り返るとどうでしょうか。
私自身は論述を目指していて、世界に対する私の解釈を書いています。
そして今日の文章は説明。
基本的には個人として書きたいものを書くと良いのだと思います。
それぞれに求められる能力が違うので、自分に向いてないフィールドで戦っても不利な現実もあることも覚えておくとよいでしょう。。
(特に何も感じなかったのに感想を書く、論理的でないのに論述をする、など)
論について

論とはなにか
私が目指しているのは論述ですが、論述とは論を述べる。つまりは論について書くことそのものを示します。
そもそも''論''とはなんでしょうか。
私なりの定義はこんな感じ
一つの事象に対しての反応(想像・空想・夢想・感情・情緒)を一般化し、類似の事象に対しての反応を、破綻なく説明できるようにしたもの。
なんのことやら、という感じです。
つまりは、論理化と呼ばれる行為です。

まだ、論であるからには類似の事象に対する一般性が必要です。

論述の文章に問われるのは、既存の論理の補強か、今まで論理化されていなかった切り口で論理化するかのどちらかです。

論理展開
論述の文章であれば、文章の核となる最も重要な要素です。
また、全行程の中で圧倒的に時間がかかる場面でもあります。
私の普段の投稿(6~7000字ぐらい)は、写真や図を含めても3時間ぐらいで書いているのですが、
書き始める前、投稿にどんなことを書くか考える時間はその10倍ぐらいはあるかと思います。
論理展開

私にとって、論述の面白さは、基本的に仮説の切り口の良さを意味します。
斬新で鋭い切り口だと面白い。鈍く使い古されているとつまらない
「AやBって実は〇〇という共通点があるんじゃないか?」
あるいはさらに発展して、
「AやBは、〇〇って言われてるけど、実は××なんじゃないか?」
といった、今まで指摘されていない事実の体系化がキモなのでしょう。
文章を書くプロセスについて

論から文字へ
なんとなく書きたい論やそれに付随する思考がまとまってきたら、それを文字に変換するフェイズに入ります。
ここまでで文章を書くという行為は8割ぐらい終わっていて、あとは文字にするだけです。
以下は私のプロセスです。

0.主張したいことがある
論述する以上は、主張したいことが必要です。
というか、主張したいことがない人には論述などできません。
世界は〇〇だと思う。これは実は△△だと思う。私は××するべきじゃないか。なぜならそれは --
あなたには主張したいことがある。だから論述するのです。
1.論を考える(前項)
今更言うことはありませんが、論述するのであれば下記の要素が満たされていると親切です。

実際に書く際は、知らない人にとって理解しづらいであろう部分を重点的に書くことになります。
2.どう書くかを考える -大まかな構造-
主張を補強するための論が見つかりましたね。おめでとうございます。
それでは、論を使って主張を説明しましょう。
そのためにはどういう事例、どういう要素をとりあげて説明すれば良いかを考えます。
あなたの主張を理解するために、あなたの主張が正当であると示すために、どんなことが必要ですか?
(このあたりは、執筆中にもしばし再考することになります)
3.見切り発車する、時には諦める
いちばん怖いのは、書かないことです。
ですので、論が全部まとまらなくても、「なんか書けそうかも!」と思ったら始めています。
書くことで意見がまとまる側面もあるので、途中で納得することも少なくありません。
一方、見切り発射は精度が低い方法でもあります。
多くの場合、私は書ききる事ができません。
タイトルだけ入れたもの、途中まで書いてやめたものなどが多くあり、これまで10本ぐらい記事を投稿してきましたが、20本ぐらいは書くことに失敗しています。
書ききれなかった時は一旦辞めたり諦めたりしましよう。
幸いnoteは下書き保存があるので適当にそこに残しておけば良いと思います。いつか書けるかも。
(実際のところ、私も6~7000字ぐらい書いて頓挫した文章があります。そろそろ世に出したいところ)
私は、そもそも考えをまとめるためにやっていること、そして数打ちゃ当たるの精神で書いています。死屍累々。
4.書ける所から始める
書けるとこから書きましょう。順番に書く必要は無いです。
実際この文章だって書きやすくて面白いところから書いています。
最終的に網羅するにしろ、まずは楽しいところから。
5.使わないかもしれなくても書く
使えそうなものは全部書きましょう。
関係あるエピソードとかも出しましょう。
色々盛って、要らないところは後で消すぐらいの気持ち。
6.反対意見を(論理的に)否定する
自分の主張をするためには、自分の意見が偏ってないことを示すことが望ましいでしょう。
そのために、現状の意見や自分の意見と反対になるものをとりあげて、感情的ではなく論理的に否定することで、意見の精度を高めます。
これは趣味の問題です。
入れない人もいると思いますが、不誠実な主張とされる可能性があります。
7.伝えるための補足をする
ここら辺で全体をふりかえってみましょう。
あなたの主張を説明するために、なにか説明不足なことは足りありませんか?
ちなみに私自身は
知らない人が読んでわかること(前提知識の共有)
を大切にしています。
8.伝わる順番に並び替える
要素が大体そろったところで、もう一度考えます。
今の並びは最適な並びでしょうか。
この流れなら理解してもらえますか?それとも、これを最初に説明する必要があるのでは?
軸がぶれないように文章を作ってください。
(最初の主張が最後で変わる、という構造でも良い)
最終的には、以下の形になるように進めています。

9.不要な部分を取り除く
書いたときにはわからなくとも、全体を通してみるとここ要らないかも…という部分はあるでしょう。思い切って消します。
総じて、テーマに対して余計な情報を入れないことが重要です。
理解の妨げになる情報は、無駄な補足より悪です。

10.修正 - 完成
誤字脱字とか。
私はこの段階で文章を発音しながら読み返し、音として気持ち悪いところを心地よくなるように直しています。
大体は、同じ言葉(音)の繰り返しを消してるんじゃないでしょうか。
ここら辺は慣れると無意識で行うようになります。
その他 : noteとして読みやすくする
あとは一応noteというプラットフォームに載せる上での小手先テクニックです
1.サムネイルを用意する
私はそんなに真面目には作ってません。
一応目に留まりやすいようにタイトルを入れてます。
2.概要を書く
noteでは、投稿を開かずとも最初の何文字かを読むことが出来るのですが、ここで注意を引けると良いかと思います。私はここに本文の概要を書いています。(論文と同じですね)
3.目次を入れる
投稿時に目次を入れることが出来るのですが、目次は最初のサブタイトルの直前に入ります。
4.タグは目に留まりやすいもの
投稿につけるタグは閲覧数が多いものを探してつけています。
良い文章の特長
最後に、私なりに良い文章の特徴をまとめてみました

終わりに
私が文章を書けるようになったのは、多分修論のおかげです。修論を通して、論を書くということについて学びました。
ちなみに、読みやすく、わかりやすい文章と面白い文章は別なので、
読みやすく、わかりやすさは文章の構成の良さを示しますが、
文章が面白いとしたら、それは単純に私の主張が面白いということです。
いいねしてってね!
この記事が参加している募集
いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!
