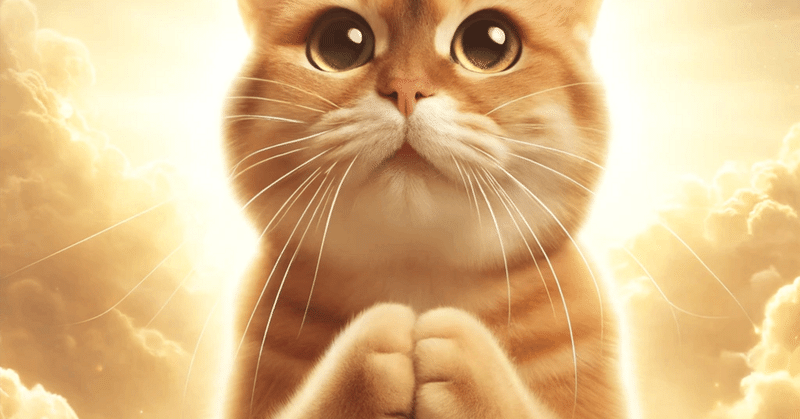
喜んで感謝すれば、悪しき「業」も消えていく/稲盛和夫氏の名言【憂世で生きる智慧】
災難に遭ったときには喜ぶこと。
災難が起こったと言う事は、「業」が消えたということです。
喜んで感謝すれば、悪しき「業」も消えていく。
謙虚さは、よい人生を歩むためのお守りになる。

いついかなる時でも、すべてのことに感謝の心で対応する。そのことには、実はとても大切な意味が秘められています。
何らかの災難に見舞われたとき、それまで自分を苦しめていた「業」が消えるか、あるいはさらなる災難を呼び込むか。それは、その時の心ひとつにかかっているからです。
心に思い描いたことが現実になる。
仏教では、「思念が業をつくる」という言葉で表現しています。すなわち心で思ったことが、「業」すなわち「原因」となって、それが現実と言う「結果」を作っていく。そうした「原因と結果」が織り成す法則が、この世には厳然と働いています。
「業」を作るのは資源だけではありません。行動もまた「業」を作り、それは必ずや現象として現れてきます。これまで知らず知らずのうちに口にしていた言葉、あるいはふとしてしまった行動が「業」となって、災難になって降りかかってくるのです。
私たちは災難にあうと、あわてふためき、うろたえ、のたうちまわります。だから、出来る限り災難にはあいたくないと思う。しかし、どれだけ良きことを思い、良きことを成したとしても、過去に作り出した「業」は現象として現れるまでは消えません。
そして災難がやってきたときの心の有り様によっては、さらなる災難を呼び込むことになりかねない。そうならないための方策が、災難を「喜んで」受け止めることです。
怪我をしたなら、「ああ、これぐらいの程度の怪我で済んでよかった。体が動かせないほどの惨事にならずに済んだ」と思う。病氣であっても、「これぐらいの病氣で、手術で良くなってよかった」と喜ぶことです。
災難が起こったと言う事は、「業」が消えたということです。だからこそ、大きな事はもちろん、ごく小さなことであっても、それによって「業」がなくなったことを「喜ぶ」べきなのです。
たとえ心からそう思えなかったとしても、理性を使って喜ぼうとする思いを持つことが大切です。
喜ぶことができれば、おのずと感謝することができます。どんな災難でも喜び、感謝すれば、もうそれは消えてなくなるのです。
災難に遭ったときには喜ぶこと。
その貴重な教えを与えてくださったのは、私が人生の師と仰ぎ、ことあるごとに様々な相談をさせて頂いていた元臨済宗妙心寺派管長の西片擔雪(にしかたたんせつ)老師です。
以前、京セラが医療用の人工関節を許可を受けずに製造、供給したとしてマスコミで大きく報じられ、非難を浴びたことがありました。
これには、そもそも許可を受けて人工の股関節を製造販売していたところ、医療関係者からの強い要望があり、また急を要するということもあってやむなく膝関節も製造した形になりました。しかし、私はそれに対して一切弁明をすることなく謝罪を繰り返しました。
京セラの本社の前には、連日テレビカメラが列をなし、私が頭を下げて謝る姿が幾度となくテレビで放映されました。私は身も心もすっかり疲れ切ってしまい、老師のところに相談にあがったのです。
老師はいつものようにお茶を点てて、私の話をずっと聞いてくださいました。そして、「それはよかったですね。災難が降りかかるときは、それぐらいのことで業が消えるのですから、お祝いしなければなりませんな」と言われたのです。
てっきり慰めてくださるものとばかり思っていた私は、老師がそう言われたのを聞いて、なんと冷たいお言葉だろうと思ったものでした。
しかしその言葉をかみしめるうちに次第に心が癒され、大いに慰められるのを感じました。
生きていて災難にあわない人はいません。それは思いもかけない時に、思いもかけない形でやってきます。
そんな時に意氣消沈し、絶望の淵に追い込まれるのではなく、「これだけの事で過去の業が消えたのだ」と喜び、感謝する。そして新たに新なる一方踏み出す。それは人生という厳しい旅路を生き抜くための、「秘中の秘」ともいえる策なのです。

謙虚さは、よい人生を歩むためのお守りになる。
人生の道を踏み外す元凶となるのは、必ずしも失敗や挫折ではなく、成功や賞賛なのです。
自分が持つ才能や能力は、決して自分の所有物ではなく、それはたまたま自分に与えられたものに過ぎない。私がやっている役割を他の誰かが演じても、何ら不思議ではないし、私の能力や才能も、私のものでなくてもいっこうにかまわない。
だからこそ、それを自分のためだけに使うのではなく、世のため人のために使うようにしよう。そう考えるようにしたのです。
なぜ、能力、才覚は自分だけのものでは無いのか?
人間に限らず、すべての生物を生物たらしめている属性ー肉体や精神、意識や知覚などーをすべて取り去ってしまうと、そこには「存在としかいいようのないもの」しか残らない。
それを書くとしてあらゆる生命は出来上がっており、また、その「存在の核」はあらゆる生命に共通のもので、それがときには花の形を取ったり、人間を演じたりする。
つまり「存在の核」以外のもの、私たちが普段自分のものと信じて疑わない体や心、思考や感情、もしくはお金や地位や名誉、能力や才能までがすべて借り物であり、みんなどこからか与えられた付属品に過ぎない。
こう考えてくると、「これは私のもの」「あの成功は自分の手柄」という考えには、何の根拠も実態もないことになる。そのことに氣づいたらおのずと驕りも高ぶりも消えて、そこに自然と謙虚さが生じてきます。
私たちが自分のものと考えているものは皆、現世における一時的な預かりものに過ぎません。またその真の所有者が誰であるのかを私たちは知る由もない。
そうであるからこそ、私たちはそれを自分のためでなく、世のため人のために使わなくてはならない。そうして、この世での生命の終わりが来たら、その預かり物を潔く天に返さなくてはなりません。
そういう思いで生きる時、心から驕りや高ぶりが消え、感謝の思いや謙虚さというもので満たされるようになるのです。

[憂世で生きる智慧]記事一覧
#憂世で生きる智慧 #仏教 #学び #最近の学び #気づき #日々の気づき #今日の気づき #名言 #格言 #ことわざ #人生 #今日の名言
今後ともご贔屓のほど宜しくお願い申し上げます。
