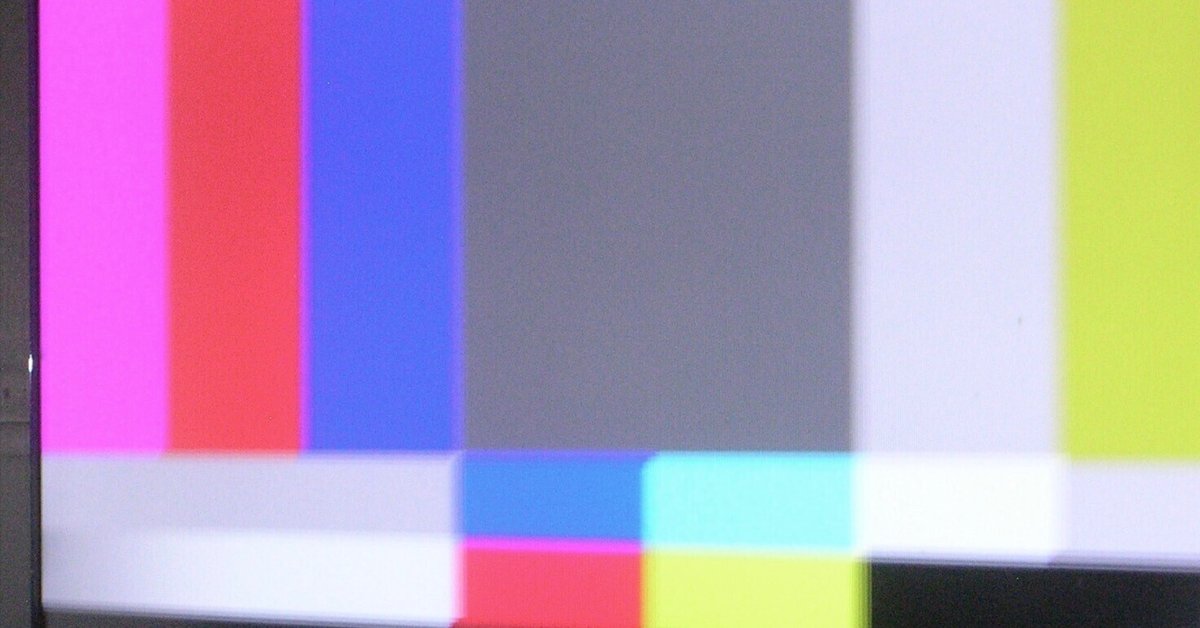
テレビについて㊲「ちむどんどん」が、これだけ批判される理由と、「ニーニー」のこれからを考える。
NHKの「朝ドラ」を見ている人は、みんなが視聴している前提で話をする人が多い。
私は、ほとんど見ていなかったので、そうした話題は分からないのだけど、このところ、インターネット上で、今の「朝ドラ」が、かなり批判されていることを知った。
私より、妻の方が日常的に「朝ドラ」を見ているので、そんな話をしたら、妻にとっては、主人公の兄は許せないけれど、主人公は、自分の気持ちを優先させて、困難があっても諦めない、という印象だと語っていて、「#ちむどんどん反省会」とは、ギャップがあった。
どうして、こんな違いがあるのだろう?
潮目をよむ
最初に反射的に思い出したのは、最近読んだ本のことだった。
自分で考える能力を育むことをせずに成人し、「みんなと同じ」であることを短期的に確認することでしか自己を肯定できない卑しい人々が、週に一度失敗した人間や目立った人間から「生贄」を選んでみんなで石を投げつけ、「ああ、自分はまともな側の、マジョリティ側の人間だ」と安心している。
たとえば能力は高くないけれど、なにか社会に物を申したいという気持ちだけは強い人がいまインターネットで発言しようとするとき、彼/彼女はその問題そのものではなくタイムラインの潮目のほうを読んでしまう。そしてYESかNOか、どちらに加担すべきかだけを判断してしまう。
この見方は、かなり辛辣と言ってもいいとは思うけれど、そうとしか考えられない出来事も少なくなく、だから、今回も、この「潮目を読む」ことが重視され、「ちむどんどん」が「生贄」のよう認定されているから、安心して叩くことが盛り上がっている部分もあるのではないか、と思った。
この批判を、「いじめではないか」と指摘する声まである。
1980年代
ただ、その批判の内容に、当然ながら納得のいくこともある。
例えば、時代設定に関しては、変だと思った。
「経験の浅い」視聴者ではあるのだけど、第90話から、見始めた。 主人公が結婚式を挙げたのが、1979年の設定だった。
それから、しばらく見ているけれど、おそらくは時間が経って、1980年代に突入しているはずなのに、画面に映っている時代の雰囲気は、そこからさらに10年くらい前の昔に見えた。
1980年は、田中康夫の「なんとなくクリスタル」の舞台になった年だ。
1980年東京。大学に通うかたわらモデルを続ける由利。なに不自由ない豊かな生活、でも未来は少しだけ不透明。彼女の目から日本社会の豊かさとその終焉を予見した、永遠の名作。
山下達郎の「フォー・ユー」が発売されたのが1982年。
ある意味で、すでに「浮ついた」空気が街中にあったはずなのに、「ちむどんどん」の世界では、そんな気配はなく、食い逃げがいるような時代でもあるので、やはり、10年は前(あるいはもっと昔)のことに思えてしまう。
空気を読まない
そんなに批判内容を詳細に検討したわけでもないのだけど、主人公・暢子の「空気を読まない」行動が、かなり非難されている印象がある。
暢子は披露宴で、「うちは沖縄料理のお店を開きます!」と宣言するのだった。
主人公は、現在イタリア料理店で働いていて、そこが披露宴の会場になっているにも関わらず、そんな発言をすることに対して、空気を読まない。わがまま、という批判がされていたのだけど、見ている私は、それほど気にならなかった。
何しろ「ちむどんどん」というタイトルだから、自分のワクワクが一番大事な主人公なのだろう、と思っていたせいもある。
さらには、この1970年代末から1980年代あたりの時代には、こういう人たちがたくさんいたから、それを知っている人間には、こうした「自分の思いを優先する言動」に、それほど抵抗がないことに気がついた。
もしかしたら、このドラマに関しては、現在の50代から70代くらいの年齢層の方が受け入れやすいのではないか。その一方で、特に同調圧力が高まったこの30年で育った人たちにとっては、主人公の行動は、我慢がならないのではないだろうか。
だから、もしかしたら、批判をしている人たちは、年齢層が30代以下ではないかもしれず、このドラマの評価に関しては、世代によって全く違い、それこそ「ジェネレーションギャップ」といえることなのかもしれない、と思っている。
脚本家
この記事↑の中で、今回の批判の対象にもなっている脚本家・羽原大介氏のこうした話がある。
そんな羽原氏が「山原編」で涙を流しながら執筆したシーンがある。それは自分のやりたいことが見つからず、モヤモヤしていた暢子が料理部の助っ人として「産業まつりのヤング大会」に出場。第4週の最後に「東京に行って、料理人になりたい」と宣言する場面だという。
脚本家の思い入れが強い、この場面に関しては、視聴者からは好意的な反応もある一方、批判的な見方も少なくないようだった。
「テンション上がっちゃって、その気になって後先考えずに宣言しちゃう暢子、やっぱり賢秀の妹ーーー!!」「ここで場の空気にテンション上がって自分の気持ちを伝えてしまう賢秀の妹なのよ暢子」などと、長男の賢秀(竜星涼さん)と比較するコメントも見られた。
これだけ感じ方が違うとすれば、そのギャップは、これからも埋まらないと思う。
ポジティブというより自分勝手が過ぎるのではないだろうか?
『めちゃくちゃ周りに協力してもらってるのに』『いい加減にしろ』『暴走&暴走で孤独を感じるって自分勝手すぎるでしょ』
こうした批判を受けている主人公の言動や行動も、脚本家も含めて制作側は、「ちむどんどん」な行動として肯定しているのだろうから、これから先も、「#ちむどんどん反省会」は、盛況が続くのだと思う。
そうなれば、私のように、そのことで興味を持って視聴を始めるような人も、少しずつ増えていくのかもしれない。
1970年代のドラマ
脚本家・羽原氏は1964年生まれ。
もちろん、すべてを世代で語るのは愚かだと思うけれど、特に若い時の価値観は、その後にも影響を与えると考えられる。
羽原氏が10代であった1970年代後半の、若者のドラマして代表作の一つとも言えるのが、「俺たちシリーズ」だと思う。
カースケはバスケットボール部のキャプテンでエースであったが、就職活動はほとんどせず、アルバイト中心でその日が楽しければよいというタイプ
主人公は、この「カースケ」だが、3人の同世代の男性のドラマだった。
一旦は3人とも勤め人になるも、結局、正直すぎた彼らは不条理な社会の慣習や人間関係に縛られることを嫌い、同じ下宿の東大志望の浪人生ワカメと4人で「なんとかする会社」を立ち上げ、自由奔放、独立独歩の生活をする決心をしたのであった。
紆余曲折を経てオッスは父からもらった資金を元手に、遂に念願のヨットでの航海に出ることになる。
もちろん、物語の基本構造の中に、主人公が自分の思いを叶えていく、というパターンはあるものの、そして、この時代のドラマの全てが、夢が大事だ、と言うことではないにしても、それ以降も、この「自分の思いに忠実に生きる」スタイルのドラマがとても多かった記憶がある。
さらに、こうしたドラマは再放送もされていたはずだ。
同調圧力
それに、同調圧力が、今ほど強くなかったと思う。
就職活動といえば、21世紀の現代では、誰もが黒のスーツを着るのが「常識」になっていて、その中で、違う色(例えば紺でも)を着ていたら、おそらくは「空気を読まない」人間として、静かに排斥されそうだけれども、例えば、1980年代の就職活動のスタイルは、今から見たら、多様性がある。
1983年には伊勢丹が女子学生向けの就活スーツを売り出します。以降、バブル期まで女子学生のリクルートスーツはスーツだけでなく、ブレザー、ワンピースなどが混在することになります。1988年刊行の『女子学生のためのリクルートファッション大研究一九八九年度版』(ビジネス・コミュニケーション・リサーチ、ぱる出版)では現在のリクルートスーツに近い、無地スーツでも「ストライプの開襟シャツを重ねて着るとシャープで都会的な印象」と紹介。他にシャネルスーツなど10着以上が登場します。
脚本家・羽原氏も、この1970年代以降の時代を生きてきて、影響も受けているとすれば、「自分の思いを大事にする」≒「ちむどんどん」の行動を主人公がとるのは必然でもあるだろうし、その世代の価値観を持っている視聴者や、世代に関わらず「自分の思いや意志を優先させる人」には、「ちむどんどん」は受け入れやすいドラマなのだと思う。
ただもう少し考えれば、同調圧力が強まってもいるのだけど、1970年代以降、時代が進むことによって、確実に野蛮さは減っているはずだ。
それは、周囲に対して気を使う人が増え、世の中に繊細さが増していることでもあるので、「自分の意志を優先させる人」の見え方が、以前と比べて、より「わがままな人」として非難の対象になりやすい、ということでもあると思う。
だから、一概にはいえないし、繰り返しになるけれど、この30年を生きてきた世代と、それ以前に生まれて育った人たちでは、「ちむどんどん」というドラマへの評価が、思った以上に分かれるのかもしれない。
嫌われる「ニーニー」
4月から見続けてて、主人公の行動に対しては、それほど批判的ではない妻も、その兄・賢秀に対しては「ニーニーは嫌い」と真面目な顔で言うくらい本気で怒っている。
私は、8月から見始めた「初心者」なので、それほどピンと来なかったが、それでも、さっそく、やらかしていた。違法である「ネズミ講」にきれいにだまされ、そのために妹の開店資金まで失うことにつながった。
当然のように批判が集中し、妻にも、また「ニーニー」は嫌われていたが、私が気になったのは頭のベルトだった。
「頭が良くなるベルト」
妻に聞いたら、それまで「ニーニー」は、ずっと頭につけていた、という。それは、懐かしいものによく似ていて、自分が子ども時代に雑誌の後ろの方のページに広告があった。個人的な記憶では、2大「頭が良くなる」(と言われる)グッズを思い出させるものだった。
一つは暗記枕。録音機能がついていて、寝ている間に英単語などが覚えられる、と言うもの。そして、もう一つが、脳を冷やして働きを最高潮にする、というベルト。
「ニーニー」がしていたのは、後者の「ベルト」を原型にしていたものだと思う。そして、どちらにしても、「頭が良くなる」が謳い文句だったけれど、そのベルトは勉強中に使って、頭の働きを良くする、という「機能」(?)が広告で説明されていたが、当時から、その怪しさについては、小学生の間でも語られていた。
それを本当に購入してしまう時点で、「やばいやつ」扱いされてもおかしくなかった。(でも、ちょっと欲しいと思う瞬間はあった)。
まして、生活している時までずっとつけている人間は見たことがなかったし、もしもいたら、本気で人から避けられていたと思う。
「ニーニー」の気持ち
子どもの時だけなく、大人になっても、「頭の良くなるベルト」を、ずっとつけていた「ニーニー」の気持ちを少し想像してみた。
自分の名前は賢秀で、親の願いとしては、かなりはっきりと「頭の良さ」を求められているのは間違いなく、そのことは、「ニーニー」自身も知っていたはずだ。
だけど、どこかで、自分自身が、決して頭が良くないのではないか。というか、人より劣っているのではないか。
そんな不安があったのだと思う。
「宇宙磁石のパワーでどんどん頭が良くなる魔法のバンドさ〜!
これで俺は沖縄の一番星になるわけさ〜!」
そんな思いがなければ、中学生で、この「頭の良くなるベルト」を欲しがらないだろうし、大人になっても、このベルトをつけ続けているのは、少しでも頭が良くなりたい、という思いがあったのではないだろうか。
もし、そんなベルトを大人になっても装着している人がいたとすれば、それは「だましてください」と言っているようなもので、何度も詐欺のような被害にあい、その上で、家族のためになりたい、という気持ちだけは本物だから、余計に迷惑が広がってしまう。
そんな「ニーニー」のことを思うと、私自身は、視聴時間が少ないせいか、頭に来る前に、なんだか切なくもなる。
この第93話で、ネズミ講の会社に乗り込む前に、その後の行動が、さらに周囲に迷惑を広げてしまうのだけど、その時に、「ニーニー」は、頭からベルトをはずす。
その後、いろいろなことがあったあと、何度もやめているのに、何度も受け入れてくれている養豚場に頭を下げて戻るのだけど、その時も頭にベルトはなかった。
だから、もしかすると、「頭が悪い自分」をきちんと見つめて、認め、その上で頑張っていこうという決意と覚悟をしたのではないか。
もしかしたら、「頭が良くないといけない」といった「呪い」が、やっと解けたのかもしれず、だから、この後は「ニーニー」・賢秀は、地道で自分ができる努力を蓄積して、本当に賢くなるのが、このドラマのもう一つのゴールではないか、と思っている。
だけど、それが違ってしまったら、妻と同じように「ニーニーは大嫌い」になるかもしれない。
今日も「ビッグになる」という不吉な言葉を「ニーニー」は言っていたし。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。
#テレビドラマ感想文 #コンテンツ会議 #ちむどんどん
#ドラマ #俺たちの旅 #俺たちの朝 #羽原大介
#リクリートスーツ #同調圧力 #批判 #毎日投稿
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
