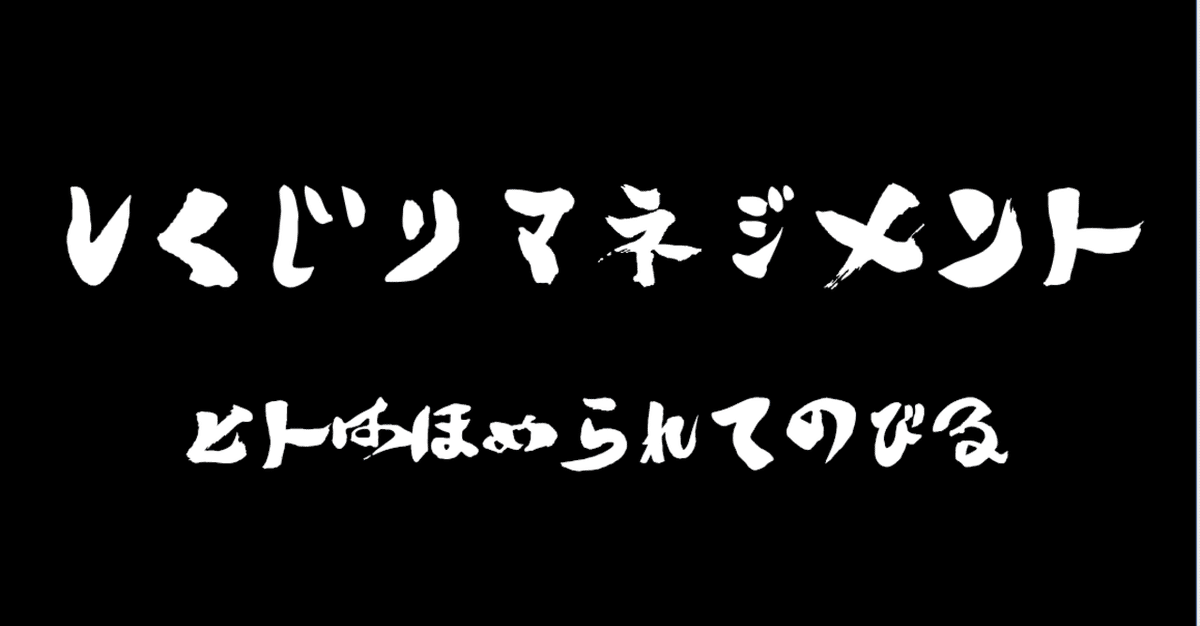
「褒めているつもりの上司」と「もっと褒めてほしい部下」のチグハグ治療法/しくじりマネジメント
メンバーのこと、ちゃんと褒めていますか?一説によると、褒めているという回答をする上司は50%。上司が褒めてくれるというメンバーは10%程度です。
ちなみに調査元は僕の経験則です笑
でも、たぶん、結構当たっていると思います。
今日はそんなチグハグの正体について、僕の経験を踏まえながらメンバーマネジメントについて書きたいと思います。
そもそも、褒める必要あるの?
ここに疑問をもたない方は次の章に読み飛ばしてください。
褒める必要性はなぜでしょうか。
「そんな大したことしていないのに」「自分が若手の時は褒められたことなんかないぞ」「褒められなくても歯を食いしばってやるのが大事なんだ」
僕も同感です。
相手に褒めてもらえるかどうかではなく、自分がやりたいと思ったことができているか。自分の目標や目指したことに到達しているか。そこで判断すべきだと思います。
ですが、残念ながら時代は違います。人による違いや濃淡はありますが、自分のやったことを認めてもらいたい。褒めてもらいたい。というメンバーは非常に多いです。
なんで、日本はそんなことになったのか?
教育制度上の思想が反映されています。
端的に言うと、子供のころから親や先生に褒められ続けて育ってきた人が非常に多いのです。つまり承認欲求が満たされ続けて、育ってきたのです。
だから、自分の承認欲求が満たされないと、モチベーションが湧きにくくなるんですね。
反発したい気持ちもあるかもしれません。でも、彼ら彼女らが悪いのではなく、育ってきた環境が違うのです(個人差がある前提です)
どんな思想だとしても、せっかく入社してくれた新人・若手が育ってくれないと困りますよね?
キーワードはHMK。
「褒める」「認める」「気に掛ける」です。dai語です(今勝手に作りました)
ご唱和ください。せーの「H・M・K」
褒めているつもりの上司と褒めてもらえないメンバー
実際にあったマネジメント場面をご紹介したいと思います。皆さんも自分ならどうするか、ぜひ考えてみてください。
あるメンバーが自分で資料を作成し、お客様に提案をしました。内容的にも顧客の考えを図解しながら、丁寧にまとめられており、色使いもセンスがあり、非常に分かりやすいものでした。お客様には真剣に話を聞いてもらうことができました。一通り説明しきることはできましたが、非常に丁寧な性格のため、説明にやや時間を使いすぎてしまい、お客様が提案をどう感じたのか、感想を確認することはできず、その日は商談時間が終了となりました。
さて、皆さんなら、メンバーにどのように声をかけますか?
↓
↓
↓
↓
↓
僕はこうでした。
「企画書の構成すごく良かったね。ただ、タイムマネジメントを今後はうまくやった方が良いと思うよ。次のアポまでに、これとこれをやった方が良いと思う。頑張ろうね」
さて、皆さんはこの僕の声掛けはどう感じますか?
今の僕なら、こうは伝えないと思います。
ここには3つのしくじりが隠されています。
しくじり①.異物混入事件!余計なアドバイス
コミュニケーションスキルで『YES & BUT』という話は聞いたことはある人もいらっしゃるかと思います。いきなり相手の話に「でも・・・」と否定から入るのではなく、「確かにそうだよね。でも・・・」のようにまずは肯定・共感を示したうえで、相手に意見をぶつける、という手法です。
ですが、これも使えば良いって、ものではありません。
今回の失敗エピソードで言うと、結局前半に褒めている風ではありますが、メンバーの記憶に残るのは『タイムマネジメントがダメだった・・・』ということです。自己肯定感の高いメンバーであれば、問題ないかもしれませんが、自分に自信が持てていない(褒めてもらいたいと思っている)メンバーなら、なおさらです。
アドバイスはアドバイスで良い(というか、しないといけない)ですが、その場で一緒に伝えるべきか、冷静に考えてみてほしいです。致命的な問題でなければ、別の機会で伝えれば良く、その場で全部伝えきってしまいたいのは、上司の怠慢です。
楽をしたいなら、なおさら急がば回れです。メンバーにアドバイスしたい気持ちはぐっと抑えて、褒めるときは褒めることに集中しましょう。
しくじり②.すり替え事件!ヒトを褒めていない。コトを褒めている
問題の要因を見つけるときにコトとヒトを分ける。ということが言われることがありますよね。褒めるときも同じです。
その人が出したアウトプットを褒めているのか、その人を褒めているのか。ということを使い分ける必要があります。
個人的には「ポジティブなことを伝えるときはヒトに着眼すること」
「ネガティブなことを伝えるときはコトに着眼すること」です。
例えば、何かミスが生じたときに『誰の作業が間違えていたのか?』ということを調べるのではなく、 『なぜそのミスが生じたのか?』原因を探しをすることを指しています。
では、褒めるときはどうか。
上記の失敗エピソードで例えると『企画書の構成』を褒めるのではなく、企画書の構成をつくった『●●さんの構造を捉える力』を褒めてあげるイメージです。ポジティブなことを伝える(=褒める) ときには、ぜひ意識してみてください。
しくじり③.仕事強奪事件!メンバーの役割を奪っている
メンバーに任せた仕事をきちんと任せきることはできていますか。
僕はできていませんでした。
もちろん、場面によっては上司の介入が必要な場面もあると思います。
メンバーが望んでいなくても、どうしても必要性が発生することもあると思います。
ですが、今回のエピソードではいかがでしょうか。
喫緊で顧客に迷惑をかけているわけでもないですし、メンバーの動きが悪すぎることもありません。もちろん、メンバーからアドバイスを求められているわけでもありません。
ですが、自分の気持ちよさだけが理由で勝手に『自分ならこう動く。こうしろ』と指示をしてしまっているんですね。僕としてはもちろん命令をしたかったわけでも、指示をしたわけでもありません。単なるアイデアです。
ですが、メンバーからすると「上司にこう言われたし・・・」と考えることを止めてしまい、それ通りに動いてしまいます。そして、それがうまくいったときにメンバーが思うのは「全部、上司のおかげです・・・」
こうなることを望んでいるわけではないですよね?
メンバーの手柄を横取りしたいなら、今すぐ管理職を止めた方が良いでしょう。メンバーが自律的に成長し、成果を出すことを目指すなら、黙って見守る努力が必要だと思います(これがなかなか難しいのですが^^;)
褒めるところがどうやっても見つからない・・・
さて、3つのあるあるについてはご理解いただけましたか?
最後にお伝えしたいのは、メンバーの褒めポイントが見つからないときにどうするか?です。
きっとこんなことを感じた経験がある上司も多いと思います。
ですが、本当にそうでしょうか?
それはあなたの基準で考えるから、すごいと思えるところがないだけではありませんか?
褒めるというのは、すごいところだけを見つけて、伝えれば良いというわけではありません。注目するのはメンバーの変化です。そのメンバーが過去と比較して変わったところを見つけ、褒めてあげるのがポイントです。
女性の髪形の変化と同じですね。感じた変化をそのまま伝えてあげるのが、メンバーにとって非常に大きなパワーになります。
終わりに・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。今回の記事が参考になれば、ぜひ「スキ」や「フォロー」をいただけると励みになります!
今後もマネジメント場面における悩ましい場面を失敗談をベースにナレッジをnoteで発信していきますので、良ければフォローいただき、またご覧いただけると嬉しいですmm
また、良ければTwitterやFacebookでシェアをいただけるとすごく嬉しいです。Twitterの僕のアカウントはこちらです。完全に今更ですが、最近始めました。いくつになってもチャレンジは大事ということで^^;
こちらもあわせて、よろしくお願いしますm(__)m
応援いただけると、非常に嬉しいです。 全力でいい記事を書きたいと思います。 よろしくお願いします。
