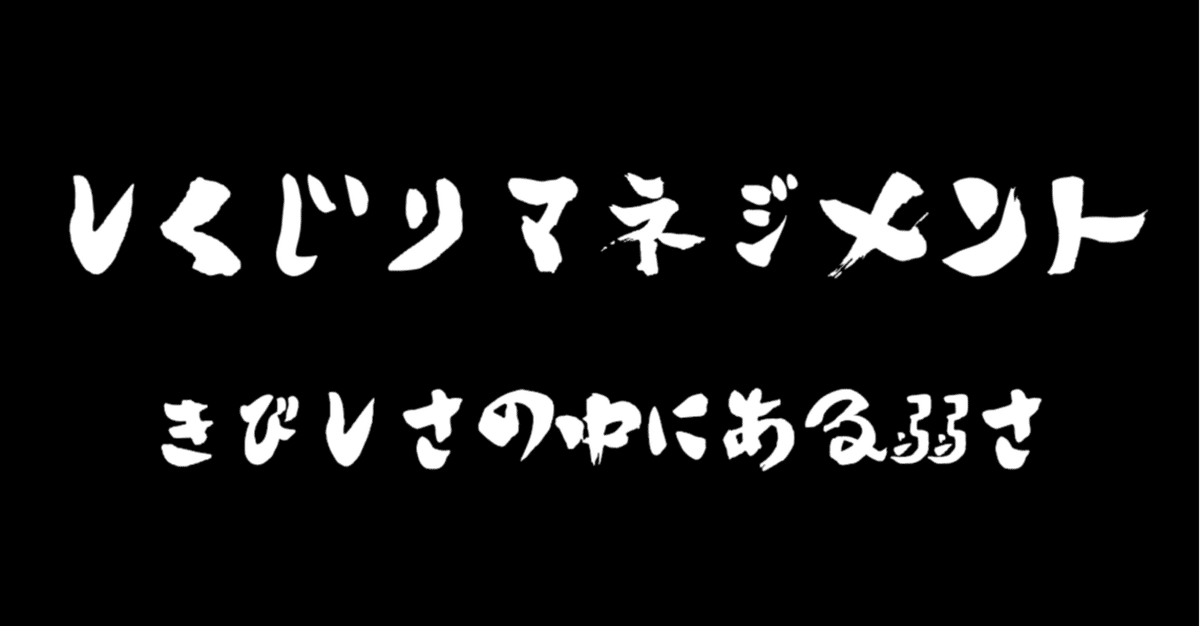
仕事はできるけど周囲に厳しい人への関わり方/しくじりマネジメント
経験豊富で頭の回転も早く、その人に任せておけば問題を解決してくれる頼もしいメンバー。・・・でも、周りの人に対して厳しくて、協働する人からはクレームが入る・・・
そんなメンバーを経験したことがある管理職の方やチームのリーダーを務める方は多いのではないでしょうか。
プロフェッショナルな人ほど、仕事に対して責任感が高く、自分だけではなく周りにも高いレベルの仕事を求めるため、周りがついていけず、「あの人とは仕事したくない・・・」と煙たがれてしまうこと、ありますよね。
僕にもそんなメンバーの経験があります。
任せた仕事はきっちりとこなしてくれるものの、周りとはうまくいかない・・・そんなメンバーに対するマネジメントの失敗とそこから学んだマネジメントノウハウについて、今日はお伝えできればと思います。
”周囲に厳しいこと”を指摘した失敗
あるメンバーのAさんは、非常に仕事も早く、的確で、分からないことがあっても過去の前例を自分で調べて、完璧な対応を行うメンバーでした。
一方でその完璧さは周囲にも求める傾向があり、「これ間違えていますよ。前も言いましたよね?」「手順が違いますよね。目的分かってます?」と周囲を威圧する言い方も相まって、周りの人からは「あの人は厳しすぎる」「仕事がしにくい」「なんであんな言い方をされないといけないのか」そんな声が上がっていました。
Aさん自身はというと、周囲を威圧したいわけでもありません。シンプルに間違った仕事をしてはならないのでちゃんとしたい。というだけでした。
ある時、Aさんに「もう少し周囲に優しくしてはどうかな。周囲からも怖がられてしまうと良くないと思うよ」と伝えたところ、「なんで私は間違ったことをしていないのに自分が変わらないといけないんですか?」「言ったことをやらない方が悪くないですか?」と返ってきました。
「まぁ確かにそりゃそうだ」
正論を言い返されてしまい、それ以上、フィードバックをすることはできませんでした。
周囲に厳しいことは”何が問題なのか?”を見極める
厳しいという事実は間違っていることではありません。言い換えると、人に対する厳しさをもっている性格が悪いわけではないのです(ただし、相手を見下す発言や侮辱する発言のような、いわゆるハラスメントと言われるような言い方については問題があります)
事実を相手に率直に伝えているだけで、それを「厳しいと捉えるのか」「端的で率直と捉えるのか」は人によって異なります。つまり、受け取り側の問題と考えれば、Aさんの言い方そのものに問題あるわけではないと捉えることもできます。
ポイントとしてはその発言・行動によって何が起きているのか?ということを押さえることが大事です。Aさんの厳しさが問題なのではなく、問題によって起きている影響・事象に問題があるのです。
例えば、Aさんの厳しい言い方によって、他組織から協力を得られなくなってしまった。もしくは協働したくないと言われている。この場合はどうでしょうか。
その組織から協力を得られなくても目的を達成できるなら、特に問題はないかもしれません。ですが、組織間の関係性が悪化することにより、自部署のパフォーマンスが下がる・仕事に支障が出ることがあるなら問題になると思います。
問題の捉え方は様々です。周囲への厳しさというパーソナリティを問題と捉えるのではなく、その影響として事象に問題を設定しましょう。
ではこの周囲に厳しい人はどのような特徴があり、具体的にどのように接すると良いのか、僕なりの考え方をお伝えしたいと思います。
周囲に対して厳しい人の特徴と対応方法5選
①プライドが高い
このタイプはプライド・自尊心が高いことが多いです。そのため、ヒトではなくコトに課題設定をすることがポイントです。
『あなたが悪いわけではない。否定しているわけではない。だからあなたが改善すべきということではない。でも起きている事象について改善する必要性があると思っている』ということを伝えるイメージです。
この事象の解決を考えたいんだけど、どうしたら良いと思う?と『相談させてくれ』というスタンスで会話するのも1つだと思います。
②理想が高く完璧主義
このタイプは高い目標を掲げている人が多いです。ビジョン的なものであれば良いですが、どちらかというと完璧主義に近く、自分に厳しく、相手にも同じことを求めます。
そして、その理想(完璧である状態)というのはどんどん高まるため、満足することはなく、どんどん自分に厳しくなり、人にも厳しくなるというループに陥ります。
あなたが管理職であれば、クオリティコントロールを心がけましょう。つまり、ゴールの状態やOKといえるレベル感は、あなたが定義できると思います。度を越えたレベル感を相手に求めるようであれば「目指すレベルはここ。ただしこのレベル感で仕事ができればOKラインである」ということを設定することで、周りにその厳しさを求める必要はないことを伝えるのが良いと思います。
③自分が正しいと思っている
このタイプは多数決的な考え方はしません。みんなの意見やみんなで判断ではなく、正しい意見をだし合理的に判断をすべきだと考えています。そのため、多数派というだけで意見に従うことはせず、自分の正しさを大事にしています。
例えば、「みんなが●●と言っている」と伝えると、具体的に誰なのか。何人なのか。なぜそうなったのか。ということが気になるのです。
チームワークやアットホームさを大事にする管理職だとすると、このタイプの言動には非常にもどかしい気持ちになると思います。ですが、その考え方そのものは肯定も否定もできません。
むしろ、考え方そのものは認め、理解してあげることを心がけてください。そのうえで『客観的に見た合理性があるか、自分にとっての合理になっていないか』を上司として冷静にみることが大切です。
④ポリシーがある
このタイプは自分なりに大切にしていること、その背景を明確にもっていることが多いです。
・給料をもらっている以上は妥協してはならない。
・責任をとれないので間違ってはいけない。
・失敗をすると自分の存在価値がなくなる。
いろんな背景がありますが、自分にとって大事にしていることがあり、それを貫くために周囲に対しても自分に対しても厳しくしていることがあります。
彼・彼女が大切にしていることに理解を示し、発生している影響・事象を解決するためにとるアクションは大切にしていることを侵害するわけではないことを丁寧に伝えてあげると良いと思います。
⑤意外と怖がり
このタイプは自分に自信がないという弱さから、虚勢を張っていたり、何層にも殻を被ったような状態になっていることが多いです。その殻を急に破ろうとするのではなく、少しずつ剝がしていくようなイメージで関わることが重要です。
卵から雛が孵る際には、中と外から同じ場所を突きあうことで殻を破ると言いますが、まさにこのイメージです。外からお前が変わるのだ。と刺激を与えて突くのではなく、中からも突くようになることが重要です。つまり、本人が変わろうとしない限り、変わらないということです。
周囲への厳しさとは反対に弱さ・脆さをもっていたりします。だからこそ、この人の一番の味方になることが大事です。心理的安全性がないからこそ、周囲を攻撃する。自分の地位を確立しようとします。相当な忍耐が必要にはなりますが、あなたがまずこのタイプを信頼することで少しずつ心を開いてくれることに近づきます。
別の記事にも書きましたが「信頼してくれるメンバーを信じるのではなく、信頼するからメンバーが信じてくれる」という順番です。順番を間違えてはいけません。
多数派の意見に同調するのではなく、少数派(というか孤立化)しているメンバーの声にじっくりと耳を傾けてほしいと思います。
終わりに・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。今回の記事が参考になれば、ぜひ「スキ」や「フォロー」をいただけると励みになります!
普段は「漫画×マネジメント」をコンセプトに「もしあのキャラをマネジメントするなら」ということで、様々な漫画キャラをビジネスパーソンという設定で考えた時の強みや弱みをどのように捉えて、マネジメントを行うのか、僕の考え方をお伝えしています。
ぜひ、こちらも合わせて、ご覧いただけると嬉しいです。
応援いただけると、非常に嬉しいです。 全力でいい記事を書きたいと思います。 よろしくお願いします。
