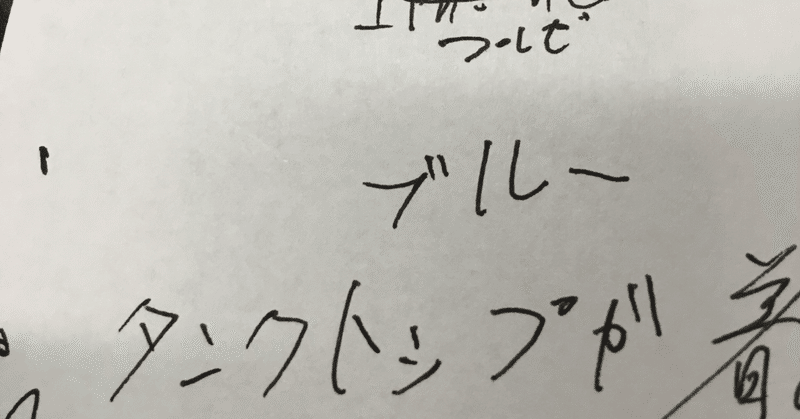
あたしの親友 ごん
【※長いからといって面白いという保証はできません。ひますぎて困り果てているんだ!という方は、そのまま読み進めてみてください。】
18歳の4月。
初めてに近い顔合わせなのに、その人はあたしの言動の一つ一つに笑いをこらえているようだった。いや、もしかしたらそんなことされてないかもしれないけど、そんなことされたような気がする感じの方が強い。
一方で、あたしもあたしでなぜか何かおかしくって、いちいちニヤニヤしていたような気もする。そう、ゆっくりと思い返すとそんな、気もする。
その人の話はいつもおかしくって、なんでも作り話にも思えて、あたしも負けじと変な話ばかりした。少しでも言葉を交わすとふざけ合って、くだらないことで笑いすぎてしまう、そんな間柄に、気がついたら、なっていた。
・
・
・
恋愛相談もたくさんしたし、たくさんされた。いや、されてない。あたしが勝手にお節介やいただけかもしれない。簡単には明かせない家庭の話しもしたけど、なんとなく悟られていた部分もあったし、その人の周りにはあたしみたいな人が集まってしまうそうだった。
その人の語彙は常時 中学生ばりにつたないのに、話しづらい話になると妙に勘だけは鋭くなって、なんでもないときに核を突いてくるのだった。
その人には、車にもたくさん乗せてもらった。その行き先のほとんどは、サークルで番組を持っていたコミュニティFMのラジオ局。その白い中古の軽には4人で乗った。そのむさ苦しいやつらとは、なぜかいつもちょうど予定が合って、月に2回 片道2時間を通った。行きの道中も収録中もその編集中も、そして、また帰りも助手席と運転席で、くだらない話は枯れなかった。
・
・
21歳の11月。
白の中古の軽は夜中の3時に迎えに来てくれた。(いや、白の軽は夏のラジオ収録の帰りに故障してめちゃくちゃ大変だった。それでその時はワインレッドの新車の軽になっていたような気もする。)その日は、日付をまたいでどうにも受け入れられない、悔しいことが降りかかって、誰よりも深い夜の中にいた。ふわっと顔が浮かんでラインしてみたら、すでに日付は変わっている時刻だというのに、すぐに、返事が来た。アパートの外に出てくるように、と。
ださい寝巻き姿で、外に出ると、白だかワインレッドだか、軽がやってきた。やってきた、けど、敷地に入ってすぐ停車すればいいのを、なぜか建物の裏まで進んで駐車場の一番奥まで行って、ようやく軽は停まった。後部座席のドアを開けて、短く挨拶をして、乗り込む。
お互い無言だったけれど、笑い出すのに言葉は要らなかった、停車したはいいもののたくさんある駐車場の柱のせいで何回切り返しても出られなかったからだ。
太った猫が我々を見て、つまらなさそうに闇へ帰っていった。その人はそんなのに気づく余裕もなく、DとR 行ったり来たり、何回も何回も切り返していた。おかしくって、おかしくて、もうここから出られなくてもいいのに、とも思った。笑い過ぎて、でも、ここから出られない車と、うじうじ悲しんでいるあたしが重なったような気もして、ようやく駐車場を出るところにはもうすっかり顔はぐしゃぐしゃだった。
・
・
・
・
お互い社会人になって、離れたところで暮らすようになった今でも、たまにラインをする。だいたいは、あたしからリンクを送るだけのことが多くて、それで、返事が来ないことがほとんどで、ほぼメモ帳状態だ。だけど信じてやまない。勝手に『唯一の、異性の親友』だと思っている。
そんなことをさらっと書いてみると、よくもっともらしく投げかけられる「男女の間に友情が生まれると思うか?」みたいな質問の存在を思い出す。個人的に、それはこの世で一二を争うほどどうでもいい問いかけだと思っている。異性との友情を信じている人には、異性の友達がいるし、そうでない人は、そうでないだけだ。
・
・
・
23歳の7月。
別々な場所で暮らし始めてから一年以上ぶりに彼を訪ねた。たくさんあの白い軽に乗せてくれた彼を、あたしはドライブに誘った。感謝の気持ちも込めて、彼が行きたいと望むところに連れて行きたかったのだ。が、行きたいところを聞いても特にないようだし、何しろどんくさい彼なので、自分が生まれ育った街なのにナビを使わないと案内ができなかった。
ちゃんと行けたのは、彼の街に新しくできたリゾートを演出しきって違和感さえ当たり前のような某カフェくらいで、あとはほとんど当てもなくアクセルとブレーキを交互に踏んだ。どこに行くでもなく走るレンタカーの中で、またあの時のようにくだらない話をたくさんした。会っていなかった一年以上の月日を手早く埋めて、ノンストップで話し続けた。
あたしが会った残念な男の人の話。その人があたしにした質問が的外れすぎて、彼はそのセリフがいたく気に入ったようで何回も誇張して真似をして、レンタカーは橋でつながっている島を目指した。
ランチもディナーも忘れて、運転し続けて話していたらどこからか花火の上がる音が聞こえた。いつのまにか夜になっていて、いや、そんなことより、その日は夏祭りだった。音のする方向を探したら、見え、た。見えたというか、花火の左斜め上だけが。あとの半分以上は森が邪魔して見えなくて、それがまた本当におかしかった。打ち上げ花火、上からでも横からでもなく、森越し?山越し?に見た。音だけは確かに届いて、すごく夏だった。
・

・
あたしは、彼に思い出したように問う、
「結婚はまだか?」
彼には、小さくて少女みたいな恋人がいる。はるちゃん。高校生のころからの付き合っていて、もう老夫婦並みに完全な2人だから、早く結婚すればいいのにと思う。
はるちゃんは、体が華奢で声も高くて可愛い。ちょっと風変わりで友達といるところを見たことはないけど、あたしとはるちゃんはボランティア団体でリーダーをしていたこともあった。もうずいぶん会ってない。
急かしたあとに、余計なお世話だなぁと気づくけど、本当に心から願っている。遅かれ早かれそうなるだろうけど、幸せになってほしいと。今度は2人とご飯でも行きたい。あたしは、あたしの周りの人が幸せになることで、幸せを感じたい。
・
・
・
あたしの人生におきた、あたししか知らない出来事や感情を、ずいぶんたくさん彼には簡単にこぼしてきた気がする。行き場のないものごとが彼には自然と集まるようだから、あたし以外の人もきっとそうなのだろうと想像する。
最後の空港に流れなかった奏とか、抜け出せなかった駐車場も、半分しか見えなかった花火もそう。深夜のサービスエリアの焼きおにぎりの自販機とか、新車で流したまま返してないCDとか、歳の離れた腹違いの兄弟とか、後部座席にいる誰にも歓迎されない男の子同士のカップルとか。
きみはきっと証人。この世からなかったことにされてしまう、小さな、なんでもない、でも、確かに存在する・していた、そのひとつひとつを知っている。あたしがいたことも証明できる。
「ツ」と「シ」は未だに書き分けられないけどね。
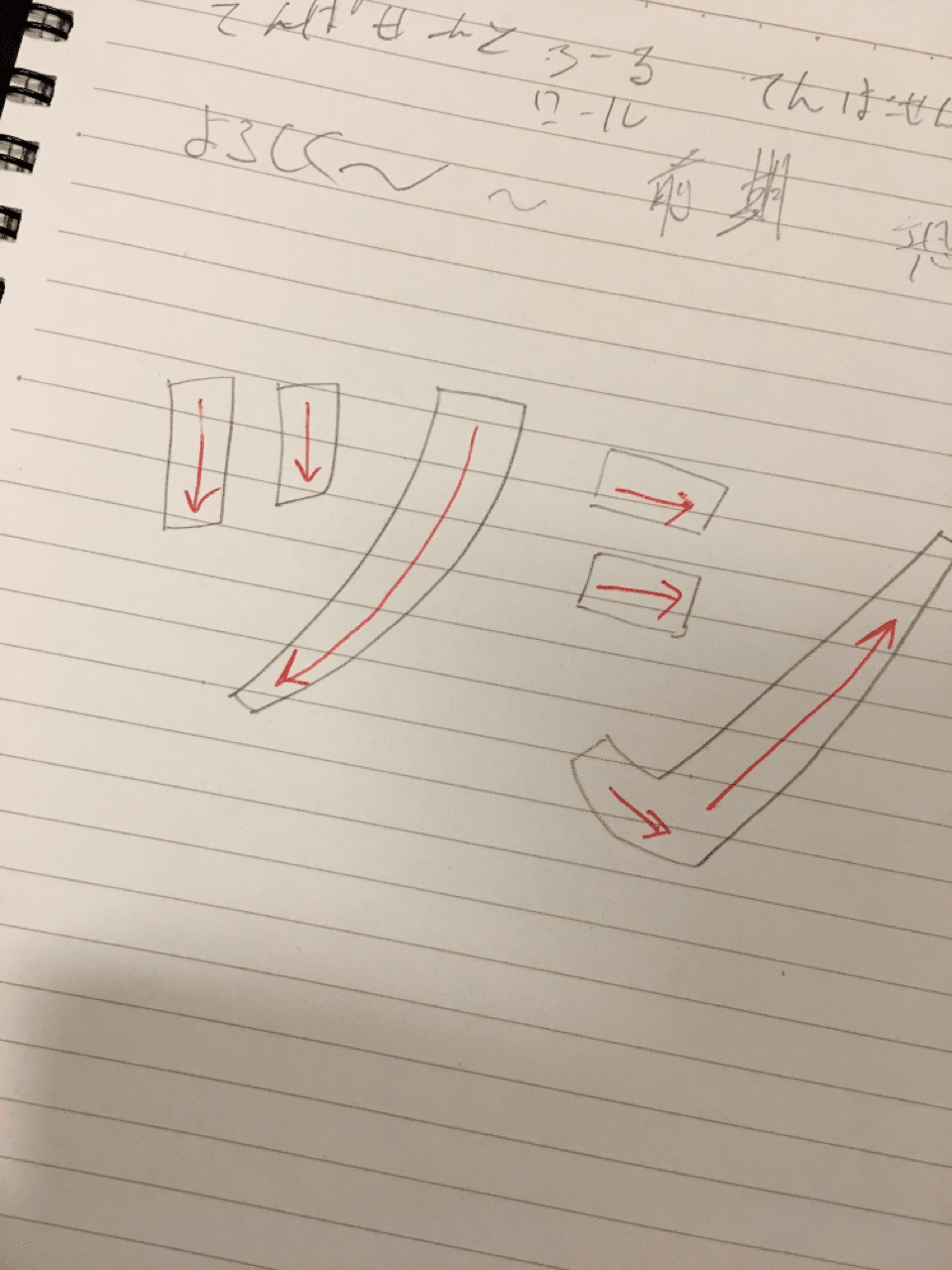
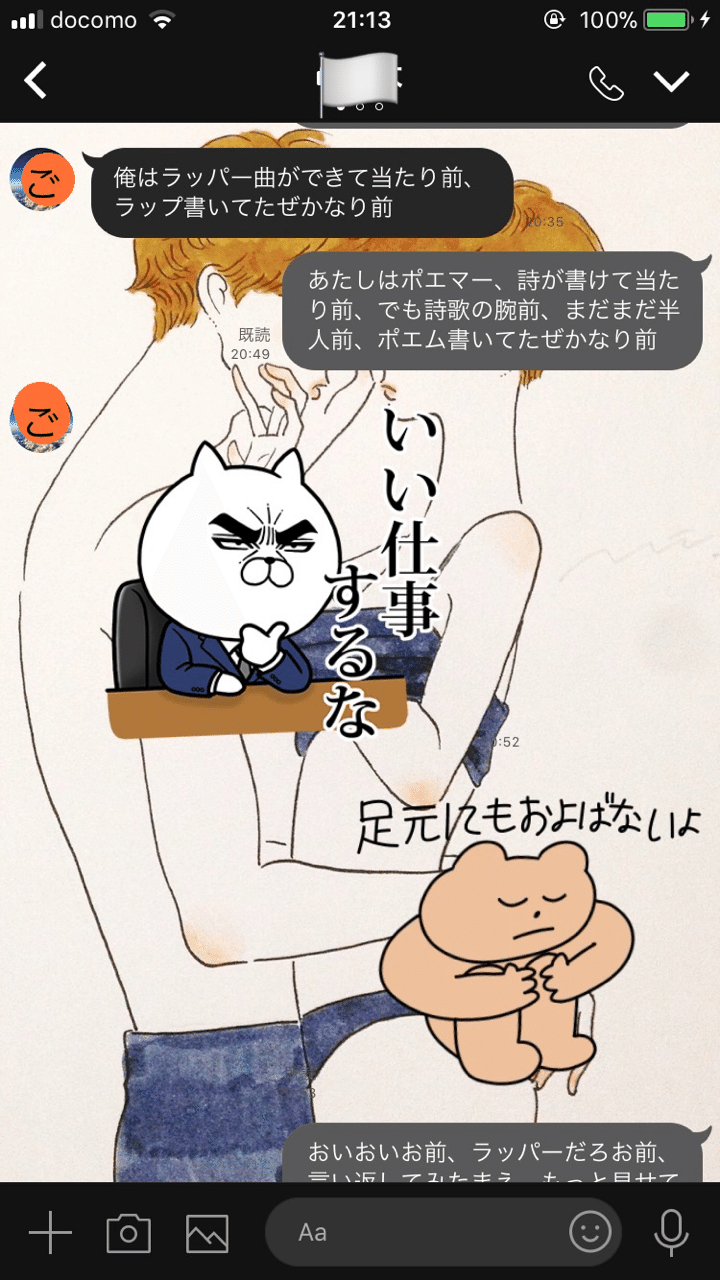
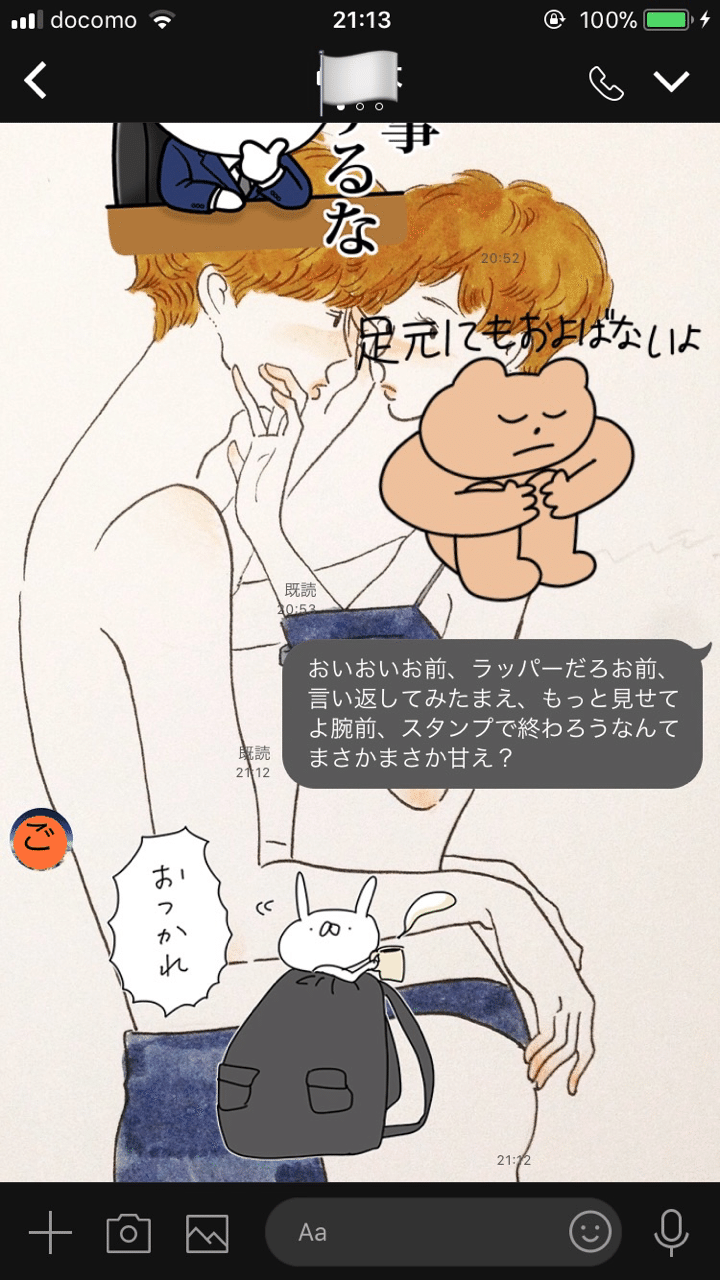
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
