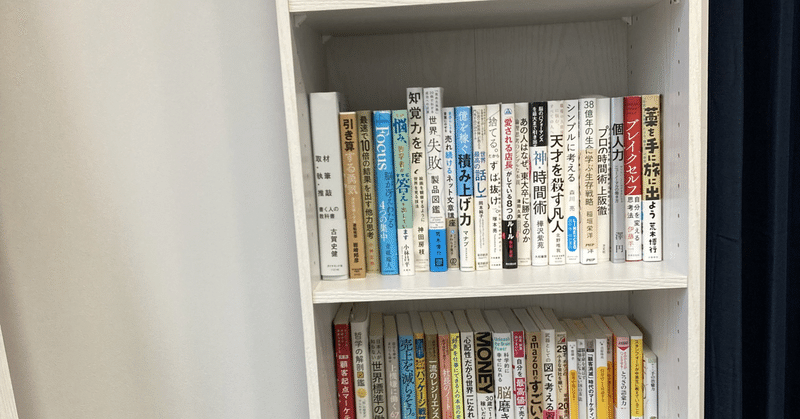
- 運営しているクリエイター
2023年1月の記事一覧
イノベーションは起こせると信じて考える。
これはカタカナ本である。
#リサーチドリブンイノベーション #安斎勇樹 #小田裕和
この本が悪いのではない。
非常に細かく“プロセス”が書いてあったように思うが、カタカナに本当に弱い私は、読んだその場ではふむふむ、と思っても、ページを巡っていくと「はて?」となってしまう。
だから、カタカナに強い人におすすめしたい。
漢字も図解もあるのに、常にカタカナに戻っていく感覚に、私の脳は少し追いつけなか
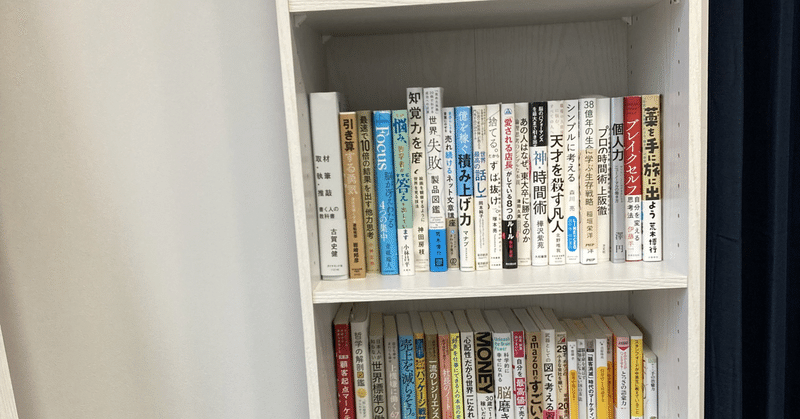
これはカタカナ本である。
#リサーチドリブンイノベーション #安斎勇樹 #小田裕和
この本が悪いのではない。
非常に細かく“プロセス”が書いてあったように思うが、カタカナに本当に弱い私は、読んだその場ではふむふむ、と思っても、ページを巡っていくと「はて?」となってしまう。
だから、カタカナに強い人におすすめしたい。
漢字も図解もあるのに、常にカタカナに戻っていく感覚に、私の脳は少し追いつけなか