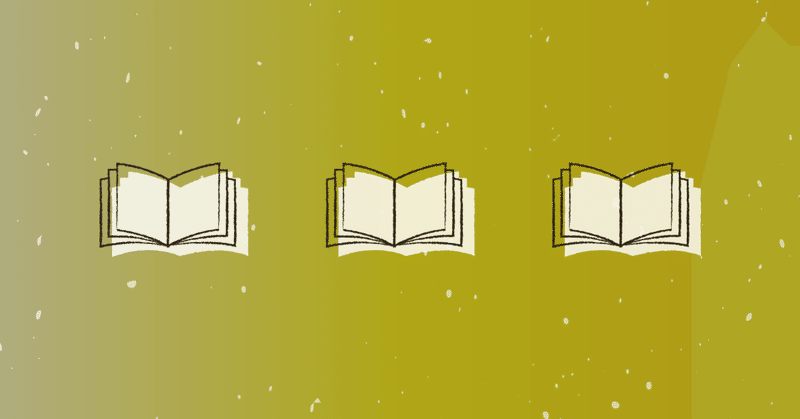
【読書案内】「思考」「バイアス」「言語」「情報収集」をテーマにした厳選本12冊!
こんにちは、Yukiです。今回は、「思考」をテーマに、これまで読んできた本の中から厳選した本をご紹介します。ただしここでは思考に限定せず、もっと広い範囲に目を向けたいと思います。
なぜなら、「思考」を支える要素があるからです。僕たちが「思考」する際に、考えることを妨げる様々な障害があることが研究によって明らかになっています。それは一般にバイアスと呼ばれています。バイアスにどう対処し、適切に思考するかは重要です。また、考えるときに僕たちは言語を使って考えています。ということは、言語も思考の大切な要素です。そして、考えるためには材料が必要です。その材料をどうやって収集するのかも無視できない要素です。
このように「思考」だけで独立してい存在しているわけではありません。その土台となる要素があってはじめて「思考」が可能となります。そのため「思考」のみならず、「バイアス」「言語」「情報収集」と視野を広げて、合計12冊の本をご紹介したいと思います。
「思考」という営み
まず、「思考」を論じた本で外せないのがグレアム・ウォーラスの『思考の技法』です。
本書でウォーラスは思考を4つの段階に分けています。「準備」「培養」「発現」「検証」です。この4段階を踏めば知的創造は可能であると、ウォーラスは言います。単なるハウツー本ではなく思考のプロセスをじっくりと考察していく点にとても意義があります。この1冊だけでもかなり骨太で、多くのヒントがちりばめられています。なお、本書はジェームス・ヤングが『アイデアのつくり方』を執筆する際に参考にした本でもあります。したがって、本書は「思考」の古典とも言えるでしょう。
ダニエル・C・デネットの『思考の技法 -直観ポンプと77の思考術-』は、これまでの数多くの哲学者や思想家が編み出してきた77の思考の道具をまとめた本です。現代風に言えば「思考術大全」と言えるでしょうか。デネットによれば、例え凡人であっても思考のツールを適切に使用すれば、誰でも難解な問題に立ち向かえると言います。情報の取捨選択や自分の意思決定にも役立ちます。
ただ本書の難点は値段が高くかつ、骨太であるということです。なので余裕があれば本書を読むと良いと思います。
最後に花村太郎の『知的トレーニングの技術〔完全独習版〕』を挙げたいと思います。花村は、思考というのは形式的に真似すれば良いのではなく、その根本まで突き詰めて初めて可能になると言います。
この視点から本書では、モチベーションの保ち方、計画の立て方、発想法といったそもそもの部分からスタートします。これを踏まえて、読書術、執筆術などにも及んで思考を考えていきます。そのため、本書は読書猿の『独学大全』と似ていると言えるでしょう。
思考とバイアス
バイアスの入門書として、まず鈴木宏昭の『認知バイアス 心に潜むふしぎな働き』を挙げたいと思います。僕たちは「なんであんなことをしてしまったんだ」「どう考えても誤りだった」「なんぜこれを勝ったのか」と、後から振り返ると後悔してしまうような行動を、なぜかその時はしてしまいます。
そうしたことはなぜ起きるのか、行動や認識、思考に現れる心の働きの偏り、歪みのようなものである「認知バイアス」を解説しています。とはいえ、現在では「認知バイアス」という言葉が一般にも浸透してきて、安易に語られがちです。著者は「認知バイアス」の解説に留まらず、この認知バイアスには意味があるのか、あるとしたらそれはどのような意味か、という問いにも答えます。
認知バイアスと思考の関係に特化した本として、植原亮の『思考力改善ドリル: 批判的思考から科学的思考へ』があります。この本では、僕たち人間が思考を働かせる中で陥りやすいバイアスを解説しています。
本書の特徴は練習問題がある点です。そのため、思考の弱点を学びそれをすぐに実践することで、知って終りにならないことがとても良いです。
バイアスではありませんが、僕たちがモノを考える際に陥りやすいものに「知ってるつもり」があります。スティーブン・スローマンとフィリップ・ファーンバックの共著である『知ってるつもり: 無知の科学』では、「なぜ人は知ってるつもりに陥るのか?」を様々な事例を用いて考察しています。
同じく「知ってるつもり」を考察した本に、西林克彦の『知ってるつもり 「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方』があります。
本書は先ほどの本と同じテーマですが、内容は異なります。西林の本では、「知ってるつもりになっていることは分かった。では如何にして知ってるつもりを解消するのか?」に重点が置かれています。
思考と言語
冒頭で述べたように、僕たちは言葉を使ってモノを考えます。ということは、思考と言葉は密接に関わっていることになります。
両者の関係性に注目した本として、今井むつみの『ことばと思考』があります。日本に住んでいる人は一般的に日本語を使用しています。他方、海外の人、例えばイギリスに住む人なら英語を使用しています。
日本語使用者と英語使用者とでは、物事の認識や思考に違いがあるのでしょうか。こうした言葉が思考に与える影響を研究の成果を紹介して解説しています。
ガイ・ドイッチャーの『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』も今井の本と同様に、言語と認識・思考の関係について考察しています。「前後左右にあたる語を持たず東西南北で位置を伝えるグーグ・イミディル語話者」「古代ギリシャ人は世界がモノクロに見えていた?」など事例1つ1つがとても興味深く面白いです。ちなみに本書の解説を今井が書いています。
言葉を使って思考しているとなると、どれだけの言葉を知っているか、あるいはどんな言葉を使用しているかが思考に影響してくることになります。
極端な話、知っている言葉の数が少なければそれだけ思考の範囲は狭まり、逆に多くの言葉を知っていれば思考の範囲も広がるのではないでしょうか。石黒圭の『語彙力を鍛える~量と質を高めるトレーニング~』は、語彙力の量と質を高める方法を解説しています。具体的には、語彙力の量と質を高めるための22のトレーニング法を解説しています。
思考のための情報収集
冒頭で、考えるためには材料が必要であり、その材料をどうやって集めるかも重要である、と書きました。僕たちが情報収集のために使うものはインターネットでしょう。ところが、このインターネットを使ってどうやって情報収集するのか、ということについてほとんど教えられません。その結果、多くの人が独自のやり方で行っていると思います。
情報化社会と言われている現在、「欲しい情報を的確に手に入れることができる」、言い換えれば情報収集スキルは重要性を増してきているのではないでしょうか。
伊藤民雄の『インターネットで文献探索 2019年版』ではその名の通り、ネットで資料を探すときにどうやったら良いかを具体的に教えてくれます。面白いのは、この本が例えば地域の郷土資料の探し方などの、かなりマニアックな資料の探し方も丁寧に解説している部分です。
もう1冊は、市古みどり・上岡真紀子・保坂睦の『資料検索入門―レポート・論文を書くために』です。3人の著者は、大学や高校などで資料検索の方法を教えてきたプロです。副題の通り、「レポート・論文」を書く際にどうやって役に立つ資料を探すかを解説しています。
しかし、レポート・論文を書かない人でも内容はかなり役に立ちます。余談ですが、この慶應義塾大学出版会の「アカデミック・スキルズシリーズ」はどの本も良書です。この本以外にも読んでみることをオススメします。
読む順番について
基本的には、興味のある本から読むのが良いと思います。特にこれといって、順番は想定していません。とはいえ「12冊でもどれから読んだら良いか分からない!」という人もいるかも知れません。
そこであくまで僕なりに順番について考えてみたいと思います。
まず「思考」のグループについてです。3冊のうち花村の本は、ウォーラスやデネットの本と比べて文章が易しく、読みやすいと思います。なので、「まずは手探り」という場合は、最初に花村の本を読んで次にウォーラスを読み、余裕があればデネット、という順番で読み進めると良いかも知れません。
次に「バイアス」のグループについて。新書の優れている点は、専門的な知識を一般向けに専門家が平易な文章で簡潔にまとめているところです。したがって、まずは鈴木の本を読んでバイアスについて一通りに学んでから、植原の本で実践トレーニングという形が、流れとしては良いかも知れません。
「知ってるつもり」のスローマン・ファーンバックと西林の本は、何を知りたいか、つまり読む目的で異なります。「知ってるつもり」をそもそもから考えたい場合は、スローマン・ファーンバックの本を読むと良いと思います。一方で、「知ってるつもり」への対処の仕方を学びたいなら西林の本が良いと思います。
続いて「言語」のグループです。すでに述べたように、新書は、専門的な内容をギュッと分りやすくまとめている点が優れています。なので今井の本から読み進めて、次にドイッチャーの本を読むと良いと思います。もし語彙力を鍛えたかったら石黒の本を先に読むのが妥当です。
最後に「情報収集」のグループです。正直なところ、この2冊であればどちらから先に読んでも良いと思っています。一応、市古みどり・上岡真紀子・保坂睦の本は情報収集の入門書なので、基本事項がしっかりと書かれています。とはいえ最後に関してはお好みです。
この記事を読んでくださった皆様のお役に立てれば、とても嬉しいです。
最後まで読んで頂き本当にありがとうございました!
読んでいただきありがとうございます! 他の記事も読んでいただけたり、コメントしてくださると嬉しいです
