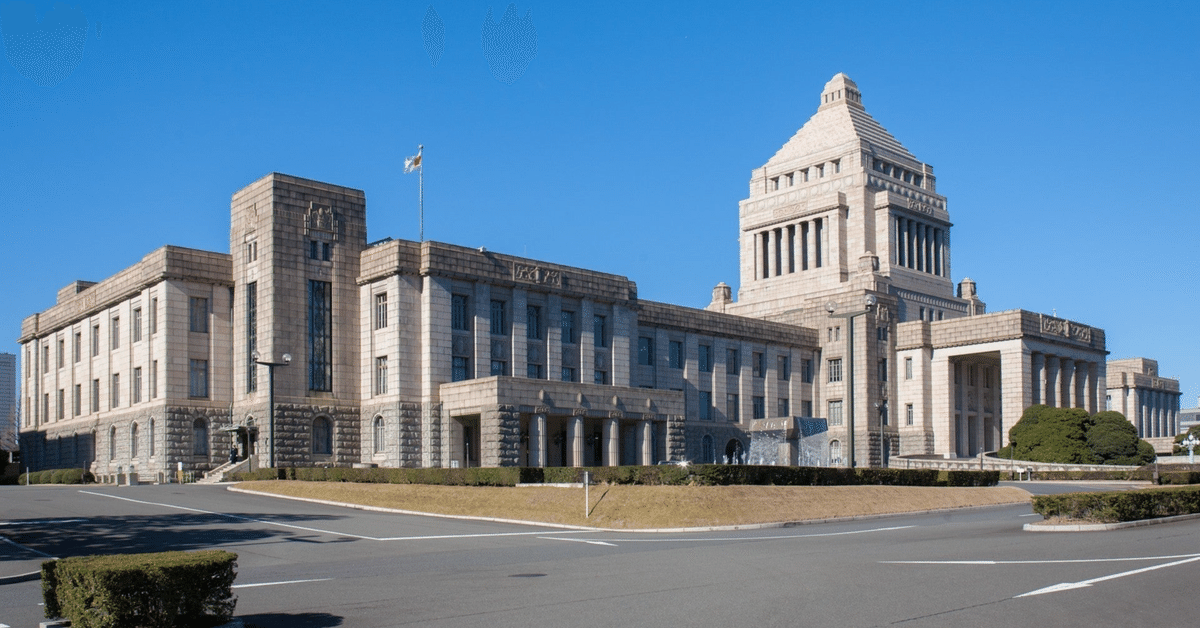
大学生のレポート:「慰安婦問題」
「従軍慰安婦問題」解決に向けた措置として、日本はなぜ国と国民による基金で個人を対象に、償い金と医療福祉事業費を支給することにしたのか?
今回の内容は、2020年秋学期(2021年1月20日)に自分が書いていたレポートの内容だ。留学と休学を経て、すっかり内容が頭から抜けてしまった。だから、最近は自分の当時書いていた文章を読み返して、勘を取り戻そうとしている。このnoteを読んで頂ければ、従軍慰安婦問題の全体像が見えてくると思います!
概要
第二次世界大戦中の、日本政府・軍により動員された「従軍慰安婦」を巡り、日韓は問題を抱えている。歴史を伝える資料の多くが失われている中、日本政府は、「道義的責任は認めるが、法的責任はない」「補償の問題は1965年の日韓基本条約などで法的に解決済み」というスタンスをとっている。これはすなわち、「当時の基準」で言えば日本が国家として行った行為に「法的責任」は付き纏わないということだ。
わかりやすく言えば、慰安婦も給料を受け取っており、そのお金は既に使っているのに、更に今になって仕事内容が不当だったから賠償して欲しいと言われても困るという論理だ。
加えて、法的責任を日本が国家として認めることとなれば韓国以外の全ての被害者にも同様の賠償を行わなければ筋が通らない。大前提として、二国間で結ばれた条約内容が存在しており、それを土台としたまま長い年月が経っている。その内容に、今になって逆行するということ自体が論理的にはあり得ない。
だが、韓国側の認識として、慰安婦問題は依然として「未解決」だ。日本側の、「国としての法的責任」を認めた上での真摯な謝罪と補償が必要だという立場をとっている。よって、日韓の間での大きな食い違いが発生してしまっている。
これがタイトルにある「従軍慰安婦問題」だ。そこで、当論文では、1994年の村山政権下での「従軍慰安婦問題等小委員会」で話し合われた、「従軍慰安婦問題」への措置に着目する。結果から言えば、題にある通り、日本は国と国民による「アジア女性基金」で、被害者個人を対象に、償い金と医療福祉事業費を支給するという決定に至った。その経緯や背景について掘り下げていく。
「従軍慰安婦問題等小委員会」の背景
日本政府は1994年以前から、元慰安婦に対する「謝罪」の意思を表す金銭的な支援を早い段階から検討していた。繰り返すが、日本の国家としてのスタンスは、1965年の日韓請求権協定で請求権に関する問題は「法的に解決済み」だ。
しかし、日韓の市民団体による「国家賠償」、すなわち日本が国家としての責任を認めた上で賠償する事への要求を受け、当時の首相を出していた社会党は問題解決への姿勢を示していた。村山政権の一つ前の宮澤内閣時から、村山政権での動きの下地は出来ていた。具体的な制度設計へと踏み出したのが1994年の村山政権からというわけだ。
具体的には、戦後50年問題プロジェクトチームの「従軍慰安婦問題等小委員会」(自民・社会を中心とする与党3党での構成)で議論が開始された。中でも、議論の核となった人物達は社会党出身だった。社会党は、かつて戦争を容認・加担した人(大政翼賛会に参画、総選挙での推薦していた)を含めて結党された政党だ。そのため、結党当初を振り返れば、戦争責任を追及する方針ではない。
だが、1951年の党大会から打ち出された「平和四原則」(全面講和、中立堅持、軍事基地反対、再軍備反対)の方針をきっかけに、社会党の思想は大きく変化した。その後は1960年の日米安保条約改定反対の闘争から「戦争・戦後責任」を問い始めるようになった。日中国交回復運動、戦犯が関わってくる靖国神社参拝問題、日韓の教科書問題、(「侵略」vs「侵攻」の解釈を巡って)、それに加えての戦争責任や謝罪と賠償等にも積極的に取り組む姿勢を示した。
これ以降の章で触れる、村山富市首相(社会党)が閣議決定した日本政府としての「戦後50年に際しての談話」には、社会党の考え方が全面的に反映されている。賠償問題に関しては、「実際のすべての被害者に公正な償い」をすべきとして、取り組んでいた。
ここで従軍慰安婦問題等小委員会に話を戻す。この委員会は、これまで述べてきた社会党の意向を背景としている。実際に掲げられた目標を簡略化したものを以下に示す。
・日本軍の関与の下で心身の癒しがたい傷を負われた従軍慰安婦の方々に対して心からのお詫びと反省の気持ちを持って償いをあらわす。
・慰安婦被害者の方々の心身の痛みや釈然としない気持ちを和らげる。
・道義的責任を痛感し、過去の歴史と向き合った上で正しく後世に歴史を伝えていく。
・暴力や女性の尊厳にかかわる問題にも積極的に取り組んでいくために、国内外に対して強い意思を示す。
・以上の内容を措置により実現し、慰安婦被害者の方々に納得頂き、「従軍慰安婦問題」を解決することを目指す。
ここまでの流れの中で、そもそも社会党が「解決済み」の問題に対して何故こんなにも必死に償おうとしているのか、弱腰なのか、という指摘が出てくるはずだ。その点を明らかにするためにもこの壮大な「慰安婦問題」を振り返っていくこととする。
沿革
この問題がどこから始まったかを遡る時に、サンフランシスコ講和条約は鍵となる。これは、第二次世界大戦終結のため、日本と連合国との間で結ばれた条約だ。当条約で、「大戦に係る賠償、財産・請求権(金銭,財産または救済に対する、損害賠償といった主張をする権利)の問題については…当事国との間では法的に解決済み」となった。
また、戦後日本より分離した地域の分離に伴う財産・請求権の問題に関しては、日本と当該地域の当局間のやりとりで解決するように定められている。この点に関して、当時の日本政府の方針は、賠償金は戦勝国(日本との間で戦争をしていた国)に対して支払うもので、日本の敗戦で独立した韓国にはする必要がない、というものだった。
条約の第14条にて、日本の賠償金を支払いの必要性が明記されている。日本の経済が賠償金の支払いによってもろくなることを恐れたアメリカの方針の影響で、実際の支払いは一部の国に対してに留まった。日本は賠償を要求したフィリピン、ベトナム、ビルマ(ミャンマー)、インドネシアに賠償金を支払った。それ以外の大半の国は,日本が多額の賠償金の支払いに耐えられないという事実から、賠償金を求めなかった。
1965年:日韓基本条約
次に重要な出来事が、1965年の日韓基本条約(日韓請求権協定)だ。ここでは「両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利、利益、そして両締約国間及び国民間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたことを確認」されている。
具体的内容としては、外交的保護権の相互放棄、つまり国外でなんらかの被害にあった国民の救済や損害賠償の支援をしないことを約束した。しかし、ここで日本は国家としての法的責任は認めていない。これを受けて日韓の市民団体が日本の国家としての「国家賠償」を求める声を上げることとなる。
そこで一度日本側は、被害者個人個人に賠償金の支払いを行う方向性を提案した。それに対して最終的に韓国側はその提案を断り、韓国が政府として受け取り、個人に支払うこととした。日本の裁判所でも判断があった通り、「個人への支払い責任は韓国政府」となった。
この当時の政府と与党との議論の中では、請求権問題に関しては国際条約で解決済みであるから個人補償はできないという意見と個人補償を行うべきとの意見が混在していた。だが、問題の解決に早急に当るという観点で調整を進める必要性に関しては合致していた。
1991年:金学順さん日本政府提訴
その後、転換点となるのが1991年だ。韓国で元慰安婦が名乗り出て、日本政府を提訴したことで日本政府が調査を開始した。
元慰安婦として名乗り出た金学順さんが日本政府に宛てた訴状には挺対協(韓国・挺身隊問題対策協議会=韓国の現在でいう「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」と呼ばれる団体)からの聞き取りでの「十四歳の時に四十円でキーセン(性的奉仕などをするために準備された奴婢の身分)に売られた」という発言が書かれていたとされる。
この内容は朝日新聞で取り上げられているが、記事の内容に関しては、あくまでも記者ではなく、挺対協が行ったインタビューが元になっていることから、捏造であるとも言われている。元朝日新聞記者の植村氏は、過去に作成した記事を麗澤大学客員教授の西岡氏と、文藝春秋社に「捏造」と断じられ、名誉を傷つけられたとして、損害賠償請求訴訟を起こす事件も発生している。挺対協が金学順を利用したという陰謀説的疑惑もある。もはやこの事実関係は、人の主観の域に入ってしまうため、決着をつけることは極めて難しい。
1992年:日朝首脳会談
だが、1992年の日朝首脳会談直前、5日前には、1965年の段階では見つかっていなかった資料が日本政府により発見されたことで追加の賠償の必要性について議論されるようになった。
当時の宮沢喜一首相は数多くの慰安婦の存在と、日本軍の関与について、会談の直前になって訪韓し、盧泰愚大統領に謝罪とお詫びを繰り返した。その様子は、事実関係を明らかにさせる前にとりあえず謝っておこうとしているとも指摘されていた。
提訴後、日本国内では、日本が賠償としてすでに支払っている資金から韓国政府が対応するべきとの主張が行われていた。韓国は日本政府から一括で受け取った資金を経済発展、インフラ整備のために使ったと言われており、韓国政府が個人に日本政府のお金を配るべきだというロジックだ。
この1992年が持つ意味は極めて大きい。過去の条約が形成された時代には無かった資料が1992になって見つかり、日本政府の慰安婦に対しての軍の関与が認められたことになる。この事実は日韓の間での食い違いの大きなきっかけと言える。日本政府の責任を追求するために必要な資料が見つかる前に結ばれた条約の段階での「解決済み」が、この資料の発見をきっかけとして180度違う「未解決」になるのか?という部分が争点だ。
当然日本側としては解決済みを突き通したいし、韓国側とすれば資料も見つかっている「日本側の非」を追求したい。法律学的観点からみれば、国際条約は、条約内容で拘束力を持ち続ける事になる。しかしそれを盾にして日本の責任を蔑ろにすることが果たして倫理道徳的に許されるのか、というのがこの問題の本質ではないだろうか。
1993年:河野談話
その後1993年の河野談話《=行政府(その時点での内閣や個々の国務大臣によって代表される)の見解表明》では、「数多くの慰安婦が存在した」、「慰安所……旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与」、「本人たちの意思に反して集められた事例が数多あり…」、「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」、「そのような気持ちを我が国としてどのように表すか……今後とも真剣に検討すべき」といった内容が公表された。
この談話に至るまでの間、ソウルにて韓国の遺族会の元慰安婦16人から聞き取り調査が行われていたが、聞き取り調査の実施から河野談話までに残された時間はわずかだった。聞き取り調査の実施から時間が空くと放置しているという印象を韓国側に与えかねないとうことで、政治決着を急ごうとしたと指摘されている。時間をかけて丁寧に対応するというのも誠意として受け取られる可能性はある。判断は各政府の価値観に委ねられている部分が大きい点で葛藤があったはずだ。
ここで留意して置かなければならないのは、『政府「談話」』のほとんどは、国会の審議を経ておらず、法律的根拠を有していない点だ。「談話」それ自体には何の強制力も拘束力もなく、法律的観点から言えば、「談話」の影響力が特定の個人や内閣に依存したものであるということだ。そのため、談話の影響力もまた、その個人や内閣の終焉と共に消えていく。以上のことから、公的な立場の人間の発する「談話」に過ぎないとも言えるが、日本の国としての姿勢を示しているといって差し支えない。だが、やはりその重みは国際条約に到底並ぶものではないということを留意して置かなければならない。
1994年:村山談話
そして、1994には「村山談話」が発表された。冒頭で触れた通り、この談話には社会党の方針が反映されている。当政権は、「植民地支配と侵略によってアジア諸国の人々に与えた多大の損害と苦痛」、「歴史の事実」を謙虚に受け止め、痛切に反省し、心からのお詫びをする必要性があると考えていた。社民党の1950年代の方針転換を原点として、日本政府は特に1980年代前半から元慰安婦に、改めて心からお詫びと反省の気持ちを表す必要あると考えていた。歴史を直視し、道義を重んずる国としての責任を果たそうとしていた。そこで政府は、与党戦後50年問題プロジェクト・従軍慰安婦問題等小委員会により、慰安婦問題への取り組む決定に至った。
解決措置に至るまでの議論
「従軍慰安婦問題」解決に向けた措置の分析
実際の解決措置
最初の段落で述べたように、国と国民による基金で、個人を対象にした償い金と医療福祉事業費を支給という措置がこの委員会での議論の結果だ。当時の出来る範囲内での最善の判断ではあったが、当然ながら妥協点もあるため、細かい部分に焦点を当てながら分析していく。
責任の所在
言うまでもなく、最大の妥協点かつデメリットは「国×国民」という形での償いになるという部分だ。この体裁だと、韓国側の最も重視している「国家としての責任」という部分が曖昧になってしまう。
基金自体は、国家賠償ではない民間事業であるため、「日本政府の責任を曖昧にしている」、「日本政府が法的な責任を認めた賠償ではない」との批判の声が予想される。日本政府の態度次第では「民間任せ」で、問題に真摯に向き合っていないとも取られる可能性がある。
韓国の被害者の主張としては、あくまでも謝罪と賠償をするべきは日本政府であって、戦争に関わった人たちの子孫である日本国民ではない。韓国の元慰安婦の家族らは「基金では不十分で、政府が正式に謝罪すべき」と述べている。その観点から言えば、「国の責任」を国民に転嫁しているという見え方もあり得る。
首相による手紙
この埋め合わせというニュアンスを持った首相による手紙がつけられていた事を明記しておきたい。一国家の代表とも言える人間が一筆添えることで、国家としての責任、誠意を示す意図があったと考えられる。ただし、首相の手紙も「個人」からのお手紙に過ぎないとも言える。
国際法の掟
また、仮に日本国として謝り直して、「国家責任」を取っていれば韓国側から完全に許して貰えるとも確言は出来ない。それ以前に国家としての責任を果たすという行為自体は極めて非現実的である。請求権問題は国際条約によって解決済みであるから国家による補償はできないという主張がなされている。その根拠は、条約という形での国家間の取り決めは、国家を拘束し、各国内法に基づいた司法判断は、それを超えられないというのが国際社会における絶対的な掟であるからだ。
各国の政策決定時には、条約と国内法(司法判断も含む)のどちらともが政策を規定する要因にはなる。だが、条約は最も重要度が高く、それに次いで国内裁判所の判決が位置づけられている。
すなわち、二国間での議論を重ね、条約改正で合意が形成されない限りは、条約の持つ力は変化しないということだ。そのような、背景から日本政府としては容易にスタンスを変えることは決してできない。
そして、一度韓国への国家賠償を認めると、他国にも同様に賠償をしないと筋が通らなくなるとも考えられる。そのような中での譲歩案として、「国と国民」の協力が導き出された。日本が国家として何かするのは国際法的に不可能な中での、苦渋の決断だ。
「国×国民」のメリット
ここまで「国×国民」という形の問題点について触れてきたが、逆を返せば、幅広い国民参加を求める事で、道義的責任を国民に理解し、分かち合って貰えるとも言える。日本国民の中では、個人単位でも被害者の方々への償いの気持ちを持っている人がおり、その気持を基金により体現させる事が可能だ。日本国民個人レベルでの意思の尊重の結果の基金設立ということであれば、被害者に対しての個人の心底からの思いが伝わり、誠意として受け取って貰えるかも知れない。
ただし、被害者の中には「日本国民への責任転嫁、あるいは飛び火は避けたい」という強い意見を持つ人もいるという事にも留意する必要がある。「誠意」を示す事の重要性を考えると、大々的に取り上げることは憚られる内容ではあるが、民間から多額の募金が集まると、政府の負担が少なくなるのは事実だ。
ただし、国として賠償金を用意することが、誠意に直結するわけではない。また、他の観点から言えば、慰安婦問題への国際社会で重要視されている「女性の尊重」への取り組みの姿勢を対外的にだけでなく、国内にも示す効果が期待される。
賠償の対象
次は「個人を対象」という部分に注目する。個人に基金で集めたお金を届けるためには、具体的に誰が対象なのかを明らかにする必要がある。そこでまず問題になるのが、元慰安婦の認定が極めて難しいという点だ。論文執筆にあたり、調査を進めいても、なかなか確実な資料は見つからず、事実関係をはっきりさせるのが困難というのが現状だ。
名乗り出る必要
さらに、被害者である元慰安婦の方々には、基金の受け取りのために名乗り出て貰う必要がある。韓国内では、日本が国家として賠償をするまで一歩も引かないという風潮があり、もし仮に「国×国民」による基金のお金を受け取れば、金に目が眩んで妥協をしたというバッシングが起こる可能性もある。個人のやり取りで言えば、和解金を無理矢理受け取らされるのと同じ論理である。日本政府の呼びかけで、名乗り出てくれた人が社会の中で攻撃の的となる可能性があるとなれば、更なる精神的なダメージを与えることの手助けになってしまう。
インドネシア政府の例
この「個人を対象」をすることによる問題点に対して、個人を対象とはしない措置も選択肢としてはあった。例としては、日本がインドネシアに対して戦後行った賠償が挙げられる。これは、インドネシア政府と日本政府の協議から、元慰安婦の認定が困難である点と、元慰安婦の方々や家族の尊厳を守る必要等を考慮した結果だ。インドネシア政府は、個人に対する賠償ではなく、高齢者福祉施設整備事業への支援を受けたいという方針を明らかにしたため、日本政府は施設69箇所整備という形での償いを行った。このような方法であれば、個人支給の対象を調べ上げ、確実に漏れなく支給をする必要はない。
更に先程述べた韓国での個人を対象にして支給をすることで発生する可能性のあるバッシングの可能性も回避出来る。そして、対社会的な利益を享受してもらう事が可能だ。ただし、被害を受けた慰安婦の方個人個人に対しては直接行き届かないということで、誠意が伝わりにい。また、相手政府の協力がないと設備の整備は実現不可能である。
国家賠償
最後は、現実性が極めて低い選択肢ではあるが、「国家賠償」を行うと仮定してみる。この方法であれば、韓国側の「被害者への生活支援やケアは自国で行うから、日本政府は真摯な公式謝罪と国家としての保障を行うべきである」という韓国側の立場を尊重出来る。
「政府と国民」ではなく、国家が賠償するという点で「日本政府」の日本軍の関与の下、多数の女性の名誉と尊厳を傷つけたという責任を明確に出来るため、被害者の声に寄り添えて、和解に繋がる可能性が高いと言える。
しかし、根本的に「道義的責任は認めるが、法的責任はない」、「補償の問題は65年の日韓基本条約などで法的に解決済み」の日本政府の国際法に則ったスタンスとの大きな齟齬が生じる。
政府と同じ認識の国民からは、「国家としての賠償行為」への強い反発感情が湧き上がると予想される。また、国家だけが責任を果たすというニュアンスが強調されるため、国内での問題への関心や意識の改善は、「国×国民」のやり方程は期待できない。
最後に
以上の内容を踏まえて、『「従軍慰安婦問題」解決に向けた措置』の議論の複雑さそして、根深さがより明らかになった。いくつもの相容れない要素が絡み合う中で、誤解が生まれ、それが現在の日韓問題となっている。問題の解決というのは妥協点を見つける作業だとも言えるため、その意味では当論文で取り上げた議論では、着地点が上手く見つけられているのではないだろうか。
ただし、本当の意味での和解に繋げることが出来ないとこの問題は永遠に終わらない。法的な枠組み、政治的意図などが背景にあるがゆえに非常に難しい現状であることは間違いない。そして、極論、個人の主観に委ねられてしまう部分も大きい。最後は感情的な部分に行き着くにしても、一つ一つの要素を細かく見て、誤解や食い違いを解きほぐしていくことが、問題の解決に繋がる。この論文を通して、正しい事実関係、双方の感情や思惑に関しての理解を深めることが、個人として出来ることだと考える。卒業論文で更に掘り下げていきたい。
終わりに
疑問点などがあれば、自分の学びの肥やしになるので是非コメント頂ければ嬉しいです。noteの形でまとめることで、もう一度自分自身の文章を丁寧に読む良いきっかけとなったと感じています。
今回はかなりヘビーなトピックではありましたが、最後まで読んでくださってありがとうございます!また次回のnoteでお会いできるのを楽しみにしています👋
僕のnoteを読んでくださって、ありがとうございます!お金という形でのご支援に具体的なリターンを提示することは出来ないのですが、もしサポートを頂いた際は、僕自身の成長をまたnoteを通して報告させていただけるように頑張りたいと思っています。
