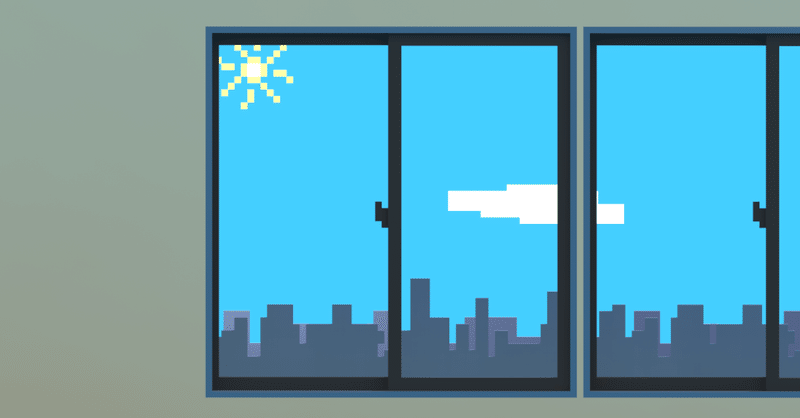
10年前に書かれた、つながらない生活について。
前書き
突然ですが、10年前の生活を覚えていますか?
あなたは2014年にどのような生活をしていたでしょうか?
自分の生活を振り返ってみると、今思えば、ネットをみて行動を決めることがずいぶんと多くなっていたように思います。
本もDVDもアマゾンや楽天で買ったり、レストランにいく時は、食べログをみて友達とLINEで相談して決めたりと、リアルな生活とインターネットがごちゃ混ぜになっていたような気がします。
Kindle本を中身を整理していたら、『つながらない生活 ― 「ネット世間」との距離のとり方』という本を見つけて、早速読み始めました。
2014年に購入しいた履歴があるので、当時から意識的か無意識にかはわかりませんが、人と繋がらないことについて、知りたかったのかもしれません。
今日のnoteでは、この本の中で気になった言葉をご紹介いたします。
周囲からの大きな声
いまの時代、バランスは片方に大きく傾いている。他の人人の声がしきりに聞こえてくるため、わたしたちは自分の声よりもそれら周囲からの声に従いがちだ。内省するのは容易なことではなくなり、実際にその機会は減ってきている。
ウィリアム・パワーズ (著), 有賀 裕子 (翻訳)
自分で考える前に、誰かが親切に正解(と思われる情報)を教えてくれたり、否応なしにツイッターやネットニュースから情報が自分のところに飛び込んでくる毎日。
そんな毎日の中では、どうしても自分の言葉を見つけるのが難しいと感じています。
そして、見つけたとしても、自分の言葉なのか、自分を信じることも、こんなにも答え(らしきもの)が溢れていると、困惑してしまいます。
2024年ではその傾向がなおさら顕著になってきている気がしてなりません。
メッセージに追われる
矢継ぎ早にメッセージが流れてくるのを、必死に追いかけつづける。このような生活にどっぷり浸かっていくにつれて、わたしのなかでは、友人メアリーのかつての口癖はデジタル時代の挨拶にぴったりだという思いが深まっていくばかりである。「どうしてる?」「忙しい、とにかく忙しい」
ウィリアム・パワーズ (著), 有賀 裕子 (翻訳)
それは、会社の仕事でもそうで、毎日夥しい数のメールが受信箱に入ってきて、それに返信することに集中していると、根本的な解決ができていないことが多くあります。
これなんですか?これはこうです・・・こんな会話は、そもそもの基礎知識がわかっていれば不要なことも多いです。
聞けば教えてもらえるのハードルが下がると、人に依存することが多くなり、自分の問題解決力も落ちていく気がします。
メッセージに追われて忙しい現象は、10年経った今も、変わらず、むしろ悪化しているのかもしれません。
だって人間だもの
わたしたちがスクリーンに引き戻されるのは、進化の過程で身についた習性によるのかもしれない。人間の脳は、新たな刺激を察知して反応するようにできている。これまで見聞したことのないできごとやモノに気づくと、脳の「褒賞システム」が作動して、神経伝達物質分子であるドーパミンが分泌される。
ウィリアム・パワーズ (著), 有賀 裕子 (翻訳)
最後にスクリーンと人間の脳の関係についての引用です。
だって人間だものと言われてしまえば、それまでですが、
本能的にスクリーンがもたらす目新しさ/新規性は、
人間の脳の欲望にドンピシャな設計になっているようです。
数百年経てば、脳も進化して、そこまでスマホ中毒にならない耐性ができるのかもしれませんが、私たちが生きている間はまだ難しそうです。
後書き
ここまでスクリーンやインターネットのネガティブな部分に焦点を当ててきましたが、もちろんメリットもたくさんありますし、私たちの生活にはもう欠かせない、生活必需品として地位を確立していると思います。
(この文章を読んでいただいているのも、書けているのも、そんな環境が世の中に存在してくれているからですし)
ただ、これだけの環境が整ったからこそ、
ネット以外のリアルな世界で、
自分の目で見て感じること、無駄だと思うくらい悩んでみることが、
今更ながら、人間にとっては非常に大切ではないかと、改めて思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
