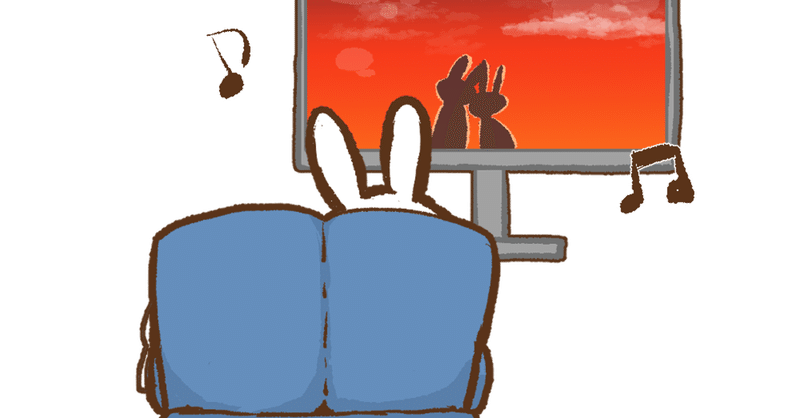
「心」の時代におけるビジネス マーケティング戦略と消費者心理
どーも、うぇいです。専門の哲学しか勉強しないとご飯が食べられなくなっちゃうので(あと僕を採用してくれた会社に申し訳ないので)、実はちょっとだけビジネス関連のことを独学しています。
本記事では、杉本徹雄編『マーケティングと広告の心理学』の「はじめに」と第一章「マーケティング戦略と消費者心理」の内容を紹介することで、心理学×ビジネスの視点の重要性を明らかにしたいと思っています。
内容は、以下の通りです。まず、第1章で現代の消費者の行動を心理学的に分析することの意味を提示します。第2章ではマーケティング戦略ってそもそもなんやねんというところから説明します。第3章では消費者の購買行動における意思決定について検討します(第3章の分量が多めです)。
記事の要約
現代においては、売り手(企業)と買い手(消費者)の関係は多様化・複雑化しています。このような局面において、企業はどのようなマーケティング戦略を策定すべきなのでしょうか。
効果的なマーケティング戦略をとるための一つの手法として、消費者心理に着目します。その際、心理学の成果を積極的に活用します。いくら多様な価値観を消費者が有しているとはいえ、人間である以上一定の心理メカニズムは共通して持っていると言えるのです。
マーケティングという視点から消費者行動を把握するために、消費者の意思決定について注目します。消費者による時間的流れを概念によって整理すると、①欲求喚起と問題認識、②認知、③態度、④行動という4つの心理的要素になります。本記事では、それらを仔細に分析いたします。
1. 売り手の「心理」と買い手の「心理」
経済学や経営学を持ち出すまでもなく、商品の売り手は商品の多くを販売し、なるべく多くの利益を得ようとします。他方、消費者は自分の気に入った商品をなるべく安い値段で買おうとするのが一般的です。
そのために売り手はブランドの構築や広告での販促を目指しますし、買い手は欲しいものについてあれこれ調べて比較検討します。
以上のような売り手(企業)と買い手(消費者)の行動は、商品の取引や売買が始まったときから既に見られるものだと考えられます。例えば、江戸時代では伝説の美人小野小町にあやかって名付けられた「小野紅」というブランドがありました。
紅ミュージアム通信 Vol. 1 江戸の女性たちの憧れ 寒中うし紅 ↓
科学技術が発展し、また消費者の生活水準が飛躍的に上昇した現代においては、マーケティングや宣伝広告の手法が著しく多様化し、高度化しています。マーケティング戦略、ブランド戦略、コミュニケーション戦略、プロモーション戦略などのマーケティング活動が、日々進歩しているのです。
現代の消費者は、場面が違えば異なる価値観を有する存在になっていると思われます。すなわち、現代の消費者は場面が変われば行動や価値観が容易に変更する存在なのです。
それでも、ある価値観や行動やには一定の共通性や普遍性があるのではないでしょうか。心理学(psychology)は、ギリシャ語で魂や心を意味する「プシュケー」と理性や学問を意味する「ロゴス」が組み合わせってできた言葉です。語源からもわかるように、心理学は心の働きに関する法則を見出す学問なのです。
一見極めて多様に見える消費者心理や行動にも、その背後には共通の心理的メカニズムや行動原理が存在しているはずです。また普遍的な原理を見出すということは、その反対にこの側面は原理的に説明できないという線引きをすることにもなるのです。
2. マーケティング戦略と消費者行動
消費者のニーズは多様化し、またデジタルメディアの影響で消費者行動の変化は激しくなっています。このような今日の市場環境に対応するために、企業のマーケティングは様々な創意工夫をする必要があるでしょう。
マーケティング戦略とは、売り上げ(利益)や市場占有率(マーケットシェア)などの目標を達成するために構築される企業行動です。
コトラーとケラーは、マーケティング戦略について次のように述べています。すべてのマーケティング戦略はSTP、すなわち、市場細分化(segmentation)、標的化(targeting)、ポジショニング(positioning)を基本としている、と。企業は様々なニーズや集団を見つけ、自社が優れた方法で満足させられるニーズや集団を標的化し、さらに標的市場が自社特有の提供物やイメージを認識するように企業は自らの提供物をポジショニングするのです。
市場細分化によって標的市場となるセグメントが設定され、当該商品やブランドポジショニングを的確に確定できれば、他社製品やブランドとの差別化をはかることになります。
STPは企業間競争におけるマーケティング戦略を構築するための基本的な行動です。STPが決定された後は、マーケティング要素である4P、すなわち製品(product)、価格(price)、流通(place)、販売促進(promotion)を適切に組み合わせることによって、マーケティング計画を遂行することになります。
3. 消費者の意思決定
マーケティングという視点から消費者行動を把握するために、消費者の意思決定について注目しましょう。
消費者による時間的流れを概念によって整理すると、①欲求喚起と問題認識、②認知、③態度、④行動という4つの心理的要素になると考えられます。以下では、各段階を順番に見ていくことにしましょう。
3.1 欲求喚起と問題認識の段階
マーケティング戦略がうまくいったかどうかは、個々の消費者が当該商品を購入し、満足したかにかかっています。そのためにはまず、当該商品を入手したいという消費者の欲求が喚起される必要があるでしょう。
個々の消費者は自分の欲求を満たすために、商品の購買をしようという動機を持ちます。したがって、企業としては消費者の欲求(ニーズ)を理解し、消費者に欲求を認識してもらい、マーケティングの対象となる商品の購入に向けて十分に動機づけられるようにすることが肝要なのです。

消費者の欲求を喚起させる要因は大きく2つあります。1つは消費者個人の内部要因で、もう1つは消費者を取り巻く外部環境要因です。前者は、消費者の心理や個人特性です。例えば、のどの渇きを感じ欲求を認識するのは、主に個人の心理的要因と言うことができます。後者の外部環境要因は、それこそ企業のマーケティング活動がその例にあたります。というのも、企業のマーケティング活動の大部分は消費者の欲求を外部から喚起するものであるからです。
マーケティング領域では、ニーズ(needs)とウォンツ(wants)を分けて捉える場合があります。コトラーとケラーによると、ニーズは人間が生きていくためや生活するための心理的な欲求であり、ウォンツはニーズが特定の欲求を満たすための特定の物(具体的には、商品やサービス)に向けられるものとして区別しています。なお、心理学においては、欲求や欲望などの概念について明確に区別される定義はないようです(6頁)。
僕は〈シリーズ 欲求の哲学〉というマガジンを執筆していますので、興味のある方は下記を参照してください。
3.2 認知的処理の段階
消費者は絶えず多くの情報にさらされています。消費者は自らをとりまく外部環境情報を、購買に至るまでにどのように処理しているのでしょうか。
3.2.1 選択的注意の獲得
消費者が一時的に処理できる情報量には限界がありますから、多くの消費情報があれば、消費者が動機づけられたり、関心を持っている情報や目立つ情報に注意が向けられます。これを選択的注意と言います。
したがって、広告表現や媒体、パッケージの工夫、店頭プロモーションの工夫などで消費者の注意を引くことが認知的処理における最初の段階でなすべきことなのです。
3.2.2 接触頻度(露出回数)の効果
広告の効果を上げるためには、一定回数以上の露出が必要だと言えます。なぜなら、人は中性的な刺激(例えば、無意味つづりや無意味図形、未知の人の顔)であっても、接触頻度が多くなるにつれて好意度が上昇するからです。
3.2.3 情報の体制化
外部の刺激や情報は、バラバラに知覚されるのではありません。ある種のまとまりをもって知覚しようとする心理が働きます。
例えば、Apple社のブランドを考えてみましょう。Appleは、iPhone、MacBook、iTunesなどの製品やサービスを、「Appleの製品やサービスはイケてる!」と思わせるものとして提示しています。

構造化、組織化された知識の単位をスキーマ(schema)と言います。マーケティング戦略においては、消費者にどのようなスキーマを引き出しうるかを考慮する必要があるのです。
3.3 態度形成の段階
製品やブランドに対して消費者が示す「好き嫌い」といった態度は、商品が購入されるかどうかについての重要な心理的メカニズムとして機能します。
企業は、製品やブランドに対して好意的な態度が形成されるようなコミュニケーションやプロモーション戦略を策定しなければならないでしょう。
企業は消費者に自社の商品を購入するするよう説得する必要がありますが、その際に心理学の知識が活きます。例えば、チャルディーニは説得の効果を規定する6つのルールを挙げています。
本記事ではその中の2つを紹介します。
3.3.1 返報性
他者から何かを与えられると自分も何かを返さないといけない気持ちになることを返報性の原理と言います。例えば、スーパーの試食や広告によく掲載されている無料お試しセットはこの原理を活用しています。
3.3.2 希少性
人は、数が少なく、入手の機会を失いかけるとその対象を価値あるものとみなすようになります。「数量限定!」や「今だけ!」のようなフレーズは、その商品に希少性を感じされるものですね。
3.4 行動の段階とその後の対応
3.4.1 行動としての購買と購買後行動
購買に動機づけられた消費者は、店舗やインターネットで商品を購入することになります。購入後に消費者は事前の期待水準を上回るか下回るかによって購買後評価(満足/不満足)を形成します。
消費者が不満を抱いた際に、それを汲み取る仕組みを売り手は構築しておく必要があります。
3.4.2 リピート購買とブランド・ロイヤリティ
消費者の購買行動は反復性を持ちます。企業にとって自社製品や特定のブランドが繰り返し購入されることは、マーケティングの効果指標として非常に重要な側面があります。なぜなら、リピート購買はブランド・ロイヤリティの形成と密接な関係があり、製品関与(消費者の製品に対する関心度や重要度)の水準や知識の形成と関連しているからです。
ブランド・ロイヤリティには、行動的なロイヤリティと態度的なロイヤリティという2つの側面があります。前者の行動的なロイヤリティとは、同じブランドが繰り返し購入されるという行動としての側面を意味します。後者の態度的なロイヤリティとは、心理的に特定のブランドに対して好意的な態度を形成するという側面を意味します。
4. まとめ
思ったより長くなってしまいました。本記事の内容をまとめると、以下のようになります。(冒頭の要約とほぼ同じものです。)
現代においては、売り手(企業)と買い手(消費者)の関係は多様化・複雑化しているのでした。このような局面において、企業はどのようなマーケティング戦略を策定すべきだったのでしょうか。
効果的なマーケティング戦略をとるための一つの手法として、消費者心理に着目することにしました。その際、心理学の成果を積極的に活用できると考えました。いくら多様な価値観を消費者が有しているとはいえ、人間である以上一定の心理メカニズムは共通して持っていると言えるのです。
そしてマーケティングという視点から消費者行動を把握するために、消費者の意思決定について注目しました。
消費者による時間的流れを概念によって整理すると、①欲求喚起と問題認識、②認知、③態度、④行動という4つの心理的要素になります。本記事では、それらを細かく分析しました。
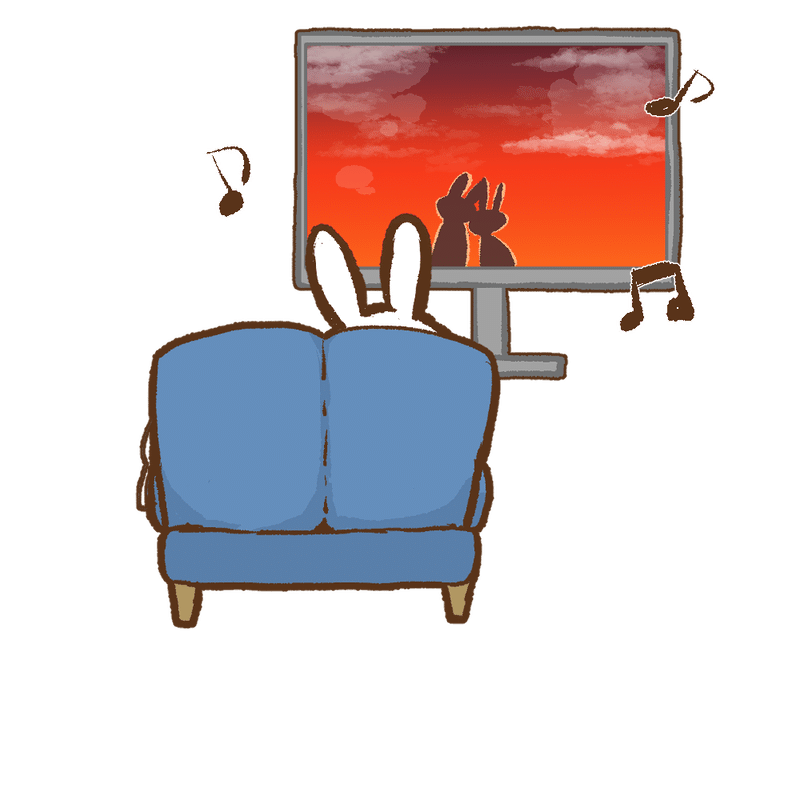
5. うぇいから一言
今回紹介した考えって、ネットで有名になるためにも使えそうな気がします。
僕は自分の記事を多くの人に読んでもらいたいから、有名になりたいと思っています。
記事を多くの人に閲覧してもらうためには、ビジネス的な思考が必要なのでしょう。なぜなら、淡々と質の良い記事を書くことも大切ですが、まず記事の存在を知ってもらわないと読んでもらえないからです。読んでもらうための工夫が求められます。
本記事で検討したマーケティングという視点は、哲学書ばかり読んでては一生気づけない視点のように思われます(哲学に興味を持っている人の多くは、そもそも「お金儲け」に興味がないのだろうけど。僕もあまり興味ないし)。
思考の材料
参考文献
その他
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
記事をお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、YouTubeの活動費や書籍の購入代として使わせていただきます。
