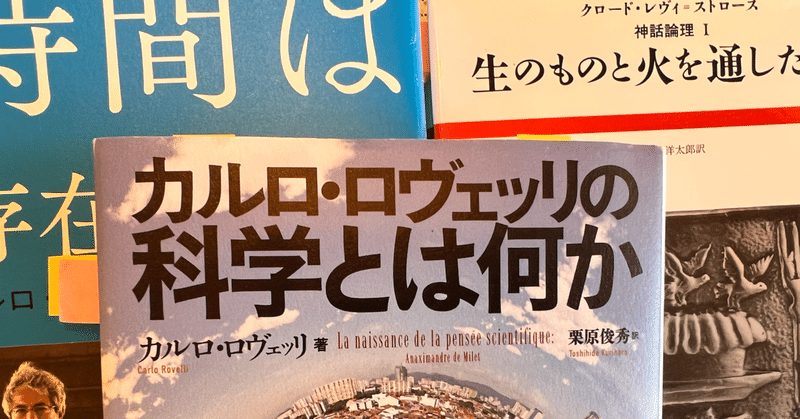
科学的思考力の極北へ -『カルロ・ロヴェッリの科学とは何か』を意味分節理論で読む
カルロ・ロヴェッリ氏の著書『カルロ・ロヴェッリの科学とは何か』を引き続き読む。
科学とは何か?
この問いに答えるためのコトバは、はじめから”常識”のどこかに転がっているようなシロモノではありません。ロヴェッリ氏は本書を通じて、「科学とは何か」という問いへの答えを”仮に”織り出すためのコトバを、ひとつひとつ磨き上げては並べていくのであります。
そのようなコトバのうち、最初のものは「世界」であります。
世界は、わたしたちの目に映るとおりではない
世界について、ロヴェッリ氏は次のように書く。
「世界は、わたしたちの目に映るとおりではない。」
一体どういうことだろうか。
私たちはふだん「世界」というコトバを見聞きするとき、私たちを取り囲み、私たち自身もその一部であるような、さまざまモノが集まった大きな”まとまり”をイメージする場合が多いのではないだろうか。
世界という言葉は特別に珍しい言葉でもなければ難しい言葉でもないと思われている。「世界一」とか「世界経済」とか「世界平和」とか「独自の世界観」とか、「現実世界」とか「仮想世界」などという場合の”世界”である。
こういった、さまざまなモノのまとまりのようなこととしての「世界」の中で、私たちはあれこれのモノたちを見たり聞いたり嗅いだり味わったり触れたりする。そういう目に見えたり手に触れたり、ありありと存在すると思われるものたちのまとまりとしての世界。この私たちの周囲をしっかりと囲んでいる確かなモノたちのあつまりというニュアンスをもつ”世界”というコトバを、ロヴェッリ氏はなんとも不穏当な文脈に置くのである。
「世界は、わたしたちの目に映るとおりではない」
世界が目に映る通りではないとすれば、目に映っているこれやあれはなんなのか?!
目に映らない”本当の”世界を捉えるにはどうしたらよいのか?!
「世界」と「目に映るとおりではない何か」を結びつけたロヴェッリ氏の言葉の言葉に促され、このような疑問が湧いてくる。
ロヴェッリ氏は同じことを次のように言い換えていく。
「真理は[…]通常、わたしたちの視界に映らない場所に隠れている。観察と思索が、真理に到達するための道具である。自然の背後には、目に見えない、五感では捉えられない実体が存在する。その実体を想像し、仮定することが、思索に課せられた役割である。」
「わたしたちの視界に映らない」=「五感では捉えられない」ものが、「世界」であり「真理」であり「実体」である。その”世界の真理”に到達するための道具、手段は「観察と思索」=「想像し、仮定すること」である。
この引用は、この本『カルロ・ロヴェッリの科学とは何か』の主人公ともいえるアナクシマンドロスの哲学のエッセンスをロヴェッリ氏が自らの言葉に置き換えたものである。
「観察と思索」=「想像し、仮定すること」の例としてロヴェッリ氏が挙げるのは、今日の物理学を初めとする自然科学の記述の体系を支えている「原子」や「電磁場」、「シュレディンガーの波動方程式」から「量子場」などである。それらは「科学によって提案された、感覚によっては捉えられない「理論的な実体」」ということになる(カルロ・ロヴェッリ『カルロ・ロヴェッリの科学とは何か』p.103)。
日常素朴に常識的には、世界といえば、私たちの「目に映る通りのもの」の集まりだと思われている。コップもスマホも靴も服もノートもペンも、目に映る通りいいまここにある。朝には太陽が東の方角から「登って」きたし、水道栓をひねれば水は「上から下へ」流れる。
しかし、そういう「目に映る通り」の姿は、文字通り私たち一人一人が目に見て経験している事柄である。
「わたしたちが見ている世界は、現実の世界とは違っている。世界にたいするわたしたちの視点は、わたしたちの経験の卑小さから制限を受けている。」
これこそが科学的思考の出発点になる。
私たちが見ている世界 / 現実の世界
|| ||
経験の卑小さに制限を受けている / 観察と思索・想像と仮定
これは、じっくり読めば読むほどたいへんな話である。
通常は、「私たちが見ている世界(五感で捉えている世界)」こそが「現実」と呼ばれる。通常「私たちが見ている世界」と「現実の世界」はイコールで結ばれており、この間に区別も対立もない。
しかし科学的思考の起点には、「私たちが見ている世界」と「現実の世界」とのあいだを区別することがある。そしてこの区別を、「制限を受けたもの」と「(観察と思索・想像と仮定によって)制限を多少なりとも解除したもの」の区別に重ねる。ここから科学的思考が動き出すというのである。
ここで、あえて「制限を受けたもの」と「制限を多少なりとも解除したもの」という奥歯になにかがつまったような表現をしているところに科学的思考の面白さがある。「私たちが見ている世界」と「現実の世界」の対立を、「偽」と「真」の対立のような決定的なところに置き換えてみたくもなるところであるが、あえて真/偽や正/誤という二項対立ではなく、「制限を受けたもの」と「制限を多少なりとも解除したもの」という程度の差のようなことを持ってくる。
しかも「制限を多少なりとも解除」するのは、観察と思索・想像と仮定である。
五感で感じることができるものよりも、想像と仮定のほうが、より科学的だなんて、なにをおかしなことを言っているのだ、何かの書き間違いではないのか、と思われるかもしれないが、残念ながら間違えていない。
経験の卑小さに制限を受けている / 観察と思索・想像と仮定
|| ||
非科学的思考 / 科学的思考
非科学的思考は経験の卑小さに制限を受けている。仮にそう言われると、確かにそうかもな、と思われる人も少なくないのではないか。
また、科学的思考は、観察と思索・想像と仮定から生まれる、というのも、納得される人が多いのではないか。
しかしここには、実はもう一セットの二項対立が重なってくる。
私たちが見ている世界 / 現実の世界
この二項対立も、重なっているのである。
経験の卑小さに制限を受けている / 観察と思索・想像と仮定
|| ||
非科学的思考 / 科学的思考
|| ||
私たちが見ている世界 / 現実の世界
手に触れたり目に見たり、感覚で世界を捉えることは「非科学的」なのだ。
人類を愚弄するとんでもないことを書いていると思われるかもしれないが、我慢できる人は我慢して最後まで読んでほしい。
*
「わたしたち」が「見る」「視点」「経験」が、”わたしたちが見ている世界”(私たちに見られている世界)を作り出す。
作り出す、という言葉のチョイスが微妙であれば、構成するとか、秩序づけるとか、顕現させるとか、発生させるとか、他の言い方に言い換えてもいい(この手の言い換えをどうするかが大問題である)。
そこで経験される何かは、見えるものでも、聞こえるものでも、いずれも経験する身体との関係を通じて発生している何かである。
身体「内部」から不断に区切り出されるー分節される限りでの身体”の”「外部」と言ってもよいかもしれない。
私たち一人一人の感覚器官ー神経系ー身体にとっての外部の経験というものは、あくまでも一人一人の人間にとって内部と外部を分けるつつつなぐ=分節する動きに付随する効果のようなものである。
この場合”経験される外部”は、経験する/される関係と無関係にそれ自体として存在しているものではない。
私たちが見ている世界
これは、私たちが生きたり動いたり喋ったりすることと全く無関係に、見られている姿そのもので、それ自体として、自ずから、「自性」をもって存在しているわけではない。
私たちが見ている世界は、私たちが見ているからこそ、わたしたちが見ている世界になっている。
◇
しかも、この「見る/見られる」「経験する/される」はさらに細かな区別分節の連鎖的絡み合いであり、異なる一人一人の人によって見え方、経験のされ方におおきな違いがある。同じ「わたし」でも昨日のわたしと今日のわたし、何かを知る前のわたしと知ったあとのわたしとでは、違いがある。
主観にとっての世界、と書くとかえってややこしくなるかもしれないが、私たち一人一人によって経験される世界というのは、それを経験するわたしたちひとりひとりに限ってのものである。
もちろん、私たちは表面的に同じような言葉を喋っている仲間同士のあいだでは、みんなで寄ってたかって同じようなパターンで言語的意味分節=言葉の配列を行うが故に、だいたいみんな「同じ」ような世界を区切り出しているように感じられる。
それこそが”私「たち」が見ている世界”である。
わたしが見ている、ではなく、わたし「たち」が見ている。
見ること、経験すること、特に伝承された言語によって意味分節することは、集団的で反復的な営みであって、そこになにか「確かさ」のようなことがあらわれる。
*
見えている世界は、現実の世界ではない
ロヴェッリ氏の本で、気を付けておきたいコトバは、上に引用した箇所にも出てきた「現実」である。
私たちが見ている世界、と、現実の世界。
経験する/される世界、と、現実の世界。
ここに”ふたつ”の世界が区別され対立することになる。
現実の”反対”はなにか、といえば、”非現実”ということになろうか。
私たちが経験する/私たちに経験される世界が、現実の世界と対立する。そう考えることが科学的思考の道を開く。
しかしそうなると、私たちが経験する/私たちに経験される世界は、現実に対する”非現実”の側に振り分けられてしまう。
現実 / 非現実
|| ||
( )/ 私たちが経験する・される世界
私たちが日常素朴に「世界」だと思って眺めているものは、現実の世界ではなく、非現実だ。このようなことを言われると怒り出す人もいるだろうが、なにも怒る必要はない。
これは意味分節の問題だからである。
通常素朴には、「現実」といえば「私たちが経験する・される世界」のことだと思われているが、これをあえて逆にする。私たちの身体が感覚的に経験できる世界を非-現実の側にわざとおくことで、上の図式でいえば( )の中に何が入るのか? 現実の側には「私たちが経験する・される世界」以外の一体何が入るのだろうか??
と、このような問いを問えるようにした。それが科学である。
言い換え先を空白にする
重要なところなので、繰り返し敷衍してみる。
現実というのは通常の意味では私たちが現に、実際に、リアルに経験していることを意味する言葉である。手に持っているガラスのコップは現実だし、それを落として飛び散った欠片も現実だし、その欠片に不用意に触れた指から流れる血も現実である。どう考えても現実である。コップも実在するし、欠片も、指も血も実在する。これは虚構でもなければ幻想でもない。
つまり、あえてわざわざ科学的な思考という名の論理体系の内部に入り込まない限りは、わたしたち一人一人の日々の経験する/されることは、下のような図式で非現実ではない「現実」の方に振り分けられるのである。
現実 / 非現実
|| ||
私たちが経験する・される世界/ ( )
参考になりそうなマルクス・ガブリエル氏の『なぜ世界は存在しないのか』の一節を引用してみよう。
「人間の存在と認識は集団幻覚ではありませんし、わたしたちがなんらかのイメージ世界ないし概念システムに嵌まり込んいて、その背後に現実の世界があるというわけでもありません。むしろ新しい実在論の出発点となるのは、それ自体として存在しているような世界を私たちは認識しているのだ、ということです。」
こういう「私たちが経験する・される世界」=「現実」という強烈な意味に貫かれながら、あえて”逆にしてみる”というのが科学のとんでもなくすさまじいところである。
それこそ弾圧もされるはずである。
*
たびたび繰り返し書くが
現実 / 非現実
|| ||
私たちが経験する・される世界/ ( )
を
現実 / 非現実
|| ||
(○○○○○○○○○○○○○)/ 私たちが経験する・される世界
にひっくり返してみるという悪戯のようなことが、科学的思考に道を開く最初の一撃である。
洋食器のスープ皿を片手で持ち上げつつ具を箸で口へと送り込むとか、そうめんをナイフとフォークで細かく刻みながら口に運ぶとか、そういうことである。
*
このひっくり返しのあとに、ようやく、この新たに「現実」とくっつくことになった(○○○○○○○○○○○○○)を、一体なにで、どうやって埋めようか、ということを議論する余地が生まれるのである。
ここで(○○○○○○○○○○○○○)を山勘で穴埋めして「以上、おわりです」と止まってしまうのではなく、人間に可能な記号の論理を組み替えながら、(○○○○○○○○○○○○○)の中身を仮設しつづけることが科学である。この辺りの話は書きの記事にもかいているので参考にどうぞ。
ロヴェッリ氏の言葉に戻ろう。
「世界がどのように機能しているかについて、わたしたちは往々にして誤った先入観を抱いている。科学の精神にもとづく観察と理性が、わたしたちの先入観を正してくれる。空間には、物体が落下するための「特定の方向」は存在しない。大地にとっては、あらゆる方向が等価である。」
ロヴェッリ氏は物理学者であり、いわゆる「理系」の人であるため、ここに書かれた科学や科学の精神や観察や理性といった言葉を自然科学に限った文脈で読みそうになるが、よくよく考えるとそうでもない。
一人一人の生きた人間にとっての言葉とその意味の経験を、観察者である他の人の言葉と意味の経験に映し出し、仮設的な記述としてピン留めしてみようとするある種の人文社会科学にとってこそ、ここでいう「観察」と「理性」が重要になるように思う。それはつまり、複数の意味分節システムを重ね合わせることで、ある常識的日常性のなかで固着してしまった意味分節システムを可動的にし、今まで問うことができなかった問いを問うことができるようにすることである。
最近の人類学などは特にこうした課題に取り組んでいると言えそうだ。
ここで上の引用の最後の言葉が俄然輝き始める。
”空間には、物体が落下するための「特定の方向」は存在しない”
*
上と下、高いと低い
「世界」「現実」に続いて、素朴な経験の分節システムから引き剥がされるのは、「上と下」「高低」である。
りんごの木の根元で昼寝をしていたら、りんごが「上から下へ」落ちてきた。
何を当たり前のことを…。
と、思われるかもしれないが、この「上から下へ」こそ、素朴な意味で「現実」の、経験する/される世界の、先入観的意味分節の最たるものである。
「上から下へ」などということが言えるようになるためには、まず事前に予め、上と下が区別されていないといけない。
上と下の区別なんて、されるもされないも、みりゃわかるだろう、と思われるかもしれない。まさに、たしかに、みりゃわかる。
そしてこの「みりゃ」+「わかる」こそが大問題だという話をしているのである。
「みりゃ」は環境に埋め込まれた感覚ー神経系ー身体が動くことであり、「わかる」というのは他ならぬ分けること、最少構成の場合、二つの極のどちらかに振り分けることである。
科学においては自然科学でも人文科学でも、いずれにしても「わかる」という言葉が出てきた瞬間に、大いに警戒したほうがいい。警戒するどころか、慄いた方がいい。「わかる」は身体的、文化的に限定され制約された私たちの見方・感じ方が「現実」の「世界」を捉え逃していることを表明する言葉であるかもしれないのだから。もちろん「わかる」は科学的な思索の過程にも登場するだろう。ただし、後者の場合の「わかる」は、あくまでも仮設的で暫定的、未確定的な「試しにわけてみました、しらんけど」というニュアンスの「わかる」である。
ロヴェッリ氏の言葉に戻ろう。
高い / 低い
「重量のある物体が落下する方向を規定する、「高い」と「低い」という概念は、わたしたちの世界認識の基礎になっている。[…]だが、アナクシマンドロスの提案する新たな世界において、「高低」の概念には根本的な修正が加えられた。[…]慣習的な「高低」の概念は、現実世界における絶対的かつ普遍的な構造の一部ではない。」
またしても、とんでもないことが書かれている。
高い/低いは「現実」の「世界」の「絶対的かつ普遍的な構造」とは関係がない。
「「高い」と「低い」を規定しているのは大地である。[…]「高い」と「低い」は、大地の存在に左右される相対的な概念である。」
東京の路上を歩く人にとっての頭の上は、ブラジルのどこかで歩いている人にとっては足の下の下である。宇宙にまでスケールを広げると、絶対的な上も絶対的な下もない。高いと低い、上と下。これらの二極の関係は、あくまでも地球という惑星の上に乗っかっている人間という動物の身体と象徴言語が分節化することによって作り出した概念のセットである。
静と動
人間という動物の身体と象徴言語が分節化することによって作り出した概念のセットといえば、静と動の区別もまたそうである。
「コペルニクスの革命を補完したのはガリレオだった。ガリレオは、絶対的な「静止」も「運動」も、この世界には存在しないと洞察した。大地のうえに折り重なっている物体の視点に立てば、たがいにたがいが静止しているように見えるだろう。だが、それは必ずしも太陽系という「系(システム)」において、大地が静止していることを意味しない。」
動くとか止まるとかいうことは、何かが何かに対して動いて見えたり止まって見えたりするという話である。
ここから「わたしたちの「現在」は宇宙全体には広がらない」という話につながる。「時間」が宇宙全体で同時に同じ時刻を刻みながら流れている、という見方は地球上の人間にはたまたまそう見えているだけで、「現実」の「世界」の法則ではない。
* *
世界、現実、上/下、高/低、動/静、時間、空間
私たちが日常を生きる上で、ごく当たり前のように言ったり書いたり読んだり聞いたりしているコトバたちは、地球という惑星の上で伝承されたシンボルを交換しながら集まって暮らしている人間たちに特有のものである。その「業(カルマ)」の流れの澱みのようなところから、あえて「世界は、わたしたちの目に映るとおりではない」と宣言することで科学ははじまる。
想像と仮定、科学的な知の暫定性
科学は、言葉をはじめとするシンボル体系を日常素朴な意味分節の体系から引き剥がし(あるいは日常のものから独立した記号のシステムをあらたに立ち上げ)、いくつかの概念からなる論理のシステムを構築する。その論理のシステムの中で、わたしたちひとりひとりが日常的に経験する/される仕方とは違った形で「世界」を記述できるようにする。
「科学とは、世界について考えるための方法を探求し、わたしたちが大切にしているいかなる確かさをも転覆させて倦むことのない、どこまでも人間的な冒険である。人間がなしうるなかで、もっとも美しい冒険のひとつ、それこそが科学である。」
ここでロヴェッリ氏は「知の暫定性」ということを書いている(p.175)。
科学の知は、どこまでいっても永遠に「暫定」的である。逆に言えば、暫定的ではない(確定している)と称する知を、かたっぱしから暫定的なものの地位に送り返し続けることこそが「科学」である。
「観察と理性が、知を獲得するためのもっとも優れた道具であることは事実だろう。だが、純粋な観察や純粋な理性によって確実な知を打ち立てられるという発想は、間違っていると言わざるを得ない。」
科学の「敵」は、不確実性ではなく、確実性である。この言葉はよく噛み締めたい。
ロヴェッリ氏も書かれているように、しばしば科学と一緒のことだと混同されてしまう「技術」においては「確実性」は追求すべき絶対的価値である。走行中にバラバラになる高速列車や、飛行中に羽が外れる飛行機など、乗りたくはない。技術の世界には「確実」ということが確かにある。
しかしこの技術的確実性を探求することは「科学」それ自体の”目的”ではないとロヴェッリ氏は書く。
科学は、新たな世界の見方を暫定的に提案する。
この提案を行う者も、この提案を吟味する者も、「人間」である。
地球上に生き祖先から受け継がれた言葉でものを考えざるを得ない「人間」にも”わかる”ように、新たな世界の見方を、従来からの世界の見方と対比しつつ、言葉で、記号の体系で、記述しなければならない。この記述には一貫性と正確さが求められるのであり、ここでさまざまな技術の技術的確実性が、大きな力を発揮する。科学は、今を生きる人間たちの間に限っては「確実な」技術を用いて、不確実な観測と記述を暫定的に試み続ける。
「知を打ち立てるにあたっての、確実かつ無謬な土台は存在しない」
◇ ◇
この話を読んで思い出すのは、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』の冒頭である。
「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」
ここにある「生のもの」と「火を通したもの」のような「経験的区別」を組み合わせて、いくつかの(最低4個の(=二項対立関係の対立関係))概念からなる命題を組み立てていくことを、レヴィ=ストロース氏は「野生の思考」と呼ぶ。
野生の思考というのは、人類の祖先が多義性を特徴とする象徴言語を自在に用いることができるようになった頃から営々と、さまざまな疑問に対する暫定的な答えを仮設するために用いられてきたと推察される。
この野生の思考が、ロヴェッリ氏のいう「科学」とよく似ていると思う。
不確実な謎に対して「わからん」とやるのではなく、暫定的に仮設的に試しにわかってみようとする。そしてそのわかり方を次から次へと組み替えていく。
この組み替えの出発点が、上/下、高/低、動/静という類の「経験的区別」からはじまるという点もよく似ている。
そして、上は下であり下は上であり、動は静であり静は動である、という具合に、対立する両極を相互に「包摂」させることが、新たな見方=新たな意味分節体系を仮に発生させていく原動力になるのだという考えもおもしろい
そこには「アニミズム」の論理が動いている。
理論物理学者のロヴェッリ氏に対して「アニミズム」とはどういうことか?!と訝しがられるかもしれないが、ロヴェッリ氏ご本人はおそらく何も驚かれないだろう。ロヴェッリ氏は他の本でナーガルジュナの『中論』や、レンマの論理のようなことにもすでに言及されている方である。
なにより関係論は、野生の思考としてのアニミズムの論理とそっくりである。
「科学」にとって重要なことは、論理である。論理は区別と結合のパターンであり、区別と結合の結節点に配置されるのは概念たちである。概念と概念、項と項を結び合わせたり切り離したりすることで、論理は蠢きつつある構造を出現させる。
この論理が構造を発生させる”区別と結合のパターン”を多様に発生させていくことが特に重要であり、アニミズムやレンマや両義的媒介項は、この多様な”区別と結合のパターン”の可能性を探索していくことに寄与する。
ここで思い出すのは中沢新一氏の『野生の科学』という本である。
これについても書いて見たいが長くなってきたのでまた次の機会にしよう。
◇ ◇
止まっているように感じられる大地が、実は動いており、宇宙空間を高速で飛んでいる。いまこの瞬間も、地球という名の巨大天然宇宙船に乗って、太陽の周囲を高速で”宇宙飛行”しているのだと思ってみるのはどうだろうか。
なんだか楽しい気分になる人もいるかもしれないし、目の前の煩わしいことがほんとうにどうでもいいことだと思えるかもしれない。現世の年収では死ぬまでに宇宙旅行に行くことはできないだろうという暗い気持ちが吹っ飛ぶかもしれない。あるいは真っ暗闇の死の深淵にポツンと放り出されているようで、言い難い恐怖に戦慄するひともいるかもしれない。
「現実」の「世界」についての「見方」を一つ以上にする可能性を模索するような諸概念の論理構造を編むことができるかどうか。
科学的な思考はここから始まるのである。
関連記事
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
