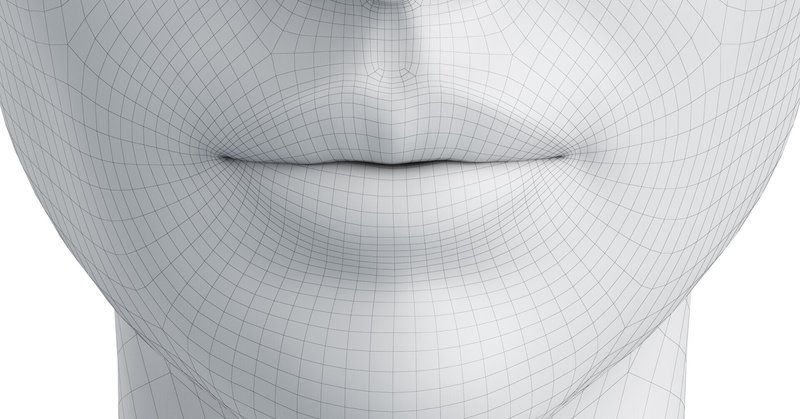
小説(つまりこれは真実なんかじゃない)・けれど・確かな痛み
目が覚める。ひとり、音のない部屋でうずくまっている。開け放した窓からは18度ほどの空気が流れ込んでくる。まだ皆目消化不良の咀嚼物が胃から吐き出されようとしている感覚がある。持ってきていた「お気持ちの薬」もそろそろ切れる。それがなければ生きていけないわけでもないし、毎日飲んでいるわけでもない。胃液が上がってくるような日、やるせない自己嫌悪で寝れないとき。こまやかな条件が付せられた私の精神安定には、いつも他者への恐怖が付随している。
暗闇の中でスマホを探る。冷たくなった金属の塊を探し当て、指先で軽く触れる。2時17分。首から頭にかけての鈍痛が思い出したようにまた痛み始める。どうでもいい通知や、明日の予定のリマインドや、返すべきラインや、返さなくてもいいけど返した方がいいメールや、返すべきだったメールや、Twitterでの新規フォローや、ショッピングサイトの割引コードの通知。それらが暗闇の中で煌々と光っている。スマホの輝度を最低レベルに下げる。疲れ切って、横になっている間に寝てしまったのは、何時だっただろうか。確か21時ごろ——とすれば、5時間ほどの間に20数件の通知が来たことになる——、20数件の、私へのこまやかな条件。このうち、私のことを信じているのは、何件あるのだろうか。少なくとも、これぐらいは。それがなければ生きていけないわけでもないし、毎日それがあるわけでもない。大概のことは、「それがなければ生きていけないわけでもない」。けれど、そうした必要不十分な事柄に、人は苦しめられ、人を傷つけてしまう。スマホを再び暗闇の奥に押しやる。「誰も私を愛してはいないのだと再確認するとき」というジェスチャーがあるのだとしたら、まさに、ぴったりと、こうなのだと思う。暗闇の中にスマホを押しやること——同時に、あまたの通知の中で、私に本当に話しかけたいと思う人などいないと感じること——、その手の動き、胃の痛み、冷たい風、明日への軽い失望、朝が来なくていいと願うと同時に、朝しか来ないで欲しいと思うこと。
返信が欲しいと願えば願うほど、人に期待すればするほど、来てしまった返信や、軽い言葉に絶望してしまう。私という生き物は、簡単に絶望しきってしまう。言葉を認めたときに、例えばあなたや私や彼や彼女が、私という存在にあてがう言葉の選択の断片をそこに落とすかということ、それが私にどんな価値を与えてしまうかという思慮の欠落した言葉を送ることを認めるときに。失望を与えることは容易い。けれど、深い喜びや、言葉が通じ合っている!という交歓は、そう易々と生み出されない。暗闇の中で、胎児のように体を丸める。私という哺乳類の個体から発せられる熱が、いくばくかの温度を生み、存在理由の肥大を増長させている。連日報道される医療の逼迫の現場。「この酸素吸わなかったら死ぬからね」「助かる命も助からないんです」「私はいいから、この子を助けて欲しいんです」。果たして、彼らのうち、本当に喜ばれる生命は、つまり、死んだとき、本当に悲しまれる生命は、いくつだろうか。私は、私という存在を、しっかりと悲しむことができない。安直なドラマや、安直な物語行為に加担したくないとはっきり感じているから。
あなたが声を出す。「寒いね」。あなたが声を出す。「そうっすね」。あなたが声を出す。「私のこと、好き?」。あなたが声を出す。「そうっすね」。あなたが声を出す。「あなたは、生きている?」。あなたが声を出す。「そうっすね」。
いつまでもあなたが声を出している箱庭を眺めて、あなたは「くだらない」と言う。ここには音がないのだし、ましてや、リアリティなどない。南極の氷が崩落していくように、滑り台から杏仁豆腐が滑り落ちていくように、あなたが私と言う存在から滑り落ちていく。まるで、何事もなかったかのように、そこにいたはずの存在や匂いや温度は遠くて、私は、そらまめだと思う。そらまめ。中の豆が抜け落ちた、そらまめのサヤはひどく滑稽だ。そこに何も存在しないのに、まるでそこに、なにものかが(それもとてもとても大事なものが)存在しているように、ぴんぴんしている。笑ってしまう。くつくつ笑い転げる。あなたを忘れることなど、同時に、私を忘れることなど、何もできないまま、痛みだけがそこで、ぴんぴんしているのだから。あなたや私や彼や彼女が、同時に、私に対する交信不能で痛みを抱えているのならば、その痛みの有無をどこかに表示してほしい、神さま、と思う。そう、例えばその人の頭上にそらまめが2個浮いているとか。だとしたら、そのそらまめ2個の人に、私は「おはよう、一緒にそこまで行かない?」と言おう。そらまめ2個分の悲しみを、私はあなたと一緒に携えたい。あなたが私のために悩んだり痛んだりした時間だけ、その痛みぶんだけ、私も痛みたい。そうすれば、私は私という存在を悲しむことができる。それはすなわち、喜ぶことができるということでもあるのだから。
あなたが声を出す。「もういいよ」。あなたが声を出す。「なんで?」。あなたが声を出す。「もうそばにいないから」。あなたが声を出す「なんで?」。あなたが声を出す。「すなわち、私はもうここにいないから」。あなたが声を出す。「なんで?」。
通知だけが光っている。あなたはそばにいないのに、私だけが滑稽なメッセージをそこらに撒き散らしている。そばにいないのに、言葉を送るということが、たくさんの悲劇を日常化させてしまった。言葉は同時に呪術であり、それゆえ、有史以降の歴史において、科学と宗教の未分離なときを、魔術化された社会と呼んだ。言葉が全てを担い、濃密な日々の合間や、人と人の間を取り持ってきたことを、未発達と呼ぶのなら、私たちは私たちの成長過程の中でも同時に、社会の構造変化を経験していることになる。社会はマクロであり、ミクロでもある。私が〈飲む〉とき〈飲まれて〉いる社会。たくさんの悲劇が日常化した私たちの人生(=社会)の中で、私たちは、毎日、私たちを弔っている。荼毘に付した、「私たちだったもの」が、美しい過去として永遠にSNS上に埋葬されている(ほら、例えばいいね欄が)。
いいね欄をそっと覗いたり、リプライを観察したり、投稿を見つめたりして、勝手に私たちは悲しくなったり喜んだりする。リアルの不在にかまけて、私たちはバーチャルな世界での実在や虚構を真実だと思い込む。そこにあなたはいないのに! そらまめも、中身が抜け落ちたままサヤの形を保っていることに気付くべきなのだけれど。けれど、だけれど、私たちはその虚構性から離れることは、多分、一生できない。私たちの生命それ自体虚構の寄せ集めのようなものだから。蝟集した虚構性(学歴、SNS上での立ち振る舞い、ファッション、髪型、マナー、手触り、視線…)が一つの印象を生み、ある定義づけを成してしまう。クロードモネ。あれが、あれであったように……。みなもに映る陽光は、陽光として描かれるより早く、それらの印象によって構成されている。同様に、私という印象や、あなたという印象も、社会的に構成された言語や虚構やプリズムを脱ぎ落としてしまったら、何が「感じられる(able to recognize)」だろうか。裸の——体毛がまとわりつき、歪な筋肉や脂肪がそこらにあって、何ひとつ飾るもののない——状態をこそ、存在と呼ぶのなら、現代社会はあまたの存在を滑落させた虚しい滑り台だ。裸で言葉にならない淫猥な喃語を発し続ける動物的な存在だけが満ち満ちて、素晴らしき原始大陸のみがある(パンゲア!祝福の旋律)。
あなたが声を出す。「服を着て」。あなたが声を出す。「うん」。あなたが声を出す。「髪を切って」。あなたが声を出す「うん」。あなたが声を出す。「それが人を愛するということだから」。あなたが声を出す。「うん」。
パンゲアが、音を立てて崩れ去っていく。ごうごうと。マルジェラのプルオーバーを纏い、ラルチザンの香水を太ももに擦り付け、エフェクターの眼鏡を掛け、音のない部屋に音を灯していく。同時に、非パンゲア的恋愛がそこらに生まれていく。たとえばブリーチを重ねた髪や、タトゥーを入れた肌や、指輪や、きついジーンズや、ロゴマークがそこらに付されたカバンや……。いくつもの分化を伴った大陸の上で、あなたと私の間の共約可能性が拡げられていく。
あなたが声を出す。「私を見て」。あなたが声を出す。「あなたを見ている」。あなたが声を出す。「私を愛して」。あなたが声を出す「あなたを愛している」。あなたが声を出す。「あなたを愛して」。あなたが声を出す。「私を愛している」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
