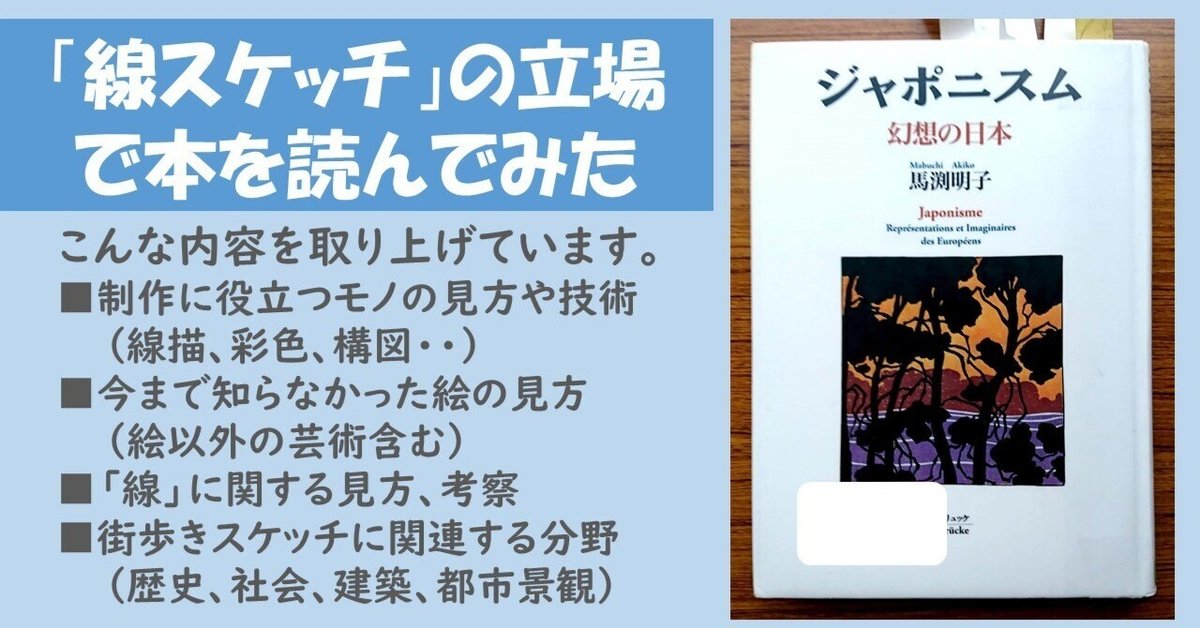
<ジャポニスム 幻想の日本> 馬渕明子 ㈱ブリュッケ(新版2015)その2.(2)
はじめに
前回の記事、その2.(1)では、日本独自の構図、<すだれ効果>をモネが作品「木の間越しの春 Primtemp a travers les branches」で採用した可能性が高いというところまでで終えました
では、どのような経緯で<すだれ効果>を採用することになったのか、著者の考察が続きます。
なお、この記事が読みやすいように議論の対象になっているモネの絵を下に再掲載します。

Public Domain via WikiArt
北斎の「竹林の不二」と歌麿の「四つ手網」
まず、モネの浮世絵コレクションの中に、葛飾北斎の「富嶽百景」があり、モネが「木の間越しの春」を発表した一八七八年以前に蒐集したものか分からないけれど、その中の「竹林の不二」が影響を与えたのではないかと推測します。
「竹林の不二」は、直接画像をお示しできないので、下記「山口県立萩美術館・浦上記念館 作品検索システム」からご覧ください。
http://www.hum2.pref.yamaguchi.lg.jp/sk2/book/E00/U0014704.jpg
画面の前景を占める竹林は画面全体を覆い、この作品の本来の主題である富士山がその向こうに見える。つまりここでは<すだれ効果>が用いられ、直接ではなく竹林越しに天下の霊峰を望むという、いささかひねった構成となっているのである。
さらに「竹林の不二」についてジークフリート・ヴィッヒマンの著書を引用しています。
後期の浮世絵の画家たちにとって、画面の中に格子を挿入することは特別な意味を持っていた。一方でそれは後方に展開する情景から前景を切り取るが、また時には驚くべき視覚的な移行を持つ空間統一をもたらす。北斎の風景はこの技法の好例を示す。例えば「竹林の不二」である。
最後に1878年制作のバカラ・クリスタル製の花瓶には「竹林の不二」そっくりの竹の文様が彫られていることから、かりにモネが「富嶽百景」を1878年当時所有していなくても「竹林の不二」は当時十分知りえただろうと推測します。
一方著者は、北斎の「竹林の不二」はその線的表現によって構図の鋭さを示しており、それはモネの作品から受ける色彩的、柔らかな印象とは違うと感じ、北川歌麿の「四つ手綱」における漁網の方が近いかもしれないと下に示す絵を挙げます。

I, Sailko, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
以上の北斎、歌麿のどちらの作品の影響にせよ、モネの「木の間越しの春」の空間表現は日本の絵画の<すだれ効果>の影響を受けたのだという結論ですんなり終わると思いきや、私にとって思いがけない方向に議論が展開していきます。
それは構図の選択の問題ではなく、「絵画において対象を見て描くとは何か」という人間の視覚の問題です。
《閑話休題》実物を見て描くとは?
話が思わぬところに進みました。ここで、線スケッチ教室で受ける一番難しい質問について紹介します。
線スケッチについて教室では「写真を使わず必ず現場で実物を見て線描することが原則です」と説明していますが、それに対して次の質問が必ず出てきます。
「なぜ写真ではなく実物を見て描かなければならないのですか?」
それに対して、人間の目で見て描くのと写真を見て描くのは根本的に違う、そして描いた絵にどのような違いが出るか私の考えを模式図を使って説明しているのですが、ここでは詳細を省きます。
ただ自分の独りよがりな考えだけではだめだと思い、これまで様々な技法書や絵の入門書を読んで誰もが納得する説明を探したのですが、あってもあっさりとした説明で済ませるだけで、きちんとした説明として印象に残るものはありませんでした。
いずれ、この件に関しては別の記事にしたいと思います。
本書では<モネの視覚体験>の小見出しの中で、私にとって予想外の上記問題に関連する考察を進めていました。以下紹介します。
モネの視覚体験
著者は、北斎の「竹林の不二」と歌麿の「四つ手網」のいずれも《木の間越しの春》と似たところを持ちつつも、基本的に描こうとした世界が異なる印象だとしてその理由を探ります。
モネの《木の間越しの春》が北斎と歌麿らの作品と異なる点は、木の葉の向こう側を描くために<すだれ効果>を用いているのでもなければ、構図の意外さやおもしろさを追求したものではないことである。(中略)ここに描かれているのはモネ自身が見た情景であり、彼のカンヴァスはまさに、風に揺らぐ木の枝の真ん前に置かれている。
歌麿や北斎の作品は目の前の世界ではなく、自分の知っている世界、経験した世界を抽象化して描いているとし、モネはあくまで眼前の木の葉、それを通して見える向こう側の景色も対等な対象としてモネの視野の中にあるがゆえに彼は描いているとその違いを指摘します。
要はモネは<すだれ効果>を利用しているけれども、それを自分の視覚体験に置き換え、自分の芸術の目的に引き寄せているのだと。
これを受けて、「現場で、実物を見て描く」ときの人間の目の焦点の役割について考察が進みます。
それはまさに私が関心を持っている人間の目と写真との違いについての記述でした。少し長くなりますが、引用します。
簾でも、竹林でも、木の葉でも、近くにある何かを通して向こう側の景色を見る場合、私たちの眼は、まず手前の遮蔽物に焦点を合わせ、次いでその奥の世界を見るために焦点距離を変える。さらに厳密に言うと、奥の世界においてもまた、それぞれの対象の距離に応じて焦点距離は変化してゆく。焦点をどこかに合わせる写真の場合には、それをどこにするかを選ばなければならないが、絵画の場合、そこに制作の時間が介入するため、画家はそれを曖昧にすることができる。
私の言葉で補足すれば、「写真は機械なので一義的(物理的)に焦点を決める必要がある(あるいは決まる)が、絵画の場合、制作する時間的な幅の中で、画家は(眼の網膜から脳を通じて)曖昧にすることができる」となります。
簡単にまとめれば「写真は静的、人間の眼は動的」ともいえるでしょう。
著者は、モネはこの作品において、焦点が避けて通れない問題であると認識しているのではないかと推測します。
ここにおいては木の葉は決して微細に質感を伴って描かれていないが、遠景の曖昧さとくらべると、焦点がそこに当てられていることがわかる。そして、そのちらちらする柔らかい葉の表現は、それが動いているという印象を与えるのである。
このあと、チャールズ・スタッキーのモネのこの絵を描いた当時の関心事である網膜生理学に基づくモティーフ選びについての文章の引用のあと、次の文で小見出し「モネの視覚体験」が終わります。
モネが日本美術でよく用いられる構図をみずからの作品に利用したのは、単なる珍しいものへの興味からではなかった。それは、対象を見て描くとは何か、という問いに答えるためだったのである。しかし西洋の伝統の中からこの答えを見つけることは、ほとんど不可能であった。いったい誰が「竹林の不二」のような作品を作り得たであろうか? ルネサンスが確立した遠近法はあくまで概念であって、実際の人間の視覚は、もっと多様な経験をする。すだれ状のものを通して向こう側を見たり、高いところから真下を見下ろしたり、見上げたり。小さい穴から覗いたり、対象を至近距離でとらえたりする。しかし、概念にとらわれる人は、自分は常に遠近法の世界で対象を見ていると錯覚する。そうした概念にとらわれない人々、すなわち異なったヴィジョンの体系にいた日本人の作品は、遠近法的な概念の世界から抜け出そうとしていたモネの大いなる助けになったのである。
ここにきて、写真と人間の眼との違いだけでなく、遠近法の世界とそうでない世界についてにまで記述が及ぶことになりました。
実は<閑話休題>でとりあげた、なぜ写真を使ってはいけないのかという生徒さんの問いには、その背後にもう一つの本質的な問題が潜んでいるのです。
それは、皮肉なことに日本人であるにも関わらず、現代の日本人は生まれて以来写真を見慣れていて、遠近法に基づいて「写真のような正確さ」で描きたいと無意識に思っている、あるいは自分の眼では遠近法を描くのが難しいので写真を利用したいと思っていることです。
著者の言うように遠近法は西洋が作りあげた「概念」に過ぎないのです。しかし遠近法による描写は大事な技法のひとつなので必ず教室で教えることになります。ですから、「大事だけれどそれにとらわれないで描いてほしい」と分かりやすく説明して理解していただくことが大変難しく私の悩みです。もちろんそれは私の教え方の実力の無さが原因ですが・・。
さて、<モネの視覚体験>で著者の考察が終わるのかと思ったらさらに<イメージの重なり>と題して、《木の間越しの春》を制作した以後、彼の作風はさらにその後大きな展開を見せていくことを述べて終章に向かいます。
続きを、その2.(3)で紹介いたします。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
