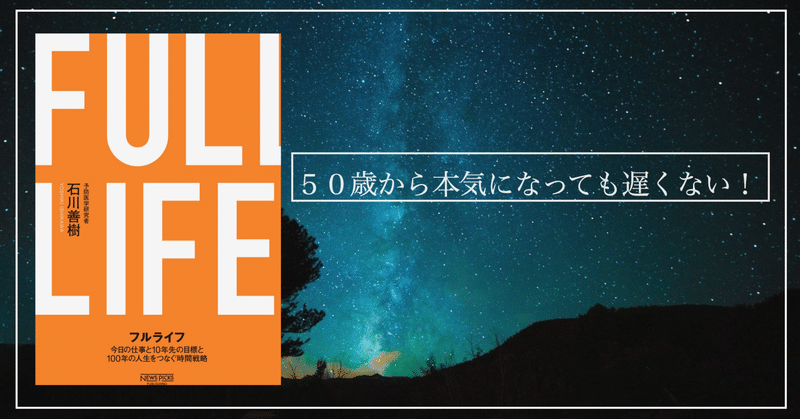
3つの「時間軸戦略」を考える|【フルライフ】
どーも!
わーさんです!
日曜日ですので、#2021年に読んだ本の紹介 をしていきます。
先週に引き続き、今週も「人生100年時代」をテーマにした本を紹介していきます。
・・・
『フルライフ』
石川 善樹
著者
石川 善樹(いしかわ よしき)
・予防医学研究者、博士(医学)
・1981年、広島県生まれ。
・東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)所得。
・公益財団法人 Wellbeing for Planet Earth 代表理事。「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマとして、企業や大学と学際的研究を行う。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念工学など。
本書の概要
・人生100年時代の”時間戦略方法”
・”重心”を見つける
読んだ感想をTwitterに投稿しました!
#2021年に読んだ本の紹介 #7
— わーさん@【学び×読書】の伝道師 (@W_notenoter11) February 14, 2021
『フルライフ』
石川 善樹
概要
・人生100年時代の”時間戦略方法”
・”重心”を見つける
人生100年を「春夏秋冬」で考えることができる一冊。
商品はこちら↓https://t.co/jzZIKBDMmS#ビジネス本 #読書 #本 #読了
今回は、人生100年を過ごすための時間戦略として打ちたてている「3つのフェーズ」を紹介していきます。
===
◉ハードワーク期

ハードワーク期は得に大切です。
「人生の基盤」になると言ってもいい時期です。
この時期の時間の使い方が大切になります。
ハードワーク期における時間戦略で、
扱う時間のスケールは以下の通りです。
・1日
・1週間
・3〜10年
この時間設定が大切になります。
・・・
「1日」の過ごし方で大切なのは、
「うかつに仕事を始めない、そして、うかつに仕事を終えない」ことです。
仕事や学業など、自身がやっていることに当てはめて考えてもらいたいのですが、大切なのは「始める前」と「終えた後」になります。
始める前にその日にやるべきことを洗い出してから仕事を始める。
例とすれば「To Doリスト」などを作成してから、視覚的に何をやるべきか確認しながら行うことが大切です。
そして、仕事を終えた時。
定時になったからすぐに帰るのではなく、その時間になるまでに「その日の振り返り」と「次の日の準備のための時間」を作る。
これが大切です。
特に、その日の振り返りをすることは、大きな成果は出なかった一日だったとしても、「しっかりと仕事をしたという実感」を得ることができます。
その積み重ねが大切になってくるのです。
本書では「To Feelの振り返り」と述べています。
つまり、仕事の終え方が大切だということです。
・・・
「1週間」の考え方としては、
基本的に「金曜日」が週の終わりと考える事が多いです。
しかし、これだと金曜日にハメを外し、土日に寝溜めをすることによって、時間が狂い、月曜日から気持ちよく仕事をすることができないことが考えられます。
これを「社会的時差ボケ」と言ったりします。
・・・
これを防ぐために、
本書では「土曜日スタート」にしようと述べています。
つまり、毎日決まった時間に起きる仕組みを作ることが大切です。
こうすることにより、
社会的時差ボケを防止し、仕事に打ち込むことができます。
また、本書では「金曜日の夜8時以降のスケジュールを黒く塗りつぶしましょう」とも述べています。
これによって、土曜日に平日と変わらない時間に起きることができます。
・・・
少しハメを外すのであれば「木曜日」に飲み会を設定する。
そのことにより、
金曜日は疲労感があるため、早く帰宅しようという気持ちになります。
これが、1週間を考えた時の理想のスケジュールです。
・・・
そして、「3〜10年」の設計をする際に考えることは、いきなり「10年」で考えるのではなく「3年単位」で考えるのが大切です。
「3年をひとつのサイクル」として考えることにより、最初の1年目は大きな成果が見えないとしても、次の2年目、3年目に変化として見えてくるのです。
これを、10年という長い期間でやってしまうと、自身の計画の方向性が見えなくなってしまいます。
そのため、10年を「3段階」にわけて考えることが大切です。
○イメージ
1段階:「1〜3年」
2段階:「4〜6年」
3段階:「7〜9年」
===
◉ブランディング期

次に「ブランディング期」の過ごし方です。
この時期に考えるキーワードは「創造性」です。
本書では、「大局観」が大切だと述べています。
・・・
まず「大局観」という言葉はわかりにくいので
将棋を例に考えます。
将棋の場合、
「序盤」「中盤」「終盤」と局面を3つに分けるのが一般的です。
序盤は研究や前例が多いため、ある程度手が決まっていることがほとんどですが、中盤以降は手が広い。候補が多いということです。
そのため、差し手に悩む場面が生まれてきます。
この時に「大局観」が大事になります。
まず、直感によって、
ある程度、考えられる手を探します。
そして、大局観によって、
俯瞰的に判断し、手を絞ります。
そして、論理をまとめて、
差し手を決めます。
この「絞り込む作業」が大切になってきます。
・・・
では、大局観が発揮される場面というのはどのような状況なのか?
本書では、
「ひとりでDoing」「みんなでBeing」という言葉を使っています。
「ひとりでDoing」は簡単に言えば、
「ひとりで作業する時間」ということです。
主に「ひとりで考える」と言った
思考を意識する時間が大切だということです。
現代はネット環境に溢れているため、時間があればYouTubeやNetflixを見たりして時間を使うことが考えられます。
その時間も大切ですが、
自分で「テーマを持って思考する時間」も大切ということです。
例えば、「自分の将来について」時間をかけて考える時間を作ることも大切になってきます。
「みんなでBeing」は「素でいることができる場所・機会」という意味です。
例えば、旅行や宴会、友人との趣味など、時に深く考えることもなく、気軽にコミュニケーションを持つことができる場所に参加する。
そこで出てくる「雑談」の内容が大切なのです。
この時期に「ブランディング力」を育むことによって、その後の人生の糧になっていきます。
===
◉アチーブメント期

最後に「アチーブメント期」です。
この時期が「本番」の時期になります。
ここで大切なのが「志」を立てることです。
「志を立てる」=「心からやりたいこと」
と考えることができますが、
それをすぐに想像できる人もそんな多くはいません。
そのため、ぼんやりでもいいので、
まずは「これをやりたい」ということを設定して、スタートさせることが大切です。
本書では、アチーブメント期を「50歳から考える」と述べています。
・・・
平成生まれの人は、
基本的に100歳まで生きることが考えられる世代です。
令和生まれであれば、
それが当たり前になっていることでしょう。
この100年時代を「春夏秋冬」で考えた時に、
人生のピークがちょうど「50歳」になるのです。
夏の時期が終わり、秋に入る頃です。
もちろん、これは肉体年齢や記憶などと言った老化関連とはまた別の話です。
つまり、言いたいことは、
「アチーブメント期に入る前に、いろんなことを経験して、輝ける準備をする」ことが大切だということです。
特に、今の時代、
終身雇用が崩壊し始めています。
ひとりの人間が一つの企業に勤めて生涯を終えることが、ほぼ不可能の時代になっていきます。
そのため、転職を何度もするのが、
普通になることが考えられます。
企業の寿命が昔と比べて極端に短くなっている時代において、人生100年生きる戦略としては「ひとつに依存するのではなく、たくさん依存する」ことを考えて生きていく必要があるのです。
そのため、自分がやりたいことを見つける時間がかかるということです。
50歳まで待って、そこから人生を考えるのではなく、
50歳までに人生経験を多く積む。
そこから「本当にやりたいこと」を残りの人生をかけて生活していくのが、これからの世代のあゆみになっていきます。
===
まとめ

今回は「人生100年時代の時間戦略」として『フルライフ』の書評をしました。
個人的な感想としては、時代の流れが激しい現代において、そこまで急がずに「50歳からでもいいのか」と思えたことがひとつの希望でした。
もちろん、それまでにいろんなことを経験して、思考して、結果を出す必要性もありますが、無理して急ぐ必要もない。
しっかりと、1日、1週間、1年、10年と計画をしながら行動していけば、50歳になった時に「志」を持って行動することができると思えました。
私は今年26歳になるので、本気になるまであと約25年あると考えると、この「25年」のうちにどのくらい、多くの経験をすることができるかが勝負になってくると思っています。
そして、3年単位で時代の流れを想像するのが難しい時代において「これは安定」という言葉を使うのも難しい。
そのため、「これは大切だ!」と思うことを信じて、追求することが後悔なく生きていけることなのかなと感じました。
本書は、図表も多く使っているので、
とてもわかりやすく構成されています。
ぜひとも、手に取って読んでもらいたい一冊です。
サポートすると、それがnoteユーザーのためになります✨ サポートよろしくお願いします🔥
