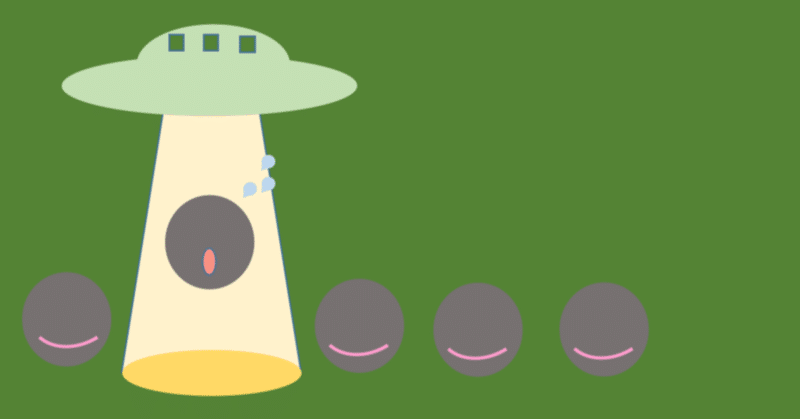
デザインリサーチとは? (その3:センスメイキング編) #197
前回はこちら
前回の「その2:情報収集編」では、質的調査の方法としてProvotypeやSemi-Structured Interviewなどのデザインツールを紹介しました。今回の「センスメイキング編」では、集めた情報から新しいインサイトを得るセンスメイキングについて紹介します。
なぜ、センスメイキングをするのか?
ここまでは情報収集に専念してきました。デザインプロセスのダブルダイヤモンドで言えば一つ目の探索のステージにいました。センスメイキングは、この図の二つ目の定義のステージであり、得られたデータから本質を捉えたInsight(インサイト・洞察)を得ようとしていきます。
ちなみに、情報収集のことをこの授業では"Kicking up dust"と言い、塵を巻き上げることになぞらえます。この言い回しになぞらえるなら、センスメイキングは巻き上げた塵に混じった砂金を見つけることでしょうか。

デザインリサーチではこのセンスメイキングのステップが必要になります。前回の記事で紹介したようにデザインリサーチにおいての情報収集は質的調査をするので、統計にかければ(計算すれば)結果が出るといった手順はありません。そのため、Provotypeで参加者がどんな反応をしていたか、Semi-Structured Interviewでどんな回答をしたかをデザイナー自身で解釈していく必要があります。
また、参加者の反応が相反することを示している場合もあります。または、たった一人からしか得られなかった回答があるかもしれません。デザインリサーチでは、こうした統計的には切り捨てられる矛盾や外れ値の部分にも注目し、むしろ矛盾や外れ値こそが問題の本質を捉えているかもしれないと考えます。こうした統計的には扱えないデータを拾い上げて解釈することが、デザインリサーチを行うからこその視点をもたらしてくれます。
センスメイキングで問題の本質を捉えることができれば、それに対する解決策もその場しのぎの対症療法ではなく、問題を根本から解決する原因療法を考えることにつながります。センスメイキングをする理由は、問題設定と問題解決のつながりを強固にするためとも言えるでしょう。
インサイトとは?
ここで少し用語解説を挟みます。情報収集によって、得られる情報をデータと呼びます。得られたデータから似たようなデータに分類できる法則をパターンと呼びます。こうしたパターンから得られる本質をインサイトと呼びます。
以下の図で言えば、dataはそのままデータで、infromationとknowledgeの部分がパターンで、insightの部分がインサイトですね。細かい分類は人によって異なるのでこの図や用語を覚える必要はないのですが、大事なのは情報収集をした後は得られたデータを抽象化して問題の本質を見抜くステップ(=センスメイキング)があるということです。

センスメイキング系のデザインツール
デザインツールはあるけれど
アイデアが降りてくるのを待つのも大事です。そうはいっても、ビジネスにおいては締切があるので、ある時点でアイデアを無理やりにでも生み出さなければなりません。そのため、デザインの世界ではアイデア発想法がいくつも考案されています。
アイデア発想法には、フォーマットが固まっているものといないものの二種類があります。フォーマットが決まっているものは、これまで集めたデータを整理してパターンを見つけるのに適しています。一方、フォーマットが自由なものは、新しいインサイトを生み出しやすいです。ただし、両者に優劣はないので、いろいろと試しながら自分に合った方法を採用すれば大丈夫です。
また、センスメイキングでデザインツールを使うのは、アイデアを思いつくためというのに加えて、センスメイキングをしたという事実を他人に可視化するという側面もありそうです。デザイナーが「私の直観ではこう思います」というよりも、「このデザインツールを使ってこのインサイトが得られました」と言う方が、他人にもデザイナーの頭の中が共有しやすく説得力があるというメリットもあるのでしょう。
授業では、「Challenge Mapping」「Ecosystem」「Theory of Change」「Stock & Flow, Causal Loop Diagramming」などの方法を学びましたが、一つひとつの具体的な使い方の説明は割愛します。というのも、これらのデザインツールを私自身使いこなせておらず、まだ上手く説明できないからです。デザインツールは知ればすぐに使えるものではなく、使い慣れることも必要なようです。
Abduction
デザインツールの紹介は控える代わりに、アイデア発想の思考法を紹介します。論理的な思考方法として演繹法と帰納法がありますが、どちらの方法でも新しい解釈は見つかりません。これらは前後で論理的な誤りがないことを重視する思考法(トートロジー的)であって、新しい仮説・視点を生み出す方法ではないからです。
そこで、新しいインサイトを得るために使われる論理展開が、Abduction(仮説形成)です。考え方としては、目の前の現象やパターンが生じる理由を遡って考えるというものです。
ダーウィンが進化論を見つけるまでの例が分かりやすいかと思います。「進化」という現象は現実世界では見えません。でも、彼は生きている生物の特徴をひたすら観察してデータを集めました。すると、共通の祖先がいそうな種同士がいることや生物の変化は環境の変化に則しているというパターンを見つけ、進化論というインサイトを得たのです。
ただし、Abductionは原因を推測する思考法で論理的な(トートロジー的な)正確さはないため、生み出したインサイトが誤りである恐れがあります。なので、インサイトの妥当性を検証する必要があります。
ケース・スタディ
パーソンズ美術大学・Transdisciplinary DesignのDesign-Led Researchという授業での体験から、今回の方法論が実際にどのように使われるのかを見ていく「ケース・スタディ」のコーナーです。今回は得られたデータとパターンからインサイトを得て、その妥当性を検証する流れを見てみましょう。
ここまでのリサーチで分かったパターンを整理します。
Careをする-されるというのは仕事上の関係だけでなく、日常生活で発生する関係性である。
人同士の関係だけでなく、セルフケアもCareの一種である。
セルフケアは軽んじられる傾向がある。
その理由は仕事などの忙しさであると思っている。
こうしたインサイトを踏まえて「セルフケアをしないのは、時間的な余裕がないからでは?」という仮説を考え、「もしそうならば、セルフケアをする時間的余裕を確保すればいいのではないか?」という解決策につながる仮説も生まれました。さらに、仕事が忙しくて時間的余裕がないのならば、週休三日制にするということが具体的な解決策になるのではないかという話になりました。
「みんながセルフケアをする社会にするために、週休三日制は有効なのか?」という問いを検証するべく、休みの過ごし方をテーマにしたSemi-structured Interviewを再び実施しました。しかし、週休三日制に対しての反応はイマイチ。どうやら休みの日が増えたとしても、セルフケアをしようというモチベーションがそもそもないし、どうやってセルフケアをすればいいのかもノウハウを知らないということが分かりました。

こうして「週休三日制を導入すれば、みんながセルフケアをする社会になる」という仮説は妥当ではなさそうであることが分かりました。
ということで、私たちは迷子になりました。"I take care of myself"と思う人がいる一方で、休みの日を増やしてもセルフケアにはつながらない。こうしたインサイトを前にして私たちは身動きが取れなくなってしまうのでした(ここまで読んだら「Abduction使ってないじゃん」と思うでしょう。まさにその通りで、だからこそ行き詰ったのかもしれません)。
まとめ
センスメイキングでは、得られたデータからパターンやインサイトを見つけ出すこと、また、インサイトはデザイナーの仮説であり妥当性を検証する必要があるということを紹介しました。
仮説検証の結果、ケース・スタディのようにインサイトが誤りだった場合はどうすればいいのでしょうか? 次回「その4:試行錯誤編」で、デザインリサーチで行き詰った時の乗り越え方を見ていきましょう。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
