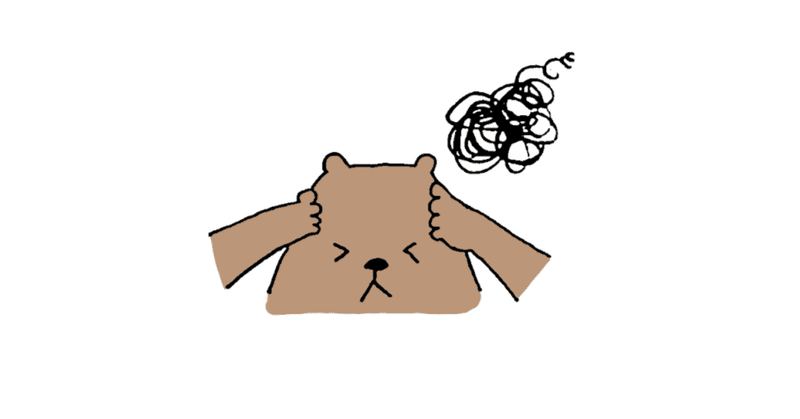
デザインリサーチとは? (その4:試行錯誤編) #198
前回はこちら
前回の「その3:センスメイキング編」では、「その2:情報収集編」で集めた情報からインサイトを得る方法を紹介しました。今回の「その4:試行錯誤編」では、得られたインサイトがイマイチな時の対処法を見ていきます。
行き詰まりから脱出するコツ
デザインリサーチでは「問題設定⇒情報収集⇒センスメイキング⇒問題設定⇒(以下繰り返し)」とひたすら繰り返すことで、問題の本質に近づくことを目指します。基本的にはこの3つのステップを繰り返していけば、デザインリサーチは進んでいきます。
ただし、「次にどう進めばいいのか分からない」という状況に陥ったり、「結局これが分かって何の意味があるんだっけ?」と我に返ったりすることもあります。こうした瞬間を行き詰まり(英語なら"Stuck")と呼ぶことにします。
デザインリサーチでは、ほぼ必ず行き詰まります。むしろ、行き詰ってからがデザインリサーチの始まりです。しかし、残念ながら、行き詰まりの解消に特化したデザインツールはありません。なぜなら、デザイナーがするべきなのは、これまでのプロセスのどこかで行き詰まったのかを見直すことだけだからです。
そのために、デザインプロセスの進め方のログを残しておくことが大事になります。ゲームで例えるなら、ステージが変わるたびにセーブしておくのです。そうすることで、行き詰った時にゼロからやり直す必要がなくなります。具体的には、以下の3つを常に記録しておけばいいでしょう。
①どんな問題に答えたいか?「その1:問題設定編」
②どのデザインツールで、どんな情報を集めたか?「その2:情報収集編」
③どんなインサイトが得られたか?「その3:センスメイキング編」
行き詰った時はこの記録を見直して、①そもそも設定した問題が不適切でないのか?、②問題は適切だけど、集め方が不適切or集めた情報が足りないのか?、③情報は十分あるけど、そこから導いたインサイトが適切でないのか?、などをそれぞれ検証します。
デザインリサーチのプロセスの記録を残しておき、行き詰まったら詰まっていない場所に立ち戻る。単純ですが、これこそが最も強力な黄金律です。こうした絡まった糸の結び目を一つずつほどいていくような地道な作業も、デザインリサーチです。
ケース・スタディ
パーソンズ美術大学・Transdisciplinary DesignのDesign-Led Researchという授業での体験から、今回の方法論が実際にどのように使われるのかを見ていく「ケース・スタディ」のコーナーです。
来た道を振り返るとき
前回は、"I take care of myself"とセルフケアの軽視という矛盾するインサイトを前に行き詰まってしまっていました。
このままではリサーチが進まないので、一旦状況を整理し直しました。これまでに設定した問い、使ったデザインツール、得られたインサイトを振り返ってみました。
ケアをする人の精神的な負担をどうすれば軽減できるのか?
ケアをする-されるの関係はどんなものがあるのか?
二人以上の関係だけでなく、セルフケアもケアの一種である。
仕事などが忙しくて時間的余裕がなく、セルフケアができない。
でも、休日が増えても、セルフケアをしようとは思わない。
ここまでのプロセスを振り返ると、セルフケアに注目すること自体は悪くなさそうです。でも、「忙しいからセルフケアをしない」という説明に基づいて考えていくと行き詰ったので、この仮説を見直す必要がありそうです。

空いた時間をセルフケアに充てない理由はなんだろうかと考えてみると、「セルフケアをするにはお金がかかる」というコメントをインタビューで答えた人がいたことが重要に思えてきました。
セルフケアをするにはモノやサービスにお金を払う必要があるとか、セルフケアをするよりもお金につながる時間の過ごし方をしなければという認識があるようです。こうして、セルフケアをすることは金銭的に贅沢なことであるという認識があるというパターンが浮かび上がってきました。
このパターンをさらに引いた視点で捉え直せば、資本主義では時間=お金という結びつきが強いと言えるかもしれません。また、資本主義では資本の増加につながる行為(個人で言えば自己投資)は評価される一方で、メンテナンスやケアは新たな価値を生まないので評価されていないのではないかという考察もできます。
こうした状況では、セルフケアは消費の一種であってお金がなければできない行為であるという思い込みが生まれます。また、他人のことを無償でケアすることはお金にならない行動なので、資本主義社会ではお互いにケアをする動機がなく、"I take care of myself"という状況が生まれてしまうと考えられます。このように、「資本主義によって"I take care of myself"に陥る状況とセルフケアの軽視の両方が生じるという説明ができるのではないか」というインサイトが得られました。ここでようやくAbduction的な思考が使えるようになってきました(その3:センスメイキング編参照)。

ただ、資本主義が原因ならば何が解決策になるのかという新たな問いが生まれます。「資本主義がケアを軽視する風潮をもたらしている」というインサイトを得ても、「資本主義をやめて、Gift Economy(贈与経済)のような別の経済システムに転換しましょう」という解決策をデザイナーとして提案・実施することはできません。またもやリサーチの進め方が分からなくなりました。
岡目八目とはよく言ったもので
そこで先生に相談したところ、「参考になるかも」と教えてくれたのが「ベビーボックス」というフィンランド政府のデザインでした。
フィンランドでは子どもが生まれると、政府から「育児支援パッケージ」を無料で贈られる。「ベビーボックス」と呼ばれる育児用品の詰め合わせボックスで、現地の社会保険庁(KELA)を通じて届く。長年続く贈り物だが、時代の変化を受けて中身も変わり、フィンランドの環境やジェンダーへの意識が見て取れる
ベビーボックスは、少子化対策というマクロな問題に対して、赤ちゃんを育てるための必需品をセットにしたギフトボックスを贈るというミクロな解決策を提案しています。この例を参考にすれば、「資本主義社会におけるセルフケアの軽視」というマクロな問題に対して、デザイナーでもできるようなミクロな解決策につながる視点はないかと考えることができます。
資本主義自体をリセットすることはできないけれど、資本主義社会で損得勘定で行動することが当たり前な人たちが、他人のことや自分のことをケアしようと思うにはどうすればいいのだろうか? 贈与経済の精神を体験できるミクロな方法はないだろうか? そんなことを考えて生まれたのが「Care Box」というプロボタイプです。
「Care Box」では、参加者が自分がセルフケアで使うグッズを箱の中に入れて、他の人に渡します。受け取った人は、そのセルフケアグッズを使っている様子を同封されているインスタントカメラで撮影します。これが終わったら、撮影した写真と自分が使うセルフケアグッズを箱の中に入れて、また別の人に渡します。これを何度も繰り返し、最終的には最初の人のもとに箱が戻ってきます。


このプロボタイプの後に参加者にSemi-Structured Interviewをして分かったのは、セルフケアのグッズ自体でケアが促されたというよりも、箱を渡していくという関係性自体に癒されたということでした。前の人が「これでセルフケアをしてね」という想いをこめた物が箱に入っている。今度は自分がこれでセルフケアをしてね」という想いをこめて何かを箱に入れる。こうした誰かが自分のことを想ってくれること、自分が誰かを想うことということの想いのやり取りそのものがCareをする-されるを実感するということでした。
そうした自分と他人との関係性に気づくこと、そしてその関係性に自ら参加していくことがCareなのではないかというインサイトが得られました。人間にとってセルフケアをすることは難しく、他人のことをケアする方が自然なのかもしれませんね。



今から振り返ると、「Care Box」の構造はマルセル・モースの『贈与論』に出てくるクラ交換と似ていることに気づきました。クラ交換とは、ある品を循環型に交換していくことによって部族間の関係を維持するという仕組みです。まさにこの仕組みが、今回のプロボタイプで行われていたのです。
まとめ
デザインリサーチにおける行き詰まりを克服するには、これまでのプロセスを振り返ること、チーム外の人からアドバイスをもらうこと、という二つの方法があることを紹介しました。
次回は「その5:結果報告編」と題して、ここまでリサーチしてきたことをどのように他人に伝えるのかを見ていきます。「デザインリサーチとは?」シリーズもついに最終回を迎えます。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
