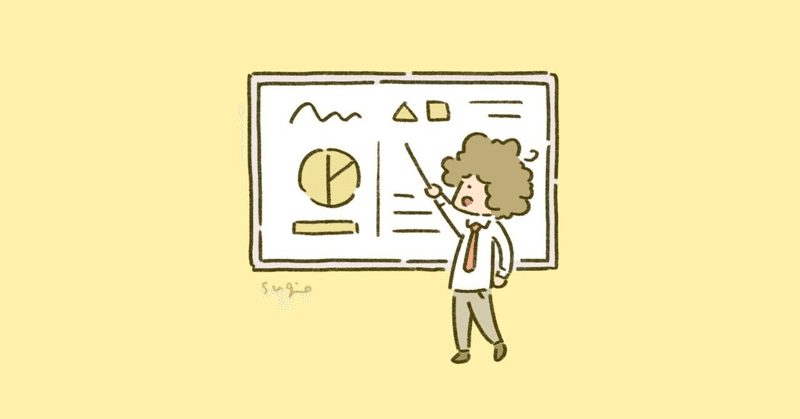
デザインリサーチとは? (その5:結果報告編) #199
前回はこちら
前回の「その4:試行錯誤編」では、デザインリサーチにおける行き詰まりを克服する方法を紹介しました。今回の「その5:結果報告編」では、デザインリサーチで得られたインサイトを報告するためにまとめる方法を見ていきます。
リサーチを終える時
基本的にデザインリサーチは、問題設定⇒情報収集⇒センスメイキングの3つのステップを繰り返すことで、調査対象をより深く理解していきます。途中で行き詰まったら「その4:試行錯誤編」で紹介したように、残しておいたリサーチプロセスの記録を頼りにしてリサーチを再開できるポイントに戻ってリスタートします。
デザインリサーチの終わりは、理論上ありません。なぜなら、何かを完全に理解することなど不可能だからです。「それはなぜか?」と問い続けるという行為は、哲学者のウィトゲンシュタインが「論理の無限後退」を唱えたようにどこまでも遡っていくことができます(だから、無限後退の終点として、神のような絶対的な存在のニーズがある)。
そこでデザインリサーチを終える基準を考えるために、デザインリサーチを行う理由に立ち返ります。「その0:リサーチの役割編」にてデザインリサーチの目的を、「問題解決のアイデアを考えるため」としていました。つまり、リサーチをする前よりも少しでも世界をありのままを見ることができ、問題解決のアイデアの種が浮かんできていれば、デザインリサーチは終了となります。
Research as Intervention
「リサーチをしたのに、理解が不十分に終わっていいのか?」という疑問もあるでしょう。たしかにデザインリサーチによってある物事を深く知ることは重要です。でも、デザインリサーチによって物事を知ろうとする態度こそが重要とも言えるでしょう。
相手に「あなたのことは全て分かりました」と言われるのと、「あなたのことをもっと知りたい」と言われるのはどちらが嬉しいですか? きっと後者のはずです。人間は情報交換をするためだけにコミュニケーションを取るのではありません。お互いに理解することは決してできないけれど、それでも理解しようとすること。それこそがコミュニケーションの本質だからです。
また、授業では"Research as Intervention"という言葉を教わりました。リサーチをする時は、必然的に世界や他者との交流があります。その過程でリサーチの対象だった相手と仲良くなることや、リサーチをされたことで相手の問題が解決していくこともあり得ます。リサーチをする段階からすでにデザインはスタートしているのであって、リサーチ自体がIntervention(介入・解決策)として機能することもあるのです。だから、デザインリサーチをしたけれど分からないことがまだあるという状況でも問題ないのです。
結果発表!
さて、デザインリサーチを終えたら、最終的にはリサーチをして何が分かったのかをまとめる必要があります。個人的なリサーチであれば「なるほど、こういうことか」と自分で納得すれば十分で、それが言語化できない暗黙知であってもデザインに反映されるので問題はありません。
ただ、チームとしてリサーチをしたならば、メンバーごとに得られたインサイトすり合わせて、チームで共通のリサーチ結果にまとめる必要があります。規模の大きい組織であれば、リサーチとその後のデザインが分業化されていて、リサーチ結果を別のデザイナーに伝える必要があるかもしれません。
リサーチ結果をまとめる
そこで、今回はデザインリサーチの結果をまとめる方法を見ていきます。リサーチの報告方法は、大きく分けて2通りあります。時系列型と要点型です。
時系列型は、自分たちのリサーチのプロセスをそのまま伝える方法です。デザインプロセスは試行錯誤の連続で、行き詰まった場面が必ずあるはずですが、そのこともそのまま伝えます。この報告を聞いた人もリサーチプロセスを追体験できるので、リサーチ結果に納得感が生まれます。
一方、要点型はリサーチで得られたインサイトの共有をメインに据える方法です。実際の試行錯誤のプロセスをそのまま伝えずに、リサーチャーが編集した情報を伝えます。整理されているので、リサーチ結果を端的に素早く伝えることがfrきます。
どちらの編集方法を使うかはTPOに合わせて使い分けることになるでしょう。実際のDesign-Led Researchの最終報告会ではどちらの形式もありました。私たちは要点型を採用しましたが、時系列型の方が多かったです。時系列型の場合は、自分の経験をストーリーとして話せばいいというメリットを生かせるので、発表準備がしやすいというのもあったのかもしれません。
ケース・スタディ
パーソンズ美術大学・Transdisciplinary DesignのDesign-Led Researchという授業での体験から、今回の方法論が実際にどのように使われるのかを見ていく「ケース・スタディ」のコーナーです。リサーチ結果のまとめ方として、時系列型はこれまでの「ケース・スタディ」と重複するので割愛し、要点型のまとめ方を見ていきます。
What is Care?
Careという単語を理解することが今回のリサーチの目的だったので、"What is Care?"という疑問に答える形でまとめることにしました。私たちのグループはデザインリサーチで得られたインサイトを以下の4つに絞りました。
・Care is consumption?(ケアは消費?)
・Care is subconscious?(ケアは無意識?)
・Care is deprioritized?(ケアは優先されない?)
・Care is connection?(ケアはつながり?)
以下では、それぞれの説明を日本語訳したものを掲載します。
Care is consumption?(ケアは消費?)
セルフケアには、時間とお金に余裕が必要だと思われている。
ケア(特にセルフケア)は、時間もお金もかかると思われている。セルフケアとは、新しいヘッドホンを買ったりやネイルをしたりなど、自分たちのために新しい商品やサービスにお金を払うことと同義であると思われている。
Some participants see free time and money as necessary components of self-care.
・Care, and especially self-care, was viewed by many of our participants as time-consuming and/or money-consuming. For many, self-care was equated to buying new products or services for themselves, such as purchasing a new pair of headphones or getting their nails done.
・Some participants noted the capitalization of 'wellness' through this commodification of self-care and its ability to create a dependency on purchasing products in order to feel as though one is taking care of oneself.
Care is subconscious?(ケアは無意識?)
セルフケアは意図的になされるものではなく、無意識になされている。
アートや瞑想、料理を習慣にしている人がいた。彼らはこうした習慣を「セルフケア」だと意識してはいないが、たしかに彼らの心身をケアする行動である。
セルフケアは気づかない内にしているもので、セルフケアが不十分な時になって初めて明らかになるものだ。
Self-care is not always done intentionally; for some, it may be done subconsciously.
・Some participants had routines or practices such as art, meditation, and cooking that they did not consciously think of as self-care but still acted as a form of taking care of themselves.
Self-care practices can be done unknowingly at times and only become apparent when there is an obvious lack of care.
Care is deprioritized?(ケアは優先されない?)
いくら時間があっても、その時間をセルフケアに使うとは限らない。というのも、人々は生産性向上や効率化を求めている。
他の仕事や用事があると、セルフケアを優先しない人がいる。空いた時間もお金を稼ぐための資源だと考える。この考え方は特に社会人に顕著だった。
常に生産的であるように求める社会的なプレッシャーのせいで、暇な時間が増えてもその分だけセルフケアに時間を使うとは限らないようだ。
More time doesn’t necessarily mean more time spent on self-care; participants feel the need for constant productivity.
・Some participants deprioritize self-care when compared to other tasks and responsibilities. They see their free time as a resource that can be commodified. We found this to be especially true amongst participants who are working professionals.
・There may be societal pressures for constant productivity, so more free time doesn’t equate to more self-care.
Care is connection?(ケアはつながり?)
ケアとは、ケアをする人にもされる人にも恩恵のある相互的な行為である。
感謝をケアと結びつける人もいる。
感謝とはケアの一つの形である。なぜなら、他人、世界、自分とのつながりに気づき、それに感謝することだからだ。
Care is a reciprocal act that benefits both the provider and the receiver.
Some participants relate gratitude to care.
Gratitude can be a form of care because it is a way of noticing the connection and appreciation for others, the world, and the self.
以上が、「What is Care?」に対する私たちのデザインリサーチの結果をまとめたものです。「Careとは何か?」という疑問が浮かんだ時に辞書を調べても、1. 気にかけること、2. 世話をすること、という2つの意味があることは分かりますが、今回のリサーチ結果ほどの深い理解には至らないことがお分かりいただけるかと思います。
1. feel concern or interest; attach importance to something.
2. look after and provide for the needs of.
エーリッヒ・フロムと同じ結論?
先ほどの4つのインサイトを私なりに要約すると以下のようになります。
資本主義社会における損得勘定の刷り込みによって、ケアは自他ともに優先されず、各々が無意識レベルで行っているという現状である。また、ケアとは身体的な世話だけでなく、相手を思いやること&相手が思いやってくれていることへの気づきと感謝によって、他人とのつながりを意識することでもある。
私たちがリサーチをした当時は知らなかったのですが、この考察と似たような指摘がエーリッヒ・フロムの『愛するということ』に書かれています。本書では、マルクスを引用しながら資本主義社会では他人のためのに行動する動機がなくなっていることを指摘し、フロイトを引用しながら愛するということは自然にできるようになるものではなく意識的に習得しなければならない技術であると述べています。また、愛の対象は自分、家族や友人はもちろんのこと、最終的には人類全体に向かうべきだとしています。
どうやら私たちはデザインリサーチによって、フロムと似たような結論に辿り着いていました。このように、デザインリサーチによって優れた思想家と並ぶようなインサイトを得られるようです。しかも、ただ本を読んで「ふーん、そうなんだ」と単なる情報として知るのではなく、実際に自分たちの体験に基づいた理解なので、自分の血肉となってくれます。
まとめ
今回の「その5:結果報告編」では、デザインリサーチの結果報告には時系列型とプロット型の2タイプがあること、デザインリサーチによって優れた思想家の主張に匹敵するインサイトを得られることを紹介しました。
ここまで紹介してきた方法論に従えばデザインリサーチができるようになるかと思いきや、最後の授業で先生は「この授業で学んだデザインやデザインツールを厳守する必要はなくて、自分流のデザインを構築していけばいい」とおっしゃていました。デザインリサーチに教科書的な正解はなく、デザイナー(orリサーチャー)ごとにオリジナルの方法を身につけていかなければならないようです。
ここまでご紹介した内容も、2021年秋学期のDesign-Led Researchで学んだことを私なりに編集してまとめたデザインリサーチ論です。授業での学びをできるだけそのままお届けしているつもりですが、どうしても私なりの解釈が挟まってしまうもの。厳密に言えばこれも私流のデザインリサーチの方法論なのかもしれません。
最後は、フロムの『愛するということ』の一節を紹介して終わります。
何かの技術的習練について学ぼうというとき、じっさいに習練を積むこと以外に方法があるだろうか。
これはデザインリサーチについても当てはまることで、デザインリサーチを学ぶには自分で実践していくしかないのです。「デザインリサーチとは?」シリーズでデザインリサーチに興味を持ったら、ぜひご自身で実践してみてください。
というわけで、全6回にわたる「デザインリサーチとは?」シリーズは終了です。デザインリサーチのことや、海外のデザインスクールで学ぶ雰囲気が少しでも伝わっていれば幸いです。ここまで読んでくださりありがとうございました!
終劇
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
