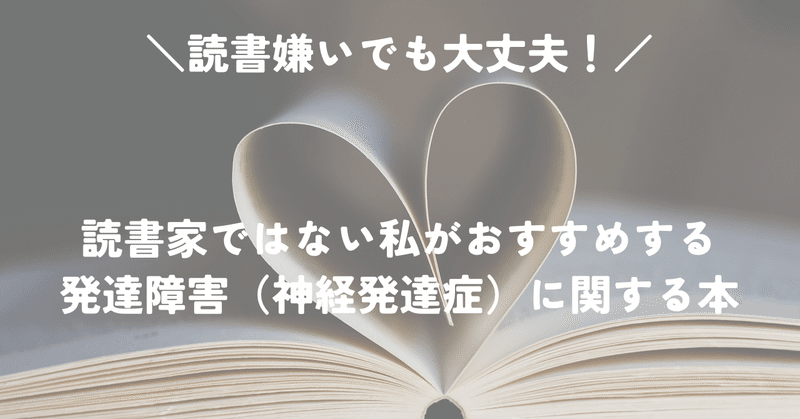
【発達障害(神経発達症)に関する本#7】『図解でわかる発達障害』
読書が得意ではない私(でも実は司書資格持ち)がおすすめする、発達障害(神経発達症)に関する本シリーズ。
🌈バックナンバーを一部ご紹介🌈
📚『「小学校で困ること」を減らす親子遊び10: 6~12歳 発達が気になる子を理解して上手に育てる本』
📚『みんなとおなじくできないよ 障がいのあるおとうととボクのはなし』
📚『大学教授、発達障害の子を育てる』
今回はこちらです!
📚発達障害の入門書として
こちらは2024年3月に出版された新しい本です。
発達障害を知るにあたっての入門書にぴったりと思い、ご紹介させていただきます。
「発達障害とは?」といった基本から始まり、関わり方、支援方法、支援事例など。
これらが文章のほか、図やイラストなどで解説されています。
文章だけより、図やイラストがあるほうが手に取りやすいですよね。
イラスト万歳🙌
個人的には、表紙の雰囲気が「りんごかもしれない」と少し似ていて取っつきやすさを感じました🍎
📚二次障害を起こさないために
第3章「発達障害を取り巻くさまざまな事情」では、下記のようなテーマを扱っています。
二次障害を起こさないためにも、知っておきたい項目です。
✅睡眠障害
✅インターネット・ゲーム
✅歯医者・床屋
✅過剰適応とカモフラージュ
✅不登校
歯医者については、息子の事例を記事にしています。
カモフラージュについては、こちらのレビューもよければご参照ください。
📚家族への支援について
ページ数は多くありませんが、家族への支援内容も記載されています。
保護者の心理については「保護者が見せる顔は氷山の一角」であり、海の中には子どもへのマイナスな気持ち、罪悪感、孤立感、簡単には表明できない複雑な思いがあると…
よくご存じでーーー!!😭
卒園した保育園にふせん付けて送りつけたい!!
当事者本人のことばかり考えて、家族のことはおろそかになりがち。
しかし、家族が疲弊してる可能性もあります。
今すぐ家族が支援につながる必要はないにしても、どういった支援があるのか、本書を読んで確認しておくだけでもいいと思います。
📚さっそく活用しました!
実は、先日から息子が投薬を開始しました。
その際に参考になったのが、第4章にある「医学的な視点」です。
✅薬物療法を始める前に
✅始める際の注意点
✅治療薬の種類
✅薬の副作用
上記の項目などが説明されていました。
💬どんな薬があるの?
💬人によって合う・合わないがあると聞くけど、息子は大丈夫?
💬副作用ってどういうもの?
投薬に対して、不安を抱えていた私。
本書を読んでから病院に行くことで、実際に投薬の話になっても「この薬の名前、本で読んだ…!」と復習することができました。
テストの一夜漬けで、覚えたところが出てきた気分😂
なお、本書にもありますが、薬物療法は最初から選択肢にある訳ではありません。
環境調整をはじめとする心理的・社会的治療を続けても効果が得られない場合に、検討するものになりますのでご注意ください。
📚他のシリーズを合わせても
「図解でわかるシリーズ」は、他にも出版されています。
合わせて読んでみるのもおすすめです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 「スキ」やフォローしていただけることで、サポートになります。 よろしければ他の記事も読んでみてください。
