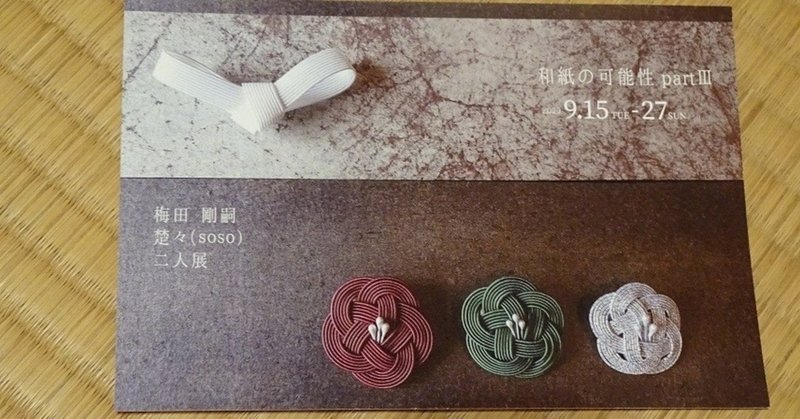#手仕事
箱張りのレシピ2 上張り。
箱の上張りの様子をレポートします。
まず 上張りの紙の裏から 糊を付ける。
糊は 正麩糊(小麦粉を炊いた糊)。
とりあえず 箱の上の部分貼ります。
次に 側面。
内側に曲げるのりしろ部分(今回は 5分【ごぶ】=約1.5mm)測って余分な部分を喰い裂き(水切り)で 切ります。
四方とも余分な部分を切ったら 側面を貼ります。
写真のように折り曲げ部分を残して喰い裂き(水切り)にして
正麩糊で
箱張りのレシピ最終章 内張り
箱の内側を貼る。
まずは 四隅から 貼ります。
箱は角が 一番痛みやすいと思いますのでその補強の意味もあります。
紙の大きさは幅約1.8cm(6分・ろくぶ)高さは箱の内側の内寸より
0.5mmほど大きくします。
今回使った紙は 横野和紙黒弁柄染め この紙に墨で黒色の染めを加えました。ベンガラも 墨も 長年色褪せがほとんどないからです。
お客様のご要望が内側は 黒色の紙で…ということでしたの
それぞれの 手(しごと)
今朝 書道家兼表具師 篆刻もするし、ナチュラリストの松下さんが
仕事場に 和紙染の体験に 来てくれました。
一枚目の写真は 柿渋に 紫墨 ベンガラ 松煙を混ぜて色の見本のために染めたもの。
模様は ドウサ液で あらかじめつけておきました。
こちらは 松下さんが ドウサ液で 模様を描いているところ。
これは乾かして自宅に持って帰って どんなふうに染め上がるのか後日が楽しみです。
とても楽しそ