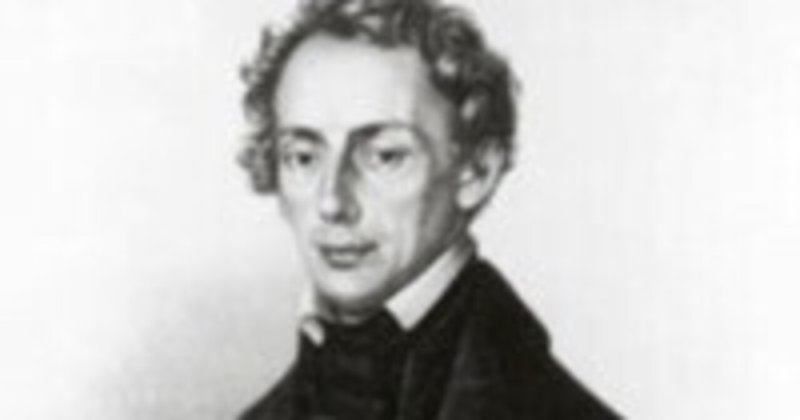
「ドップラー効果」を確かめた意外な方法
物理で習う現象の一つに、ドップラー効果というものがあります。
音の周波数が多いと高音、少ないと低音として聞こえます。音源が移動していると、近づく場合は周波数が詰まるため高音に、遠ざかる場合は周波数が引き延ばされるため低温に聞こえます。これがドップラー効果です。

この現象は、オーストリアの科学者クリスティアン・ドップラー(1803~1853)が理論化しました。その理論は、オランダの科学者クリストフ・ボイス・バロット(1817~1890)の実験により、1845年に確かめられます。

ところで、ドップラー効果を証明するには音程の高さを測らなければなりません。チューナーのような便利なものがない時代、どうやって確認したのでしょうか。
バロットの実験方法は、以下のようなものです。
「トランペット奏者を列車に乗せ、同じ音を吹かせる。沿線に絶対音感を持つ音楽家を待機させ、音を聞かせる」
理論通り、列車が近づくと音が高く、遠ざかると低くなりました。
19世紀半ばの話ですので、こうした「アナログ」なやり方だったのが面白いですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
