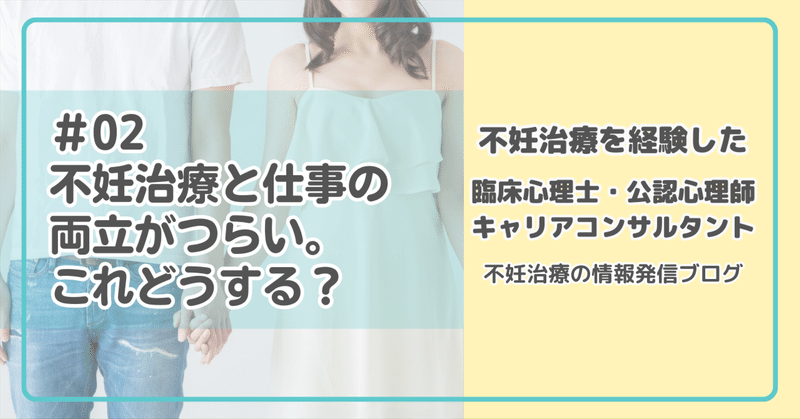
不妊治療と仕事の両立がつらい。これどうする?
こんにちは。不妊治療経験歴のある臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタントのあやです。
●この記事の目的・目標●
この記事では不妊治療と仕事の両立で問題になりやすいことと、その問題に対するヒントをいくつか提示することを目的とします。
はじめに
厚生労働省『不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック』によると、不妊治療を受けたことがある夫婦は18.2%で、5.5組に1組が治療を受けたことがあると回答し、「不妊治療と仕事の両立ができない(できなかった)」と答えた人は34.7%で、主な理由として「精神面で負担が大きいため」、「通院回数が多いため」、「体調、体力面で負担が大きいため」と続きます。
ところで「精神面で負担が大きいため」について具体的には記されていませんが、恐らくこれらの悩みは独立してあるわけではなく、関連しあっていると思いますので、ここで改めて不妊治療と仕事の両立で大変なことについて、このデータや複数の経験談を参考に改めて整理しました。
不妊治療と仕事の両立ここが大変
1. 先が読めない通院
タイミング法から人工授精は特に、卵の育ち具合を頻回にエコーチェックしなくてはならないので、人工授精自体の処置も含めて予期できない通院が1周期あたり3〜4回に及ぶこともあります。
いつ通院を求められるかわからないので、先の予定を立てることが難しいです。休日であっても、遊びの約束が入れづらかったり、病院の受付時間を気にして行動しなければいけない場合もありストレスです。
2. 心身ともにかかる負荷
服薬・採血・痛みを伴う検査・手術室での採卵処置など、たいていの不妊治療は痛いことのオンパレードです。毎日自分で注射を打ったり、数日おきに筋肉注射に通う人もいます。タイミング法でもホルモン剤を使うことも多く、不妊治療中は服薬に伴う体調変化に悩まされがちです。
また精神的にもさまざまな負荷がかかります。治療そのもののストレス、経済的なストレス、ままならない状況に対するストレス、体調不良からくるストレス…とこちらもストレスだらけです。
これに加えて仕事のストレスもあるならばたまったものではありませんね。
3. とにかく職場に気をつかう
1と関連して通院や処置日に合わせて仕事の遅刻・早退・休暇を申し出なければならないことも多く、周囲への申し訳なさや精神的な負担を感じやすいでしょう。他の人に仕事の皺寄せがいってしまうことが気掛かりであったり、職場に内緒で不妊治療を行なっている場合は周囲からどう思われているかが気になってストレスを感じるケースも多いです。
4. キャリアアップがしづらい
治療の終結に見通しが立たないので、転職や昇進、転勤をためらいキャリアアップのチャンスを見送らなければならないケースもあります。
一方で治療の負担から、正社員から非正規雇用にキャリアチェンジをせざるを得ない場合もあり、特に女性の場合は治療とキャリアがトレードオフになりやすい側面があります。
仕事をセーブしても確実に妊娠できるかどうかわからない、いつ妊娠できるかもわからないため、日々悶々と過ごす方かもいらっしゃるかもしれません。
不妊治療と仕事を両立しやすくする考え方
1. 時間管理がしやすい治療も検討する
不妊治療を始めたばかりの方は特に、なるべく体の負担を少なく、金銭的な負担も少ないタイミング法からスタートする方が多いと思います。
一方で体外受精や顕微授精といった高度不妊治療の場合、体への負担が大きくなるデメリットはありますが、薬で卵胞期・(仮の)排卵日・黄体期をきっちり管理するため、人によっては通院日が最小限で済みやすいメリットもあります。
何の負担を取るかにもよりますが、仕事との兼ね合いて通院日数を減らしたい場合は医師と相談して治療方法を考え直してもよいかもしれません。
2. そもそも仕事と治療を完璧に両立させようと思わない
書いてて悔しいですが…
時間・お金・体力はどうしても有限ですので、何を優先させるかを定期的に確認することも必要かと思います。不妊治療に重きをおきたい場合は、働き方や仕事内容の変更も一つの手だと思います。
職場に対して申し訳なさがあるならば、配慮してもらう代わりに業務でお返しできる部分を提示してもよいと思います。
一方で、大事な仕事やプロジェクトを抱えていて手が離せない場合は、治療方法を変更したり、治療を1周期見送るなどペースの再検討してもよいかもしれません。
3. なるべく1人で抱え込まない
不妊治療のストレスを減らすために、治療の理解者を増やすことはとても大切です。とくに職場では上司や管理職など職務上キーとなる人から治療の理解を得られると動きやすいです。
プライベートなことですので職場の人に不妊治療をしていることが広く知られるのが嫌ということであれば、治療の話は上司のみで留めていただき、周りには「家庭の事情で急に休まなくてはならないことがある」などと説明してもらうことをお願いしても良いと思います。
4. 手を抜く部分をしっかり決める
ストレスをそれ以上増やさないように心がけることも大切です。
例えば家事の手を抜いて、オフは心身を休めて楽しいことをする時間に充てたり、仕事は終業後30分以内には完全に帰るのを心がけるなど、ストレスがたまらないよう自分で線引きをするなど、ある種の自己防衛スキルも磨けるといいですね。家事は家族や格安の家事代行サービス、外食などをうまく活用するのもコツです。パートナーや家族と「あえて手を抜く場所」を話し合ってみてはいかがでしょうか。
5. 自分の人生の責任は自分しかとれない
周りが何を言おうと、どう思おうと、その人たちが自分の人生の責任をとってくれるわけではありません。2でも述べましたが、限られた人生ですので、したいことや譲れないものを定期的に確認することをおすすめします。
そういえば、子供がいてもいなくても、自己肯定感を持って生活するには「自分軸」で「納得して」生きることが大切ですね!
仕事をセーブした方が良いかもしれない状況
不妊治療も仕事も頑張りたい、あるいは頑張らざるを得ない状況の方も多いかと思いますが、心身ともに疲弊している状況であれば仕事の負荷を落としたり、休止を考えた方がよいと思います。
すぐに決めることが難しい場合は、例えば半年〜1年以内に仕事量の負荷を減らすかどうかを決めていこう、などと目安を設けてみましょう。
心身の負担が大きく日常生活に支障が出ている場合
例:
身体症状…倦怠感(だるさ)の悪化、朝体が重くて起きづらい、夜寝つくまでに時間がかかる、中途覚醒、早朝覚醒、集中力の低下、など
精神症状…生理周期に関係なく気分の落ち込みが1ヶ月以上続く、涙が止まらないことが増えた、イライラ、焦りと不安がひどくなった、など
ご自身が今どれほど心身ともに参っているかがわからない場合は、カウンセラーや医療機関にお問合せください。
当カウンセリングオフィスはこちらからどうぞ
https://tokyo-anone.com/
不妊治療か仕事か、優先順位を決められないとき
妊娠・出産も仕事もどちらも「自分」のアイデンティティを作る大切な側面ですから、どちらをとるか決められない方も多いかもしれません。
それは強欲ですか?
いえいえ、決してそんなことはないですよ!
妊娠・出産とキャリアの両方を望むことは自然なことです。
ではそのように悩んだ時は次の考え方がヒントになるかもしれません。
両方頑張るリスクを理解して、同時進行して様子見する
「頑張りすぎないでね」「無理しないでね」とアドバイスを受けることがあるかもしれませんが、果たして多少の無理はいけないのでしょうか。
様々なリスクを納得の上であれば、ちょっときついけど両方頑張ることもアリだと思います。頑張ることも、その方の良さかもしれません。
また、決められない時は物事が停滞している状況そのものに意味があるのでその時は決めるタイミングではないのかもしれません。
老年期に後悔しない選択を考える
精神分析家のエリクソンは生涯発達において、人生の最終ステージの老年期では、これまでの経験や知識がその人の中で統合されて「いい人生だった」と納得できる状態を理想的であるとしています。
未来の自分を予測することは難しいですが、何を選択すれば未来の自分が納得してくれるかを考えて行動することをおすすめします。
今回のまとめ
今回は不妊治療と仕事の両立の大変さと、少しでも両立しやすくする考え方について書きました。
いま流行りのタイムパフォーマンス(タイパ)を意識し効率的に治療に取り組む、勇気を出して理解者を広げる、人生の優先順位を自分軸で考える工夫などをすると、より「仕事との両立」に縛られない過ごし方ができるかもしれません。
ただ、人によって状況によってケースバイケースですから、うまく行かない事情もあるかもしれません。
現状特に女性側が治療とキャリアのトレードオフになりやすい状況ですが、治療への理解が広まって仕事と治療を両立しやすい環境になればいいのになと切に願っています。
最後に
・今後取り上げて欲しいテーマがあればお知らせください。
不妊治療当事者の方(男女問わず)でも、ご家族や職場の方でも結構です。
参考にさせていただきます。
・心理学に関するメディア取材や記事監修も承ります。
(2023年夏ごろ、オトナンサーに心理学に関する執筆記事が掲載予定です。)
ご連絡はtwitterDMもしくはtokyo.anone★gmail.com(スパム対策のため、★を@にかえてください)までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
思い立った時にいつでも・どこでもカウンセリングを受けられます。
臨床心理士によるオンライン不妊カウンセリング
カウンセリングオフィス東京anone
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
