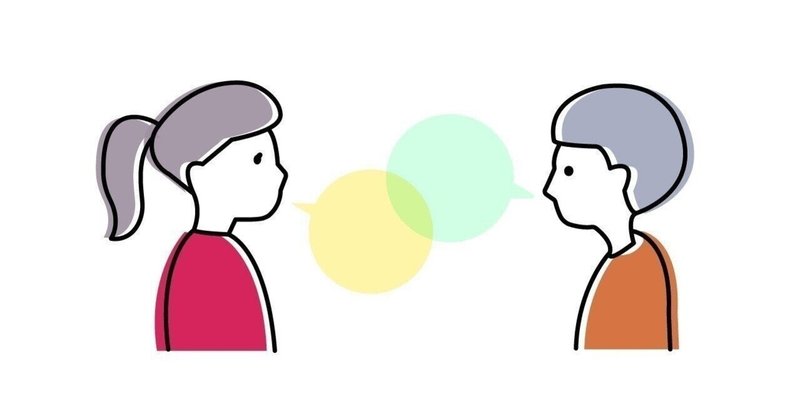
笑える哲学本
先日、本屋をぶらぶらしていたら、おもしろそうな本を見つけた。パラパラ立ち読みしていたら、おもしろくて「ガハハ」と声を上げて笑いそうになってしまったので、購入して自宅で読むことにした。
思いがけない出費だが、おもしろい本は、誰にも気兼ねせず思いっきり声を上げて笑いながら読みたいので、よしとしよう。
どんな本かというとコレです。
みんなが知っている「桃太郎」とか「浦島太郎」とか「さるかに合戦」の話の中に、有名な哲学者が登場し、いろんな哲学的ツッコミを入れていくという本。昔ばなしの部分は漫画になっていて、しかもこれがすっごくおもしろい。
個人的には「桃太郎」が一番おもしろかった。発売されてまだ間もないので、本屋で見かける機会があったら、ちょっと読んでみて下さい。人によるけど、私は好きな世界観です。
哲学・・・というと、「難しい」というイメージがあるが、ちょっと前に、哲学についての本を数冊読む機会があり、その時に「哲学ってなんかおもろい」と思い、頭のはしっこでなんとなく気になっていた。
哲学カフェの存在を知る
そこで、先週くらい、図書館で「哲学カフェのつくりかた」という本を借りて、読んでいるのだが、これもなんだか心に響くところがあり、じっくりゆっくり読んでいる。
社会人になってから、ハウツー本はサーっとポイントだけを読み流すような感じで読むようになってしまったのだが、なんだかこの本は、一つ一つの言葉がじんわりと心にしみてくるような感じで、ゆっくり読まずにはいられない。
哲学カフェを主催している人々が、哲学カフェについて書いた本で、「そもそも哲学カフェとは?」というところから、実際に長年、哲学カフェを主催してきての経験談や思うところを書いていて、そこがとても興味深い。
おそらく、テーマに興味がない人にとっては、ものすごく退屈な本、つまり、万人受けするようなものではないけれど、はまる人にははまる類の本だと思う。今の私には、ぴったりはまった感じだ。
哲学カフェというのは、ざっくり言うと、人々が集まってあるテーマについてざっくばらんに話しあうというものであるらしい。(私も参加したことはないので、あくまでも本からの知識。)目的や結論は特になく、じゃあ単なるおしゃべりと何が違うかというと、もっと本質的な問いを考えていくという点が違う。また、誰でも参加自由、途中退室自由、とも書かれていたが、それもその時々で臨機応変らしい。
ファシリテーターとは
いずれにせよ、参加者な思うことを思うままに話す、対話する、ということらしい。しかし、それだとなにがなんだかわからなくなるから、必ず「ファシリテーター」という進行役・司会役の人が存在する。その「ファシリテーター」の視点でこの本は書かれているのだが、「ファシリテーター」としての苦労や喜びが垣間見えておもしろかった。
実は私も、「ファシリテーター」というものに興味があって、ある手法の「ファシリテーター」研修というものを、だいぶ前に受けたことがあるのだが、「ファシリテーター」というのは、全体の空気の流れを左右する大変な仕事だと痛感した。参加者が自由気ままに発言することのポイントをつかみ「これ」と思う方向に議論を舵取りするわけだけど、「これ」と思ったことが的外れだったり、空気に自分も飲み込まれて流されたりする。
たとえば、ABEMA TVに、討論版ニュース番組みたいな「アベプラ」という番組があるのだが、この司会者の平石さんは、優れたファシリテーターであると思う。ぜひ時間があったら、興味のある回をみてもらいたいなと思う。
個性の強い出演者たちの討論を生放送でまとめるのは、かなりの手腕が必要だろう。「もうみんなめちゃくちゃにしゃべって~!俺が大変だろー!!」って叫びたくなることもしょっちゅうなんじゃないかと思うけど、平石さんはいつも冷静で、時には、危うくない程度に熱くなるという、絶妙なバランスを持っている。
アフリカでのこと
実は私も一度だけ研修以外で、実地で議論のファシリテーターをやったことがある。もう10年以上前、アフリカでのことだ。中学生くらいの教室で1時間、授業をすることになって、そこで話し合いをすることにしたときのこと。
生徒は20人くらいだっただろうか。まず、「このクラスや学校で問題になっていることはない?」と聞いたら、いくつか意見があり、その中で「図書室に本が少ない」という意見があったので(ちょっと記憶があやふやだけど図書室に関する問題だった)、それをテーマに「なぜ図書室に本が少ないか?」と掘り下げ、そこから「どうやったら図書室に本が増えるか?」と議論した。
日本と違って子供達はどんどん発言するので、それをまとめていくのに苦労したし、まだアフリカに行って1か月もたっていなかったので、英語にも四苦八苦した。
しかし、言語よりも、いろんな意見がでて、そこからさらに議論が発展するということの楽しさを沸々と味わえた1時間だった。
こんなふうに、今までの人生でも、「議論する」「対話する」ことの楽しさを感じる場面はところどころにあった。今改めて「哲学カフェのつくりかた」という本を読んで見て、またあの気持ちを味わいという気持ちがわいてきてしまったのである。
哲学カフェへ…行くかも?
つまり、哲学カフェに参加したいなぁとぼんやり考えるようになってしまった。なので、ちょっと調べて、行けそうなところを探してみようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
