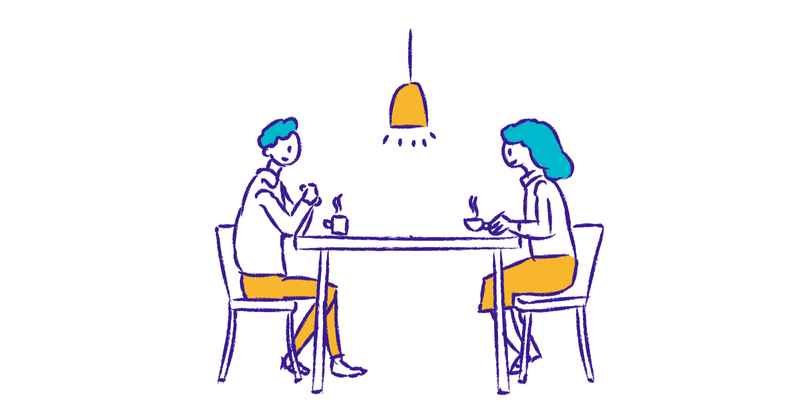
中学受験経験者のパパ×中学受験未経験者のママ
我が家の小5長男は、塾なしで中学受験の勉強中です。
夫と私で役割分担をしつつ、進めています。今回は、そんな私たち夫婦について、中学受験経験の有無という観点から、書いてみようと思います。
各科目の具体的な夫婦での役割分担については、過去の記事に書きました。記事の最後にリンクを貼っておきますので、興味があれば参考にどうぞ。
夫と私のバックグラウンド
我が家は、タイトルに書いたように、夫は中学受験経験者です。さらに地域も、現在我が家が住んでいる首都圏。息子が受けるかもしれない中学校も受験して合格しています。
一方、私は中学受験とはさっぱり縁のない子供時代を過ごしました。地元は阪神間(関西)でのんびりゆったり。思い返せば、小学校の同学年から1人、灘に入学した同級生がいたのですが、当時は「灘」という学校も知らず「遠くの中学校にいったんだな」程度の認識でした。
こんな正反対の私たち夫婦ですが、中学受験の勉強をする息子と接していて、それぞれにメリット・デメリットがあるなと感じています。(あくまでも私目線。夫の見解は知りませんが。)
中学受験経験者パパのメリット・デメリット
まずメリット。やっぱり何と言っても、学習内容が分かること。そして、個人差があるとは思いますが、勉強を教えてあげることができること。もちろん所々忘れている部分もあるものの、基本的には、どの単元をどの程度まで深く勉強すればいいのかという知識があります。(ただ、中学受験の内容は年々変わっているので、当然アップデートもしています)
もう一つのメリットは、勉強の大変さを分かってあげられること。特に息子も夫も得意な単元と苦手な単元が似ている、理系男子なので、よく2人で「国語やだよね」とか、「植物の暗記覚えられないよね」と言っています。塾に行っていない息子にとっては、苦労や大変さを分かち合える存在でもあると思います。
次にデメリット。これは、経験があるがゆえに、それを基準にして息子を見てしまうことです。良くも悪くも、比べるものが夫の中にあり、かつその基準がけっこう高いレベルなので、結果、息子に求めるものも高くなる傾向があるように思えます。
たとえば、日曜日、息子が遊んでしまい、理科・社会・算数の勉強をする予定が算数しかできなかったような場合。私からすると、家族みんながリラックスして過ごしている日曜日に、1人だけ勉強に向かうこと自体がすごいと思うのですが、夫からすると「算数しかできてない」「こんなに勉強しないで大丈夫か?」と、自分の基準からマイナスに見てしまうことが、度々あるように感じます。
パパに限らずママでも、中学受験を経験していて、かつ、それなりに結果を残してきて、それに満足しているような場合は、注意が必要じゃないかと思います。自分の成功体験を基準にして子供を見るということの危うさを感じます。中学受験の漫画「二月の勝者」に出てくる島津家が典型的なパターンですよね。意識して、「自分は自分」「子供は子供」、さらに、自分のときとは環境が全く違うというゼロの視点から子供を見ることが大事なのではないかと思います。
夫は基本的には、息子のペースを尊重していますが、無意識でも自分の体験から子供を見てしまうようなときがあるので、そんな時は私は夫に、
「できていないことじゃなくて、できたことを見てね」
「机に向かっているだけでもすごいんだよ」
と、減点ではなく加点で見てねと言っています。
中学受験未経験者ママのメリット・デメリット
次に私について。メリットは、既に書いたように、どんなに勉強時間が短くてもテストの点数が低くても、「中学受験をすると決めて勉強している」だけで息子を尊敬できることです。予定通りに進まなくても、やってるだけで「すごい!」って思います。
しかも自宅で、自分を律しながら(よく遊んじゃうけど)、勉強にむかう、あるいは向かおうとしている姿勢はそれだけで尊敬です。私から見ると、加点しかありえません。
そのため、予定より遅れてしまっていても、遊んで勉強時間が少なくなった時も、特に声をかけることはありません。既に頑張っているので、「もっと」という声かけは必要ないのではないかと思っているからです。
ただこれは、夫から見ると「やるべきところをゆるめすぎている」とうつってしまう時もあるかもしれません。「ただ好きに遊ばせていたら受験は難しいよ」「やるべきときはやらないと」というのは、私がよく夫に言われることです。
私はこういわれると、正直迷います。なぜなら、息子の時間の使い方は、息子が選んでいいと思うからです。有限な人生の時間を、何にどういう配分で割り当てるのかは、息子が決めればいいと思っています。
息子が「合格のために頑張りたいから、遊んじゃったりしたときは、声をかけて」と言えば、そうするかもしれませんが、それも「本当に本心なのかな?」と思います。結局のところ、小学生の意見は親のフィルターを通した情報をもとにして形成されていることと、無意識にでも親の意向をくんでしまうことを考慮すると、息子の望むことをサポートしたいとは思うものの、そもそも果たして息子が本当に望んでいることは何なのか?という答えが分からないからです。息子にだって分からないかもしれませんが。そうすると、行動に現れることが、息子のやりたいことに一番近いのではないかと思うと、遊んでいるところをストップして「勉強!」と言うことは私にはできないと思うのです。
ちょっと話がそれてしまいましたね。
一方のデメリットは、夫のメリットの裏返しですね。勉強の内容を教えてあげられないことと、中学受験そのものに対する知識がないことです。
今は中学受験を意識し始めてから1年以上たち、はじめた当初よりはだいぶ知識はつきましたが、それでも「模試の違いって?」「説明会の予約はいつから?」「偏差値って?」というところからだったので、けっこう苦労しました。
まとめ
こうやって書いてみると、正反対だからこそ、バランスが取れているのかもしれません。けっこういい組み合わせかも?お互いが綱引きみたいに引っ張り合いをすることで、一方向に熱くなりすぎることの抑止力が働いているように感じます。
中学受験は夫婦の意見が別れると大変だと言いますが、違う視点を持っていることも大事かなと思います。お互いにお互いの考え方を、一歩離れた視点から見ることで、第三の視点が見つかるような気がします。
ただ意見が別れて夫婦で話し合いをするときは、子供がいないところのほうがいいですね。子供が自分の受験のせいでケンカしていると思ってしまう可能性があるからです。これは、自分の反省。私は問題があると、すぐにその場で話し合って解決をしたいほうなので、気を付けなければと思っています。
夫婦でお互いのよくないところをつつき合うのではなく、それぞれの得意や良いところを生かして、息子にとってベストの道をサポートしていければなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
