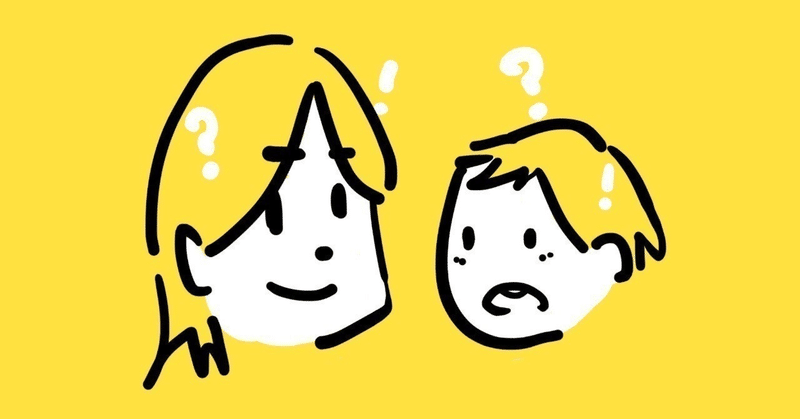
中学受験での親子のコミュニケーション
先日、Twitterのスペースで「塾なし中学受験」について話しました。
いくつかトピックがあったのですが、その中で「いつから子供は自分事として意識するか」という話があり、その話の流れで、子供とあまりケンカをしなかったということを話しました。そんな私と長男とのコミュニケーションについて、Twitterでご自分用のメモとしてまとめてくださった方がいたので、紹介します。(ツリーになっててちょっと長いですが、全部)
中学受験のバトンスペース第3回で、「子どもとの喧嘩があまりなかった」というご家庭の親子のコミュニケーションに感銘を受けたからめも!
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
優秀なお子さん&親御さんだから、我が家で実践できるかわからないけど、確かにできる部下を尊重しながら育てようと思ったらこう接するかも…
9:58
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
塾なしの中学受験は、小3秋に、受験するなら勉強しないといけないけど、塾に通う/家でやるのメリデメを話した時に、家で勉強すると言ったので、話し合って決めた。家庭学習はそれまでもやっていた。
勉強をどういう形でやっていこうか自分で考えるのを始めたのは4年生の初めから。(1:58:30)
1:29:27
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
スケジュールから遅れたり、勉強しないこともあるが、そういう時は子どもを呼んできて、「目標に向けてこれをやる」という受験にするのか、「今日できることをやって、たまたま受かるところに行く」のか、どっちのタイプでやるの?というのを、随時確認しながらやっていた。
なので、そんなに勉強しなくてイライラするというのもあまりなかった。
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
目標を一緒に話して、どうしたいのかを確認して、進めて、ちょっとずれてきたなと思ったらまた話して、シェアして、進める。
1:48:27
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
やらないときは、何も言わず3日くらい見守る。3日経って、ちょっとこんな感じになって遅れてるけど、どうする?とエクセルの表を見ながら話す。
ここ削る?やらなかった分、1日30分長く勉強する?週末にやる?と聞いて、本人に決めてもらう。
決めた翌日、この時間から始めなかったら終わらないなという時間になってもやらなかったら声をかけるか迷うが、そういう時も本人を呼んで、声をかけてほしいか自分でやり出すのを待ってほしいか、本人に聞いて確認する。
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
なので喧嘩はあまりない。
アーカイブはこちら。
— ぽむこ (@pomko_ikuji) September 23, 2022
聞けるのは9/17から1ヶ月間かしら?
レモンさん、あかねさん (@akane_noda_2022)、子育て全般で使えそうな、コミュニケーションの取り方が勉強になりました。
どんな選択肢があるのかを提示して、子どもの意思を尊重して話し合っていく姿、少しでも真似したいです! https://t.co/xrBn3W8kO4
ここに書かれているとおり、私は長男に限らず子供と話して、子供に決めてもらうことを意識して子育てをしてきました。
ただ、これは比較的簡単にできる子供と、なかなか難しい子供がいると思います。それぞれの特徴や条件をあげてみます。
①話し合える子
・客観的に物事を見て、理性的な判断ができる
・自分の気持ち、感情、意志を適切な言葉で表現できる
・「どうしたい?」「それはなぜ?」の問いの繰り返しを苦痛に感じない
・自分の考えが頭の中でまとまるのが早い
・相手の言ったことを理解できる、理解できない場合は、その点について適切な言葉で質問できる
②話し合うのが難しい子
・感情的
・客観的に物事を把握できない
・深く繰り返す問いが苦手
・すぐ「わらかない」「いやだ」「めんどくさい」などと言う
・考えることを面倒くさがる
・自分が理解できない点を明らかにするための、適切な質問ができない
・自分の気持ち、感情、意志を適切な言葉で表現できない
わがやの3人の子供は、
長男:小さい頃からずっと①
長女:中学年くらいまで②、小5くらいから②から徐々に①へ、まだ②寄り
次男:②
という感じです。
子供が①と②のどちらになるか、あるいは①、②をどういうバランスでとりいれた子になるかは、いろんな要素があると思います。
3人の子供を見ていると、「小さい頃からずっと問いかける育児をしてきて~…」と、育て方の結果だとみるのは乱暴な決めつけだじゃないかという気がしてます。それよりはずーっと、生まれながらの性格が大きく影響しているのでは?と感じます。
私は小さい頃からしつこく子供に問いかけてきたけど、長男はいつも最後まで粘り強く答えてくれたし、長女はだんまりを決め込んだり「わかんない」で終わることが多かったです。
なにが言いたいかというと、「スペースで紹介したようなコミュニケーションは、できる子もいるしできない子もいる」ということと、「できる子には関り方よりももともとの子供の個性がけっこう影響してるかも」ということです。
「わがやの子供はどうかな?」くらいの軽い気持ちで子供を観察してみるといいかもしれません。
さらにもう1点、このコミュニケーションをとる前提条件として、親が子供の意志を尊重する気持ちがあるかどうかが大きく関わっていると思います。
私の場合は、受験をするしないも完全に本人に決めてもらおうと思っていたので、Twitterに書かれているような質問を長男にしてきました。
しかし、親側に「受験は絶対」「偏差値〇以上は最低ライン」「1日〇時間の勉強は当たり前」みたいな、子供に超えてほしい絶対的なラインが設定されていると、こういうコミュニケーションは成立しないと思います。子供がせっかくがんばって考えたことが、親のラインより下だった場合に否定してしまうからです。こうなると、親子で共通の目標を設定するための話し合いではなく、単なる親が自分の希望を押し付けるやりとりになってしまいます。
親が子供に要求するライン設定すること自体は、否定も肯定もしません。各家庭の事情があるので、各家庭で決めることだからです。
ただ、子供の裁量が少なければ少ないほど(親が決めたことを子供に要求すればするほど)、子供が受験を自分事をするのは難しいと思います。自分で決められないのに、責任感だけ持てと言われても、無理な話なので。
なので、親が決めてしまう部分が多いなら、子供に自分事として受験に取り組むのは「そうなればいいよね」程度の期待にとどめて、親がひっぱっていく、かなりどっぷりとかかわっていく気持ちが必要なのかなと思います。(なんて書かなくても、どの親も全力でサポートしてるだろうけど…)
私にとって初のスペースは、とっても勉強になることばかりでした。私の他に3人のスピーカーの方がいらっしゃったのですが、みんな境遇が違っていて、おもしろかったです。
いろんな家庭のやってることを、ちょこちょこつまみぐいしつつ、自分の家庭にあった中学受験のスタイルや親子のコミュニケーションを探せればいいなと思います。
中学受験関連の記事はコチラ
中学受験関連のkindle本はコチラ(読み放題kindleunlimited対象)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
