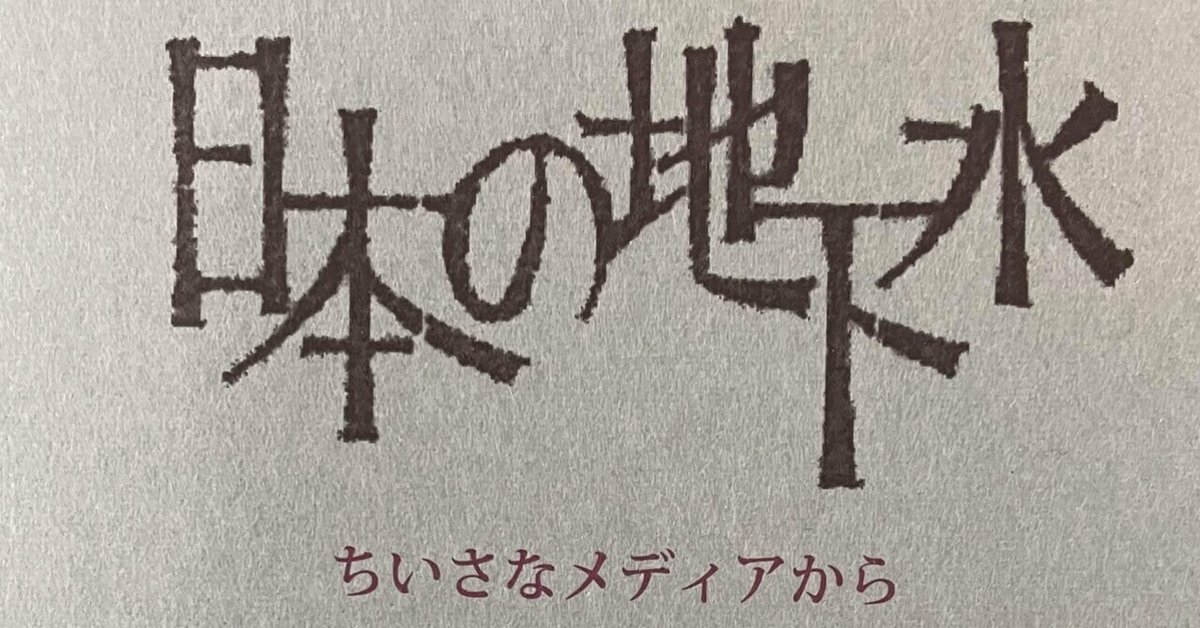
鶴見俊輔『日本の地下水―ちいさなメディアから』についてのメモ⑪―冊子ではないミニコミ
鶴見俊輔『日本の地下水―ちいさなメディアから』(編集グループSURE、2022年)には様々なサークルの雑誌が紹介されているが、その形態は必ずしも雑誌というわけではない。「難民とともにある日本像―「週刊ポストカード」」は、『週刊ポストカード』を紹介した文章であるが、鶴見俊輔によれば、このメディアは、日本アジア・アフリカ作家会議がはじめたもので郵便葉書1枚半の紙面に、世界人口の過半数をしめる第三世界の情報をつづめたという。鶴見はこの葉書を用いたことに対して以下のように述べている。
政治運動のパンフレットをさして、紙の弾丸と呼ぶことがある。私は、この言葉は好きではない。
たたかうということに、心をうばわれていると思う。小論文、あるいは資料の目的は、まず、対象のありかを照らしだしてしらせることにあり、しらせることをとおして、間接に、運動を、そしてたたかうことを助けることにある。
ところが、たたかうことに心をうばわれてしまうと、敵(と見なされたもの)をののしりたおすことに毎ページをもさくことになって、そういう文章が、たまってくると、もっているものにとっては、たたかう意欲が増してくるということにはならない。
情報量の多い今の日本では、必要な情報を手ぎわよく小さく集約してしらせる形のほうが、ありがたいし、たたかう力を増すことになる。
(中略)
第三世界、とくに東南アジアについての本は、日本では売れない。売れない中に、大きな本を出してのりこんでゆくよりも、日本人にとって重大な情報を葉書大の小さい紙面にちぢめておくりだすという。途方もない方法をとるというところに、『週刊ポストカード』の創意がある。
ここで鶴見は『週刊ポストカード』の形式や流通させる方法を高く評価している。鶴見は雑誌の内容だけでなくこのようなコミュニケーションの方法も含めて(広い意味での)サークル誌を読んでいたのだろう。
斬新なメディアの形式だけでなく、鶴見は『週刊ポストカード』の内容にも注目している。興味深いエピソードを以下に引用してみたい。
(『週刊ポストカード』)遠くの国々についての情報をつたえているだけの葉書新聞ではない。この小さな紙面の一部に、ヴェトナムからの難民をなるべく多く受けいれることが、日本人にとって、千載一遇の好機だという論説(山口文憲、六月十三日号)も出ている。
「おい、お前の彼女、あれインド人か?」
「ちがうよ、けど、ジイさん、バアさんはベトナムから来た。」
「なんだ、日本人か。」
そういう会話があたりまえになるように日本がなってほしい。それが日本のためになるという日本文化の把握がある。
この文章を執筆した山口文憲はべ平連に参加して鶴見とも交流のあった人物である。鶴見は戦争時の経験から「日本を外に開く」ということを重要であると考えていたので、山口の文章は鶴見を引きつけたのだろう。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。
