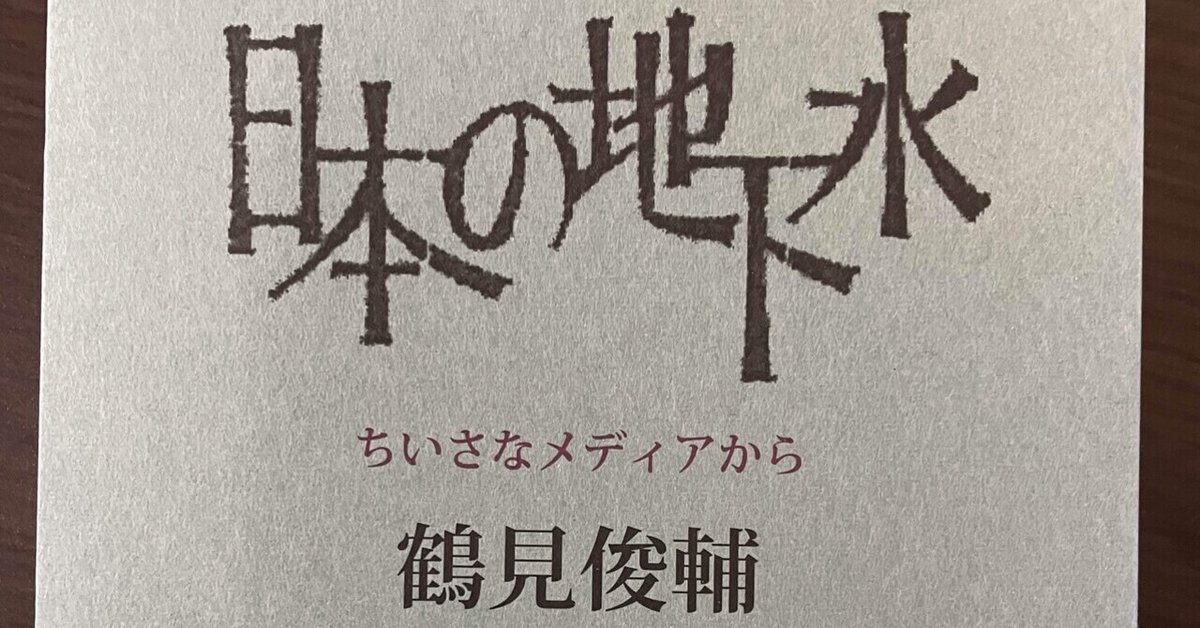
鶴見俊輔『日本の地下水―小さなメディアから』についてのメモ⑦―地下水を汲み出す
鶴見俊輔が、後年「老い」について関心を持っていたことは多くの彼の文章や対談で述べられている。鶴見が老いについて関心を持ったきっかけは、以下の宮城哲「鶴見俊輔研究序説:「自己」・「サークル」・「老い」の問題群をめぐって」も紹介されているが、折原脩三が40代に書いた「老いるについて」(『銀行研究』1965年3月号)というエッセイである。鶴見は、折原の定年後の著作活動を視野に入れて働いている間から読書に励んでいた姿を評価している。
この老いについての関心を持ったきっかけは、一例であると思われることに鶴見俊輔『日本の地下水』(編集グループSURE、2022年)を読んでいて気が付いた。鶴見が老いへの関心を持っていた同人誌として『日本の地下水』では、『騒友』(1968年8月)、『石風草紙』(1970年5月)、『耕人』(1971年5月)を紹介している。以下に鶴見の紹介の中で興味深い部分を引用してみたい。
いったい人間は、いつからもうろくするのか。私は十代のころ、「君は若くていいなあ。若いうちに本を読んでおくといい」などと、三十代、四十代の社会人に言われたものだが、すでに四十をこした今になってさとったことは、若い頃とちがって、中年以後に一生懸命に本でも読まないとあっというまにもうろくしてしまうということだ。四十をこえ、五十をこえての読書と執筆とは、自分の正気を保つための必死の訓練だと思う。『騒友』の同人たちは、もうろくを防ぐことに成功している人たちだ。
(前略)喰べるためには心に叶わぬ事もして来なければならなかった人たちが、六十という、昔ならば隠居ぐらしに入る年令を超えてなお、青年のような意気込みと、喜びを語る声として、尊く聞いたことである。こうした言葉が吐けるのは、生きるための、心に染まぬ仕事をする間にも、たやまぬ研究と精進が続けられて、頭脳や心の中に静かに沈殿し秘かに蓄えられた宝を持っている人たちなのだからである。中年を過ぎて、突如として立派な作品をものにしたり、論文を発表したりする人も、そういう人等なのだ。
「若い時はいいね、本が読めて」/などという言葉をきくと、へんな気持ちになる。読書が必要なのは、むしろ、中年以後で、自分のもうろくにたいする抵抗として十代、二〇代以上に、読むことが必要になるのだ。八〇代、九〇代になったら、もっと切実な読書の時代がひらけてよいはずだ。
ここで興味深いのは、鶴見が老いについての問題意識を同人誌から継続的に得ていたという点である。鶴見の老いに関する問題意識は、宮城の論文でも紹介されているように1980年前後から本格的に展開されるが、その問題意識への助走が「日本の地下水」で行われていたと言えるのではないだろうか。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。
