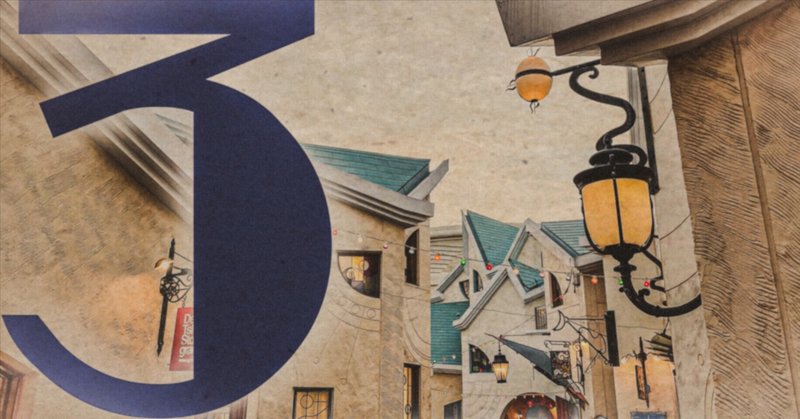
曲がりくねった道をまっすぐと進む【イクスピアリおたのしみマニュアル③】
JR舞浜駅直結のショッピングモール「イクスピアリ」のテーマは「路地の楽しみを舞浜に」である。
東京ディズニーランドと同じ会社が運営していて、日本国内に数多あるショッピングモールの中でも一味違うイクスピアリ。【イクスピアリおたのしみマニュアル】と題したシリーズでは、様々な視点から、「ディズニーランドに入らないディズニーリゾートの楽しみ方」を提案してきた。
イクスピアリが建設された背景には株式会社オリエンタルランドが夢見ていた「舞浜リゾート」があり、同社とディズニーの間には「東京ディズニーリゾート」開発計画上の駆け引きがあったことを書いた。
また、ディズニーランドの生みの親であるウォルト・ディズニーが晩年にショッピングモールを熱心に研究していたことも見てきた。
現代、ショッピングモールはディズニーランドに学んだ「テーマ化」によって、新たな姿を見せつつある。イクスピアリは架空の歴史を持った「街」として演出されており、それが商業施設の構造にも関係しているということを見てきた我々ならば、イクスピアリがこの手のショッピングモールの極地にあることを理解できよう。
この記事では【イクスピアリおたのしみマニュアル】番外編として、イクスピアリに見られるディズニーランド的手法を見てまわる。
サインに見る「テーマ化」
さて、「ディズニー化」とはある一側面から見れば、大量生産された紋切り型のサービスや商品に対して「テーマ」を与えることで、他と差別化された特別な体験を作り出すことであった。
「テーマ化」の前提にあるのは「規格化」であり、それ故にイクスピアリの最も〈特殊な〉部分が表れているのは各ゾーンの「サイン」であると、私は考える。
「サイン」とは、お店の名前やマップ、ここが何階でどういうゾーンであるなどを示す看板の類である。
『駅をデザインする』を執筆した赤瀬達三氏は、地下鉄駅出口の黄色看板を標準規格化し、各地下鉄路線にラインカラーを設定した。正に日本における「案内サイン」の先駆者である。今日、どの駅を訪れても共通した看板の大きさ・表示形式・色・フォント・用語を使用しているのは、紛れもなく彼の功績であると言って差し支えないだろう。
駅のデザインでは本来、場面づくりを担当するのは空間構成の仕事で、運賃や運行条件、列車の行き先など文字や記号でなければ伝えられない情報の伝達を担当するのが案内サインの受け持ちだった。
ところが駅が次第に複雑化するなかで、空間自体では筋道を示すことができなくなり、案内サインにその負担まで押しつけられるようになった。これは駅に限ることではなく、今では多くの都市施設がそのような状況に置かれている。
彼によれば、駅において人々を導くのは空間であり、案内サインはあくまで補助的な要素だ。しかし近年は、乗り換え線の増加や各社の利害関係、そして度重なる開発によって、日本の駅の構造が混濁の一途を辿っている。


ちなみに彼は、快適な駅を整備する上での四つの階層を定義している。第一に「安全であること」、第二に「楽であること」、第三に「居心地がいいこと」、そして第四のレベルは「満足度が高いこと」である(同書籍14〜15頁)。
こうした文脈を踏まえると、商業施設としてのイクスピアリは「路地の楽しさ」をテーマとしており、故にわかりにくい。赤瀬氏が「楽であること」と定義している「歩く距離が短い」「移動する先がよく見える」「施設配置がわかりやすい」といった項目とは真逆であるとすら言える(同書籍14〜15頁)。
こうした点を考える上で参考になる言葉を、赤瀬氏から借りてみよう。
赤瀬氏は、神奈川県内を走るみなとみらい線の各駅のサインを担当した。デザイン委員会が掲げた課題は「共通性と個別性」だったとのこと。みなとみらい線の各駅は各地域を代表する意匠が取り入れられ、別の建築家が設計することになっていた。
一方でサインとは「大半が不慣れな鉄道利用者にわかりやすい資格情報を提供するために設置するもの」であり、「利用者の利便性を考えれば、情報の掲出場所は各駅共通が」望ましかった(同書籍45頁)。
各サインは画面構成のみを統一し、背景色やフォントは各駅の雰囲気に合わせて設定することで、赤瀬氏は「共通性と個別性」の再現を図った。
イクスピアリもこれと同様で、各施設のサインは共通した画面構成を持っていながら、異なるデザインを持っているのである。
速水氏が指摘した「テーマパーク性」もまた、「現代の施設(ショッピングモール)を統一のテーマでカスタマイズ」したというものであったことを思い出して欲しい。両者の概念は「システム化されたものに対してナラティブを適用し、異なる表層をまとわせる」という意味で、同じことを説明しているのだ。
最後に、イクスピアリのサインを見ていく上で、便宜上いくつかの分類に従った。
サインは、複数のサインの相関関係で人を動かすものである。赤瀬達三氏が担当したような駅のサインは通例、「サインシステム」という形で規格化されている。
そして、このサインシステムは「指示サイン」、「同定サイン」、「図解サイン」から構成されている。
指示サインは施設などの方向を示すサイン、同定サインは、そこに施設があることを示すサイン。「トイレはあっち」と示して、「ここがトイレ」と受ける。(中略)。図解サインは、位置関係や順序などを、図を用いて案内するもの。
彼はまたサインシステムには「どんな内容を、どんなかたちで、どんな位置に」という要素があると書いているが、そのことには深く立ち入らないことにする(話があまりに複雑になってしまうためだ)。
ここでは、各施設を彩る「サイン」を、各ゾーンの歴史(=「ナラティブ」)や書くゾーンのテナントと共に見ていこう。
タウンエリア
ザ・コートヤード



アール・デコとも見えるような規則的なデザイン。額縁の色はゴールドで、煉瓦造りの壁によく映えている。
後に紹介するB'ウェイにしてもそうだが、狭く入り組んでいて天井の低いこうしたエリアでは、特に案内表示が大きな役割を持つと思われる。曲がり角が多い複雑な通りの場合、仮に脇道が少なかったとしても、目的地へ辿り着くのにはそれなりの負荷がかかるものだ。
これは、地下通路の入り組んだ地下鉄、ハブ駅などにも言えることである。
1階のザ・コートヤードに存在するレストランはどれも、気軽に入れる明るい雰囲気を持っている。そのため、各店舗の外観はそれなりにオリジナリティがあり、ザ・コートヤードの雰囲気を統一するのは店名を表示するための白い帯となっている。

クリスピー・クリーム・ドーナツやマクドナルドといった米国産ファストフード店やラーメン屋、他にもサーティーワンや築地銀だこなど、馴染みの店が並ぶ。二つのフードコートをも併設し、多くのお客を迎え入れる“商売の町”だ。
トレイダーズ・パッセージ


図解サイン(中、右)
黒とゴールドをベースとしたデザインである。店名看板のモチーフとして星が使われているのは、建物の天井と同様だ。
ちなみにこの店名の看板、overrideを筆頭に入り口から入って左側の看板と、Kastane等の右側の看板でデザインが異なっている。
また、元々は駅のコンコースだった、というストーリーを思い出させるきっちりとした額縁も特徴的である。特に、赤い背景のDIRECTORYとFLOOR GUIDEは、鉄道の時刻表と同じ壁面に設置されていて、溶け込んでいるのである。

道が広くかつ真っ直ぐセレブレーション・プラザ(中央の広場)に繋がっているため、あまり案内らしい案内はない。その代わり、イクスピアリの玄関口としての役割を果たすべく様々なエリアに階段やエスカレーター、そして小道を伸ばしており、DIRECTRYとタイトルのついた巨大な案内表示が設けられているようである。
トレイル&トラック



図解サイン(右)
ブラウンとベージュを基調としたハイコントラストなチェック柄が印象的である。トレイダーズ・パッセージが駅のコンコースならば、こちらはまるでレトロな客車を思わせるようなデザイン。
“Sports""Games""Trail × Track"の紋章は、イクスピアリに集った人々によって作られたもの。一際存在感を放ち、エリア名の表示としてもこの上なく有用である。
例えば男性のスーツなども元々はスポーツウエアだったりするため、実はスポーツというテーマと上品さは隣り合わせなのである。
網目状に入り組んだ通路が特徴的なこのゾーン。トレイル&トラックとは言うなれば「小道&小道」という意味なわけで、その名の通りである。店名が大胆に壁面全体で表現されていたり、通路の入り口に店名を示す看板が設置されていたり、はたまたポスターを飾ってみたり……と、施設の場所を示すための涙ぐましい努力が感じられる。


ミュージアム・レーン




イクスピアリの興味深いところは、アール・デコとアール・ヌーヴォーという敵対する二つの様式が同時に存在しているところかもしれない。これらの様式は、20世紀を代表する二つの「様式」である。
ミュージアム・レーンは全体的にアール・ヌーヴォー調。同じ時代に造られたザ・コートヤードと真逆の優美で開放的な雰囲気だ。
イクスピアリとしてもメインのエリアなのか、入り口を示すサインは豊富だし、案内も比較的親切だ。
さらに着目するべきは、各店舗の突き出し看板にはすべて全く異なる意匠が付けられている。ミュージアム・レーンはもともと、海と共に暮らす人々の住んでいた街だから、彼らの生活の跡が色々な場所に現れるのであろう。
看板は、貝殻を頭に乗せた素朴なものから、アール・ヌーヴォーの雰囲気をたっぷり感じさせるものまで存在する。
店舗によって異なる看板、雰囲気に合わせた装飾、街並みに溶け込むそれら……と、イクスピアリの魅力を端的に表しているデザイン。折角イクスピアリに来たなら是非とも訪れてみてほしいゾーンだ。
グレイシャス・スクエア






グレイシャス・スクエアにはIからIIIまで3つの区分があり、着目すべきは壁面の色である。
グレイシャス・スクエアIには高級感と落ち着きがあり、夕陽を受けたようなオレンジ色の壁面と青い屋根がよくマッチする。金色の縁の中に美しくデザインされたパネルが嵌め込まれ、エリア名を表示している。
グレイシャス・スクエアIIには騙し絵と神聖な宮殿のような雰囲気があり、壁面の色はよりグレイシャス(?)なシャンパン色になっている。エリア名は石板に刻印されており、四隅には赤い宝石が埋められている。
グレイシャス・スクエアIIIは後に紹介するB'ウェイの上にあり、おそらく近代になって発展したのだろう。白を基調にしつつ水色のアクセントが加わって、シネマエリア色に染まっている。
そういえば、グレイシャス・スクエアの店名は、アーチの下部を黒く潰してしまってそこに掲示することが基本的であるようだ。突き出し看板などを別で用意した方がストーリーを表現する幅も広がって良いように思うのだが、これはサンセリフ体で1行に書くような店舗のロゴが比較的多く、看板にするには似合わないから……なのだろうか(想像の域を出ないが)。
バリエーション豊かな複数の様式がひとつのゾーンの中に共存しており、それ故に立て看板のデザインは多様である。ひとつひとつ見てまわるのもまたおもしろいかもしれない。
シェフズ・ロウ


図解サイン(中・右)
デザイン自体は、ミュージアム・レーンと後に紹介するガーデン・サイトを足して割ったような雰囲気である。
おだやかで繊細なデザインと、ガーデン・サイトよりも深く渋い深緑が、シェフズ・ロウに並ぶレストランには相応しいのであろう。
1階のザ・コートヤードとは対照的に、シェフズ・ロウにはその名(シェフの“通り”)のとおり、ゆっくりと腰掛けて食事を楽しめる店が並ぶ。ザ・コートヤードが“商売の町”ならば、ここは“芸術の街”なのである。
WORLD BEER CUPというビールの世界大会を戦う舞浜の地ビール「ハーヴェスト・ムーン」も、ここでなら食事といっしょに楽しめる。ザ・コートヤードの場合、成城石井で売ってしまうのに!
シネマエリア
ガーデン・サイト




金属線と草木の意匠が施された庭園のようなゾーンである。シネマエリアの1階はすべてがガーデン・サイトであるのみならず、「舞浜オリーブの庭」というガーデンを併設していたり、「ディズニーアンバサダーホテル」「舞浜アンフィシアター」といったさまざまな施設に通じていたりと、サインの役割が大きいのも特徴。
アルフォンス・ミュシャの絵画を思わせるような曲線的なデザインが、文字通り“型破り”な額縁となっている。
以前の記事で紹介した通り、イクスピアリを完成させた加賀見俊夫社長(当時)は著書『海を超える想像力─東京ディズニーリゾート誕生の物語』の中で、東京ディズニーリゾート全体のテーマを「知恵(Sage)」に「自然(Nature)」としている。とくに「自然(Nature)」は、人々がさまざまなものを創造する場所、すなわち「知恵(Sage)」が腰掛ける椅子と位置付けているのである。
こうした点から、ガーデン・サイトの圧倒的な存在感には理由があった……とも言えるだろう。
シアター・フロント



図解サイン(右)
シアター・フロントの何よりの特徴は、その圧倒的な没入感!
夜のネオン街をそのまま再現し、夕焼け空で蓋をしたこのゾーンは、各施設の看板を建物の中に組み込んであたかも“ストーリー上にもその施設がある”かのように見せかける。ハワイ発祥のハンバーガー店であるクア・アイナには“HAWAIIAN"という大きなネオンサインが付けられ、メキシカンフード店のGuzman y Gomezが入ったテナントには死者の日の装飾が。
看板は圧倒的な存在感を保ちながら、しかし溶け込んでいく。この理念は店名だけでなく、ゾーン名の表示にも遺憾なく発揮されていて、シアター・フロント自体が一つの映画かのように演出されている。
エリアの雰囲気は、1920年代に映画がアメリカ全土に広がった当時を思わせるアール・デコ様式である。ところで、吉田鋼市氏は、『図説 アール・デコ建築─グローバル・モダンの力と誇り』の中で、アール・デコが「国民性や地域性や歴史や伝統という要素を含み込む余地をももっていた」と指摘し(4頁)、「インターナショナルとナショナルの中間的なものでもある」とも言う(12頁)。
シアター・フロントの商店街は、そうした雰囲気を少しでも感じさせてくれる。
B'ウェイ



シアター・フロントならぬシアター・バックとしての性格を持つこのエリアには、エンターテイメントを陰で支えるアーティストたちの描いた流れ星のモチーフが散りばめられている。この流れ星の部分には“B'WAY * IKSPIARI"という文字が入っているようだ。実際は基本的にはスター・ウォーズに登場するスター・デストロイヤーみたい。

バックヤード(あるいはスター・デストロイヤー)の雰囲気を与えるのは、狭くカクカクと入り組んだ通路。この通路を右にいけば良いのか左に行けば良いのか、ゾーンの入り口にも中にもたくさんの案内があるのも特徴である。
小さな立て看板はシアター・フロントと同じデザイン。これ、私も最初は不思議だったのだけれど、2つで1つのゾーンなのだから当然と言われれば納得はできよう。
好きなエリアはなんですか?
いかがだっただろうか?
JR舞浜駅を降りたほとんどのゲストが真っ先に向かうのは、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーといったディズニー製のテーマパークであろう。
しかし、イクスピアリの中に一度でも迷い込めば、そこには正に「路地の楽しみ」があふれている。遠路遥々やってきてディズニーパークの華やかなエンターテイメントをひとしきり楽しんだゲストは、疲れ切った翌日にここで心を癒して帰ることができる。また、東京23区に住むゲストにとって、ここは最も身近な“リゾート”地である。
「だれがいつこの名称を認めたのか。当社では『東京ディズニーリゾート』と名づけたつもりはない!」
株式会社オリエンタルランドが目指した「舞浜リゾート」も、ディズニー社がこだわった「東京ディズニーリゾート」も、どちらも「リゾート」である。
彼らの作り上げるリゾートは、喧騒の中で過ごす我々にひとときの安らぎとインスピレーションを与えてくれる。その意味でイクスピアリは、このリゾートの存在意義を端的に表現した、象徴的な街なのである。
第一回▶︎『重なりあう二つの歴史【イクスピアリおたのしみマニュアル①】』
第二回▶︎『希望か野望か、それとも陰謀か?【イクスピアリおたのしみマニュアル②】』
第三回▶︎『曲がりくねった道をまっすぐと進むには【イクスピアリおたのしみマニュアル③】』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
