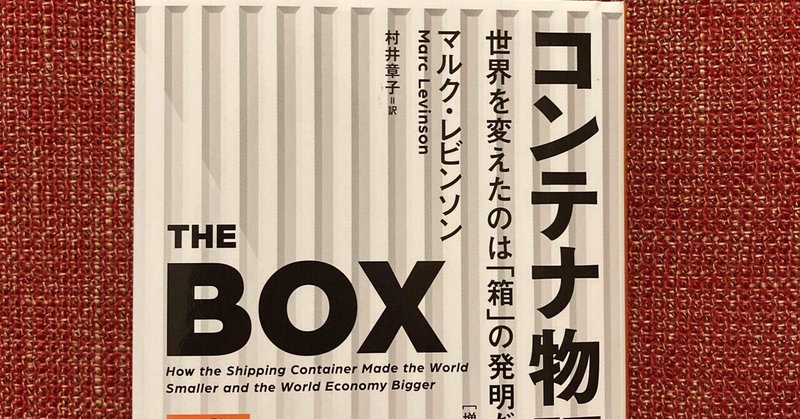
【コンテナ物語】世界を変えるのはなんて事ないものなのかもしれない
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆
〜侮れないただの「箱」〜
本書はタイトルのとおり、コンテナに関する本である。
コンテナという「箱」が、国際物流と世界経済に大きなインパクトを与えるまでが描かれた一冊である。
コンテナに目をつけた著者の観点は非常に面白い。コンテナという見た目にも平凡なただの「箱」が、世界にどれだけの影響を与えたのか、非常に楽しく読ませてもらった。
かつて、船の輸送は今とは比べものにならないほどコストがかかった。
荷物の積み下ろしは主に仲仕が人力で荷物を運ぶ形で行われていた。そして、その積み下ろしの作業のために船は何日もその港に停泊しなければならなかった。船の輸送にかかるコストは、沖仕たちの人件費や船の停泊期間にかかるものが大方であった。
さらに、内陸部に荷物を輸送するためには、鉄道やトラックなど、海上輸送とは別の料金体系での輸送費がかかる。総じて、荷主から送り先までの間の輸送費は今では考えられないほど高かった。
そんな状況の中、本書で度々出てくるマルコム・マクイーンという人物が、「貨物を箱ごと輸送する」というアイデアを思いついた。箱の状態で、海路陸路を運ぶことでシームレスな輸送を可能とし、輸送コストを抑える。これが現在のコンテナの原型となるアイデアである。
このアイデアが世界的な標準になるまで長い年月を経るわけだが、ただの箱が世界標準となり、世界に巨大なインパクトを与えるように進化するまでの経緯をたどっていくのが本書である。
〜世界を変えるものに誰も気づかない〜
さて、コンテナが普及するまでの過程の中で、沖仕たちが組織する労働組合の反発があったり、港における雇用の形を大きく変えてしまったり、コンテナの規格を定めるまでの困難があったり、各国の輸送費の規定で混乱するなど、様々な出来事が本書では語られるのだが、本書全体を通して見られるのは、多くの人がコンテナのもたらす世界の変化を見誤っていた、という点である。
昨今のスマートフォンのような、誰の目から見ても世界を変えてしまう予感があるものではなく、世界を変えるのがただの「箱」というのを、一体誰が予測できたのだろうか。
海運の大手企業や国や自治体の多くが、コンテナのもたらす変化を、誰も正確に予測できていなかった、というのがコンテナ物語の根幹にある事実なのだろう。
コンテナのもたらす世界の変化に対して、誰も正確に予測が出来ず、コンテナリゼーションを軽視して失敗した者、逆にコンテナリゼーションに過剰な投資をして失敗した者など、その姿は様々である。
そりゃそうだ、あんなただの鉄の箱がイノベーションを起こすなど誰が予測出来るのだろうか。
そういった意味でもこのコンテナの話は面白い。僕らが生きる現代においても、もしかすると、世界を一変させてしまうのは、現状誰も見向きをしていない何かなのかもしれない。
〜コンテナの未来〜
さて、このコンテナ物語自体は非常に面白く読んだのだが、本書の著者であるマルク・レビンソン氏も巻末の解説文にも、「今後、コンテナがどのように進化していくのか。コンピュータ化が進んでさらに大規模な港が出現するのか。さらに大きなコンテナ船が作られるのか。」などなど、コンテナの更なる拡大を予想する記述が見られた。
しかし、僕は、コンテナ輸送は今より格段に大きくなったりはしないと思う。
コンテナが経済にもたらしたのは、いわば"量"によって経済を大きくすることだった。大量生産、大量消費による経済の拡大においては、コンテナの功績は大いなるものだ。
しかし、様々な識者によると、"量"に頼る経済成長は望みが無くなってきた。
人口減少や環境問題の観点から、規模によって成長する経済は廃れていくだろう。
そうなった時に、新しい経済の世界において、今日のコンテナのようななんて事はないものが、次の経済を拡大していく役割を担うのだろうと思う。
それがなんなのかはまだ僕らにはわからない。
しかし、今目の前にあるもの以外にも、コンテナのように、世界を一変させるものがあるかもしれない、と考えるのは、希望があるじゃないか、と、僕は本書を読んで思ったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
