
指揮官の無能さを心理的に分析する『軍事的無能の心理学』(1976)の紹介
軍事史では、平時に高い地位についた軍人が、戦時にひどい失敗を重ねた事例が数多く記されています。このような軍人は一軍の司令官として大きな権限を持っているにもかかわらず、戦地で発生した問題を適切に解決できず、何ら有効な手を打たないか、あるいは非現実的な対策を講じて事態を悪化させ、軍隊に損失を与えます。
このような事象が起こる要因に関しては、軍事社会学や軍事心理学の分野で議論されていますが、ひときわ大きな影響を及ぼした研究者の一人にノーマン・ディクソン(Norman Dixon)がいます。第二次世界大戦(1939~1945)に陸軍将校として従軍した経験を持つイギリスの心理学者であり、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの教授を務めました。彼の『軍事的無能の心理学』(1976)は出版された当時から多くの論争を引き起こした著作として知られています。
Dixon, Norman. 2016(1976). On the Psychology of Military Incompetence. Basic Books.
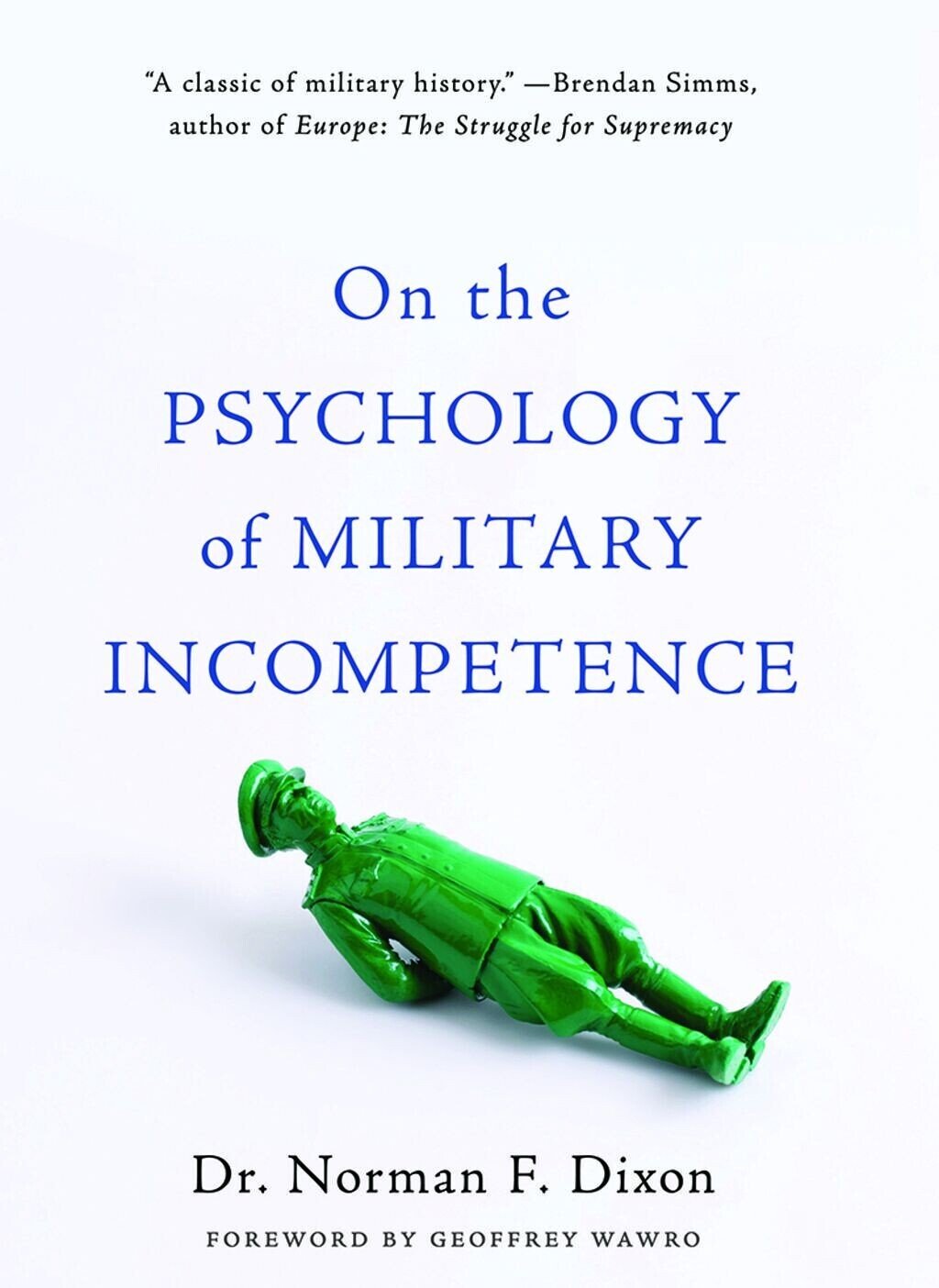
著者の論旨は、将官に相当する高級士官が、その職務を遂行する上で重大な支障を来す要因として能力の不足だけに注目するのではなく、認知の過程に注目する必要がある、というものです。特に注意すべきが権威主義的パーソナリティの傾向の強さであり、これが強いということは、権威に対する従順性、服従性が強く、規律や規則を絶えず意識し、地位の向上に熱心な性格であることを意味しています。
著者はこのような性格特性を持った個人は、職務を秩序立てて進めることを好み、ある事柄に対して矛盾した認知(認知的不協和)を許容できる程度が低く、独創性や創造性を軽視する傾向があると論じています。言い換えれば、権威主義的パーソナリティは、そうでない人々に比べて予想外の出来事を受け入れ、自分の知識や信念を見直しながら、新しい知識を学ぶことが難しくなり、それだけ先入観の奴隷になりやすいといえます。
だからといって、彼らが全面的に無能であるというわけではないと著者は強調しています。むしろ法令や規則を厳守することが求められる平時の軍隊勤務では高い評価を受ける傾向にあると著者は指摘しています。だからこそ、彼らの能力は平時から戦時に移行したとたんに劇的に低下するように見えます。著者の視点は認知心理を踏まえており、彼らの問題の解決に必要な学習プロセスが阻害され、自分の状況認識を絶えず更新することが難しくなると、適切な指揮をとることが困難になると考えています。
一部では著者が権威主義的パーソナリティを強調しすぎていると批判していますが、著者は必ずしも性格特性だけですべて説明できると主張しているわけではありません。戦争で任務を遂行する軍人は、睡眠の不足、疲労の蓄積、粗末な食事、責任の重圧、戦闘の危険といった深刻なストレスに耐えなければなりませんが、こうしたストレスに対する耐性は高齢化によって失われていくとも論じています。また、野戦軍の司令部では情報が錯綜し、有意義な情報とそうでない情報を見極めることが難しくなることも考慮されています。司令部の通信が不安定である場合、あるいは指揮官を補佐すべき幕僚が偏見を持っている場合にも、状況認識の更新が滞りやすくなるでしょう。
指揮官となる個人は、組織内で高い評価を受けている場合が多いため、このことも意思決定を制約すると著者は指摘しています。ある状況下で、それぞれの行動方針を列挙し、その中から一つを選択しようとする場合、個人は予想される利得と損失の組み合わせを参照し、最大の利益が期待できるものを探そうとします。この時に、過去の業績で高い評価を受けた人物は、その期待に応え、あるいは評価を維持しようとする傾向が強くなるため、リスクが大きい行動方針を選択肢から除外しようとする傾向を示します。危険を冒さないことは、戦争において必ずしも合理的な意思決定であるとは限りません。というのも、それは部隊の活動から積極性、新規性を奪い、防御の側に回りやすくなるため、戦いの進展を味方が主動することができなくなるためです。
著者は、このような指揮の問題が起こるメカニズムを示すために、いくつかの歴史的事例を取り扱っていますが、その一つにクリミア戦争(1853~1856)が含まれています。この戦争は、ロシアがオスマンの支配を受けていたモルダヴィア、ワラキアへ侵攻したことで始まり、ロシアの勢力が南方へ拡大することを封じる意図でイギリスとフランスが後に参戦しています。著者がこの戦争で注目しているのは、当時のイギリス派遣軍を率いたラグラン男爵フィッツロイ・サマセット(1788~1855)の失敗です。

ラグラン男爵は若くして陸軍に入隊し、ナポレオン戦争(1804~1815)で数多くの戦闘を経験しています。最後の決戦となったワーテルローの戦い(1815)ではウェイントン公爵アーサー・ウェルズリー(1769~1852)の副官を務めました。しかし、彼はワーテルローの戦闘で右腕の切断を伴う重傷を負い、その後は陸軍中央で補給の仕事を任され、その後も進級を重ね、選挙に出馬して国会議員の地位も手に入れています。1854年にクリミア戦争が勃発したとき、彼は陸軍中将でしたが、同年のうちに陸軍大将(6月)に進級し、イギリス派遣軍の指揮を引き受けました。彼は66歳と高齢でしたが、大規模な戦闘を指導した経験はなく、ロシア軍の能力を極めて過小に見積っていました。そのため、彼は1854年の冬までにはロシアの黒海艦隊の基地が置かれていたセバストポリを陥落させることが可能だと確信していましたが、それは大きな間違いでした。
ラグランは単に戦略を誤っただけでなく、軍司令官として戦闘間に命令の実行を監督し、現地の状況の推移に即応した指導を行うことができませんでした。このため、戦闘間でさまざまな戦術的な間違いが生じています。バラクラヴァの戦い(1854)では、戦闘間の通信過程で誤解が生じ、味方の騎兵を敵の砲兵に正面から突撃させる事故で大きな損害を出しました。その後のセヴァストポリの攻囲(1854)では、若く経験が少ない人員で無謀な陣地攻撃を実施させています。
この戦闘では部下の指揮官が砲兵の火力支援を待たず、間違って30分も早く歩兵の突撃を発起したせいで、壊滅的な損害を出しました。そもそも、2,000名の歩兵が敵火の下で200メートルの距離を躍進し、6メートルの幅がある乾壕を通過するという戦場機動には無理があり、歩兵の脆弱さに対する認識が欠落していました。本来であれば、ラグランが戦地に連れて来た幕僚が計画立案を補佐すべき立場にありましたが、ラグランは個人的に親しく付き合いがあった60歳以上の同世代の軍人ばかりを幕僚として選んでいたので、司令部における彼らは幕僚として十分な能力を発揮できませんでした。
ラグランは1854年末から1855年の春まで本格的な戦闘を行っていませんが、この間に派遣部隊では糧食、燃料が著しく不足していました。ラグランは、クリミアでの越冬がいかに困難であるかを前もって認識しておらず、部隊の宿営地では燃料の不足が深刻でした。薪がなくなって暖を取ることができなくなると、兵は次々と天幕で凍えて病気になり、回復しないまま死亡する事例が相次ぎました。また、戦闘で負傷した兵も適切に治療されることなく死亡していきました。この期間に派遣部隊が失った戦力は全体の35%近くに上っており、1855年1月になると、被服や毛布が貴重品となったことから、兵は戦死者を裸にして地中に埋葬しなければならないほど追いつめられていました。ラグランは、この問題を解決するために具体的な手を打つことができておらず、自身もコレラに感染して1855年6月に死亡しています。
著者は、軍事史においてラグランのような司令官の事例は必ずしも特異なものとは言い切れないとして、次のように述べています。
「高級指揮官の軍事的無能さが長く続いた例として、クリミア戦争は残念ながら特別ではない。ただし、その後も繰り返された愚かさの原型だったことは事実である。その後の戦争で生じた犠牲者の数と比べれば、その数値は小さいが、計画の不備、不明瞭な命令、知性と情報の欠如、社会的な圧力に対する指揮官の致命的な脆弱さが組み合わさった結果、18,000名の兵が早すぎる死を余儀なくされた。軍隊の階層構造での地位がその人物の能力ではなく、その人物の豊かさ、社会的な身分、『適任である』という評判に基づいて与えられた人物の不手際で、彼らは死んだ。あまりにも安易に兵士が消耗品と見なされたために、彼らは死んだのである」(Dixon 1976: 50)
この著作で示された分析に関しては、さまざまな批判も加えられています。これは著者の歴史的事例の取り扱い方が一次史料によらない二次分析であるためです。ただ、本書が軍隊の運用を左右する指揮の問題に取り組み、後続の研究に影響を及ぼしたことは間違いないと思います。戦争における意思決定の非合理性を心理的アプローチで説明することは、今では目新しいものではなくなっていますが、本書が出版された当時はまだ珍しく、この点で独創性がありました。戦争の実態を理解するだけでなく、高級士官の人事を考える上でも興味深い一冊です。
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

