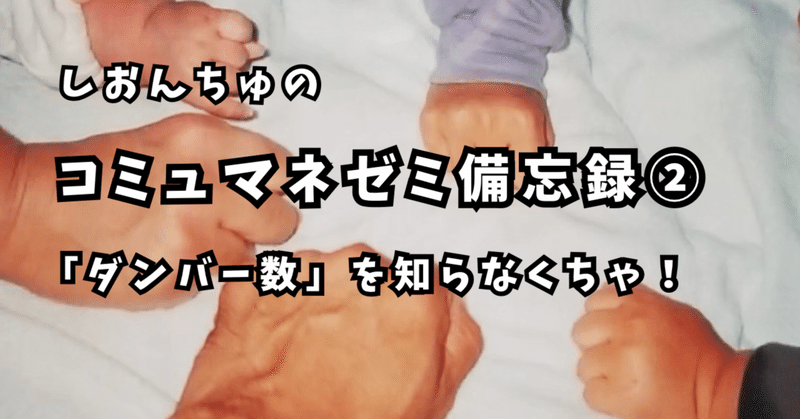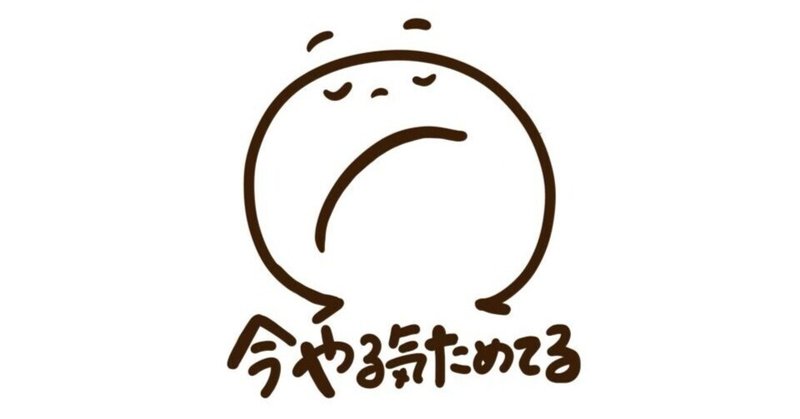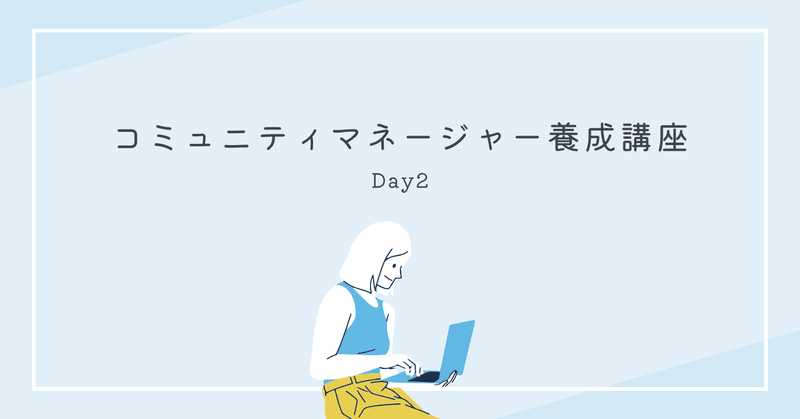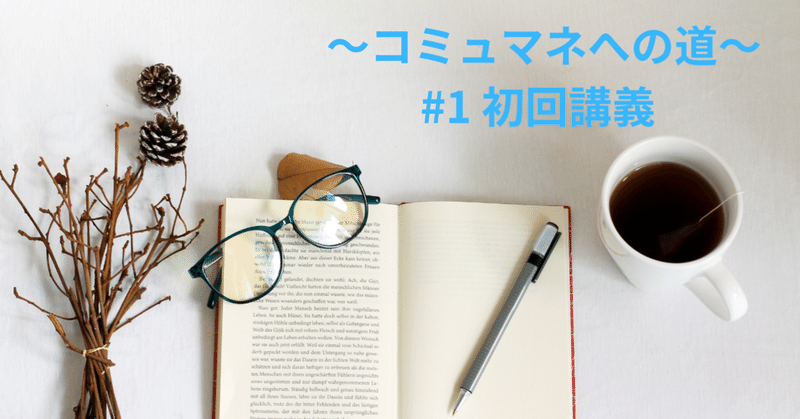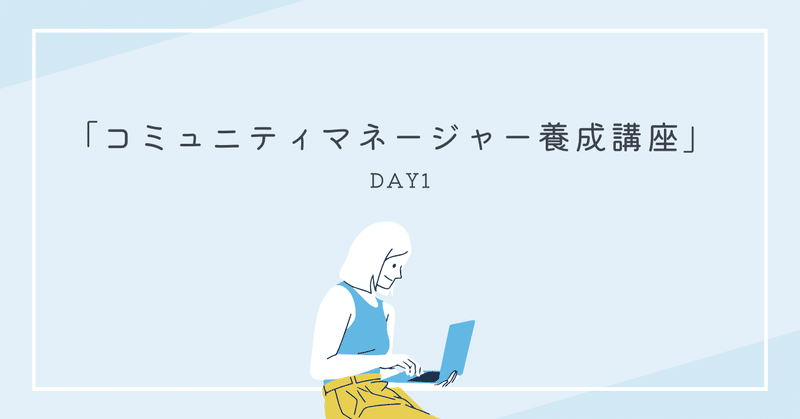#TABIPPOコミュマネゼミ

コミュニティマネージャー始めました#5~ダニエル・キムの「成功循環モデル」に着目したコミュニティの質向上のためにできる取り組み~
こんにちは、白波です。 今回は、私が参加しているコミュマネゼミの課題から、ダニエル・キムの「成功循環モデル」について話をしつつ、私の考えるコミュニティの質を高めるための土台作りの話をしていく。 コミュニティの定義の再確認以前の記事でも定義について触れたが、今回もまずはコミュニティについて前提条件を確認しておこうと思う。 ここで強調しておきたいのが、特定の目的意識を持ったという部分である。メンバーの誰もがそのコミュニティに対して、自分の意図や目当が必ずあり、それを叶えるため