
小学校のテストについて思うこと
【1分で読めて役立つ】小学校教員の情報発信🖋
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は、「小学校のテスト」について書いていきたいと思います。
この記事は、
✅子育てに関わる方
✅教育に興味のある方
に特にオススメの内容です。
目次は、以下の通りです。
1⃣テストの点が大事にされすぎている気がする
✅教育に私は、小学校の段階からテストの点が大事にされている気がするのです。
中学校や高校では、テストの点数がすごく重要視されていますよね。
現状の入試というシステムがテスト中心のため、そうならざるを得ないのは仕方ないのかもしれません。
エリアによっては、小学校の段階からテストの点数を上げるための勉強が必要があるかもしれません。

しかし、勉強って、テストの点数をとるためだけにするものではない気がします。
テストの点数をとるための勉強もありますが、そうでない勉強もある。
そのあたりを教える側が理解するだけでなく、子どもにも伝えていく必要があるのではないかと思います。
子どもたちが「テストの点数さえ取れればいいでしょ」という発想にのみ囚われてしまうと、「学ぶ楽しさを見失ってしまう危険がある」と感じるからです。
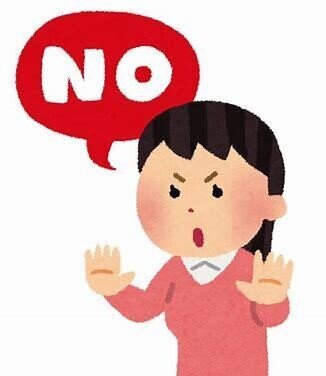
これは個人な考えですが、テストの点数は、あくまで、
✅「自分の学びに生かすための数値でしかない」
と考えています。
それぐらいのスタンスで捉えていた方が、気楽に勉強を楽しめると思います。
そして、気楽に勉強を楽しむことが結果にも繋がっていくと思うのです。
そもそもテストって何のために行うのでしょうか。
ちょっと考えてみます。
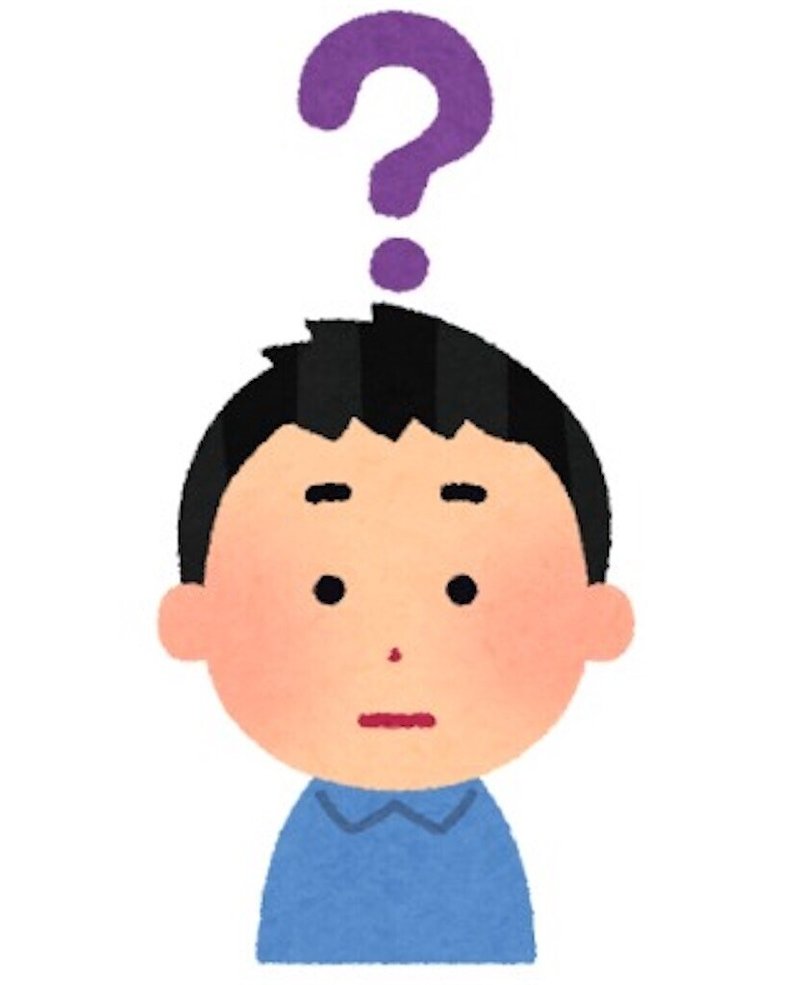
2⃣テストは何のため?
テストは、
✅客観的に学習の到達度をはかるため
✅自分の分かること・分からないことを具体的に知るため
の大きく2種類の目的で行っていると思います。
・客観的に学習の到達度をはかるため
テストで数値化されると大体の学習の到達度を知ることができます。
かけ算のテストを何枚かして、7割程度の点数だとしたら、学習内容のどこかに課題が残されていることが分かるでしょう。
そうやって現状を知るという側面は、学習を進めていく上でとても有効だと私は思います。
また、この学習の到達度は、絶対評価を行う時の分かり易い指標とも言えるかもしれません。
実際に学校現場では、教員が主観で行うより、客観的になるので、評価に使用されることが多いという現状があります。

・自分の分かること・分からないことを具体的に知るため
実際に問題をやってみると、分かった気になっていたことがあることに気付かされます。
できそうで、できない。わかりそうでわからないって状態です。
あれを体験して、自分の分かることや分からないことの線引きを明確にするというのもテストの目的の一つかなと思います。
大まかな到達度だけでは、具体的に何から手をつければいいかわからないことがあります。
しかし、実際に「~といった問題が分からない」という具体例があれば、学習もはかどりそうです。

テストのことを考えていたら、評価を気にした勉強ばかりだと子どもも大人も窮屈なのではないかなという気がすごくしてきました。
この文章、飲みながらつらつら書いていたので、まとまりがないかもしれませんが、テストについてはまたこれからも考えを書いていこうと思います💡
今回は、以上になります。
お読みいただきありがとうございました😊
この記事が少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。
テストについて思うこと等、教えていただければ幸いです。
これからも学校現場のことや教育、仕事や日常生活に役立つことを書いていきます!!
みなさんの応援が私の励みになります。
ぜひ、応援のスキやフォローをお願いします😊
いただいた分は、若手支援の活動の資金にしていきます。(活動にて、ご紹介致します)また、更に良い発信ができるよう、書籍等の購入にあてていきます!
