
緊張と緩和のバランス
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は、緊張と緩和のバランスについて書いてみたいと思います。
今回は、子どもへの指導というよりは、自分の生活の中をメインに書いてきます。
目次は以下の通りです。
①緊張と緩和について
2つの言葉の意味をデジタル大辞泉で調べてみました。
緊張とは?
1 心やからだが引き締まること。慣れない物事などに直面して、心が張りつめてからだがかたくなること。「緊張をほぐす」「緊張した面もち」
2 相互の関係が悪くなり、争いの起こりそうな状態であること。「緊張が高まる」「緊張する国際情勢」
3 生理学で、筋肉や腱(けん)が一定の収縮状態を持続していること。
4 心理学で、ある行動への準備や、これから起こる現象・状況などを待ち受ける心の状態。
緩和とは?
[名](スル)厳しさや激しさの程度を和らげること。また、和らぐこと。「制限を緩和する」「混雑が緩和する」
緊張はいくつかの意味がありますが、今回は、1の心やからだが引き締まること。の意味で使っていきたいと思います。
本来、「緊張」の対義語は、「弛緩」ですが、緩むというよりは、緊張が和らぐという意味で話をしていきたいため、今回は、「緩和」を用いていきたいと思います。
人にもよりけりだと思いますが、人前では、基本的に、緊張している状態と緊張が和らいでいる状態の2つの状態を行き来していると私は思います。
【緩みきった弛緩の状態は、家で一人でゆっくりしている時といったイメージでとらえています。】
学校や職場で、生活している中で、緩み切ることはあまりないと思いますので、緊張している状態と緊張が和らいでいる状態の大きく2つの状態で考えていきます。
私の場合、学校現場で子どもたち、あるいは大人と接していく中で、2つの状態を行き来するわけですが、その2つの状態のバランスがとても大切だと思っています。
②では、2つの状態のバランスをとることがどうして大切なのかについて考えを書いていこうと思います。

②緊張と緩和のバランスを取る必要性
私がなぜ、緊張と緩和のバランスをとることが大切と考えているか。
それは、「精神面の安定及び生産性の向上」と「行動への刺激」に効果的だと思っているからです。
1 精神面の安定及び生産性の向上
ずっと緊張状態では、精神的に疲弊してしまうことは誰もが容易に想像することができると思います。
逆に、緊張がずっと和らいでいる状態でいても、怠けてしまって、やる気を失ったり、生産性が上がらなかったりすることがしばしばあります。
シンプルですが、以上のようなことから、適度なバランスをとることが大切だと思っています。
しかし、ことのほか、バランスを考えて行動したり、対策したりしている人は多くないように感じています。
自分の仕事の生産性を上げるために、あえて緊張を緩和させる時間をとるという選択を計画的に行えるようになると自分のメンタルを良い状態に保つことができると思います。

2 行動への刺激
緊張している時【極度の緊張は除く】は、体は少し硬くなりますが、「頑張ろう」という気持ちが自然と働いて、動けることが多いかと思います。
逆に和らいだ状態でいる時は、「少しのんびりしようかな」という気持ちが働いて、動きがゆったりとしたものになると思います。
そのため、一般的に何かを行う場合は、少し緊張している状態の方が、効率よく動くことができるといえそうです。【創造的な仕事の場合は、ゆったりとしている時間が長いほうがいいかもしれません】
そのため、ちょっと気張ろうという時に、緩和している状態から、緊張のスイッチをオンにすることは、行動への良い刺激になります。
同様に、ちょっと休憩しようと、緊張のスイッチをオフにするのも行動への良い刺激だと思います。
目的や状況に合わせて、2つの状態のバランスを考えて行き来しながら、行動へ刺激を与えていくと良いと私は思います。

③私の緊張と緩和のバランス
私の場合、仕事をしている時は、全体を10として比で表すと「緊張:緩和=3:7」くらいのイメージです。
私は、緊張と緩和を一人で何かをする時と人と接するときとで、使い分けています。
私は、学校で働いていて、授業をしている時間が長いのですが、授業中も同じようなバランスでいます。
45分の授業でしたら、大体「12分の緊張と33分の緩和」くらいのイメージです。
授業中もそれ以外も、人と接するときは、緩和の状態で接するように心掛けています。
緊張の状態だとなんだか心理的にゆとりがない気がして、相手にとってあまり良い対応ができないと考えているからです。
とりわけ、頭が柔らかく、柔軟な思考をする子どもたちを相手にするときは、自分も心にゆとりをもって接したいと思っています。
逆に、自分が主体で発信をしたり、一人で作業をしたりするときは、無駄を省いたり、生産性を上げたりするために緊張の状態にするよう心掛けています。
ぜひ、この機会にちょっと日常を振り返っていただければ幸いです。
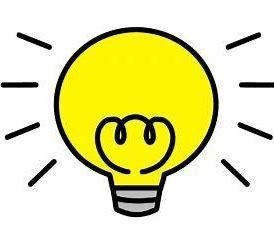
以上、緊張と緩和についてでした。
ちょっと専門性があがりますが、「緊張と緩和をクラスの経営に生かすこと」についても、後日書いてみたいと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
旅人先生Xはこんな人です。↓↓↓↓↓↓
皆さんのスキやフォローが毎日投稿の励みになっています。
ぜひ、応援のクリックをお願いします!
いただいた分は、若手支援の活動の資金にしていきます。(活動にて、ご紹介致します)また、更に良い発信ができるよう、書籍等の購入にあてていきます!
