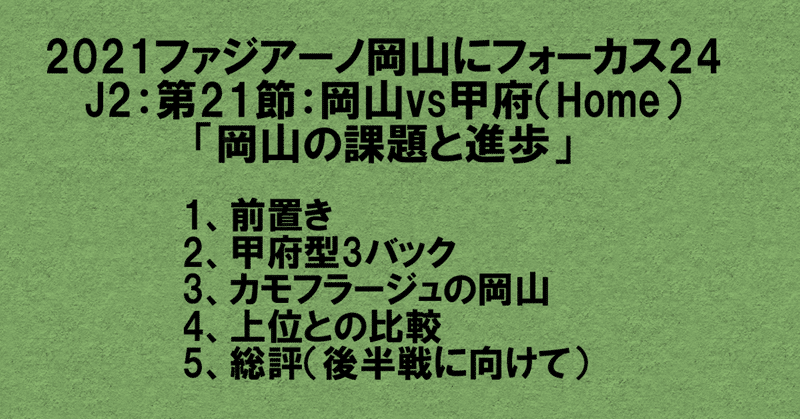
2021ファジアーノ岡山にフォーカス24 J2:第21節:ファジアーノ岡山vsヴァンフォーレ甲府(Home) 「岡山の課題と進歩」
1、 前置き
「昇格」。このワードから岡山が遠ざかっている。昨シーズンは、コロナの影響の過密日程。今季は、昨季からの臨時ルール変更(交代枠が5人・給水タイム)が継続された事と、様々なレギュレーション一時的な変更(入場者制限・昇格&降格・その他)が、行われた中で、影響を色濃く受けたチームの1つである。
有馬ファジを評価する上で、この辺りをどこまで考慮するか。これによって、評価の良し悪しに、個人差が出てくるのは致し方ないだろう。私自身、前半戦総括にトライする時間が許せば、今週末には、投稿したいと考えている。出来るだけ簡潔かつ、シンプルにまとめる事にトライしようと検討中だが、このレビューが、完成が遅くなれば、五輪前に投稿を行うかもしれない。投稿断念の可能性もあるので、期待しないで待っていただきたいが、ここに投稿した事で、自身にプレッシャーをかけていく。
「ヴァンフォーレ甲府」と言えば、J2昇格元年のホームの開幕戦のカードであったと記憶している。当時は、ミクシーやFC2ブログで、簡単な文章を書いていたが、私感がかなり入っていたというか、熱量だけで書いていた。色々と交流の仕方にも、今振り返ると、失敗が多く、私の事を快く思っていない方も多いのではないかなと思うと、後悔の念が無いと言えば、嘘となる。
人は、熱くなると周りが見えなくなる部分があるので、今は、冷却水を常に浴びているように、冷静に物事を考える意識が根付いたので、当時とは、感じ方や見え方が、違って来る。「蹴鞠談義」というブログを投稿していた時期があるが、形に拘り過ぎて、サッカーに入っていけなかったのは、今となっては勿体ない。ただ、記録を残すという点では、ある意味データベースに近い形で、残っているが、サービスが、終了すれば、消滅すると思うと、寂しい。
また、「蹴球」ではなく、「蹴鞠」であったのは、歴史好きで、日本における昔のサッカーというか球技は、蹴鞠であった。足を使う競技という事で、現代は、行われていないが、「ゴールにパスをする」、「浮き球だけゴールに運ぶのが理想」といった感じに考えて、そういった名称にしたと曖昧ながら記憶している。
当時の甲府は、開幕戦が引き分け多いという話題であったが、実際に引き分けに終わった。ただ、実力差は大きかった。やはり、当時のメンバーと、今のJリーグ全体を見渡して、比べてみると、今のJリーグの全体のレベルは、間違いなく底上げされている。そして、J3まである事を考えても、待遇には差があるもののJリーガーを目指してきた子供達が、実際にJリーガーに成れた子供達も多く、欧州移籍する選手も増えて、夢のあるリーグになりつつある。
一方で、満足な結果を残せず、引退していった選手も多く、プロの厳しさというのを感じて、または、怪我により、プロの道を断念した選手も見て来た。現在の岡山であれば、39増谷 幸祐が、長くピッチから遠ざかっている。根拠もなく、怪我から復帰してくると、勝手に思っていたが、ここまで、遅くなると、流石に心配となってくる。9李 勇載も原因不明というか公式発表もなく、そういった選手達が、ピッチから遠ざかっているというのは、チームとしても痛手であると同時に、サポーターとしても一日でも早く元気な姿を見たいと、考えている方も多いのは、間違いないだろう。
こうして、考えても見ると、サッカーの1つ1つのプレーを見ても、色々な要素の集合で、それをどう捉えるのか、または、どう解釈するのか。それも多岐に渡るだろう。そういった魅力のあるスポーツだからこそ、嵌る方も多いスポーツである。そのサッカーについて、本日の試合で見えたファジアーノ岡山の課題と、前進できた点について、まとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

2、 甲府型3バック
まずは、いつも通りメンバーについての雑感について、まとめていく事から始める。
「ファジアーノ岡山」
・バランス重視の4-4-2を継続。
・11宮崎と41徳元の復帰と、10宮崎のスタメン復帰。
・18齊藤の久々のリザーブ入り、4濱田はリザーブに回った。
・5井上と7白井は、フル出場継続。
「ヴァンフォーレ甲府」
・後方のバランスを崩さない3-4-2-1。
・前節をベースとしたスタメン。
・メンデスが左CBでスタメン復帰、13北谷がリザーブ入り。
・甲府型3バックにより両WBがほぼフル出場。
京都戦のショッキングな内容の完敗を受けて、掴みかけていた自信という心の拠り所を打ち砕かれた岡山が、今季苦手としているホームに。前節6発のゴールを決め大爆発した甲府を迎えた。守備を立て直せたとかどうか、無得点に終わった得点力に改善や工夫が見られたどうか。そこを再確認できるという意味で、前半戦最終節の相手としては、申し分のない対戦チームである。
甲府の3バックは、特殊であった。岡山サポの多くは、WBは、ハードワークするポジションという認識であると思うが、甲府のWBは、ハードワークというまで、走らない。岡山の勝利の方程式の3バックに近いイメージだが、甲府は、どうしてスタートから採用しているのか。その辺りもハードワークしない事に関係している。
3バックと言えば、攻撃時に、サイド深くまで侵入していくという攻撃スタイルをイメージするが、甲府のサイド攻撃の軸は、アーリークロスである。状況によっては、上がるシーンもあると思うが、基本的には、シンプルに前線の10ウィリアン・リラを的にするというサッカーである。的となった10ウィリアン・リラに、京都の9ピーター・ウタカみたいに無双された訳ではないが、甲府のこの攻撃の真の狙いが嵌った。
それは、2シャドーの39泉澤 仁と、18鳥海 芳樹のスピード・テクニック・アジリティに優れる小柄な選手と、2ボランチのスペシャルな左足を持つ16野津田 岳人と、視野の広いゲームメーカー26野澤 英之の存在である。アーリークロスの毀れ球を2シャドーが、アジリティを活かして、セカンドボールを回収後、ドリブル、パス、シュートという攻撃のあらゆる手段で、DFを搔乱す。
前節、京都の9ピーター・ウタカが、1人でしていた事だが、3人で行う事で、持続的な攻撃と、攻撃の安定感が生まれる。更に、ボランチの2選手が、クリアボールや2次攻撃の毀れ球、サードボールを拾う事で、3次攻撃を仕掛ける。16野津田 岳人は、ミドルシュートや展開力で、6野澤 英之は、サードボールで、バラバラになった岡山と甲府の選手のエアポケットを突くパスで、崩しにかかるといった狙いを持っている。
実際に観戦した後に、スタメン選手の基本ポジションを見ただけで、こういったサッカーがしたいという意図が見えてくる。実際に、先制点もアーリークロスではなく、ロングスローに近いスローインからではあるが、セカンドボールを拾った18鳥海 芳樹の仕掛けから得たFKをスペシャルな左足を持つ16野津田 岳人が決めた。
そして、基本スタイルを持つが、状況によっては、WBも上がるという形を見せた甲府。DFからの一本のロングパスを受けた右WBの23関口 正大が、深い位置からクロスを入れると、マイナスのボールは、16野津田 岳人の下へ、岡山の選手が寄せに行くが、ペナルティエリア内にいた39泉澤 仁がスルーパス受けると、GK31梅田 透吾の至近距離からのシュートを放ち、31梅田 透吾の手を弾いて、突き刺して、追加点。前節の京都の2失点目に似た形である。強いチームは、DFラインを突き破って、裏に通して来る。
甲府の3点目は、FKから。FKに甲府の選手が、直接合わせた訳では無いが、頭で繋いでボールを5井上 黎生人が、競った所で、甲府の選手の体が入っていたことで、バランスを崩して手が上がってしまってハンドとなってしまった。有馬 賢二監督は、甲府の選手のハンドではなく、「選手が下にいた」というアピールが聞こえたので、甲府の選手の競らなかった(ジャンプしなかった)選手のファールをアピールしていた。
甲府は、クロス、スローイン、FKといったゴール前に、どうボールを集めるかという狙いを持ったサッカーをしていた。セカンドボールやサードボールへの反応で、この試合の岡山は、後手を踏んでいた。いつもであれば、岡山が、回収して、攻撃に移る事が多かったが、この試合では、それが出来なかった事で、甲府の3点に繋がった。
甲府は、如何にリスクを小さく、ゴール前に速く運ぶかというサッカーに特化していた。セカンドボールを拾うという岡山のお株を奪うサッカーで、最終的に1失点こそしてしまったが、甲府側からすると、快勝という試合であった。10ウィリアン・リラが、スタメンで出場するようになって、リーグ戦では、11節から磐田にしか負けていない甲府。完成度の高さが、際立った。
「ヴァンフォーレ甲府のサッカー」
・ゴール前にリスクを小さく運ぶというバランスを意識。
・毀れ球を拾ってからの持続的な攻撃を意識。
・攻撃的なボランチで、高い得点力を実現。
・サッカーを体現するために適材適所の布陣。
3、 カモフラージュの岡山
岡山のサッカーは、戦力差を覆す事にある。今の岡山に一番足りないのは、エースである9李 勇載である事は間違いない。前節の京都の1人でも何でもできる9ピーター・ウタカと、今節のターゲットとして有効な10ウィリアン・リラ。戦術にも成り得るスペシャルな存在の有無は、勝敗を左右する。岡山の採用している4-4-2(4-2-3-1)という基本システムは、バランスに優れ、応用力がある。
有馬 賢二監督が、好んで採用するのは、その辺りにある。勝ち続けるには、チームとしての対応できるサッカーの幅が必要となって来る。4-4-2(4-2-3-1)で、対戦チームに応じて、スタイルを変えるのは、勝つための対策とチームの成長。この2つの両立を目指しているからである。前回のフォーカスでも触れたが、有馬 賢二監督は、先を見据えている。
では、この試合は、岡山が、前項で述べた甲府のサッカーに対して、どういった準備をした上で、どういったプランであったのかについて、フォーカスを当てて行く。まずは、甲府の両WBのバランス感覚に優れる両選手への展開と、DFラインから隙があれば、ロングパスを入れてくるという甲府の攻撃の始まりへの対策については、どうか。
・甲府のビルトアップへの対策
この試合の岡山は、20川本 梨誉と14上門 知樹の両選手が、DFラインに積極的に寄せて、ロングパスやアーリークロスといった攻撃を制限するという手段をとっていた。後ろからしっかり繋いで、前に運んで行くチームに対しては、20川本 梨誉と14上門 知樹が、中央に入れさせない事で、サイドに誘導してそこで、奪う事を狙いつつ、そのチームの攻撃の良さを消すサッカーと、自分達の持ち味を出すサッカーを展開したファンタジスタシステムという対抗策で、攻守一体の安定感を見せた試合もあったが、この試合では違う対策をしている。
前節の京都戦と、今節の甲府戦では、中央に無理に入れず、むしろ積極的にロングパスを入れてくるチームに対しては、待っていてもそこにパスは出てこないので、甲府のしたいサッカーを展開されてしまう。そこで、両FWは、前から献身的にプレスをかけていく事で、プレッシャーをかけて、良いボールを前線に配給させないという対策を行った。
また、岡山が、ボール奪取した時には、甲府のボランチは、攻撃に特色ある選手であるので、寄せに行った岡山の2選手の後の不規則なポジションに対して、岡山のボランチから良い縦パスを何度か通す事ができていた。更に、中央に10宮崎 幾笑も絡んで、縦パスを呼び込んで、3人が近くでプレーしようとする。これが、岡山のFWの基本方針である。10宮崎 幾笑のシュートというシーンも、その狙いの1つ。攻撃で、影が薄かった10宮崎 幾笑の存在感が試合を重ねる毎に増しているのは、ポジティブに考えたい。
ただ、積極的にDFラインに寄せに行くという事は、それだけ運動量が増えてしまう。20川本 梨誉の出場時間が増えて、守備の負担も増える中で、20川本 梨誉の存在感が、やや薄くなるのは、致し方ないところである。それでも、20川本 梨誉は若く、試合出場を続け、経験を積んで行く中で、心身共に伸びる事で、プレーが安定し、また、自信が漲っていたミドルシュートや、ボールキープといった持ち味が光るプレーは増えてくる事も期待できる。
しかし、甲府のビルトアップに対して、奪いきるためには、人数が足りず、あくまで、攻撃を遅らせる。ロングパスやアーリークロスを簡単に前線に入れさせない事が一番の目的という点に留まる。そして、この役割でフル出場した14上門 知樹を中心に、20川本 梨誉、2列目の41徳元 悠平や10宮崎 幾笑といった選手も参加し、状況に応じて、対応したが、消耗も当然大きかった。
・甲府の前線への素早く運ぶ速い展開への対策
さて、甲府の前線に入った後の岡山の守備は、どういった対策と準備、方針で対応したのか。4濱田 水輝で、跳ね返す、抑える。ではなく、セカンドボールを拾う事を主体に、拾った後にマイボールにする事で、対応する選択をした。これは、7白井 永地と6喜山 康平という守備の巧い両ボランチと、5井上 黎生人と、22安部 崇士といった機動力と運動量があって、足下の技術が安定している選手の特性を活かす選択である。
また、抑えておきたいポイントは、左から11宮崎 智彦と、22安部 崇士、5井上 黎生人、2廣木 雄磨の4選手は、どの選手も持ち上がるプレーができるという点にある。また、ビルトアップも利き足に合ったサイドで、プレーすれば、簡単にボールロストすることはない。よって、状況によっては、前に運ぶ。もしくは、不利な状況でも最低でもクリアする事で、ミスによる失点をしないという強みがある。
そして、この強みに、岡山のある意図に、左SHの41徳元 悠平が絡んでくる。5井上 黎生人は、攻撃参加もできるが、後方に控える事が多い。逆に22安部 崇士は、縦に運んで行くというプレーを既に何度も見せており、印象に残っている。これは、11宮崎 智彦の年齢やコンディションなどの関係による運動量の少なさをカバーするという狙いがある。
11宮崎 智彦が、サイドレーンを上がれない時に、41徳元 悠平が、前にいる事で、本来11宮崎 智彦がすべきプレーを、41徳元 悠平がこなす。また、22安部 崇士が、11宮崎 智彦が、持って上がれない時に、左のハーフスペースで、SBのように持ち上がる。更に、6喜山 康平や7白井 永地が、この色々な選手が、絡んだサイド攻撃に絡む事もある。
この22安部 崇士の持ち上がりを可能としているのが、5井上 黎生人の存在である。CBが1人上がるという事は、もう1人のCBの横や近くへのパスコースの選択肢が減る可能性が高い。そう考えると、4濱田 水輝のコンディションの問題もあるかもしれないが、もしかすると、甲府の毀れ球への反応の速さを警戒して、4濱田 水輝のスタメンを避けた可能性もあるかもしれない。
岡山のここまでのリーグ戦を見ていると、後でのビルトアップ時にミスよるショートカウンターでの失点を嫌っている傾向にある。DFラインの補強方針を見ていても、足下の巧い万能なCBを補強が、続いている。京都戦でも、綻び(致命的なミス)は、生じなかったので、このCBの強化方針(8田中 裕介、5井上 黎生人、22安部 崇士)は、形となっている事は間違いない。
この狙いは、甲府戦では、どうであったか。マイボールにした後に、落ち着かせるという狙いは、一定の効果はあった。しかし、腰を据えて、前に運ぶということまではできなかった。甲府の前線の3枚、時にはボランチ2枚、状況によっては、WBの選手が上がってくることで、岡山の毀れ球奪取率は、思ったように伸びず、自陣でプレーする時間帯が長くなってしまった。
攻撃は、最大の防御。これを、甲府に、リスク管理を徹底した上で行われた事で、岡山の跳ね返す力が高い4濱田 水輝の不在が、結果的には、響いてしまった。次節は、後半戦の最初になるが、新たな組み合わせを模索するのか。それともこの方針を続けて、中断期間で、新たな策を準備するのか。2戦連続の複数失点を受けて、どういった手を打つのかは、興味深い所である。
・岡山の勝利への策
大きくこの2点を持って、攻守の対策と準備とした岡山であったが、岡山の狙いとしては、基本的には、先制逃げ切りであり、失点しない事がベースにある。また、この試合では、0-0で、推移した上で、用意していた作戦がある。それは、リザーブメンバーと、後半途中からの戦い方を見ていると、よくわかる。
流石に3失点する事は、大誤算であったと思うが、41徳元 悠平の左SHと、2廣木 雄磨の右SBには、それぞれのポジションにおける攻撃上の欠点があるが、それを狙いによってカモフラージュしている。それは、守備を意識したものであり、状況に応じて、交代カードで、欠点であった選手から、そこが長所の選手に代える事で、試合を動かすプランであった。
まず、41徳元 悠平の左SHだが、クロスを入れる事と、14上門 知樹との連携プレーが狙いというのは、以前のフォーカスで触れたが、そこは変わりない。ただ、ここで起用されてきた14上門 知樹や27木村 太哉といった選手と比べて、1対1や複数人で、対応された時に、局面を打開できるドリブルで突破するというプレーは、大きく減った。
ただ、一方で、深く侵入しないので、守備のリスクは下がるが、相手チームの守備を乱せないので、ドリブル主体の攻撃と比べると、攻撃の破壊力というのは、どうしても見劣りしてしまう。また、2廣木 雄磨も安定したビルトアップや、運動量を活かしたオーバーラップが持ち味ではあるが、1対1で、突破するという仕掛けを苦手とするので、深く侵入してもフリーでなければ、攻撃の発展性に乏しい。
スペースを空けることやボールロストするリスクは下がるが、一方で、チームとしての得点力は、どうしても下がってしまう。これは、チームの攻撃面の総合力不足というのも関係している。0-0で推移して、その限られた攻撃の交代カードをきることで、勝負する筈であったが、残念ながら、思い描いていた状況で、そのプランは、使えなかった。
それは、ドリブラーである27木村 太哉と18齊藤 和樹のSHでの同時起用である。これは、点差さえ、開いていなければ、面白いプランであった。2点差、3点差とスコアの差が広がった事で、守勢に回った部分はあるかもしれないが、数えるほどしかなかったサイドからの仕掛けが、目に見えて増えた。
また、岡山には、諸刃の剣とも言える超攻撃的なSB(最近SHでの起用も増えた)16河野 諒祐というカードも残していた。彼の持ち味は、元FWらしい技術を活かした仕掛けとミスを恐れない積極的なクロス・ドリブル・パス・シュートにある。2廣木 雄磨であれば、深く侵入した時の攻撃のアクションが限られるが、16河野 諒祐は、瞬時に様々なアクションを起こせる選手である。
一方で、SBらしからぬ軽い守備というのが、弱点ではあるが、先述した11宮崎 智彦のように、チームの戦い方でカバーする事で、弱点をカモフラージュして、良さを前面に出し、巧く持ち味を発揮してきた。もちろん、隠しきれない事もあるが、飛びぬけた選手や総合力がJ2屈指の選手を多数要する事が難しい岡山にとって、こういった工夫は、必用不可欠である。
このサイドアタッカーを一気に投入する事で、岡山は、試合を動かすというプランは、結局、3点差開いた点差を1点返すという結果に終わったが、勝利の方程式である3バックで、4濱田 水輝に、積極的な守備のアクションをしてもらい、攻撃の起点を作らせないプランも考えていたと思うが、それも結果的に空振りに終わった。
・スタートから3バックの可能性への言及Part2
このように岡山は、我慢する時間と、勝負をする時間を作るという戦い方を、採用する傾向にある。この試合の甲府のようにスタートから、一糸乱れぬ一体感という戦い方は、まだできないが、4濱田 水輝を、CBでスタートから起用して、10ウィリアン・リラを封じて、下がった後に、戦い方を変えるという選択肢も考えることができた。
また、前節キックオフ時から3バックを採用するという選択肢もあるという主張もしたが、フル出場1試合しかない10ウィリアン・リラが下がったのを確認して、4バックに変更するという勝利の方程式の逆のパターンも面白いかもしれない。この辺り、チームとして、より得点する事は難しくなるが、前半での失点の可能性の下がる3バックで、強力なエースストライカーを抑えるというのも面白い選択肢と言える。
この辺り、有馬 賢二監督が、3バックを逃げ切りだけではなく、チームの基本戦術としてしてのオプションとして将来的に、採用する可能性があるのか。今季の昇格は、上位に連勝の後に、連敗した事で、現状維持=後退という結果を受けて、来季も有馬 賢二が、岡山の監督であると仮定して、後半戦を、どう戦って行くのか。夏場の補強を見て注目していきたい。
「ファジアーノ岡山のプラン」
・前から積極的に寄せていく事で、甲府の自由と時間を制限。
・甲府の速い攻撃の展開に対して、セカンドボール回収で対抗。
・勝負時まで我慢して、機を見てサイド攻撃で勝負。
・先制できれば、勝利の方程式3バックで逃げ切り。
4、 上位チームとの比較
今季の岡山は、面白い特徴があるチームである。先制に成功すると、7勝1敗。先制を許すと、9敗1分。そして、スコアレスドローが3回という両極端な結果となっている。これは、何を意味するのか。有馬 賢二監督が、就任当初の課題であった先制するが、追いつかれるという悪癖はほぼ克服に成功した。
一方で、先制された時に、同点や逆転に持っていくことが出来ていない。理由は色々とあるが、シンプルに結果を見た時に、これは、先制されたら勝てないのではなく、複数得点する攻撃の形ができていないと、捉えるべきである。仮に、全試合2得点できた場合は、どうか。15勝4分2敗。大きく勝ち越せている事から、守備自体は安定している。
また、毎試合1得点できていた場合はどうか。9勝6分6敗と、1点毎試合取れていれば、勝ち越せているという事が分かった。現段階で、1試合平均1得点以上決めているチームは、12チーム。1試合2得点以上決めているチームは存在しない。見方を変えて、30点以上のチームは、6チーム(内5チームは1~5位)。上位に食い込んでいくには、1試合平均1.5得点以上は必要であるのが、今季のJ2である。
個人にフォーカスを当てると、前半戦で二桁得点決めたのは、3選手。首位の磐田の11ルキアンと、2位の京都の9ピーター・ウタカ。意外にももう1選手は、9位の東京Vの19小池 純輝。そこに甲府の39泉澤 仁が、9得点。長崎の7エジカル・ジュニオールの8得点。次点で、33高木(新潟)、13清武(琉球)、7谷口(新潟)の7得点で、続いている。
以降は、下位チームの選手の名前も出てくる。上位陣でも多彩な得点パターンがあるチームもあるが、やはりエースの存在の有無は、順位に直結すると言っても過言ではない重要な要素と言える。そう考えると、岡山のエースと言える9李 勇載の不在で、健闘していると言えそうだ。
岡山も巻き返しに向けて、当たりに当たっている補強の次なる一手として、ストライカーの獲得に動いていても不思議ではない。可能であれば、クロスに対して、合わせるのが巧い選手であれば、チームに幅ができる。41徳元 悠平、11宮崎 智彦、16河野 諒祐、2廣木 雄磨、24下口 稚葉といった名前を見ても、クロスからのアシストに期待できる選手が多く、技巧派ストライカーは、20川本 梨誉が既にいる。
先制できる試合が増えれば、勝ち点も相対的に増えるだけの安定した守備と、勝利の方程式3バックのある岡山が、後半戦(五輪後)に巻き返せるかどうか最大の注目ポイントと言える。しかし、費用対効果で考えると、9李 勇載の復帰が最大の補強となる可能性があり、前置きでも触れたが、完全復帰する日が早く来てくれると信じている。
また、先行逃げ切りに関してだが、磐田と長崎は、先制したら勝率100%である。J2もレベルが高くなってきた中で、逆転を許さないチームが増えて来たと同時に、チーム間の戦力差が縮まった事で、スコアが動きづらいリーグになりつつあると感じる。逆を言えば、逆転できるチーム力を構築できれば、J1が近づくという事であり、そこも目指していきたい。
「上位チームの特徴」
・前半戦で、二桁得点できるストライカーの有無。
・平均得点1.5点以上の高い得点力と安定した守備。
・先制した試合が多く作る(先制逃げ切りが基本のため)。
・同点~逆転に持っていく得点力(上位でも逆転が少ない)。
5、 総括(後半戦に向けて)
前半戦最終節という事で、本格的にレビューに仕上げた。岡山は、やはり、如何に先制点を決めるか。これが、出来れば、勝ち点は、驚くべき程増えても不思議ではない。コンディションと試合感覚が研ぎ澄まされつつある6喜山 康平と11宮崎 智彦。少しずつだが、フィットしてきた10宮崎 幾笑。5井上 黎生人や7白井 永地といったフル出場を継続している選手の安定感も大きい。
徐々に怪我から戻って来る選手達。怪我人が多発した時期に、チームを支えた若い選手達。多くの選手が、今季の岡山で出場機会を掴み、チーム一丸となって戦って来た。特に、31梅田 透吾や20川本 梨誉の清水から武者修行に来た、両選手が、J1水準に迫るプレーの質には、驚かされた。
そういった驚きと、歓喜、失望、ホームでの不振と、色々とあった前半戦だが、エンジンのかかって来た岡山の得点源14上門 知樹、中盤において攻守で圧倒的な存在感をみせる6喜山 康平、チーム状況に合わせて守備の様々な役割をこなす5井上 黎生人、総合力の高いFGGK(Fantastic Great Goal Keeper)31梅田 透吾。
最後の上位との4連戦。4連勝も期待できる2連勝から始まったが、最終的には、実力差を感じる2連敗であった。この悔しさを糧に後半戦、来季に繋がるサッカーを展開していって欲しい。補強・復帰・復調・好調・覚醒などのワードをポジティブな意味で、聞ける後半戦になってくれると期待したい。
そのためにも、この甲府戦での最後の1得点を奪った諦めない姿勢を、1つでも多くの勝ち点を獲得する事で、活かして欲しい。勝敗や内容、結果、順位。変動や変化があったが、諦めない姿勢だけは、スコアが開いても不変であった。ここは、点差が開いても貫いて、大量失点で、敗れる試合を少なくして、開いても1点でも返す。これを続けて、アウェーの神戸戦のような同点劇、プレーオフでの松本戦のような勝利という名ゲームを、また見せて欲しい。
文章・図版=杉野 雅昭
text・plate=Masaaki Sugino
ここから先は
¥ 150
自分の感じた事を大事にしつつ、サッカーを中心に記事を投稿しています。今後とも、よろしくお願いいたします。
