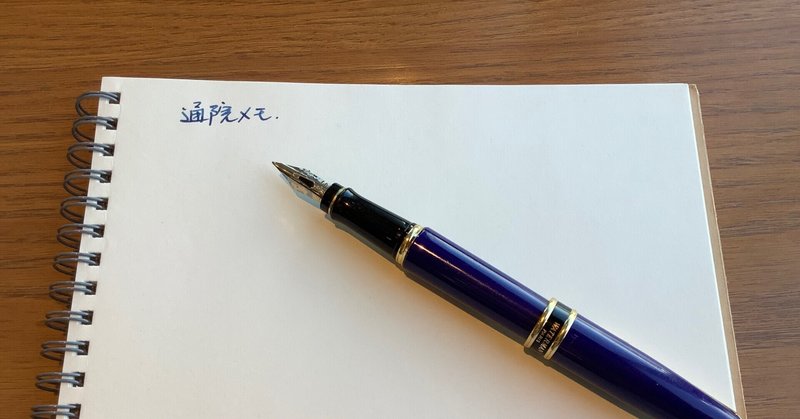
202111118 通院メモ 自分の中にあった劣等感について
自分の中のこれまでずっとあり続けたのが,「何でも自分でやってみたい」,「何でも知りたい」ということだった。
基本的に,これはADHDの特性と言えるところでもある。
ただし,頭の回転はそんなに早くない。
自分に合う人というのは,大概が自分と同じ価値観を持っていたり、自分の頭の回転能力が似たような人になる傾向があると思う。
おそらくその選別みたいなものが起こるのは、中学校から高等学校,高等学校から大学へと進学したときなど受験をきっかけに起こると思う。
中学校まで地域の公立学校に通っていると,それこそ能力の差がたくさんある,とても多様性がある環境に存在している。
そのために,平均付近にいる人にとってはとても居心地のいい環境である反面,何らかの能力が突出していたり,逆にすごく苦手なことを持っていたりする人間からすると,押し付けや我慢をとても強いられる環境であるように思う。
受験をすると,自分と似たような能力の人たちがその環境に集まるために,能力的な多様性は少し絞られる代わりに、お互いのことを理解しやすい状況になる。
そうすると,その環境で切磋琢磨して一生の友達だと感じる人間に出会うという可能性も高くなるのではないか。
まあ、この辺は最近接領域やらヴィゴツキーなどで検索してもらうと知ることが出来る。
話を戻して、なんでこんなことを書いているかというと、大学時代に同じ分野を研究している人たちの集まりがあって,自分のゼミの先生方が東大や京大出身で,その関係で東大や京大の学生さんもたくさんいた。
その人たちの議論を聞いていると,ものすごく頭の回転が速いのと,次への理論の展開がすごく速いのだ。
また、機会があって国のトップ官僚の人たちとお話をする機会があったのだけれど、まあとにかく理解が早く、飲み込みも早く、反応が早く、そして返しがすごく的確で、一つ言えば十のことをわかってもらえる感じがあった。
そういう人たちの中で話題になっている書籍などの情報に触れると、「この人たちと話をしようと思うならば、その本を読んでおかなければ」とすべき思考がすごく上がる。
もう、すごい劣等感が出てきた。
これが,良い方向へと回ることもあった。
新しいことに取り組もうとするエネルギーにもなっていた。
とにかく、先を走っている人に追いつきたかったし、追いつこうとしなければ話題にもついて行けない。
並ぶと言うことは無理だとしても、それでも先を走っている人から何かを吸収しようと思うのならば、頑張らないといけない。
そう考えていた。
おかげで、これまで仕事に関する専門書というものを読んだことが無かったので、視野が広がるきっかけになった。
しかし、そういう人たちはドンドン先へ進む。
自分は頭の回転がそれほど速くない。
本を1回読んだくらいでは、なかなか理解できないことも多く、そしてFacebookなどの話題にもついて行けない。
自分は置いてきぼり感が強くなる。
焦る。
仕事やら勉強やら、優先順位がゴチャゴチャになって、どれも回らなくなる。
睡眠時間を削ったり、休日に勉強会などでかけて、どんどん頭に詰め込もうとする。
オーバーワークになって、疲れて、さらに効率が悪くなる。
こんなことの積み重なりが、大きな疲労へとつながっていったのが、今だったらわかる。
とにかく、追いつきたかったのだ。
そうした自分になりたかった。
そして、これが躁が激しいときや、躁寄りの混合状態になると、人の批判へと向かうことにもつながっていた。
そして、躁から鬱へと落ちたとき、強烈に自責の念に駆られた。
そうしたところに気がつくことが出来た。
鬱から抜けた先週くらいから、そして知能検査の結果を聞いて自分の特性や障碍などについて受容できたからか、自分を責めるというところが無くなった。
自分を自分で慰めるでは無いけれど、自分で「よく頑張ったね」と言えそうな感じになった。
「そんなに苦しまずとも、自分なりの生き方があるはず。人を追いかけてもその人になる訳では無く、自分が生きやすい方法や工夫を積み重ねていくしか無い。自分は自分で有れば良い。」
こんな風に考えられる様になった。
これまた、さらに気持ちが楽になった。
自分に対する認知が変わった瞬間なのかもしれない。
健康を維持することが出来ていれば、活動できるときに自分が活動できる範囲で取り組み続けていけば良いんだというのが見えてきた。
劣等感の反動で、名を残す結果が欲しいと思っていたが、そんなことはどうでも良くなった。
やれることをやる。
それだけ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
