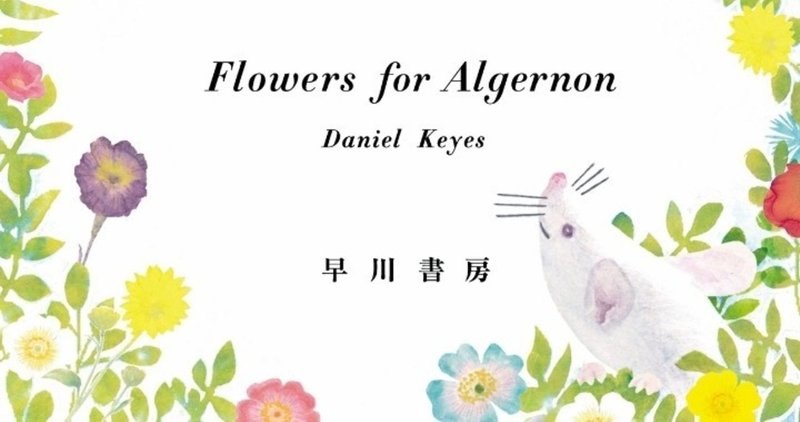
『アルジャーノンに花束を』から見る愛と親子関係について
僕の一番好きな小説であり、SFの傑作として名高い『アルジャーノンに花束を』を久しぶりに読んで色々思うところがあったので読書感想文的ななにかです。
ネタバレ普通にしますので、自分で読みたいって方は読んでからこちらどうぞ。
あらすじ
知らない人のために簡単なあらすじです。
本作の主人公チャールズ・ゴードン(チャーリイ)は32歳でありながら、知的障害を持っておりその知能は6歳程度しかない。
伯父の友人であるハーマンが営むパン屋で、簡単な雑用をすることで雇ってもらい、友人であり、パン屋の従業員仲間からの助けも得ながら生きてきた。
ある日のこと、チャーリィは知能を高める実験の人間として初めての被験者として選ばれることとなる。
賢くなりたいとずっと願っていたチャーリィはこの実験に参加し、そして実際に知能が高まっていく。
しかし、知能が高まるにつれて、かつての友人でありパン屋の従業員仲間が実は自分をバカにしていたことを知り、知的障害を負っていた頃には理解できなかった現実について戸惑いや怒りを感じ、
そして知的障害の頃に通っていた支援センターの先生であるアリス・キニアンへの恋慕の中で葛藤や困惑しながら人間として成長を遂げていく。
遂には、実験の実施者である大学の教授の知能を抜かし、知能の極地とも言える地点に達したときに同様の実験を先んじて受けていたネズミのアルジャーノンの奇怪な行動から、この実験の欠陥に気づくこととなる。
それは、実験によって上昇した知能はその上昇した速度に比例して低下するというものであった。
一度は知の極地とも言える地点に達していながら、今度はそれらを失っていく恐怖と喪失感を感じながら、チャーリィは最後に何を得るのか…?
チャーリィは何を得たのか
この本を初めて読んだときぼくは(恐らく高校生か大学1年生くらいだったと思うが)、愛する人であるアリスのことを忘れ、そして様々な知識など得たものをすべて失ったチャーリィの切なさを思い、バッドエンドであるとすら思った。
しかし、今読み返して思うのはこの話は確かに切なく悲しい話ではあるが、間違いなくハッピーエンドであるということだ。
なぜそう思うか。
それは「チャーリィが愛を手に入れたから」である。
愛とは何か
愛を手に入れたから幸せだと述べるのであれば、愛とはなにかについてを語る必要があると思います。
以下はエーリッヒ・フロムの『愛するということ』より引用
愛は能動的な活動であり、受動的な感情ではない。そのなかに「落ちる」ものではなく、「みずから踏みこむ」ものである。(中略)わかりやすい言い方で表現すれば、愛は何よりも与えることであり、もらうことではない
とある。
文字通りですけど、つまり愛とは「与えること」なんですね。
であるからして、フロムは愛するのは感情などではなく、訓練可能な技術であると論を展開するわけですけど、それは今回の本題とずれるので置いておきます。
気になる人は読んでみてください。
チャーリイに愛はなかったのか
手術を受ける前のチャーリイは優しい人物として描かれており、実際に後に恋人になるアリスにも、賢くなった後にかつての自分のことに触れながら激昂されるシーンがあります。
以前のあなたには何かがあった。よくわからないけど……温かさ、率直さ、思いやり、そのためにみんながあなたを好きになって、あなたをそばにおいておきたいという気になる、そんな何か。
実際、彼はパン屋の同僚が横領を働いているのを見つけたときも彼が仕事を追われるのを心配し、こっそりと止めるように言うシーンなどが象徴的に描かれています。
このように思いやりのあるかつてのチャーリイには愛がないのだろうか?
ぼくは彼には「愛はなかった」と思う。
なぜチャーリイに愛がなかったと言えるのか
手術前の彼の願いは「賢くなりたい」であったが、それは表面的なもので、彼の本当の願いは「愛されたい」というものでした。
知能が良くなる前はこんなことを言っているし…
お母さんわいつもぼくにかしこくなってもらいたがていたからぼくがかしこくなったところを見たらみんなきっとびくりするだろう。ぼくの頭がよくなったのを見たらもうぼくを追ぱらたりわしないだろう。
そして知能が上昇したあとははっきりとその事を自覚します。
利口になりたいという私の異常なモティベーションは人々をまず驚かすのだがそれが何から発しているかということがようやくわかったと思う。それはローズ・ゴードン(母)が日夜願いつづけていたことなのだ。(中略)私は、彼女が望んでいるような利口な子になりたいという気持を持ちつづけていた、そうすれば彼女は私を愛してくれるからだ。
つまり、チャーリイは自分の中の満たされていない感情を満たすこと、「与えてもらう」に必死で、
「与える」という愛の真髄には決してたどり着いていなかったわけです。
愛するためにはまず満たされる必要がある
愛する為には何が必要か。フロムはこう述べています。
愛に関していえば、重要なのは自分自身の愛にたいする信念である。つまり、自分の愛は信頼に値するものであり、他人のなかに愛を生むことができる、と「信じる」ことである。
「自分の愛は信頼に値する」とはどういうことかと言えば、自分の愛が未来になっても変わることがないと根拠のある信念を持つことだとしています。
そして自分の愛が変わらないということを信じるためには、自分の中にある芯が
境遇がどんなに変わろうとも、また意見や感情が多少変わろうとも、その芯は生涯を通じて消えることなく、変わることもない
と信じることが必要だとしています。
簡単に言えば「私は私」だと感じられる。ということであり、これはつまり「自己肯定感」だと言えると思います。
自己肯定感がない人は本当の意味で他人を愛することができないというのがフロムの話からも読み取れるんじゃないかなと思います。
かんたんなたとえ話をするなら、
水の中で溺れまいともがいている人は、他の溺れている人にロープを投げて助けることはできない、みたいなイメージですかね。
溺れている人を助けるのなら、まずはしっかりと地面に立って安全なところからロープを投げてあげなければなりません。
溺れている人同士で捕まっていてもいずれは疲れて二人とも沈んでしまうのがオチです。
自己肯定感は親によって育まれる
チャーリイは知的障害があることで、母から酷い仕打ちを受けます。
母親は他の子と同じように賢くなると信じ、勉強を教えこもうとします。
その証拠に彼女はチャーリイが通常学級ではやっていけないことを先生から告げられた時に過剰な反応を示します。
「この子は正常よ! 正常です! 他の子供たちのように成長するはずです。他の子よりりっぱに」母さんは先生をひっかこうとするが父さんがひきとめる。「この子はきっと大学へ行くようになる。いまに大物になる」
そして始終父親と母親(ローズ)は口論を繰り返すようになります。
「おねがいだ、ローズ。この子をほっておいてくれ。この子をおびえさせているのがわからないのか。しじゅうこんなことをやっていたんじゃあ、かわいそうに、この子は――」
「じゃあ、どうしてあたしを助けてくれないの? あたしはみんなひとりでしなくちゃならない。毎日、この子に教えこんで――他の子に追いつくようにしてやらなくちゃならない。この子はのみこみがおそいだけ、それだけのことよ。他の子と同じように、勉強すればできるのよ」
「あんたは、自分を欺いているんだよ、ローズ。それは、自分やおれに対しても、この子に対しても卑怯だよ。この子が正常だとあんたは思いこもうとしている。まるで動物に芸を仕こむみたいにこの子を追いつめている。どうしてほうっておかないんだ?」
「他の子のようになってもらいたいからよ」
あるがままの自分を愛してもらうことができず、そして自分の存在が不和を生んでいるということは幼いチャーリイにとって非常に辛かったことだと思います。
このときにチャーリイが親から受け取るメッセージは至極単純で、
「賢くないお前はダメで存在してはいけない」
であったことは想像に難くありません。
実際に、妹が成長し年頃になったときに家を追い出されてしまうのですからあらゆる意味でそのメッセージを浴び続けたチャーリイは本当にかわいそうです。
チャーリイは愛する心を手に入れたのか
冒頭部で、この話はチャーリイが愛する心を手に入れたからハッピーエンドだとしました。
なぜそう言えるのか。
知能が失われる前に、恋人であるアリスと遂に結ばれるシーンがある(精神的な問題でそれまで行為に及ぶことができなかった)のですが、ここで彼は愛とは何かを理解したと考えます。
私は自分の肉体以上のもので彼女を愛した。愛の神秘をわかったようなふりはすまい、でも今のこれはセックスと言っては言いたりない、女の肉体を使うと言うだけではたりない。地上をはなれ、恐怖の、苦悩の外へただよい、自分自身より大きななにかの一部になることだった。(中略)そして私の肉体は宇宙の広大な海に呑みこまれ、不思議な洗礼をほどこされる。私の肉体は、与えることによって震え、彼女の体はそれを受け入れて震えた
ここではっきりと彼は与えることの愛を知ります。
そして、知能の低下が進みあらゆるものが失われ、アリスのことも忘れてしまうことで、愛する心を失ってしまったかのように思われますが、最後の締めでこうなるわけです。
ついしん。どおかニーマーきょーじゅにつたいてくださいひとが先生のことをわらてもそんなにおこりんぼにならないよおに、そーすれば先生にわもっとたくさん友だちができるから。ひとにわらわせておけば友だちをつくるのはかんたんです。ぼくわこれから行くところで友だちをいっぱいつくるつもりです。
ついしん。どーかついでがあったらうらにわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてやてください。
周囲からの反応を気にするのではなく、与えるのだと。
彼が言いたかったことはこういうことなんだと思います。
ここから、我々は、すべてを失ったかのように見えても彼の中になにかあたたかいものがあることを感じて、感動する訳です。
それはかつてはなかった彼の愛する心なのだと思います。
なぜ彼は愛する心を手に入れることができたのか
それは「愛されていたと実感することができた」からです。
知能が低下することがわかって、チャーリイは両親に会いに行くことを決意します。
はっきり言ってこの両親は毒親なのですが、愛されていたと知るために彼は行動を起こします。
まず彼が会いに行ったのは父親のもとでした。
父親は母が厳しすぎるしつけを行ったときに、たしなめてくれる存在であり愛してくれていたかを確かめるのに勇気を出しやすかったのだと思います。
彼との対面を考えただけで興奮した。彼の思い出は温かなものだ。マットはあるがままの私を喜んで受け入れてくれた。ノーマ誕生前――口論が金銭のことでもなく、隣り近所の外聞のことでもないときは、私のことだったころ――よその子供がやることを無理強いしたりしないで、この子はほっておいてやれと彼は言うのだった。そしてノーマ誕生後――他の子とはちがうが、この子自身の生活というものがあるはずだと言うのであった。いつも私をかばってくれた。彼の顔に浮かぶ表情を見るのが待ち遠しい。
しかし実際に会いに行くと、父親は成長したチャーリイと言葉を交わし髪を切っても結局自分の息子であると気づくことすらできませんでした。
私は立ちあがりながら、彼が気づくのを待ちかまえた。彼は眉をよせた。「なんのことかな? 冗談で?」 冗談ではないと私は言った、よく私を見て一生懸命考えれば、私がわかるだろうと。彼は肩をすくめ、櫛と鋏をしまうためにむこうをむいた。「あてっこなんかしている暇はないですよ。店を閉めないとね。三ドル五十セントいただきます」
愛してくれていたはずの父親はなぜチャーリイに気づけなかったのか。
これは単純に「実際には父親はチャーリイのことを愛していなかったから」です。
なぜそう言えるか。
チャーリイが母からお仕置きを受ける記憶を呼び覚ますシーンでこんな描写がでてきます。
彼女がおしおきをはじめると、マット・ゴードンは背中を向けて家から出ていってしまった
また、妹のノーマと喧嘩したあとチャーリイが漏らしてしまうという思い出の中でも父親の反応は異常です。
マットはすわったまま膝の上の新聞を凝視する。チャーリイは、ヒステリーの発作と金切り声に怯え、椅子にちぢこまり、すすり泣く。なにか悪いことをしたのかな? そしてズボンの中が濡れて、水滴が足を流れていくのを感じながら、母が戻ってきたら必ずされることになっているおしおきをじっと待っている。
ここから見えてくる父親の姿は、面倒を回避しようとするもので、チャーリイを愛し積極的に世話をしてくれていたというわけではないのです。
母親との接触で愛されていたことを確信した
チャーリイが知的障害を持っていることがわかる前、そしてそれが発覚したあとのしばらくはチャーリイのことをなんとかしてあげようとする母親の姿が頻繁に描かれます。
多くは厳しいしつけとして描かれますが、こんなシーンも思い出すのが印象的です。
そしてまたあるときは、あたたかな風呂のような優しい愛撫があり、私の髪や額をなでる手があり、私の幼年時代の大聖堂の天井に刻まれる言葉があるのだった。
この子はよその子と同じよ。
この子はいい子よ。
彼と母親との思い出は常に、寂しいものではなく、こうしたあたたかいものがあることを思い出します。
一方でこの「この子はよその子と同じ」という言葉をチャーリイは知能の面で劣る自分のありのままを否定する言葉として捉えているというのがポイントだと思います。
そして実際に母親に会いに行くことを決意し、かつての家へ足を運んだチャーリイを見た母親は一目で自分の息子について気づくのでした。
「なにか用ですか?」嗄れたその声は、記憶の回廊に響きわたるまぎれもない木霊だった。 口を開いたが言葉が出てこない。たしかに口は動いている、私は懸命に彼女に話しかけよう、言葉を吐きだそうとした、なぜならばまさにその瞬間、彼女の眼が気づいた気配を見せたからだ。(中略) はじめは、ほんとうに私がわかったのかどうか自信がなかったが、そのとき彼女は息を呑み、「チャーリイ……」と言った。叫んだのでも呟いたのでもない。まるで夢からさめたようにそう吐きだしたのだ。
そして遂に母親と言葉を交わすことになります。
母親は認知症になってしまっており、夢うつつのような状態ですがチャーリイが息子について(つまり自分のこと)を訊ねた時に母親はチャーリイについてこう語ります。
「男の子が一人いたの。とっても利口で、よその母親がそりゃうらやんだものよ。ところが、あいつらがあの子に悪魔の呪いをかけた(後略)
その後母親は一時的に正気を取り戻し、今のチャーリィとの再開を喜び、そして喜んでくれた母親を見てチャーリィは積年の「母に喜んでほしい」という思いを果たせたと、あらゆる苦悩は洗い流されたと感じるシーンへと続きます。
この母親が正気を取り戻してからのシーンも感動的ではあるのですが、僕はおそらく、正気を取り戻す前のこの母親の言葉こそがチャーリィの心を癒したのではないかと思うのです。
知的障害というのは呪いのようなもので、母親にとってチャーリィは本当に大切な「特別な」存在だったということがチャーリィをずっと苦しめていた愛されることへの欲求を満たしたんじゃないかと思うのです。
だからこそ、こうして愛されていたことを確信したチャーリィは母親に喜んでもらうこと、与えることの愛を知ることができたのではないでしょうか?
さいごに
最近知名度を得てきた毒親というワードですが、まさしくチャーリィの両親は毒親と呼ぶに相応しい親に違いありません。
しかし、チャーリィを救ったのは、またこの毒親の愛情であったと言えると思います。
子を持つ親の皆様、そしてこれから親になる皆様にはどうか子どものありのままを愛し、慈しみ、沢山触れ合って育ててあげてほしいなと思うのです。
これを持って、読書感想文はおわり。
現在モロッコにあるアフリカ唯一のラーメン屋さんruly's ramenを引き継いで
ラーメン&日本食料理屋のオープンを準備中です!
準備の様子や普段のこと、考えていることを載せているので気になる方は是非下記のアカウントもチェックしてみてください!
【SNSアカウント】
インスタグラム
https://www.instagram.com/ramen_maroc/
https://twitter.com/ShunyaSuzuki44
サポートをいただけたら当分の間はモロッコでの運営資金にさせていただければと思います! ある程度うまく回り始めたら皆さんに還元できるような企画を実施したいです!
