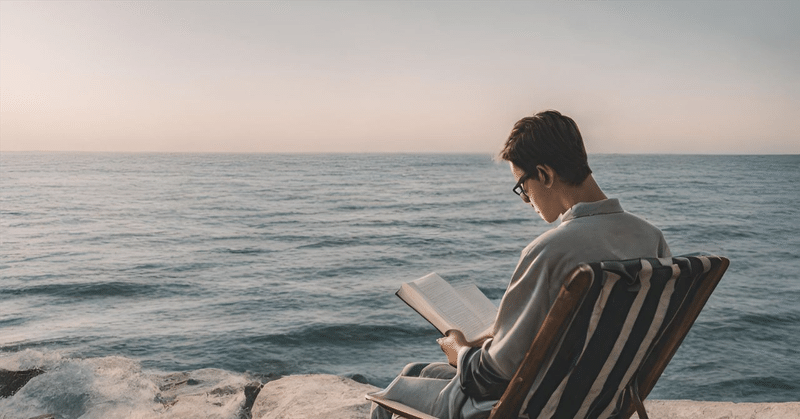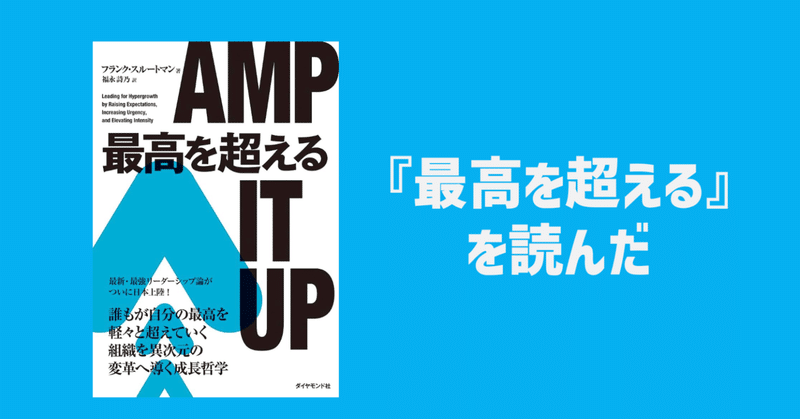仕事をする中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねたいと思っています。現在CMO(Chief Marketing Officer)として働いているのでマーケティングに関する…
- 運営しているクリエイター
#読書感想文
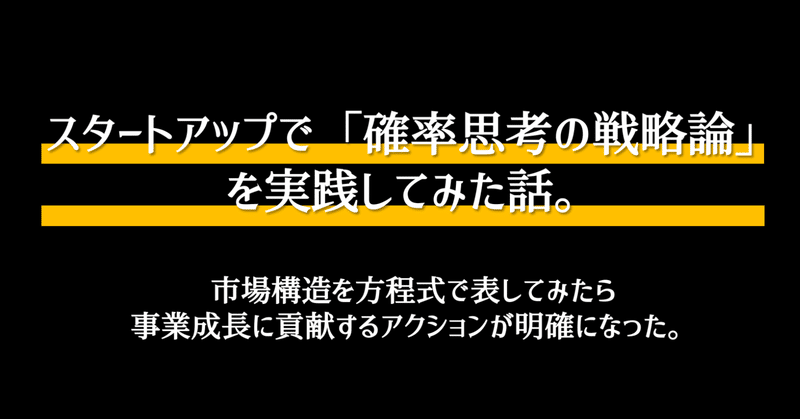
スタートアップで「確率思考の戦略論」を実践してみた話。市場構造を方程式で表してみたら事業成長に貢献するアクションが明確になった。
このnoteは「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021」の21日目の投稿になります。 記事にもし参考になる部分がありましたら、ぜひハッシュタグ「#アプリマーケアドベント 」を付けてシェアをお願いします!🎉 自己紹介株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川と申します。広告代理店出身で、デジタル領域とマス広告領域の両方を経験した後に、3社の事業会社を経験してきています。 タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。 課題|市