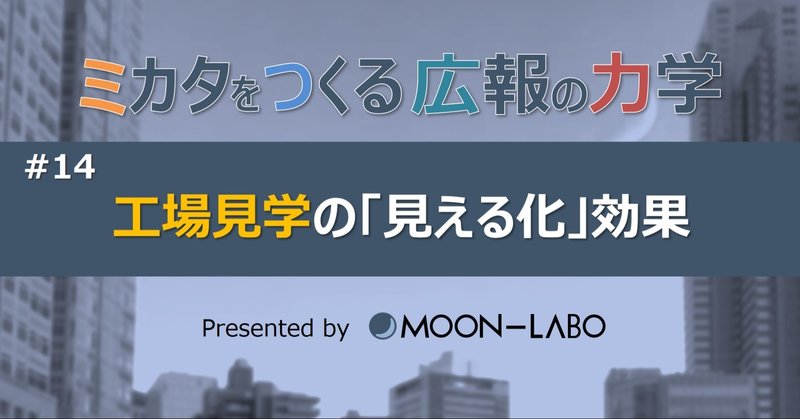
【ミカタをつくる広報の力学】 #14 工場見学の「見える化」効果
今回は工場見学、つまり生産部門に関わる広報の話です。
工場見学はCSR施策としてはお馴染みのイベントなので、製造業では実施経験のある人も多いかと思います。
普段あまり表に出ない生産部門の「見える化」について書いていきます。
※初めての方は、「#00 イントロダクション」をお読みいただくと、コンセプトがわかりやすいかと思います。
工場見学のPR効果
かつては取引先による視察や小学校の社会科見学で行われていた工場見学ですが、最近はすっかりエンタメ化してテーマパークのような扱いに。
特にコンビニやスーパーでよく見かける食品や飲料のブランドになると、
ファミリーにも人気のレジャーとしてエントリーするほどです。
テーマパークやミュージアムのように展示形式で作られている施設は別ですが、元々の工場見学は、工場での生産工程や衛生管理などを開示する「ディスクロージャー」のようなものだったので、信頼性の担保やガバナンスの表明という機能を持っていることは言うまでもありません。
ファンマーケティングをベースに考えた近頃の市場戦略において、特に製造業のPR活動では、より深いコミュニケーションでファンを獲得できる強い武器だと言えるでしょう。
ですが、工場の側から見ると、状況は少し違ってきます。
見られている効果
広報の立場からすると「見せている」なのですが、工場で働いている人の立場からすると「見られている」になりそうです。
確かに、見られていたら落ち着いて仕事ができない、ということもあるかもしれません。
ちなみに、私のいた会社の職人さんは、「しょっちゅうは困るけど、たまにならいいよ。見たいなら見せてあげる」と言っていました。管理職の立場になるともう少し意見が違って、「たまに見学に来てもらうと、現場が引き締まる」のだとか。
立場によって言い方はそれぞれですが、「たまになら、良い緊張感がある」という意見は共通のようです。
良く出来た工場になると、見学されているのが気にならないくらい、見学通路と作業場を隔てているものがあります。
もちろんセキュリティの管理も必要なので、社外秘の部分が見えないよう配慮もされています。
出来るだけ作業の邪魔にならないように、なおかつ、見学者には存分に楽しんでもらえるよう工夫をするのが、広報の腕の見せ所ということになるかもしれません。
「見える化」は双方向
工場見学の「見える化」は、工場の側に限った話ではありません。
実は、工場見学の「見える化」は双方向なんです。
つまり、工場からも見学者が見えている、ということ。
当たり前のことなんですが、これが結構な影響力を持っています。
開発部門のときに書いたと思いますが、バックヤードで仕事をしている人には、お客さんの反応が見えにくいからです。
私のいた会社でも、品質が低下して得意先からクレームの入った商品がありましたが、工場にはその声が届かない。品質が落ちて怒られたということを話しても、いまいち実感を伴わないわけです。
ところが、その得意先に工場見学に来てもらっただけで、品質は向上しました。
クレームの主が作業を見に来て緊張したのもあるかもしれませんが、重要なのは、工場を見たお客さんが、とても興味を抱いて、生産部門と直接コミュニケーションをとったこと。
つまり、両者の間に信頼関係が生まれたということなのだと思っています。
工場にとって何よりも影響力があるのは「お客さんの顔が見えること」かもしれません。
そう考えると、お客さんと工場が双方向でコミュニケーションできる場をつくることこそ、工場見学の意義であり、広報の役割と言えるのではないでしょうか。
おわりに
今回は工場見学というテーマで製造業をメインに書きましたが、バックヤードとお客さんのコミュニケーションという意味では他の業種・業態でもありうる話です。
製造業、サービス業、B2B、B2Cを問わず、ファンをつくる活動にもなると思いますので、様々な効果を期待できるのではないでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
共感してもらえましたら、スキやフォローをいただけると励みになります。
ではまた次回お会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
