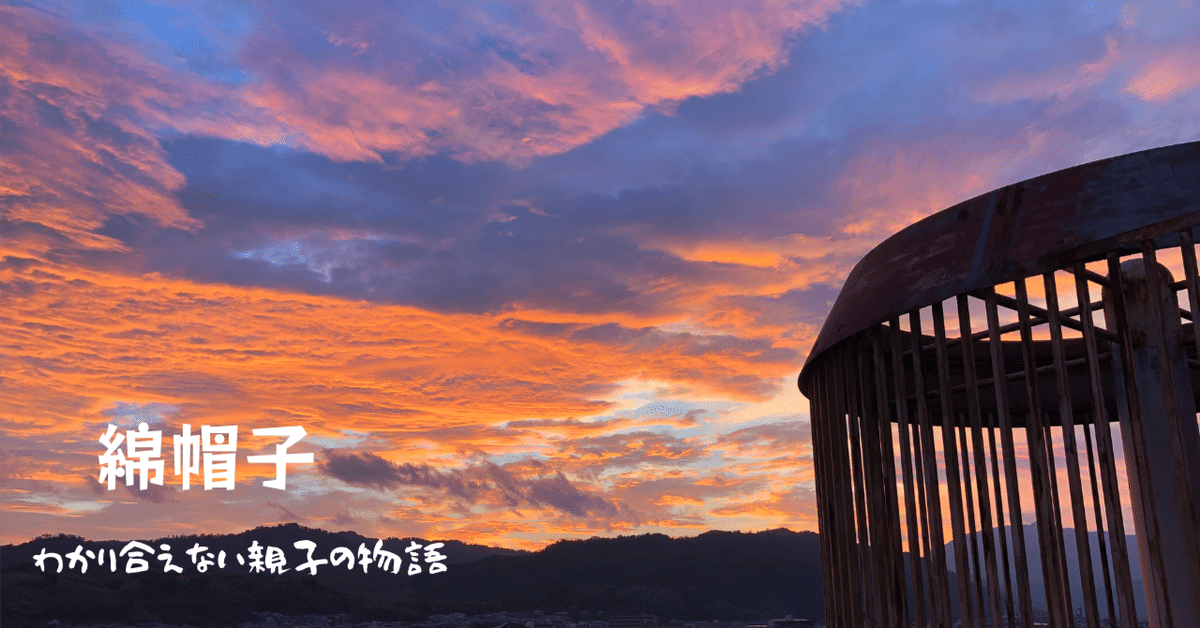
綿帽子 第四十一話
春は瞬く間に過ぎ行き、多分近々夏が到来するであろうまだ四月後半。
継続している朝の散歩はとっくに済ませてから、一旦帰宅した。
町人達の挨拶は相変わらず続いているけれど、それをお袋に伝えたところで、軽くいなされるのは目に見えている。
時々、ちょっとは耳を傾けてほしいと思いはするのだが、真剣に話を聞いてくれたことはないのだ。
だからそれに関してはもう諦めた。
それでも早く体を、いや、全てを治したい俺は午前中のうちにもう一度と家を出た。
お袋には昼食までには帰って来いと言われているので、それまででもと思い歩く。
とはいえ散歩コースもネタが尽きているので朝通った道を再び行くことにした。
あれ以来蛇にも出会っていない。
蛇のシーズンはどうやら過ぎ去ったようだ。
本当は白い蛇を見るまでに一度毒蛇を見たのだが、お袋が蛇の上を跨ぐという離れ技をやってのけたので、数に加えるのはやめにした。
ヤマカガシだった。
今まで通ったことのない道で、進めば進むほど何故だか嫌な予感がした。
雰囲気も悪く、引き返そうと声を掛けたが先を進むお袋は俺の言うことを聞こうとはしない。
仕方なく歩いていると、道の中央に無数の真っ黒な虫がウジャウジャと一箇所に集まっている場所を発見した。
俺はお袋に道の端の方を歩くように促した。
なんだかホラー映画のワンシーンを見ているようで気持ちが悪かったからだ。
しかし、その横にまさかヤマカガシが潜んでいるとは思わなかった。
虫だかりが保護色の様になって分からなかったのだ。
慌ててヤマカガシがいるから避けろと伝えたが、頑固なお袋はうるさいと言って耳を貸さない。
「ヤマカガシや避けろ!」
俺は怒鳴った。
「うるさいて、なんや」
お袋はそう言いながら一瞬振り返り、後ろ向きのまま歩き続けた。
そして、寸前のところでヤマカガシを跨ぐという離れ技をやってのけたのだった。
本人は跨いだことすら気づいてはいない。
「お前と歩くとほんまに疲れるわ」
とそれだけ言い放つと、またくるりと反転して歩いてゆく。
「俺の方がどっと疲れたわ」
心の声が滲み出て空気となって辺りに漂ってゆく。
兎はあれから遠くを走っている姿を一度見かけたけれど、あれ程の衝撃的な出会いはもうない。
まあ、人間よりも動物との出会いがある年と思えば良いか、もしくは人間の前に動物との出会いから始まったのか。
そんな考えても仕方がないようなことを自問自答しながら歩いていた。
そして、牧場跡地の手前まで来た頃である。
ふと空を見上げると、二羽のカラスが激しく鳴きながらクルクルと上空を旋回している。
不思議に思いながらそのまま歩いていると、道の中央に何やら黒い物体が落ちている。
視力が極端に落ちているので、それが何なのか、直ぐには確認できなかった。
目を凝らしながら近づいてみると、黒い物体は子供のカラスで、どこからか分からないが血を流している。
グッタリとしているが、僅かに動いてはいる。
なるほど、良く見ると足が一本折れて歩けなくなっているようだ。
車に引っ掛けられて、そのまま動けなくなったんだな。
そして、上空を旋回しているカラス達は親か、親じゃなくとも仲間かな。
さて、どうしたものか。
「最近こんなこと多いな、放っておくと今度こそ車に確実に轢かれる。
しかも道の中央だ、車がまた通るのも時間の問題だな」
そんなことを考えていると、先ほどまでかなり上空を旋回していたカラス達が、今度は俺の頭の上で激しく鳴きながら旋回しだした。
「え、お前達、俺?」
相手はカラスなので話せはしないのだが、なんとなくカラス達が伝えたいことは俺には伝わった。
助けろと言っているのだろう。
「うーん、困った」
助けろと言われても良いアイデアが直ぐに思いつく筈もなく、かといってこのまま放置しておけば、確実にこの子ガラスは車に轢かれて死ぬだろう。
だからといって一体どうすれば良いのか?
本当に時間はない、車が通れば確実にそれで終わる。
俺は考えた。
確か、親父に一度聞いたことがある。
動物の死骸が道端にある時、それは一体どうやってその場所から消えてなくなるのかと。
その時親父は、「心ある人が片付けてくれるんだろう」と言っていた。
なるほど、それは確かにそうかもしれない。
そういうケースもあるのだろう、親父らしい答えだと思う。
「だけど参考にはならないな」
流石親父、いいこと言ってた。
でもこのカラスはまだ死んでない。
しかも、生きてて頭の上で親ガラス達が早く早くとクルクル回ってるよ。
俺は親父の言葉をヒントに頭の中で連想を繰り返した。
多分、道路に動物の死骸がある場合は、心ある人というよりも行政機関の関連で何かある。
この場合死骸ではないけれど、動物を保護する機関はあるのだから、保護してもらえばいんじゃない?
連想する必要のないくらいのシンプルかつ無理矢理な回答。
俺は直ぐに役所に電話して事情を説明した。
すると、役所の中でそういったケースに対応して動物を保護する部署があると言う。
「少々お待ちください、担当の部署に確認を取りますので」
「はい、分かりました」
受話器の向こうでなにやら話し声がする。
しばらく待たされた後、その場所に居てくれないと見落とす可能性があるので待っていてもらえないかと返事がきた。
そして、捕獲するのに道具が必要なのでちょっとだけ時間をくれと言っている。
「え?」
「昼までに帰らなきゃならないのに、困ったな」
「だけど俺がこの場を離れたら来てくれても直ぐに場所は分からないか」
仕方ない。
俺は「待っています」とだけ伝えて電話を切った。
それから20分が経過したが、一向に待ち人が来る気配はない。
まずい、本当に車が通るかも。
ここは昼頃になるとかなり飛ばした車が通るのだ。
カラス達には、直ぐ助けが来ると伝えはしたが、まだ頭の上でクルクルと旋回している。
伝わっている気はしないが、仕方ない。
困ったな、本当に困った。
できることは全てやった。
他にできることと言えば、子ガラスを車が来ても轢かれる心配のないように安全な場所に移動させること?
でも、一体どうやって?
来てくれる人でさえ捕獲用の網と籠を持ってくると言っているのに。
「うーん」
俺は悩んだ。
悩んで、悩んで、そして、悩んだ末に思いついたことはただ一つ。
「掴むか」
そう、この場合掴んで運ぶしかない。
ただし、感染症を患ったばかりで免疫力も低下している。
子ガラスは足からダラダラと出血しているし、体にも虫は居るだろう。
これを掴まなきゃならないのか。
こいつはどうしたものかと、考えた。
考えたけど何もしなければ埒があかないのだ。
俺は意を決して子ガラスを掴むことにした。
そっと近づいて子ガラスの方に両手を差し出す。
そして、掴もうとしたその瞬間子ガラスが動いた。
「え?おいおい、動いたら掴めないだろう。お前足千切れそうだぞ、動くなって」
もう一度手を伸ばす。
やっぱりダメだ。
そこはやはり自然界の生き物、防衛本能が働くのだろう。
手を伸ばす度に子ガラスは動き、結局道の中央からはズルズルと抜け出すことには成功した。
ただし、あまりにしつこく手を伸ばしたせいか、子ガラスは右に道を横切って牧場跡の地面にたどり着くと、その場で力尽きた。
全く動く様子はない。
「まずいな〜」
頭の上のカラス達はより一層激しく鳴いているし「分かった分かった、とにかく落ち着け。直ぐに役所の人が来て獣医さんに連れて行ってくれるから」
と、とりあえず伝えてはみた。
足元の子ガラスを見つめながら、周囲に注意を払う。
すると、何やら車が近づいてくる音がする。
俺は、道路に向かって歩き出した、どちらから来るか分からないので道路に出て見張ることにしたのだ。
すると、思った方向とは反対側の少し離れた所に車が止まっている。
近づいて行って声を掛けた。
「役所の方ですか」
「そうです、電話下さった方ですね」
「はい、まだ生きていますがかなり弱っていて早めに連れて行かないと死んでしまうかもしれません」
「分かりました、そのカラスどちらにいますかね」
「こちらです」
役所の人はトランクを開け、中から捕獲用の網と籠を取り出した。
「あの、こういったケースで電話をかける人って他にも居たりするんですか」
「2〜3年に一度くらいはあったりしますね」
「2〜3年に一度ですか」
やっぱりレアなケースなのか。
「この後、獣医さんに連れて行ってもらえますよね」
「あ、それは大丈夫です。捕まえたらそのまま連れて行きますので安心して下さい」
良かった、とりあえず一安心だ。
「あ、此処ですね」
「すみませんが、逃げないようにそちら側に回ってもらええますか?多分これなら大丈夫だと思いますが」
「はい、分かりました」
俺は網を被せる反対側に回り、子ガラスの逃走に備えた。
「じゃ、行きますよ」
と言うと、役所の人は一気に子ガラスの頭上から網をかぶせた。
「お!」
網を被せられた子ガラスは思いの外動きを見せず、あっさりと網の中に収まった。
「あー、やはり弱っているようですね。ちょっと押さえていて下さい、籠を開けますから」
俺は子ガラスが動かないように網の縁を足で踏んで固定した。
「では、入れます」
役所の人が網の端に籠の入り口を当てて、包みこむように子ガラスを籠に押し込む。
あっさりと籠の中に入った。
かなり弱っているみたいだ。
「車に引っ掛けられたんですかね。獣医さんに連れて行ってレントゲンやら色々と調べてもらいますね」
「後のことはもう大丈夫ですから、有り難うございました」
「いえいえ、こちらこそ有難う御座います、それではよろしくお願いします」
「はい、それでは失礼します」
役所の人は子ガラスの入った籠を車の後部座席に乗せると、そのままあっという間に走り去った。
「ふー、これでようやく家に帰れる」
ところで、頭の上にいたカラス達だが、子ガラスが牧場跡地に入ってからも、しばらくはまだ頭の上で旋回していた。
それが、役所の人が到着すると、少し離れた高い位置での旋回に変わり、網をかけて捕獲すると、近くの木の上に止まってこちらを眺めだした。
相変わらず激しくは鳴いていたのだが、車に乗せて走り出すのを見届けると鳴き声も収まり、やがて何処かへと飛び去って行った。
「カラス頭いいな〜」
納得の行動だった。
カラスが頭が良いのは知っていたが、どうやら俺はカラスに選ばれた人間だったらしい。
言い方を変えると、たまたま運悪くその場を通ってしまったと言うことだ。
俺は苦笑いを浮かべながらも、カラスの行動に感心した。
カラスだってその場に消え入りそうな命があれば、あらん限りの知恵を絞って行動に出るのだ。
そこにはきっと、助けたいという思いが全力で詰まっているのだ。
俺は携帯を手に取ると家に電話をかけた。
「もしもし」
お袋が電話に出た。
「お前か、何してんねん。昼とっくに回ってるやろ」
「いや、カラスがな」
「カラス?またアホなこと言うてんのかいな。早よ帰って来い、昼いらんのか」
「いや、だからカラスがな」
「カラスなんてどうでもええ、アホが。早よ帰って来い、そんなもんどうでもええ」
ダメだこりゃ。
「分かった、今から帰るわ」
「ああ、早よ帰ってき」
俺は電話を切ると、後ろを振り返った。
遠くの木の上で二羽のカラスが並んでこちらを見ている。
俺はカラスに向かって軽く手を振り、それから中指ではなく親指を立ててカラスにサインを送った。
「これで大丈夫だぜ」
カラスがその意味を分かったかどうかは分からないが、俺は再び前を向いて歩き出した。
第四十話はこちら
↓↓
私の記事をここまでご覧くださりありがとう御座います。いただいたサポートはクリエイター活動の源として有意義に使わさせていただきます。大感謝です!!
