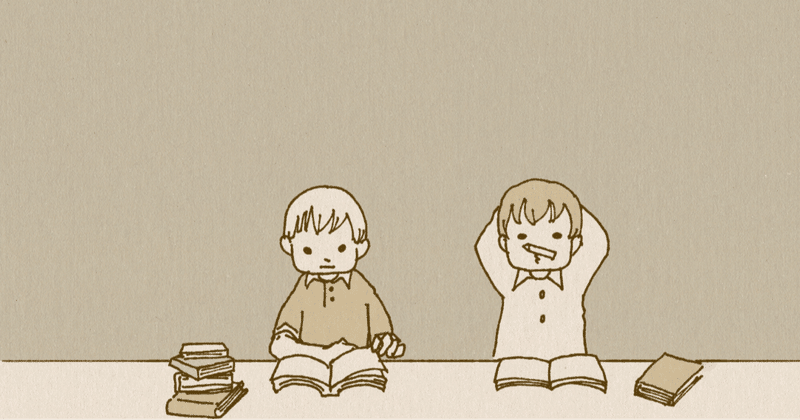
近頃の子供たちについて
「近頃の子供たち」
これは、いつの時代にも先輩世代によって口にされてきた言葉なのだろう。
大きな石をひっくり返すとそこに無数の蟻たちが、密かに、気づかれることもなく彼ら独自の社会を形成している有様を見ることがあるように、
その時代を築き上げてきた現役世代の基盤をいつか覆してやるぞと好機を若い世代が待ち構えているかのように。
光陰矢の如し。
私も現在 67 歳。振り返ると長くもあり短くもあった 67 年間ではある。
「定年退職してからは年金生活だよ。毎日テレビの前に座ったきりで退屈でたまわんわ。スズキ、お前はどうしてるの?」
高校時代の友人たちから時々そんなメールが届く。
毎日、自分のしたいことをする時間がたっぷりあるなんて、羨ましいと思う反面、自分の生きてきた道を否定して今さら引き返すことはできない。
人は人、オレはオレ。こちらは未だ現役だ。
若かりし頃にはキリスト教の伝道生活みたいなことをしていたため、「社会的活動期間」に大きなブランクがある。
なのでフツーの定年退職者のように年金も受給できない。しかも、宗教的呪縛なのか金銭的に潤った時期などは数えるほどしかない。
慢性金欠病患者なので、この歳になっても複数の仕事をこなさなくてはならない。
その一つに塾の講師としての仕事がある。
主に小中学生が対象なので、目の前に座るのはつぶらな二十四の瞳とは年齢差にしてなんと半世紀。
何かとギャップを感じるわけだ。
何よりも、私の若かりし頃には塾に通ってるヤツなんていなかった。
あの時代、塾に行ってたのは大学受験のための高校生くらいのものだった。
塾では小中学生を中心に教えている。
小学生には国語と、時たま算数を、中高生には英語を教えている。
で、「近頃の子供たちは」、ということになる。
自分の子供の頃と比較しても、そもそも器である社会自体が大きく変わっているので単純な比較対象などしても意味はない。
ではあるのだが、毎年、新しい学年を受け持つたびに「劣化」を感じざるを得ない。
無論、体力ははるかに向上しているし、学力だって比較にならないほど進んでいる。
ただ、感受性とか道徳感とか、子供たち一人ひとりの芯とも言えるべきものが成熟していないように感じるのである。
そんな訳で、まあ、自分の目の前に次世代を築く子供たちが座っているので、この立場を利用して少なからず「社会貢献」を、と思うのである。
講師としてある程度カリキュラムにしたがって授業を進めるのは当然のことだが、特に国語を教えていて感じるのは、日常的に本を読む、読書を楽しんでいる子供たちが多くはない。
自分の子供の頃を振り返ってもそうだったが、感受性の強いこの時期に読む本から受ける影響は大きい。
だが目の前にいる子供たちは、正解とされる受け止め方、感じ方、答え方に沿って、テキストに載っている文章を読むのである。
これは、歴史でも理科でも地理でも同じなのだが、今思い返すと、印象に残っている授業とか先生とかは、授業や教科書という枠組みから飛び出し子供たちの興味関心に合わせて話を展開してくれた授業であり先生だった。
国語を教えるのであれば、まずは本を好きになるように指導することだ。
歴史なら、どの時代であれ、その時その場所に実在した人たちの息遣いがわかるように、子供たちの目の前に映し出すことだ。
なんで、私は時々テキストをしばし放置して自分が読んで感動した小説やエッセイなどの一部を子供たちに読んで聞かせる。
本といってもその数は膨大だ。
大海原を自由に泳ぎ回る無数の魚たちを思わせる。
私の書棚にも、そうした膨大な数の書物の中から海の潮の流れの采配で出会ってきた相当数の本が並んでいる。
私は私で、いつも手元に本がないと指先に震えがきてしまうほどの活字中毒患者である。
たいていはジャンルの異なる二冊あるいは三冊を携帯し、一日を通じて読み進めている。
優先順序としては勿論、未読書があればそれを齧り、咀嚼し終わるとその合間に別の本で口直しをする、といった感じだ。
時には読み始めたらあっと言う間に引きずり込まれてその一冊だけに集中して完読してしまうこともある。
すでに読んでしまったものを再読することもある。
そして多くの場合、以前読んでいるにもかかわらず新たな感動を覚える。
自分の書棚の限られたスペースに置くほどの本であれば、しばらくの時を経るとまた旬がめぐって読み頃になっている。
そんな本や作家の一人に浅田次郎がいる。私と同じ世代の人だ。
彼の書いたエッセイの一つ、『勇気凛凛ルリの色』の中に「ヒロシの死について」という章がある。
ある時、これを当時 5 年生だった子供たちに読んで聞かせた。
言っておくが、このクラスは、今ここで言っている「近頃の子供たち」の典型で、多くの意味でヒジョーに教えにくい子供たちで構成されていた。
(私が見たところ) 感受性に乏しく、 (私が見たところ) 何かに感動するといったことがほとんどない子供たちで、休み時間になれば昨日観たテレビのお笑い芸人がどうだったこうだったという話で持ちきりなのである。
この浅田次郎の章は、私にとっては必涙率 100% の感動モノである。
実際、読み聞かせていて最後まで続けられるかどうか自信がなかったが、こみあげてくる涙をこらえ、ときおり声を詰まらせては間をとりながら、とにかく最後まで読み終えた。
・・・で、本から目を上げ子供たちを見ると・・・
二十四の瞳がどれもウルウルに真っ赤なのである。
涙を拭っている子供もいる。
普段なら絶対にそんなことなどあり得ない塾の教室の中で。
友だちの前で泣くなんて考えられないことなのだが、このエッセイに綴られた言葉には力があった。
私たち大人と同様、子供たちだって人前に出るときには日常的に、当たり前のように仮面をつけている。
言葉の感動はそうした羞恥心の仮面をいとも簡単に取り払ってしまったのである。
こんな時、「言葉」というものがいかに世界主要宗教の経典の中にあって崇高かつ超越的なものとして位置づけられているかを再認識せざるを得ない。
そして一見平凡に思える私たちの日常生活においても然りで、「言葉」には確かに人間の内面のみならず外面をも変えてしまうような力がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
