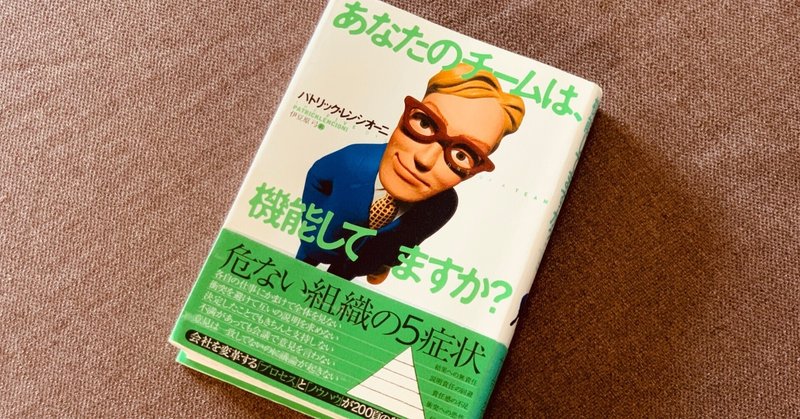
【読書録】『あなたのチームは機能してますか?』パトリック・レンシオーニ
今日ご紹介するのは、パトリック・レンシオーニ氏のビジネス書『あなたのチームは機能してますか?』(伊豆原弓訳、翔泳社、2003年)。原題は、"The Five Dysfunction of a Team"。著者は、組織と経営チームの強化育成を専門とする経営コンサル会社のトップだ。
これは、私の尊敬している、とある経営者の方に薦められた本だ。私にとっては、とてもたくさんの気づきを得られ、有益だった。
本書のテーマは、チームワーク。とりわけ、チームが機能不全に陥る5つの要素とその相互関係について解説するものだ。
本書の構成は、200ページ余りのビジネス小説と、その後の30ページあまりの解説から成り立っている。
まず、本書の大部分を占める小説について。主人公は、業績不振のIT企業のCEOに突如任命されたキャサリン。彼女が、機能不全に陥っている経営幹部チームのメンバーを、チーム会議での対話によって一つにまとめていくというストーリー。
これが非常に面白く、一気に読んでしまった。ものすごくリアルな、チーム運営上よく遭遇する場面が出てきて、感情移入してしまった。
せっかく設定したチームミーティングに、他の仕事をぶつけて欠席しようとするメンバーがいる。会議で辛辣な皮肉を言って、場を凍らせるメンバーがいる。どうしても協力を得られず、会社を辞めてもらう必要のあるメンバーがいる。こういった難しい場面に遭遇したときの、キャサリンの葛藤、決意、時には後悔などの心の声が、生々しく綴られている。
読み進めるうちに、いつの間にか、自分がキャサリンと一体化した感覚になる。展開されるシナリオに一喜一憂しつつ、同じ状況に自分が陥ったら同じようにできるだろうかと考えながら、ドキドキしながらページを繰っていった。
そして、長い物語が終わると、小説のなかで出てきた、チームの5つの機能不全というテーマについての解説が始まる。
5つの機能不全とは。それらは、
①信頼の欠如
②衝突への恐怖
③責任感の不足
④説明責任の回避
⑤結果への無関心
だという。これらの5つが、①から⑤の順に、ピラミッドの最下層から最上層へ積みあがっていくイメージ図が書かれている。
以下、備忘録として、この5つについて重要な記載を引用しておく。
第1の機能不全:信頼の欠如
第1の機能不全である「信頼の欠如」については、次のような解説があった。チームで安心して自分をさらけ出し、弱みを見せられるというのが信頼で、それができる環境がないことが機能不全だという。
チームを構成するときの信頼とは、メンバー同士が相手に悪意がないことを信じ、グループ内で身を守ったり慎重になったりする理由がないと確認することである。要するに、チームメイトが安心して互いに弱みを見せられなくてはならない。
(中略)
(…)チームのメンバーが心から安心して自分をさらけ出すことができなければ、保身を気にせずに行動を起こすことはない。逆にそれができれば、互いに計略を張りめぐらせ、政治的かけひきに頼ることなく、やるべき仕事だけにエネルギーと注意を集中できる。
チームが信頼を比較的短時間で築くための手法には、以下のようなものがある。
●個人の歴史に関する演習(個人に関する少数の質問に答えてもらうもの)
●チームの有効性に関する演習(メンバーがチームメイト一人ひとりについて、最も貢献している点と、改善点を1つずつ上げ、メンバー全員が1つずつ回答する)
●性格・行動性向プロファイル
●360度評価
●実験的チーム演習
さらに、チームの信頼構築を促すためにリーダーがとるべき役割は、以下のとおり。
●率先して弱みを見せる
●弱さを罰しない環境をつくることであると説く
第2の機能不全:衝突への恐怖
第2の機能不全は、衝突への恐怖。ここでは、「前向きな衝突」「生産的な衝突」「健全な衝突」という言葉を使い、ポジティブな意味での「衝突」を恐れて避けてしまうことが、機能不全であるという。
(…)生産的な衝突のあるチームは、それができるだけ短時間で最良の解決策を見出すためのものだと理解している。普通のチームより短時間で徹底的に問題を話し合って解決し、その白熱した議論には、余計な感情やダメージをともなわず、早く次の重要な課題に取り組みたいという熱意がある。
意見の衝突を避けているチームは、メンバーの感情を傷つけないために衝突を避けた結果、かえって危険な緊張を高めていることが多い。重要なアイデアについてメンバーが腹を割って話し合い、意見のちがいをあきらかにしないと、裏で個人攻撃が起きることがある。(中略)
(…)健全な衝突は、実は時間の節約にもなる。(中略)むしろ衝突を避けると、おなじ問題を何度くりかえしても結論が出ないということになる。
衝突回避という機能不全を克服するための手法は、以下のとおり。
●問題を掘り起こす
●リアルタイムの許可(議論がおきているときに、必要なプロセスであると念を押す)
●性格・行動性向分析法など
リーダーの役割は、以下のとおり。
●メンバーが衝突しているときは自制し、ときに混沌とした状況になろうと、自然な解決に任せる。
●自身が、衝突における適切な行動の模範を示す。
●必要で生産的な衝突を避けない。
第3の機能不全:責任感の不足
次は、第3の機能不全「責任感の不足」。以下のくだりが、私にとっては、目からウロコだった。
チームにおいては、責任感には「明確さ」と「支持」という二つの側面がある。優れたチームは、迅速に明確な決定をくだし、その決定に反対した人も含めて、メンバー全員の全面的な支持を得て前進する。会議が終わるときには、今決定したことを支持するかどうかひそかに迷っている人は誰もいない。
責任感不足の大きな原因となるのは、全員一致を求めること、そして確実性を求めることである。
全員一致:優れたチームは、全員一致を求めることがいかに危険かを理解し、完全な合意に達しなくても支持が得らえる方法をさぐる。理性的な人間が決定を支持するためには、我を押し通す必要はなく、自分の意見が聞かれ、考慮されたことがわかれば十分であると理解しているからだ。(以下略)
確実性:優れたチームは、一致団結して支持できることを誇りに思い、その決定が正しいかどうかの確証がなくても、責任をもって明確な行動に従う。何も決定しないよりは、何か決定したほうがよいことを理解しているからだ。また、優柔不断よりは、大胆に決定してまちがえる方が、そしておなじように大胆に方向転換をする方がよいことを理解している。(以下略)
(…)上級管理者のチームが明確な決定をくだし、支持することができなかった場合、大きな問題となるのは、未解決の意見の相違が組織の下層深くまで浸透することである。この機能不全は、ほかのどの機能不全よりも、部下の間に危険な波紋を広げる。(以下略)
このくだりを読んだときに、まず、「全員一致」や「確実性」が、責任感不足の原因になる、という点については、感覚に反するもので、意外に思えた。しかし、全員の意見が一致せず、不確実な状況でも、恐れずに決断をするという場面を思い浮かべると、確かに、チームとしての一体感や責任感が生まれるというイメージは沸く。
この「責任感の不足」という機能不全を克服する策には、以下のようなものがある。
●カスケード式伝達(決定事項につき、社員やほかの関係者に何を伝えるべきかを決める)
●期限を決める
●不足自体と最悪ケースのシナリオ分析
●低リスク療法(比較的リスクの低い状況で決断力を示す)
リーダーの役割は、以下のとおり。
●決定が結果的に間違っていても動じない。
●つねにグループの議論をうながし、チームで決めたスケジュールを守るよう促す。
●確実性や全員一致を重視しすぎないこと。
第4の機能不全:説明責任の回避
第4の機能不全は、「説明責任の回避」。
(…)チームワークに関して、この言葉(注:「説明責任」)は、メンバーが仲間に対して、チームに悪影響を与えかねない行動や態度をとがめようとすることを意味する。
この機能不全の本質は、仲間の態度をとがめることによって対人関係が気詰まりになることに耐えようとしないことと、難しい会話は避けようとする人間の一般的な性質である。優れたチームは、このような本来の性質を克服し、他人との「危険領域に踏み込む」ことを選択する。
(…)チームのメンバー同士が親しいと、貴重な人間関係を危険にさらすことを恐れ、相手の責任を追求するのをためらうことがある。しかし、互いが期待を裏切ったこと、グループの基準を低下させたことに対し、メンバーが憤るようになり、かえって人間関係が悪化するだけである。優れたチームのメンバーは、互いの責任を追求することによって、相手を尊敬していること、相手の仕事ぶりに高い期待を寄せていることを示し、それによって人間関係を向上させる。
(…)チームの仕事で高い水準を維持するために最も有効な手段は、仲間同士のプレッシャーである。その利点の一つは、業績管理や改善措置をめぐる官僚主義的な手続きが少なくて済むことだ。尊敬するチームメイトの期待を裏切ることに対する恐怖は、どのような方針やシステムよりも、いい仕事をしようとする意欲につながる。
このくだりを読むと、説明責任を、チームメンバー間で、チームに悪影響を与える行動や態度について指摘して、プレッシャーを与える、という意味で使っているようだ。それができるチームは、お互いの期待に応えるために、自然と高い水準の仕事をする。そしてそれができないチームは、そうならないばかりか、仮に人間関係がうまくいっているように見えても、チームメンバー相互間の不満が胸の内で募り、人間関係はいずれ悪化していく、ということなのだろう。
この「説明責任の回避」という機能不全を克服するための手法は、以下のとおり。曖昧さを除去し、フィードバックを与えるルーティンを作るだけで、説明責任を追求しやすくなる。
●目標と基準の公表
●簡単な定期進捗レビュー
リーダーの役割は、以下のとおり。
●チームが説明責任に関して最大の役割を果たすよう働きかける
●説明責任は全員一致で決めるようなことではなく、チーム全員で分担する仕事であること、必要なときにはリーダーがためらわず手を貸すことを、チームのメンバー全員にはっきり知らせておく。
第5の機能不全:結果への無関心
最後の機能不全は、「結果への無関心」。
チームの究極の機能不全は、メンバーがグループ全体の目標以外のことを気にするようになることである。(中略)
(…)結果以外でチームが重視するものとは、どのようなものだろうか。その最大の候補が、チームの地位と個人の地位である。
チームの地位:チームのメンバーが、単にグループの一員であることに満足できなくなることがある。そのようなチームは、具体的な結果は達成できるに越したことはないが、そのために犠牲を払い、不便を強いられる価値があるとは考えられない。(中略)成功とは「特別な」組織になることだと考え、この機能不全に陥る危険性がある。
個人の地位:これは、チームを犠牲にして自分の地位やキャリアを高めたいという、ありがちな人間の性質を指す。(以下略)
これは、比較的分かりやすかった。結果を重視しなければ、そもそも結果を出すために構成されたチームであるという存在意義を失わせることになるのは明らかだ。
この機能不全を克服する策は、次のとおり。
●具体的な結果を公約する
●具体的な結果の達成に連動して報償を与える
リーダーの役割は、次のとおり。
●利己心を捨て、客観的になる。
●グループの目標達成に本当に貢献した人にだけ評価と報酬を与える。
まとめ
これらの5つの機能不全は、相互にリンクしている。
第1の機能不全である「信頼の欠如」があると、恐怖ゆえにチームメンバーと対峙できず、第2の機能不全「衝突への恐怖」が生まれる。これは、分かりやすい。
「衝突への恐怖」があると、生産的な衝突が生まれず、各メンバーの意見が十分に議論に取り込まれない。そのため、決定を明確に支持する気持ちになれないメンバーが出てきてしまい、第3の機能不全「責任感の不足」につながる。
「責任感の不足」があると、チームメイトに相互に何を期待すべきか明確に理解できず、それゆえ、互いの行動や態度をとがめることができない。こうして、第4の機能不全「説明責任の回避」が生まれる。
「説明責任の回避」により、チームでメンバー相互の責任を追求しなければ、自分の責任範囲のことだけに目が向き、全体の結果を重視しない、第5の機能不全「結果への無関心」に至る。
ここまで読んできて、陳腐な言い方だが、チームメンバーによるチームワークの良し悪しが、チームの成果に及ぼす決定的な重要性について腹落ちした。
チームメンバーの一人ひとりは、感情を持った生身の人間だ。そんな不完全な人間たちが、信頼、衝突、支持、責任追及という、面倒で厄介なプロセスを経て、良い人間関係を構築、維持しながらひとつにまとまるというのは、並大抵のことではない。チームワークというと、言葉にするとシンプルだが、真のチームワークに到達するまでの道は険しい。そして、それを率いていかなければいけないリーダーの役割は、あまりにも重い。
しかし、本書は、そういう重責を担うリーダーに対して、気を付けるべき5つの機能不全を解きほぐし、それぞれの落とし穴に落ちないような対策を含め、数々のヒントを与えてくれる。
チームをまとめるリーダー的な役割を担う方には、きっとお役に立つ本だと思う。
ご参考になれば幸いです!
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
