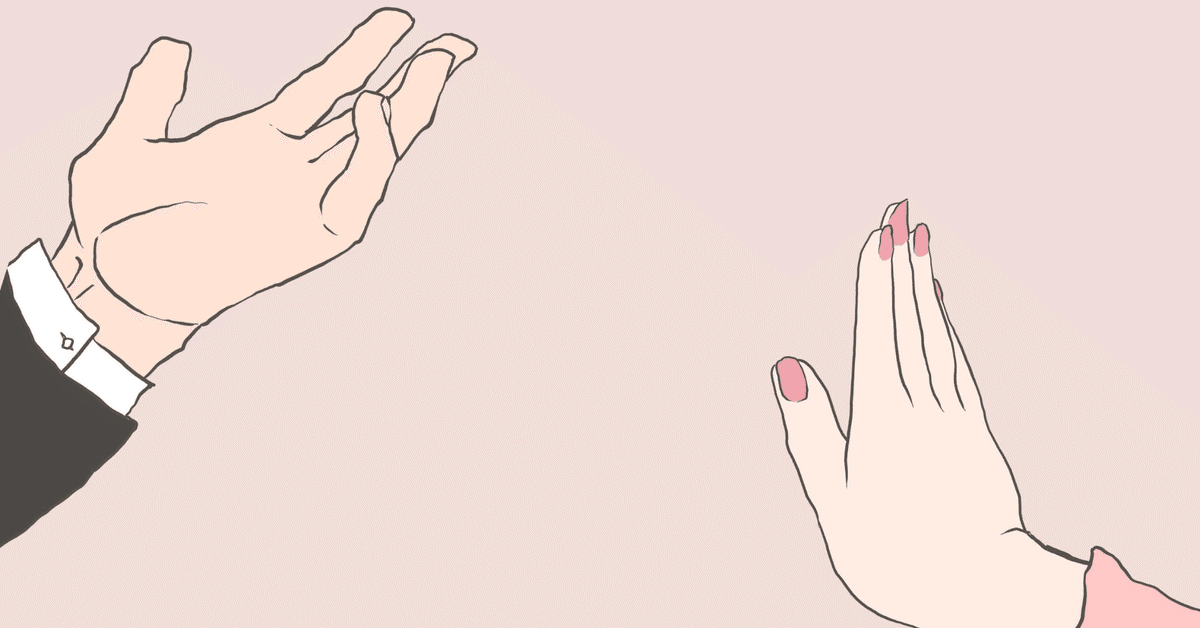
「浮気された🟰裏切られた」の図式の裏にあるもの
浮気とは何だろうか?
どこからが浮気になるのだろうか?
あなたは改めて考えてみたことがあるだろうか。
《浮気》
心がうわついて変わりやすいこと。一人の異性だけを愛さず、あの人この人と心を移すこと。
浮気をする人はずるい。
浮気心はあってはならない。
浮気はふしだらなこと。
浮気はだらしない人がすること。
浮気は心の弱い人がすること。
…浮気は悪いこと。
この感覚に違和感をもつ人は、私たち日本人の中には少ないのではないかと思う。
そして
浮気をされた女性(男性)が陥りやすいパターンとしてよくあるのが
「信じていたのに裏切られた」
「許せない」
「私は大切にされていなかった」
「私は女性(男性)として魅力がないのだ」
などに近い感覚ではないだろうか。
でも果たして
浮気されたということは、裏切られたということと本当にイコールなのだろうか。
そして
浮気は本当に悪いことなのだろうか。
かつての日本には
現在のような結婚制度はなかった。
江戸時代の長家では、暗黙の了解のうちに今で言う《オープンマリッジ》のような感覚があり、生まれてきた子どもたちの父親は定かではなことも日常的にあったと聞いたことがある。それもあってなのか、この時代の庶民の子どもたちは集団の中で育てていくことが常であったとも言われている。
同じように《大奥》について考えてみると
一人の将軍に対してたくさんの妻が当然のごとく存在していたが、その時代に「浮気された」と言って苦しむ妻の割合はどれほどいたのだろうか。ゼロではないような気もするが、今ほどの割合ではなかったのではないだろうか。
では、なぜ同じような現象に対して
昔の人と今を生きる私たちでは反応が違うのか。
それは、そこに横たわる前提が違うからだろう。
前提というのは、「こうあるべきだ」「こうあることが当たり前だ」というような常識・モラルといったようなものである。
私たちは、無意識のうちに親や周囲、育ってきた環境や社会から刷り込まれてきたことをもとに常識やモラルを形成して大人になっている。
その前提に「浮気や不倫は悪である」という常識・モラルが刷り込まれているのだ。そういう前提が刷り込まれやすい文化であり社会なのが今の日本なのではないだろうか。
以前読んだ本の中で、脳科学者の先生が言っていたことだが、動物には種によって《添い遂げ型》と《乱交型》が存在するそうだ。
《添い遂げ型》は、一旦決めたパートナーを変更することはなく1on1が基本。中にはパートナーが死んでしまっても新しいパートナーを作らない種もいるそうだ。
一方で、《乱交型》は自分の遺伝子をもつ子孫を残す可能性を少しでも高くするために、パートナーを変えて繁殖を行う。
そして、私たち人間にはDNAレベルでこの両タイプの存在がいるとのこと。
それなのに…
《浮気🟰悪》という、単一的なものの見方があたかも正しいように扱われていて、世の中の多くの人はその正義に則って物事をジャッジしている。
浮気は本当に悪なのだろうか。
少なくとも今の私にはそう断言することの方がおかしいのではないかと思える。
このことについては、また綴りたい。
(近未来のいつの日かへ続く…)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
