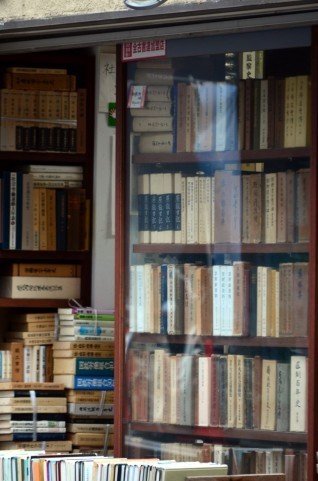
- 運営しているクリエイター
#平家物語
神々の「進化」を記す「平家物語神学」
平家物語巻11第107句「剣の巻」は、以下のような神々の系譜を載せています。
それ神代と言うは、天神のはじめ、国常立尊は色はありて体なし。虚空にあるごとく、煙のごとし。
国狭槌尊より体はありて面目なし。豊斟渟尊より面目ありて陰陽なし。第四より陰陽ありて和合なし。埿土煑尊埿土、沙土煑尊、大戸之道尊、大苫邊尊、面足尊・惶根尊等なり。
この系譜は、日本書紀本文と一致(独り神に関する限り、第一別伝とも
中世における日本神話~平家物語が語る「草薙の剣」
平家物語巻第11第107句「剣の巻」は、壇ノ浦の戦いで海中に没した三種の神器のうち、「草薙の剣」について述べています。
この部分の記述は、当時の人たちに、日本神話がどのように受容されていたかを知る貴重な手がかりのように思われます。
剣の巻は、草薙の剣が登場するまでの経緯についてこのように語り出します。
それ神代と言うは、天神のはじめ、国常立尊は色はありて体なし。虚空にあるごとく、煙のごとし。
「錦の直垂」と、例えば北陸とか、とにかく地域の活性化
観光立国と言うのを考えてみた場合、即効性のある事もない事もあるわけです。
でまあ、即効性はないけれども、何というか、自分たちが暮らす地域について、外国人でも都会人でも、あるいは日本の他の地域の「田舎」の人に説明してみる、
つまり、「自分が暮らしている地域」について「部外者」に説明すると言う事なのですが、
これは、即効性がある・なしは別にして、日頃、その地域に暮らしていると当たり前に思っている
どんな体制でも、それで生活している人がいると言う事。
「宿所には女房達、死したる人の生き返りたる心地して、うれし泣きどもせらりけり」
(平家物語 巻三 第三十句 関白流罪)
藤原行隆さんは、左少弁と言う官職についていたのが解任され、十年以上に渡り、無職の状態でした。
そこへ、平清盛さんからの呼び出し。さては、誰かが告げ口したか、
処罰されるのではないかと恐れおののきながら出向いてみると、
清盛さんは、行隆さんのお父様の顕時さんにはお世話にな











