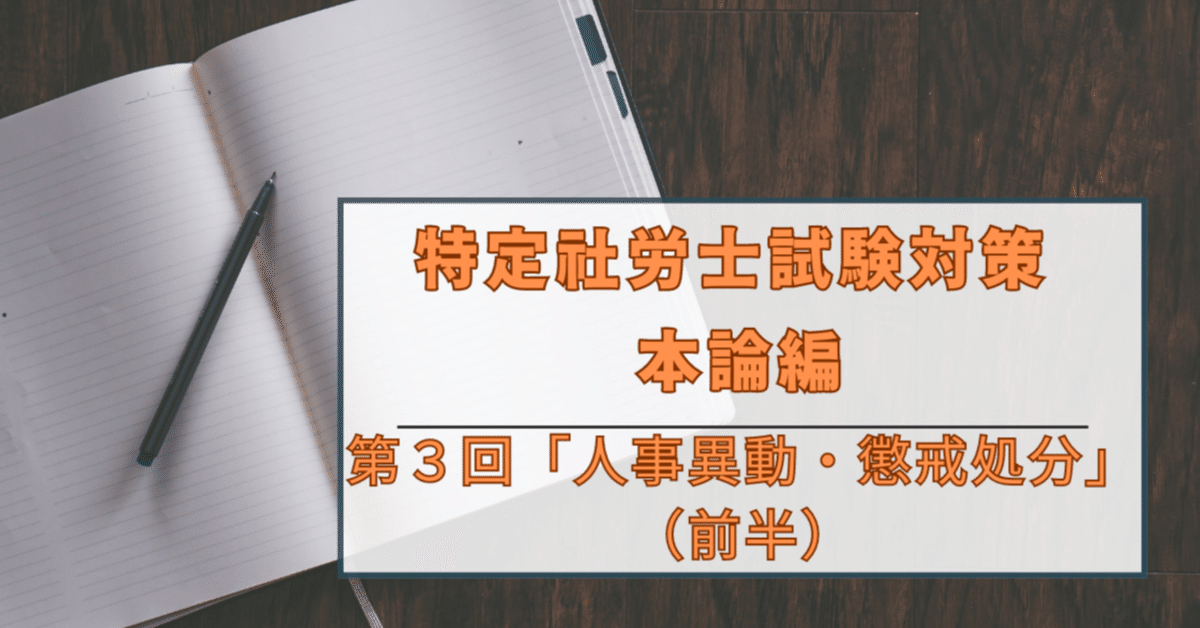
特定社労士試験対策(本論編:第3回「人事異動・懲戒処分」(前半))
北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。
第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。
勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、余計なノイズがない早朝を中心に試験勉強を進めております。
法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。
3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。
前回のまとめはコチラ↓
「本論編」の3回目「人事異動・懲戒処分」について、今回は、以下の項目について学習しました。
「人事異動」:基礎知識の整理
1.人事異動の類型と機能
①人事異動の類型
・企業内での異動=配転(配置転換)
・企業外への異動=出向
②人事異動の機能
2.配転に関する基礎知識
・配置転換(配転)・・・同一企業内での労働者の職種・職務内容又は勤務場所の変更であって、相当の期間にわたって行われるもの。
・配転命令権の有無・・・配転に関する取り決め(特約)があればその取り決めの内容が優先するし、ない場合は、労働者の職種や雇用形態、採用の経緯などの諸事情を踏まえて判断すべきとされる。
・配転命令権の行使の可否・・・配転を行う必要性、配転によって被る労働者の不利益などを考慮して、当該配転命令権の行使が権利の濫用といえる場合には配転命令は無効とされる。
3.出向(在籍出向)に関する基礎知識
・在籍出向・・・従来勤務していた企業(出向元)における従業員としての地位を保持しつつ、法人格の異なる企業(出向先)において、相当期間勤務する就労形態。
①業務命令で出向を強制することの可否
<出向命令権の有無>
・使用者の指揮命令権が出向元から出向先に譲渡されるものであるため、出向命令権発生の前提として、民法625条1項が適用され、労働者の承諾(同意)が必要となる。
<出向命令権の行使の適否>
・個々の出向命令について権利の濫用に該当するか否かが問われる。
②出向からの復帰命令
③出向中の法律関係
・一般的に、労働時間管理のように業務遂行の指揮命令に直結する領域は出向先、退職や解雇といった従業員としての基本的な身分に関わる領域は出向元が使用者責任を負っていると考えられる。
4.転籍の取扱い
①個別的同意の必要性
・転籍(移籍出向)・・・従前の勤務先を退職することになるのであるから労働者からの個別的同意なしには行い得ないのが原則である。
②転籍後の法律関係
・転籍元と転籍先の協議で、転籍者の利益を不当に侵害しないよう配慮することが求められる。
○テーマ1「配転を制約する趣旨の特約」
①特約の種類
<明示の特約>
<黙示の特約>
・職種や職務内容に関するもの
・勤務場所に関するもの
②特約の機能
○テーマ2「育児・介護と転勤」
①問題の所在
②配転に関する権利濫用法理
<転勤命令が権利濫用となる場合>
(1)業務上の必要性が損しない場合
(2)業務上の必要性が損する場合であっても
不当な動機・目的をもってなされたもの
労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
等、特段の事情の存するもの
○テーマ3「出向命令権の根拠となる『同意』」
①問題の所在
・使用者が労働者に対し、在籍出向を命ずる場合、「労働者の承諾(同意)」が必要だが、承諾のレベルとしては、出向命令の都度、対象となる労働者の個別的同意が必要である。
②緩和された解釈
・企業側の利益を重視し、労働協約、就業規則、労働契約などに出向があり得ることが明示されていれば良いという考え方(包括的同意説)が出てくる。
・しかし、バランス的に労働者への不安にも相応の配慮をすべきとのことで、労働者の利益に配慮した具体的規定が必要であるとする考え方(具体的同意説)もある。
#北海道 #社労士 #社会保険労務士 #特定社労士 #特定社会保険労務士 #資格試験 #資格勉強 #note毎日投稿 #note毎日記事投稿中 #早起き #早起き習慣 #早寝早起き #朝のルーティーン #わたしのチャレンジ
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
