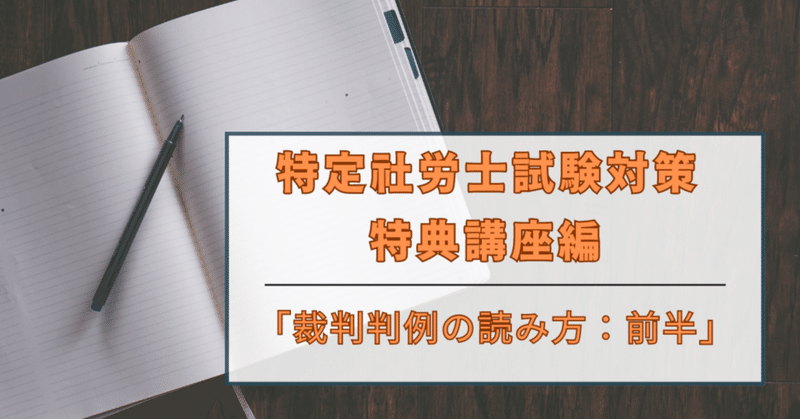
特定社労士試験対策(労働判例読み方講座:前半)
北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。
現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。
毎日、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。
法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めております。
過去問分析講座で、これまでの第1回から第18回までの本試験(特定社会保険労務士試験)について勉強しまして、これまでの出題の内容と、最近の傾向、そして解答にあたっての考え方やポイントなどについて学びました。
過去問については、改めて、何度か自分で解いてみて、また解答例の検討ということをしたいと思います。
そして、特定社労士試験対策講座ですが、7/24から公開された講座の動画として、「労働判例の読み方講座」と「答案の書き方講座」が公開されました。
今回は、これらのうち、「労働判例の読み方講座」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。
前回のまとめはコチラ↓
「労働判例の読み方講座」の前半では、以下の項目について学習しました。
判例を読む際の前提となる基本知識
1.裁判を受ける権利(憲法32条)
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
2.裁判所の種類(憲法76条1項)
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
3.事件の分類・種類
・民事事件(労働事件、家事事件も民事事件の一つ)
・刑事事件
4.審級制(三審制)
・一般の民事事件・・・地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
・労働事件・・・地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
・家事事件・・・家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所
5.最高裁判所の判決のパターン(高裁の判決に対して)
・上告棄却
・破棄・自判・・・高裁の判決を破棄して最高裁自らが判断を行う。
・破棄・差戻し・・・高裁の判決を破棄して高裁に審理をやり直させる。
6.判例の定義
・狭義の「判例」・・・最高裁が下した結論(判決とその理由付け)
・広義の「判例」・・・下級裁判所が下した結論も含む裁判例
7.裁判(民事裁判)の手続の流れ
・原告が訴状を作成(自ら又は弁護士)
→ 原告が訴状を裁判所に提出(訴えの提起)
→ 裁判所が訴状を受理
→ 裁判所が被告に訴状を送達
→ 被告が訴状を受領
→ 被告が答弁書を作成(自ら又は弁護士)
→ 被告が答弁書を裁判所に提出(原告にも送付)
→ 原告が反論の準備書面を作成し裁判所と被告に送付
→ 被告が再反論の準備書面を作成し裁判所と原告に送付
→ 証人尋問
→ 審理の終結(=結審)
→ 和解の試み
→ 判決言い渡し
#北海道 #社労士 #社会保険労務士 #特定社労士 #特定社会保険労務士 #資格試験 #資格勉強 #note毎日投稿 #note毎日記事投稿中 #早起き #早起き習慣 #早寝早起き #朝のルーティーン #わたしのチャレンジ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
