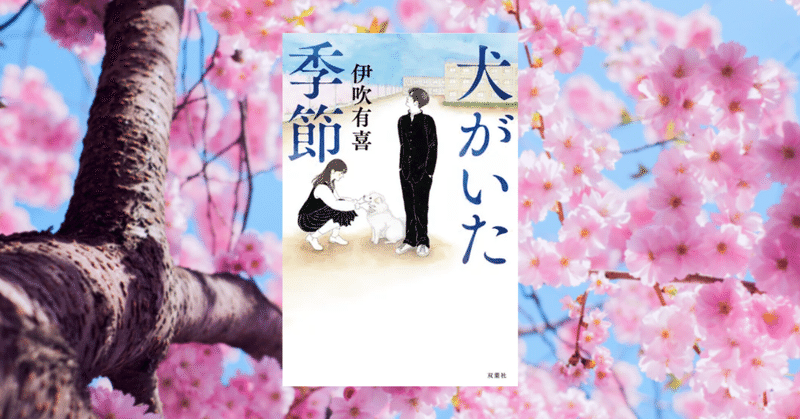
『犬がいた季節 / 伊吹有喜 著』青春の甘い匂いがする──。【2021年本屋大賞】
今回は2021年本屋大賞ノミネート作品の一つである『犬がいた季節』についての読了感想記事を書いていこうと思います。
ストーリーや登場人物、描写への考察をこと細かに記していくつもりですので、まだ本作品を最後まで読み終えていない方は、ページバックすることを強く推奨します。読了後にまた、立ち寄っていただければと思います。
それでは、よろしくお願いいたします!
■誰にとっても想起できる青春を描いた作品
読んでいる最中、僕の胸の奥では様々な感情が湧き起こっていた。
青い恋模様にじれったい気持ちになったり、爽やかな友情にワクワクしたり、切ない気分に陥ったり、たくさんの感情に揺さぶられました。
18歳という思春期の只中にいる青年たちの物語があんまりにも純粋で、それこそ若者を目に映す尊老のような温かい眼差しで、八稜高校の生徒たちの青春の行く末を見守っていました。すでにあの頃の青春を終えた方は、僕と同じような面持ちで読んでいたのではないでしょうか。
本作品では主に高校3年生という人生の節目に立たされた生徒たちの色んな青春が綴られています。
淡い恋の物語、男同士の友情、将来への不安や目の前にある進路のこと。
いずれかが僕らの記憶とリンクしている部分があって、こんな風に過ごした時期も昔はあったなと想起できるように描かれていたと思います。
誰にとっても懐かしくあり、全く同じでは無いにしろ、作中に散りばめられた生徒たちの葛藤が自分の経験と重なるところがあって、思わず感情移入してしまう辺りに伊吹有喜さんの力量を感じることができます。
作品に共感することができたのは物語の完成度だけではなく、作中に登場する生徒たちから、「若者らしさ」を感じ取れる所も一つのポイントです。
自分の中では色々なことを考えていて、意見や信念があるのにそれを面と向かって口にすることができない。ただ単純にそのことを伝える為の言葉を知らないのではなく、言葉にする為のあと一歩の勇気や自信がなくて、結局言えずに終わってしまう。この若者らしい"後悔"を随所に感じられます。
大人になっていくにつれて、自分の意見を示さなければならない場面って増えていきますよね。学生の頃であれば助け舟を出してくれる大人や先輩が周囲にいるのですが、社会に出てからは中々そうはいかない。
意見や意思を示さないことで背負うはめになる不利益が発生し、後になって痛感させられた出来事として実感することで、意思を伝えられる人間として成長していく。このような場面は学生よりも、やはり社会に出てからの方が遭遇する機会が多いと思います。
僕も思春期の頃、意思を伝える技術や経験が未熟だったばかりに考えを言葉にできず、あの時ちゃんと伝えておけば……という思い出が幾つかあります。誰にでもある苦い経験です。
そんな未熟だったが故に相手へ自分の意思を伝えられなかった場面が作中にも存在していて、その部分も共感を生む要素になっていると感じます。
『第3話 明日の行方』では、語り手の奈津子が自分の意思を示すことができなかったことに葛藤、後悔しているシーンが何度も描かれています。
祖母をいたわりたいが、どうしたらいいのかわからない。おそるおそる、奈津子は祖母の肩に手を置く。(P.177)
「悔しい。何もなければ、まだ生きてた気がして」
父が泣いているようで、奈津子は顔を横に向ける。
こんなとき、どうしたらいいのか。本当に、わからない。(P.183)
あのときテレビで見た煙の下に祖母はいた。崩壊した街のなかで、必死になって助けを呼び、泣いていたのに。
いつも、ただ見ているだけ。何もできずにいる──。
言葉にならない声が漏れた。不用意に出たその声の大きさに驚く。気付かぬうちに、拳を握っていた。
悔しい。何もできずにいた自分が。(P.184)
目の前で泣いている人を目の当たりにしても、身動きが取れない。
こういった逡巡も、若さゆえに起こる出来事だと思います。
物語の世界ではこんなとき、若者であっても意思を明確に表現する人物を描くことの方が多い(その方が話を進展させることができる為)のですが、それをしなかったことで、等身大の若者を表現しているように感じました。
逆に自分の中で明確な意思があるのに、行動に移すことができない。
これも、人生経験がまだ浅いばかりに生じる未熟さ(若さ)、ですよね。
『第1話 めぐる潮の音』に登場したコウシロウの想いを書いた場面。
「ほら、忘れるなよ、コーシロー。これが優花さんの花だよ」
彼女の前では「シオミ」とぶっきらぼうに呼ぶのに、自分の前では「ユウカさん」と彼はいつも優しげに言う。
これでいい、とコウシロウがつぶやいた。
「ただ、何もかも……もっと自分が大人だったらと思うよ」
そっと枝を元の位置に戻し、コウシロウは桜を見上げた。
「本当に、本当に、好きだったんだ」(P.89)
好きな子に想いを伝えることができず、ただ立ち止まっている。
どうするべきか分かっていても、言葉にすることができない。
家族に対して意思を示すことのできなかった奈津子とはまた違う観点から、青年のほろ苦い青春を描写したシーンとして描かれています。
作中の生徒たちはこのような葛藤をそれぞれ胸の内に秘めており、そんな自分の心を正直に明かす術や勇気を持っていなかったところが、読者の青春時代どこかで繋がっていて、登場人物に深く感情移入させる大きなテーマの一つになっているのだと、僕は感じます。
そんな中で、言葉にすることはできずとも、行動で意思を伝える唯一の存在が作中にはいます。それが「コーシロー」です。
■生徒たちにとってのコーシローはどういう存在?
ある日、八稜高校に迷い込んだ一匹の白い子犬。
学校で暮らし、人間の言葉は話せずとも、人と人を繋ぐ不思議な存在。
読んでいてまず思ったのは、コーシローはとても頭がいいですよね。
人間の言葉を正確に理解していて、生徒との会話の内容を分かった上で自分の気持ちを表現することができる。授業の内容を聞いているだけで、自分が生きている世界の仕組みをおぼろげながらわかってきた、とそれ以外の事柄についても理解している描写がありました。とてもかしこいです。
また、匂いで目の前にいる人が今抱いている感情を読み取る能力を持っており、作中では特に”恋の匂い”をキャッチすることで、その生徒を後押ししたり、応援するために一生懸命に吠えたりする描写が見られたりしました。
誰に対しても素直で、健気で、話をしたりするときなんかは丁寧な言葉遣いで語りかける様子がすごく愛らしくて、各話の導入部分などにあるコーシロー視点の描写では、思わずニヤニヤしながら読み進めていました。
(カフェで読んでいたのですが、マスクをしていたので助かった)
そんなコーシローは八稜高校の生徒たちにとって、どういう存在だったのだろうか?
同じ学び舎で共に生活はしているものの、クラスメイトでもなく、飼い犬という表現も合っていないだろうし、ましてや先生でもない。
とにかくコーシローは、八稜高校の中に於いて特殊な存在なんですよね。
自分がこの学校に通っているとしたら、なんかこの高校って白い犬が住み着いてるよね、という状態では絶対に済まないだろうし、実際に触ってみたり、匂いを嗅いでみたりしている内にだんだんと愛着が湧いてきて、学校に行けば会える友達の一人のような位置づけになっていくのだと思います。
ただ、"友達"という表現にも僕は少し違和感があって、犬のコーシローはそれ以上に特別な何かがあるように感じます。
物語の中で生徒たちがコーシローへ語り掛けるシーンがありますが、コーシローに対しては誰もが素直な自分の気持ちを打ち明けています。
自分が好きな人のことを友達にも家族にも言えないのは、年頃の青年にとっては珍しいことではありませんよね。それがなぜ、コーシローには包み隠さず話すことができるのだろう?と考えた時に、やはりコーシローが思春期の生徒や、成熟した大人が持っていない要素を備えているからではないかと考えました。
その要素とは何かというと、少し前の方で書いたような自分の心を正直に明かす勇気だったり、コーシローが本来持っている素直さのことです。
感情とは伝播するもので、知らず知らずのうちに伝わってくるもの。
コーシローが恋の匂いを、大好きなユウカさんから感じる甘い匂いだと認識したように、犬から人へ伝わっていく感情もあるのだと思います。
だからこそ、コーシローが持つ感情を素直に伝える勇気が生徒たちにも伝わって、内に秘めていることを言葉にできたのではないでしょうか。
そう考えたときに、大人になる為の大事なことを教えてくれるコーシローは友達以上の何かであるかのように感じ、勇気をくれる象徴的な存在として描かれているように見えます。
■青春の終わり
青年の出会いと別れのときにはいつもコーシローがいましたが、コーシローもまた生涯で幾つもの出会いと別れを経験してきました。
この作品は八稜高校の生徒たちの青春を描いた物語であると同時に、コーシローが過ごした人生の物語でもあります。
各話ごとに年代が進み、物語の全体では昭和63年(1988)~令和元年(2019)までの月日が流れています。その内、コーシローは約12年の歳月を八稜高校で暮らし、たくさんの青春の匂いを感じてきたことになります。
年代が移り変わっていくにつれて、コーシローも子犬から成犬へと成長し、次第に年老いていく姿が描かれています。
スリッパを咥えて校内を駆け回っていた頃もあれば、昔よりも鼻が利かなくなったり、眠っている時間の方が長くなってきたと描写されていたりもして、ページを捲るごとに物語の終わりとコーシローの最後のときが訪れている感覚がして、読み進めるのが少し辛かったです。
そんな感情に浸ることができるのも、本作品の良さでもあります。
中でも、コーシローの成長を表現する描写で一番印象に残ったのが、
話しても言葉は吠え声になってしまう。だから最近は、ほとんど吠えない。
という一節で、経験則から物事を合理的に選択する辺りに、成熟した様子を感じ取ることができます。時の流れを感じさせる一節でもあり、ちょっとだけ寂しい雰囲気も漂ってくるすごく良い文章ですよね。
生徒たちを見送るコーシローの別れの描写も切ないものがあるのですが、やはり話が進んでいく内に成熟していくコーシローの姿が細かく描かれていたので、コーシローとの別れも確実にやってくるのだと覚悟していました。
本を読み終えるまでカフェにいたのですが、最後のシーンでは人目もはばからずボロボロと涙を流しながら読んでいました。
匂いと共に巡る走馬灯。目を開けると、初めてみる桜の色。
悲しい気持ちではなく、すごく嬉しい感情が溢れて涙してしまいました。
これ以上にない、美しい終わり方だったと思います。
犬は人間よりも錐状体と呼ばれる色覚に関わる細胞がとても少ないらしく、世界がほとんど灰色や茶色の景色に見えるらしいのですが、コーシローが見た桜の色はいままでの人生で見てきた色の中で、いちばん美しい色だったに違いありません。
コーシローへの色んな人の想いが最後に見せた奇跡なのだと思います。
数々の出会いと別れ、青春とその終わりを体験した生徒たちは最終話で大人になり、十数年後の未来でもコーシローがいた季節によって紡がれた絆を繋ぎ続けています。あのとき想いを伝えることができなかった人間のコウシロウも、一匹の白い犬がくれた勇気によって、大人になった今、想いを伝えることができました。
人と人を繋げてきたコーシローの存在が、大人になった生徒たちの心に深く刻まれている様子に、最後まで心が躍りました。
本作品は登場人物へ、思わず感情移入させられてしまう描写が多く、心がたくさん揺れ動いた一冊でした。これから青春を迎える方や、青春を終えた大人たち、その両方が読んで楽しめる物語になっていると感じます。
今回は『犬がいた季節』の感想を書かせていただきました。
最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
