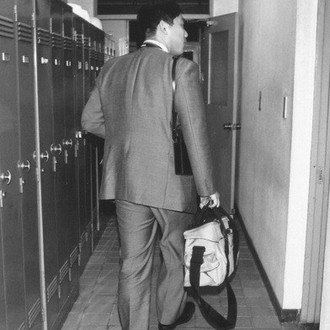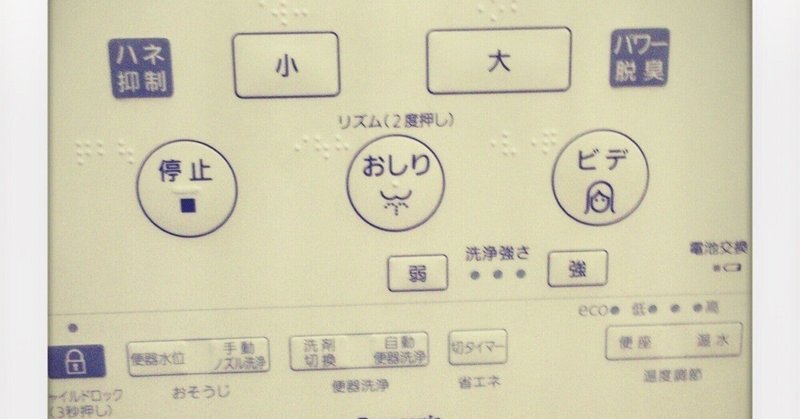- 運営しているクリエイター
2020年8月の記事一覧
老親の入居施設で医療の判断はできない
老人ホーム等の施設に入居しても、家族への問合せは結構ある。お任せとはならない。
老人に体調不良はつきものであるが、それを訴えられた施設の職員が独断で病院に診せにいくことは基本的にない。必ず家族に状況報告があり、対応について訊ねられる。この時、家族は「良きに計らえ」とは言えない。
職員としては、自らの判断で決めたのではなく、家族の意思を確認してそれに従ったという建付けが必要なのだろうと考えている
老人ホームからの突然の知らせ
私がサラリーマンで、電話を頂いても出られないケースがあることから、老人ホーム側には、緊急じゃない場合は電話ではなくメールでの連絡をお願いしています。実際、会議や電車での移動中等、出られない確率は結構高いので、そうしてもらっています。
先日、老人ホーム管理者からメールが届きました。何だろうと思って開くと「病院に診せたいと思うがどうか?」との連絡でした。
これなら緊急じゃないのだろうか? という疑
お年寄りの記憶の残り方
母は、数年前に彼女の妹、つまり私から見れば叔母を亡くした。
もちろん、そのことは亡くなった直後に母に伝えていて、その時はとても驚いてショックを受けた様子だった。
ところが、それから時間を経て一周忌が近づき、改めてその話をしたところ、「え、そうだったの?」と再び驚かれてしまった。つまり、母は妹の死を全く覚えていなかったのである。
そして、この話はその後更に2回ほど伝える機会があったのだけど、都
老人ホームは上手に活用
遠隔地の実家で一人暮らしをしていた親が、何かのきっかけでその生活を継続できなくなる。
……いつかは訪れること。
自宅に引き取るという選択肢もあるけれど、
・部屋に余裕がない、
・親の友人知己が誰もいなくなる、
・介護体制を組み上げなければならない、
・具体的に誰が介護をするのか、
等などを考えると、二の足を踏むことになる。
介護離職も頭を掠めるが、後の生活を考えると厳しい。結局、老人ホームにお
【尾籠注意】病院で 食事の後の 阿鼻叫喚
遠隔介護中の母が、ちょっとした病で入院することとなった。そのお見舞いに行った際に、こぼしていたこと。
神妙な面持ちで母はポツポツと語る。
「病院ってね、食事の時間がビシッと決まっているのよ。そうすると、同じ部屋の人が一斉にご飯を食べることになるでしょ? すると、「その次」のタイミングも重なるのよ」。
そういう発想は、私にはなかった。驚いた顔を見て、母は続けた。
「私みたいに歩ける人は良いけど、