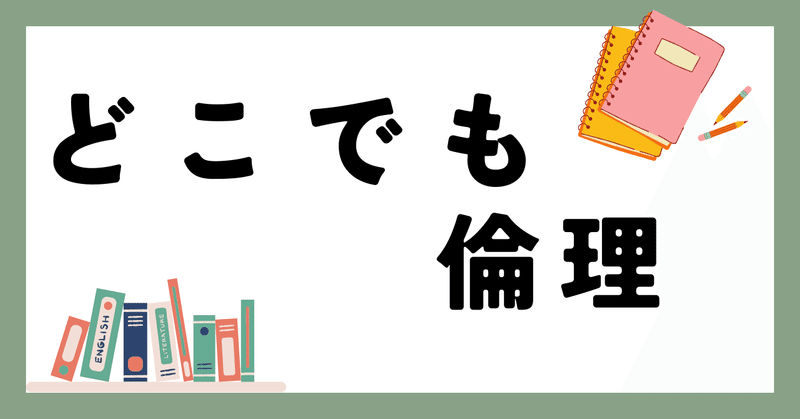
どこでも倫理『ふだんづかいの倫理学』
こんにちは、リードプロジェクトの藤原です。
今回は倫理学の入門中の入門書として書かれた『ふだんづかいの倫理学』について紹介したいと思います。倫理学は大学時代に講義で学んだ以来だったのですが、この本は身近な例に基づいて書かれておりとても分かりやすかったです。仕事とプライベートどちらでも倫理観は必要になるので、これを機会に学ぶのもいいと思います。
注意点
本に書かれていることはすべてが正しいわけではなく、受け入れがたいものや理解が難しいものもあります。
それでも1冊の本から役に立つ教訓を1つでも見つけられたなら、読者様の人生にとってプラスになるのではないでしょうか。
倫理とは
そもそも倫理とは何なのか。
そして、倫理、道徳というのは、人間の生き方や行為についての価値規範のこと。
倫理というのは人間があって初めて生まれます。「人間以外の動物にも倫理があるんじゃないのか」という考え方もありますが、ここではそうしておきましょう。
倫理の対象となるのは人間の生き方や行為になります。「単なる思考やイデオロギーにも倫理はあるんじゃないのか」という意見が私の脳内で生まれましたが、憲法19条に思想・良心の自由が明記されているので、あまり考えても仕方なさそうです。行動が起きてから判断する、ということですね。
価値規範の価値は善悪の価値、規範は人々に存在する(少し曖昧な)善悪の基準になります。これらを合わせて倫理といいます。人間の生き方や行為についての価値規範、といえば倫理です。(大事なことなので2回言いました)
倫理・道徳の必要性
「でもさー、倫理といってもなんとなく分かっているし、わざわざ学ぶ必要ないよねー」
そこで面白い実例をひとつ紹介します。(本に記載されているものですが)
NHKのドキュメンタリー番組で「ガリンペイロ」と呼ばれる金掘り人について2016年に放送されました。アマゾン奥地にある金山には〇人を犯した男や元麻薬患者が集っています。とてもじゃないが法や道徳なんてものはなさそうです。しかし…
面白いドキュメンタリーだったのですが、特に私が興味を惹かれたのは、無法で道徳も何もないと思えるここにも、明確なルールがあったことです。
一つは他人のこれまでのことを詮索しないこと。だから本名を使わない。
もう一つ、他の者が掘った金を盗まないこと。
さらに、掘った金の七割は鉱山の元締めが取り、金掘り人たちは残りの三割、それを仲間で平等に分けること。
驚いたことにこの金山にもルールがありました。悪事に慣れた彼らにとっては他の人間から金を盗めば済むのにそれをしない。この“寄せ集め”集団を維持するには最低限のルールを守ることが必要だと、参加者の大半が理解をしていたということです。
無法者の集団でこれですから、普通の生活では倫理や道徳が必要になってきます。社会や会社、家庭やビジネス、至る所で倫理は関わってくるものです。
最後に
『ふだんづかいの倫理学』では他にも「倫理における正義・自由」など、倫理や倫理学を簡単に知れる内容となっています。気になった方は読んでみてはいかかでしょうか。
リードプロジェクトは個人運営ですが、1年かけて読書のモチベーションを上げるアプリの開発に取り組んできました。既に完成間近であり、公開できる日も近いです。気になる方はnoteのフォロー登録をお願いします。記事の内容が面白いと思った方はハートボタンを押してくれると励みになります。
他の記事の紹介です。ここまで4記事書いてきましたが、創業物語がよく見られています。普段は知ることがないですし、いい刺激になっているのかもしれません。
Amazonのアソシエイトとして、READ-projectは適格販売により収入を得ています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
