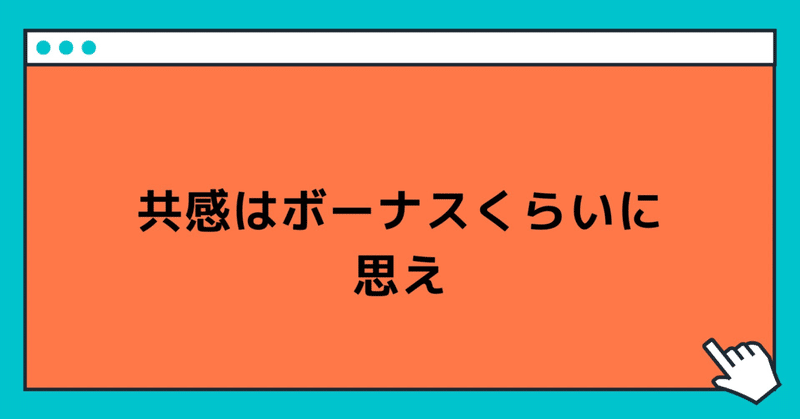
共感はボーナスくらいに思え
相手の心を理解する
相手の考えていることを受け止める
これはコミュニケーションにおいて
大事なことであるのですが
一方で
「この人は自分のことを理解してくれない」
「自分の考えを受け止めようとしない」
など
相手に対して
無意識に共感を求める人も
増えているように思います。
共感することが
大事だと認知されるようになったことで
共感してもらえて当たり前
という期待が
生まれているんですよね。
それによって
「わかって欲しい」
「共感して欲しい」
と期待することで
ストレスが生まれているので
共感してもらえることに
あまり慣れすぎない方が良いよ?
というお話をします。
◯共感するか否かは相手が決めることだと弁える
共感してもらうことが
数直線でいうところの
0で
共感してもらえないことは
マイナス評価
になってしまう人がいる。
たとえば
入院患者さんでも
「あの先生は前の先生より話を聞いてくれない」
「この看護師は、面談の機会を作ってくれない」
「うちの親は自分のやりたいことに
関心を持ってくれない」
などと話されることがありますが
共感してくれる人を基準にしているから
生まれるストレスがあるんです。
ですが
他人に共感してもらうことって
自分でコントロールできる
範疇を超えているというか
ある種の
他人への過剰な期待で
自分ではどうしようもないことだと
弁えて(わきまえて)おいた方が良い。
◯共感では解決しないと理解する
そして
共感されることって
快楽を伴うので
もっと聞いて!
もっと共感して!
と
深みにハマることがある。
すると
辛いことや悲しいことがあった時に
自分でどうにかしようとする前に
人に聞いてもらうことを優先させてしまう。
それの何がいけないか?
と思われるかもしれませんが
人に聞いてもらうだけでは
問題は解決しない
ということを
わかっておかなきゃいけないんですよね。
聞いてもらうことは
もちろん有難いし
気持ちが整理されますから
否定するわけではないのですが
問題解決しないまま
ただ聞いて貰おうとばかりいても
結局ストレス源は残り続けるので
どこかで自分で対処する必要が出てくる。
◯共感を求めすぎると愚痴や不満が増える。
そして
共感する話題ばかり
しようとすると
ネガティブな話題や
他人を陰で攻撃するような
話題しか話さなくなるんですよね。
ストレスを共感し合うことで
対処していると
快楽を伴うので
また愚痴は不満を言い合って
共有しようとする。
すると
また日常のネガティブな部分に
目が行くようになる。
そうなるとどうなるか。
性格の悪い人になるわけです。
楽しい話題を
共有し合える関係だと
良いのかもしれませんが
ネガティブな話題の方が
人は引っ張られますし
自分の成功体験よりも
失敗体験の方が
他人から共感されやすかったり
励まされるので
ネガティブな話題ばかり
話しがちになってしまう
という側面もあるでしょう。
◯共感はボーナスくらいに思っておけ
そこで本日の
タイトルにつながるわけですが
共感されることが
悪いことではありません。
むしろ良いことだし
コミュニケーションを築く上で
有効なのですが
共感してもらえることはボーナス
くらいに捉えておいた方が良い。
つまり
当たり前じゃないんだよ
ということです。
滅多にないから
有難いことだ
ということ。
数直線でいうと
共感してもらえることは
0ではなく
プラスだと思っておく。
あの人は共感してくれない!
と怒るのではなく
まぁそういうものだろう
くらいでいましょう。
そもそも
共感では問題は解決しないので
あくまで
一時の快楽
でしかないと思っておいた方が
自分が楽になる。
自分が相手に対して
共感することはしても
相手に対して
共感しろよ!
と思わないでいましょう
というお話でした😌
サポートしていただけると相当喜びます😭
